キーワード「日本の食事情」③(最終) /「公立小学校の挑戦」志水宏吉 岩波ブックレット №611 2003年 ①【再掲載 2015.6】 [読書記録 一般]
今回は、6月21日に続いて
キーワード「日本の食事情」の紹介3回目 最終です。
出典は不明です。
東海林さだおさんと椎名誠さんとの対談のおもしろさを思い出しました。
わたしは、東海林さだおさんの「丸かじり」シリーズが大好きです。
思わずクスクス笑ってしまい、家族から気味悪がられます。
電車の中で読むのは、わたしには無理です。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「調理は 生食、煮る、蒸す、焼く」
・「玉葱は『実力があるけれども恵まれない状況』」
・「キャンプは訳の分からない内に始まって訳の分からない内に終わる」
・「おでんの竹輪麩の哀しさ。大根が王道。おでんはサラリーマン」
もう一つ、再掲載となりますが、志水宏吉さんの
「公立小学校の挑戦」①を載せます。
公立学校の教育を充実させるためのアイデアを教えてくれます。
かつて勤務先での講演会で聞き、大変納得できた、「スクールバス・モデル『力のある学校』の8つの要素」を思い出しました。
どこに力を集中させればよいかが分かります。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆キーワード「日本の食事情」③(最終)
◇日本食
□調理
① 生食
② 煮る
③ 蒸す
④ 焼く
※ 煮るが主役 … 植物性のものが多い → 醗酵文化
□主食物と副食物
□塩梅(塩… 梅…酢)
◇「人生途中対談」東海林さだお・椎名誠 文藝春秋 1996年
<出版社の案内>
ラーメン、酒、野菜、魚、おでん、CM、病気、本屋…。この15年間にさまざまなテー
マで語り合ったショージとシーナの二人の対談が一冊に。あまねく、人生の指標として読
んでもらいたい。
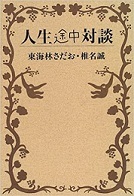
□牛肉とシソの葉のバター丼
バターを
→ すぐ牛肉(火を通す)醤油・お酒
→ シソの葉(一人分五枚) + バターの小さな塊
→ ご飯に熱々で
□つまみ
① ビール → カツ系統,塩鱈,たこの薫製
② 日本酒 → 刺身,貝,モツ煮込み
③ ウィスキー → ピーナッツ,チーズ
□玉葱
保守系議員みたい 地味・保存性有り
「実力があるけれども恵まれない状況」
□湯麺
野菜の甲子園
□アウトドア料理
おにぎり → お抜き
アウトドア
カレー・豚汁
→ 缶詰 マヨネーズ革命
→バーベキュー
キャンプファイヤー純情物語
キャンプ 訳の分からない内に始まって訳の分からない内に終わる
↓
◎ 「あのとき声を掛ければ!」
屋外の飯は気分がうまい
ウィスキーは屋外がよく似合う
焚き火
沈黙が許される
火が有れば怖い動物は来ない。温かくて気持ちがいい。
∥
◎ 文明の最初は火
焚き火は贅沢
□おでん
おでん三役
① コンニャク
② 竹輪
③ 昆布
◎ 竹輪麩の哀しさ 大根が王道 おでんはサラリーマン
☆「公立小学校の挑戦」志水宏吉 岩波ブックレット №611 2003年 ①【再掲載 2015.6】
<出版社の案内>
2002年に刊行し話題を呼んだブックレット『調査報告「学力低下」の実態』において明
らかになった、子どもたちの学力の全体的な低下と階層間格差の広がり。学校に今できる
ことは何なのか。同報告において特筆すべき例として挙がった『効果のある学校』の姿を,
実地での調査・聞き取りをもとに描き出す。」

◇教育改革と学力問題
1 問われる90年代 改革路線 - 教育の武装解除
□イギリス 1988年 教育改革法
①「教育の中央集権化」
②「教育の場への市場原理の導入」
↓
◎ 効率、競争を重んじる経営主義
∥
◎ 教育の場に市場主義・競争原理
↑↓
□日本 「新しい学力観」「観点別評価」「教育の個性化・個別化」
藤田英典 イギリス 「教育の再武装化」
日本 「教育の武装解除」
|
◎ 教育機会の制度的平等や高水準でバラツキの少ない学力など諸外国に対して日本が
誇りうる教育の成果をみすみす損なってしまうような改革路線を日本はひた走った
1999年~
「学力低下」論
「学びからの逃走」(佐藤 2000年)
↓
◎ ゆとり教育路線
2「効果のある学校」の発見
□東京大学
市川伸一、志水宏吉、苅谷剛彦、耳塚寛明
↓
① 子どもたちの「基礎学力」は着実に低下している
② それは、子どもたちの生活・学習状況の変化と密接に関連している
③ また、子どもたちの学力には「分極化」傾向が見られる
④ それは、子どもたちの家庭背景と密接に関係している
⑤ しかしながら、そうした「学力低下」や「格差の拡大」を克服している学校が確か
に存在する
□克服している学校
◎ 大阪府松原市立松原第三中学校
◎ 大阪府松原市立布忍(ぬのせ)小学校
∥
◎ 意欲も基礎学力も高い
◎欧米「効果のある学校」effectiv schools
3 フィールドワークの概要と本書の構成
□志水宏吉
2003.4~ 大阪大学
週一回 布忍小学校 フィールドワーク調査に入る
キーワード「日本の食事情」の紹介3回目 最終です。
出典は不明です。
東海林さだおさんと椎名誠さんとの対談のおもしろさを思い出しました。
わたしは、東海林さだおさんの「丸かじり」シリーズが大好きです。
思わずクスクス笑ってしまい、家族から気味悪がられます。
電車の中で読むのは、わたしには無理です。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「調理は 生食、煮る、蒸す、焼く」
・「玉葱は『実力があるけれども恵まれない状況』」
・「キャンプは訳の分からない内に始まって訳の分からない内に終わる」
・「おでんの竹輪麩の哀しさ。大根が王道。おでんはサラリーマン」
もう一つ、再掲載となりますが、志水宏吉さんの
「公立小学校の挑戦」①を載せます。
公立学校の教育を充実させるためのアイデアを教えてくれます。
かつて勤務先での講演会で聞き、大変納得できた、「スクールバス・モデル『力のある学校』の8つの要素」を思い出しました。
どこに力を集中させればよいかが分かります。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆キーワード「日本の食事情」③(最終)
◇日本食
□調理
① 生食
② 煮る
③ 蒸す
④ 焼く
※ 煮るが主役 … 植物性のものが多い → 醗酵文化
□主食物と副食物
□塩梅(塩… 梅…酢)
◇「人生途中対談」東海林さだお・椎名誠 文藝春秋 1996年
<出版社の案内>
ラーメン、酒、野菜、魚、おでん、CM、病気、本屋…。この15年間にさまざまなテー
マで語り合ったショージとシーナの二人の対談が一冊に。あまねく、人生の指標として読
んでもらいたい。
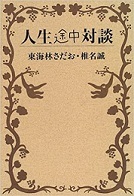
□牛肉とシソの葉のバター丼
バターを
→ すぐ牛肉(火を通す)醤油・お酒
→ シソの葉(一人分五枚) + バターの小さな塊
→ ご飯に熱々で
□つまみ
① ビール → カツ系統,塩鱈,たこの薫製
② 日本酒 → 刺身,貝,モツ煮込み
③ ウィスキー → ピーナッツ,チーズ
□玉葱
保守系議員みたい 地味・保存性有り
「実力があるけれども恵まれない状況」
□湯麺
野菜の甲子園
□アウトドア料理
おにぎり → お抜き
アウトドア
カレー・豚汁
→ 缶詰 マヨネーズ革命
→バーベキュー
キャンプファイヤー純情物語
キャンプ 訳の分からない内に始まって訳の分からない内に終わる
↓
◎ 「あのとき声を掛ければ!」
屋外の飯は気分がうまい
ウィスキーは屋外がよく似合う
焚き火
沈黙が許される
火が有れば怖い動物は来ない。温かくて気持ちがいい。
∥
◎ 文明の最初は火
焚き火は贅沢
□おでん
おでん三役
① コンニャク
② 竹輪
③ 昆布
◎ 竹輪麩の哀しさ 大根が王道 おでんはサラリーマン
☆「公立小学校の挑戦」志水宏吉 岩波ブックレット №611 2003年 ①【再掲載 2015.6】
<出版社の案内>
2002年に刊行し話題を呼んだブックレット『調査報告「学力低下」の実態』において明
らかになった、子どもたちの学力の全体的な低下と階層間格差の広がり。学校に今できる
ことは何なのか。同報告において特筆すべき例として挙がった『効果のある学校』の姿を,
実地での調査・聞き取りをもとに描き出す。」

◇教育改革と学力問題
1 問われる90年代 改革路線 - 教育の武装解除
□イギリス 1988年 教育改革法
①「教育の中央集権化」
②「教育の場への市場原理の導入」
↓
◎ 効率、競争を重んじる経営主義
∥
◎ 教育の場に市場主義・競争原理
↑↓
□日本 「新しい学力観」「観点別評価」「教育の個性化・個別化」
藤田英典 イギリス 「教育の再武装化」
日本 「教育の武装解除」
|
◎ 教育機会の制度的平等や高水準でバラツキの少ない学力など諸外国に対して日本が
誇りうる教育の成果をみすみす損なってしまうような改革路線を日本はひた走った
1999年~
「学力低下」論
「学びからの逃走」(佐藤 2000年)
↓
◎ ゆとり教育路線
2「効果のある学校」の発見
□東京大学
市川伸一、志水宏吉、苅谷剛彦、耳塚寛明
↓
① 子どもたちの「基礎学力」は着実に低下している
② それは、子どもたちの生活・学習状況の変化と密接に関連している
③ また、子どもたちの学力には「分極化」傾向が見られる
④ それは、子どもたちの家庭背景と密接に関係している
⑤ しかしながら、そうした「学力低下」や「格差の拡大」を克服している学校が確か
に存在する
□克服している学校
◎ 大阪府松原市立松原第三中学校
◎ 大阪府松原市立布忍(ぬのせ)小学校
∥
◎ 意欲も基礎学力も高い
◎欧米「効果のある学校」effectiv schools
3 フィールドワークの概要と本書の構成
□志水宏吉
2003.4~ 大阪大学
週一回 布忍小学校 フィールドワーク調査に入る




コメント 0