「日本国民を作った教育」沖田行司 ミネルヴァ書房 2017年 /「加藤秀俊著作集3」中央公論社 1981年 ②【再掲載 2017.2】 [読書記録 教育]
今回は、沖田行司さんの
「日本国民を作った教育」を紹介します。
大変大雑把で部分的な要約ですが、
印象に残っている本です。
出版社の案内には、
「荒廃が叫ばれる日本の教育、その新たなすがたを見出すため、いまふり
かえるこの国の学びの歴史。
寺子屋・藩校・私塾といった江戸時代の学びの場に蓄積された教育遺産
とは何か。
明治維新ののちはじまった『国民教育』とともに、日本は何を手にいれ、
何を失ったのか。
そして敗戦後、占領下の教育政策をへて、いかにして現代の日本人が誕
生したのか。
学びのかたちの変遷に現代へのヒントをさぐる、温故知新の教育読本。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は‥
・「教育が立身出世主義と結びつく度合いは、封建的な身分制社会が
濃厚であった国ほど熾烈である。」
・「かくして、学問・教育のみならず、経済文化に至るまで、国家に
よってオーソライズされたものに価値を見出すという思考パター
ンが国民の間に広く浸透していくのである。」
・「国民教育のはじまりは京都町人の番組小学校」
・「山県有の言葉、『軍人勅語のようなものが教育にも必要』から生
まれたのが『教育ニ関スル勅語』」
もう一つ、再掲載となりますが、
「加藤秀俊著作集3」を載せます。
今回紹介した2冊ですが、
どこかでつながっているような印象をもちました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「日本国民を作った教育」沖田行司 ミネルヴァ書房 2017年
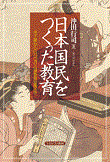
◇現代の教育を考える
□戦後教育とは何であったか
立身出世と教育 - 教育に熾烈な競争の原理
◎ 教育が立身出世主義と結びつく度合いは、封建的な身分制社会が
濃厚であった国ほど熾烈である。
教育に熾烈な競争原理が導入されることになった日本の近代教育
を一貫して支配してきたのは、この競争の原理である。
こうした国家主導型の教育システムにおいて、立身出世とは個人
と国家との距離を縮めていくことを意味したのである。
かくして、学問・教育のみならず、経済文化に至るまで、国家に
よってオーソライズされたものに価値を見出すという思考パターン
が国民の間に広く浸透していくのである。
□江戸の「学びの形」 常識の力と教育
□横井小楠(1809~1869)
肥後熊本藩 ~ 時習館で学んだ
□学びの共同体
- 私塾
□江戸の教育論
◇日本人の近代教育の変容
□ 国民教育のはじまり
京都町人の番組小学校
立身出世主義と国民教育
□「教育勅語」をどう見るか
1890(明治23)「教育ニ関スル勅語」
= 山県有朋 1882「軍人勅語」のようなものが教育にも必要
◇沖田行司(おきたいくじ)
同志社大学社会学部教育文化学科教授 博士
1979 同志社大学大学院文学研究家博士後期課程修了
1989~1996 ハワイ大学日本研究科客員教授
2004~2013 中国人民大学客座教授
☆「加藤秀俊著作集3」中央公論社 1981年 ②【再掲載 2017.2】

◇世相史研究序説
□文字にならない歴史
記憶の保存
口承の伝承 → 文字の伝承
「歴史」 = 記憶に対する恐るべき執念の集積
↑
◎偏りがある - 社会の頂点に立つことのできた限られた人々
∥
◎ 数十億の人間の殆どすべては,誰にも知られないまま,不快沈殿層
をつくっている。その上に文字になった記録が薄い上澄み部分をつく
ってのっかっている。
◎「歴史学」は上澄みをよりどころにして成立した学問
∥
エリートの思想と行動の軌跡
|
※ しかし,それだけを歴史と考えるのは間違いではないか?
∥
◎ 上澄みは上澄みで結構。しかし,少なくともそれと並んで熱い沈殿
層にも目を向けなければならない
□正史と稗史
◎歴史学 …①社会の頂点に立つ人々=上澄みをよりどころにした学問
②政治性
③正史 政治史を以てその主流とすべき
◎民俗学 …① 沈殿した記憶の歴史に照明
② 常民が主人公 ~ 世相史
◎「正史家」
物事を因果の網の目で説明する
|
網の目に乗らないものは偶発的・例外的
切り落とす = 植木屋の職人のごとき
◎稗史
因果律にも法則的にも別段興味を持たない = 自然観察家
行き当たりばったり 事実の寄せ集め
∥
◎世相史
ぼさぼさした個別的事実の集合体
小さな経験とその産物
□市井のジャーナリズム
常民の変化
~ 自らの手で記録が可能に
新聞の誕生 ~ 日録(ジャーナル)
① 市井の記録家
江戸期
西沢一鳳,喜多村信節,神沢卓幹,浜松歌国 - 随筆
菅江真澄,橘南渓 -旅行家
鈴木牧之 -雪国博物誌
場期末・明治 服部誠一,菊池貴一郎,宮武外骨,石井研堂
② 常民の成長が早かった
江戸・大阪・京都 寺子屋-普通教育
武官優位
→ 文官優位
→ 浮浪・有閑知識人 = 自由なインテリ
③ 日本人の大多数は世俗的-即物的関心
18世紀 ~ 今世紀
◎稗史材料は優れている(他国に比べて)
= 世相史は日本史しかつくれない
□世相史の確立に向かって
歴史学徒としての世相史学,世相史方法論の確立
~ 記録保全
民具,常民の記録
「日本国民を作った教育」を紹介します。
大変大雑把で部分的な要約ですが、
印象に残っている本です。
出版社の案内には、
「荒廃が叫ばれる日本の教育、その新たなすがたを見出すため、いまふり
かえるこの国の学びの歴史。
寺子屋・藩校・私塾といった江戸時代の学びの場に蓄積された教育遺産
とは何か。
明治維新ののちはじまった『国民教育』とともに、日本は何を手にいれ、
何を失ったのか。
そして敗戦後、占領下の教育政策をへて、いかにして現代の日本人が誕
生したのか。
学びのかたちの変遷に現代へのヒントをさぐる、温故知新の教育読本。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は‥
・「教育が立身出世主義と結びつく度合いは、封建的な身分制社会が
濃厚であった国ほど熾烈である。」
・「かくして、学問・教育のみならず、経済文化に至るまで、国家に
よってオーソライズされたものに価値を見出すという思考パター
ンが国民の間に広く浸透していくのである。」
・「国民教育のはじまりは京都町人の番組小学校」
・「山県有の言葉、『軍人勅語のようなものが教育にも必要』から生
まれたのが『教育ニ関スル勅語』」
もう一つ、再掲載となりますが、
「加藤秀俊著作集3」を載せます。
今回紹介した2冊ですが、
どこかでつながっているような印象をもちました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「日本国民を作った教育」沖田行司 ミネルヴァ書房 2017年
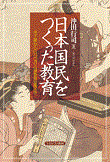
◇現代の教育を考える
□戦後教育とは何であったか
立身出世と教育 - 教育に熾烈な競争の原理
◎ 教育が立身出世主義と結びつく度合いは、封建的な身分制社会が
濃厚であった国ほど熾烈である。
教育に熾烈な競争原理が導入されることになった日本の近代教育
を一貫して支配してきたのは、この競争の原理である。
こうした国家主導型の教育システムにおいて、立身出世とは個人
と国家との距離を縮めていくことを意味したのである。
かくして、学問・教育のみならず、経済文化に至るまで、国家に
よってオーソライズされたものに価値を見出すという思考パターン
が国民の間に広く浸透していくのである。
□江戸の「学びの形」 常識の力と教育
□横井小楠(1809~1869)
肥後熊本藩 ~ 時習館で学んだ
□学びの共同体
- 私塾
□江戸の教育論
◇日本人の近代教育の変容
□ 国民教育のはじまり
京都町人の番組小学校
立身出世主義と国民教育
□「教育勅語」をどう見るか
1890(明治23)「教育ニ関スル勅語」
= 山県有朋 1882「軍人勅語」のようなものが教育にも必要
◇沖田行司(おきたいくじ)
同志社大学社会学部教育文化学科教授 博士
1979 同志社大学大学院文学研究家博士後期課程修了
1989~1996 ハワイ大学日本研究科客員教授
2004~2013 中国人民大学客座教授
☆「加藤秀俊著作集3」中央公論社 1981年 ②【再掲載 2017.2】
◇世相史研究序説
□文字にならない歴史
記憶の保存
口承の伝承 → 文字の伝承
「歴史」 = 記憶に対する恐るべき執念の集積
↑
◎偏りがある - 社会の頂点に立つことのできた限られた人々
∥
◎ 数十億の人間の殆どすべては,誰にも知られないまま,不快沈殿層
をつくっている。その上に文字になった記録が薄い上澄み部分をつく
ってのっかっている。
◎「歴史学」は上澄みをよりどころにして成立した学問
∥
エリートの思想と行動の軌跡
|
※ しかし,それだけを歴史と考えるのは間違いではないか?
∥
◎ 上澄みは上澄みで結構。しかし,少なくともそれと並んで熱い沈殿
層にも目を向けなければならない
□正史と稗史
◎歴史学 …①社会の頂点に立つ人々=上澄みをよりどころにした学問
②政治性
③正史 政治史を以てその主流とすべき
◎民俗学 …① 沈殿した記憶の歴史に照明
② 常民が主人公 ~ 世相史
◎「正史家」
物事を因果の網の目で説明する
|
網の目に乗らないものは偶発的・例外的
切り落とす = 植木屋の職人のごとき
◎稗史
因果律にも法則的にも別段興味を持たない = 自然観察家
行き当たりばったり 事実の寄せ集め
∥
◎世相史
ぼさぼさした個別的事実の集合体
小さな経験とその産物
□市井のジャーナリズム
常民の変化
~ 自らの手で記録が可能に
新聞の誕生 ~ 日録(ジャーナル)
① 市井の記録家
江戸期
西沢一鳳,喜多村信節,神沢卓幹,浜松歌国 - 随筆
菅江真澄,橘南渓 -旅行家
鈴木牧之 -雪国博物誌
場期末・明治 服部誠一,菊池貴一郎,宮武外骨,石井研堂
② 常民の成長が早かった
江戸・大阪・京都 寺子屋-普通教育
武官優位
→ 文官優位
→ 浮浪・有閑知識人 = 自由なインテリ
③ 日本人の大多数は世俗的-即物的関心
18世紀 ~ 今世紀
◎稗史材料は優れている(他国に比べて)
= 世相史は日本史しかつくれない
□世相史の確立に向かって
歴史学徒としての世相史学,世相史方法論の確立
~ 記録保全
民具,常民の記録




コメント 0