「私の教育観」学研教育ジャーナル編集部 2000年 ⑥(最終) / 『灯し続けることば』大村はま 小学館 ⑧(最終) 2004年【再掲載 2012.12】 [読書記録 教育]
2020年の最終日は、12月27日に続いて、学研教育ジャーナル編集部による
「私の教育観」の紹介 6回目 最終です。
出版社の案内には、
「秋山仁、金田一春彦、俵万智、山田洋次…。37人の著名人が自らの生い立ちや天職を
得た動機などを語り、学校・家庭・社会の教育問題へ提言する。『教育ジャーナル』掲
載の『ひと・模様』(途中改題)をまとめる。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「素直な子がいちばん 教える方も教わる方も疲れない」
・「(川渕三郎さんの)恩師は吉岡たすく先生 - 演劇を用いて 話の巧さ」
-「テレビ寺子屋」のおなじみの講師の吉岡さん、川渕さんの恩師とは存じませんでした。
・「これから雑誌と本と毎月一冊ずつ買うてあげる。どの本がほしいか自分で探しなはれ」
- 素晴らしい言葉掛けですね。
・「『むかつく』『キレル』『べつに』『ウザイ』 - ミーイズムと拝金主義」
もう一つ、再掲載となりますが、大村はまさんの
『灯し続けることば』⑧を載せます。
森繁久弥さんのエピソードは、ずっと頭のどこかに残っています。
本年も、拙ブログとおつきあいくださり、ありがとうございました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
☆子供たちの学習に
文部科学省の
「子供の学び応援サイト(臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト)」
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「私の教育観」学研教育ジャーナル編集部 2000年 ⑥(最終)

<社会教育>
◇江崎玲於奈 1925大阪生
急がれる若き創造力の育成
人生を変えた三高の校風
① 自由闊達にやる
② テイストを磨く 審美眼鑑識眼
DNAと遺伝外情報
先生が再充電できる大学院制度を
◇小川三夫 1947生 宮大工 西岡常一門下
本物をつくる
法隆寺五重塔に感動
西岡棟梁の教え方
1年間刃物道具研ぎ-法輪寺三重塔 8年間一人で
鵤工舎(いかるがこうしゃ) の指導法
昭和52年5月独立
23人の弟子
共同生活が原則 - 見習いは飯炊きと掃除
「素直な子がいちばん 教える方も教わる方も疲れない」
教えることは教えないこと
弟子は自分で覚えるしかない 我慢比べ
木は寝かせて使う
耐えること
千三百年前の工人と対話
「本物を残しておけば必ず技術は蘇る」
◇川渕三郎 1936大阪生
小中学校のグラウンドを緑の芝生に
サッカーに学ぶ国際性
恩師・吉岡たすく先生 - 演劇を用いて - 話の巧さ NHK放送劇団
四国行きが人生を決めた
「百年構想」の原点
◇ジョージ・フィールズ 1928東京生 オーストラリア人
野茂・イチローに続け
「0歳教育」に共感 - 井深大『ゼロ歳教育』
マーケティング畑一筋に
「東京オリンピアン」世代の活躍
偏差値教育と塾の全盛
日本型「いじめ」の特性
世代交代は進む
◇谷沢永一 1929大阪生
義務教育は諸悪の根源
母の適切な言葉
「これから雑誌と本と毎月一冊ずつ買うてあげる。どの本がほしいか自分で探しなはれ」
読書家の心得
① まず買いなさい
② 捨てる ツマラナイ本は捨てる
教師は「お通夜のお坊さん」
◇寺島実郎 1947北海道生
よみがえれ団塊パワー
「むかつく」「キレル」「べつに」「ウザイ」 - ミーイズムと拝金主義
パブリックを意識する時
社会工学がキーワードに
若者が社会参加できるような仕組み作り
◇矢島稔 1930東京生 昆虫学者
「昆虫の森」に夢かける
虫と昆虫の違い 蝶の羽化に感動 大切な先生の一言
子どもたちが主役の「昆虫の森」
☆『灯し続けることば』大村はま 小学館 ⑧(最終) 2004年【再掲載 2012.12】
<出版社の案内>
「国語教育の神様」とまで言われた国語教師・大村はま、98歳になる今日までの著作・
執筆から選びだした珠玉のことば52本と、その周辺。自らを律しつつ、人を育てること
に人生を賭けてきた大村はまの神髄がここに凝縮された。 「熱心と愛情、それだけやれ
ることは、教育の世界にはないんです」「したことの悪さより、しかられた傷のほうが大
きいということはないでしょうか」「熱心結構、いい人あたり前です」「スタートラインが
一緒でも、ゴールには同時に入りません」「しかられ上手であることが必要です」etc.子ど
もにかかわるすべての大人、仕事に携わるすべての職業人に、折に触れてページを開いて
読んでほしい。
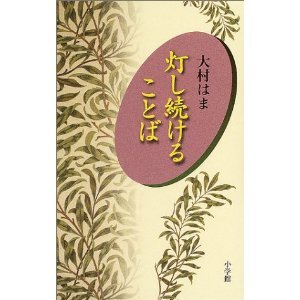
◇バケツの水を捨てるときのように
掃除の後、バケツの水を捨てるときに、ぐるぐるぐるぐる回してポイと捨てると、底の
ほうに沈んでいた澱が浮かんできて捨てられます。
でもその回転を途中でやめたら、また澱が沈んでしまいます。
人間の頭もそれと同じではないか、と子どもに話すことがありました。
ゆっくり少しずつやっていたのでは、アイディアが出てこないということがあります。
ですから、ぐるぐるかき回して、ぱっと捨てるように進めていくのです。
とくに文章を書くときなどに、そういう場面があるようです。
カードやメモに、頭に浮かぶことを次から次へと頭がからっぽになるまで、「書くこと
がない」というところまではき出していくのです。
こうやっていくと、自分でも知らなかったような自分の持っている考えが浮き上がって
きます。
そのようにしなければ、私たちは心の底に沈んでいる自分の大切な思想を引き出すこと
ができないもののようです。
それを目覚めさせるために、ぐるぐる回していくこと、からっぽになるまで頭を使い、
鉛筆を止めずに書き続けること。
そこからいい文章、いい見方が生まれて来るというのは、私の実体験でした。
◇「なんにも考えてこなかったのですが…」
教師たちの会に、俳優の森繁久弥さんを講演にお招きしたことがありました。
みんなが楽しみに待っているところへ、森繁さんが走るようにはいっていらっしゃいま
した。
「遅くなりました。いま旅から帰ってきたもので」
とおっしゃり、
「なんにも考えてこないで、先生がたの前でお話をするなんておこがましいようですけれ
ど」
というふうに話し始められました。
しかし、大変面白く、心にしみるお話でした。
さてお話が終わって、
「何かこの際、お聞きしたいことがありましたら」
となると、一人の方が
「大変おもしろいお話でした。なんにも考えてこられないのに、どうしたらそういうふう
に、のびのびと、しかし筋の通ったお話ができるようになるのでしょうか」
と尋ねられました。
そのときです。森繁さんが、瞬間キリっとした表情になりました。
すぐまた元の穏やかな表情に戻りましたが、私にはその瞬間がわかりました。
「なんにも用意してこなかった、と言いましたが、本当は、う-んと用意してきました。
みなさんに楽しんで聞いていただけるように、長い間、この話の案を練っていました。
なんにも考えてこなかったと言ったのも、それも私の案でした」
会場はシーンとなりました。
私はいろいろな案があってこそ、ないように見えるすばらしさが心にしみました。
案はいくら練っても練りすぎることはないということ、それをなんでもないように、重
い感じにならないようにして、気軽に聞いてもらうためには何倍もの苦心がいることを知
りました。
なんにも考えていないような自然さがあるからといって、なんにもないんだと思ったり
するのが、どんなに浅いものの見方か、話すことの難しさに思いを致していないことであ
るかと気づきました。
「私の教育観」の紹介 6回目 最終です。
出版社の案内には、
「秋山仁、金田一春彦、俵万智、山田洋次…。37人の著名人が自らの生い立ちや天職を
得た動機などを語り、学校・家庭・社会の教育問題へ提言する。『教育ジャーナル』掲
載の『ひと・模様』(途中改題)をまとめる。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「素直な子がいちばん 教える方も教わる方も疲れない」
・「(川渕三郎さんの)恩師は吉岡たすく先生 - 演劇を用いて 話の巧さ」
-「テレビ寺子屋」のおなじみの講師の吉岡さん、川渕さんの恩師とは存じませんでした。
・「これから雑誌と本と毎月一冊ずつ買うてあげる。どの本がほしいか自分で探しなはれ」
- 素晴らしい言葉掛けですね。
・「『むかつく』『キレル』『べつに』『ウザイ』 - ミーイズムと拝金主義」
もう一つ、再掲載となりますが、大村はまさんの
『灯し続けることば』⑧を載せます。
森繁久弥さんのエピソードは、ずっと頭のどこかに残っています。
本年も、拙ブログとおつきあいくださり、ありがとうございました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
☆子供たちの学習に
文部科学省の
「子供の学び応援サイト(臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト)」
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「私の教育観」学研教育ジャーナル編集部 2000年 ⑥(最終)

<社会教育>
◇江崎玲於奈 1925大阪生
急がれる若き創造力の育成
人生を変えた三高の校風
① 自由闊達にやる
② テイストを磨く 審美眼鑑識眼
DNAと遺伝外情報
先生が再充電できる大学院制度を
◇小川三夫 1947生 宮大工 西岡常一門下
本物をつくる
法隆寺五重塔に感動
西岡棟梁の教え方
1年間刃物道具研ぎ-法輪寺三重塔 8年間一人で
鵤工舎(いかるがこうしゃ) の指導法
昭和52年5月独立
23人の弟子
共同生活が原則 - 見習いは飯炊きと掃除
「素直な子がいちばん 教える方も教わる方も疲れない」
教えることは教えないこと
弟子は自分で覚えるしかない 我慢比べ
木は寝かせて使う
耐えること
千三百年前の工人と対話
「本物を残しておけば必ず技術は蘇る」
◇川渕三郎 1936大阪生
小中学校のグラウンドを緑の芝生に
サッカーに学ぶ国際性
恩師・吉岡たすく先生 - 演劇を用いて - 話の巧さ NHK放送劇団
四国行きが人生を決めた
「百年構想」の原点
◇ジョージ・フィールズ 1928東京生 オーストラリア人
野茂・イチローに続け
「0歳教育」に共感 - 井深大『ゼロ歳教育』
マーケティング畑一筋に
「東京オリンピアン」世代の活躍
偏差値教育と塾の全盛
日本型「いじめ」の特性
世代交代は進む
◇谷沢永一 1929大阪生
義務教育は諸悪の根源
母の適切な言葉
「これから雑誌と本と毎月一冊ずつ買うてあげる。どの本がほしいか自分で探しなはれ」
読書家の心得
① まず買いなさい
② 捨てる ツマラナイ本は捨てる
教師は「お通夜のお坊さん」
◇寺島実郎 1947北海道生
よみがえれ団塊パワー
「むかつく」「キレル」「べつに」「ウザイ」 - ミーイズムと拝金主義
パブリックを意識する時
社会工学がキーワードに
若者が社会参加できるような仕組み作り
◇矢島稔 1930東京生 昆虫学者
「昆虫の森」に夢かける
虫と昆虫の違い 蝶の羽化に感動 大切な先生の一言
子どもたちが主役の「昆虫の森」
☆『灯し続けることば』大村はま 小学館 ⑧(最終) 2004年【再掲載 2012.12】
<出版社の案内>
「国語教育の神様」とまで言われた国語教師・大村はま、98歳になる今日までの著作・
執筆から選びだした珠玉のことば52本と、その周辺。自らを律しつつ、人を育てること
に人生を賭けてきた大村はまの神髄がここに凝縮された。 「熱心と愛情、それだけやれ
ることは、教育の世界にはないんです」「したことの悪さより、しかられた傷のほうが大
きいということはないでしょうか」「熱心結構、いい人あたり前です」「スタートラインが
一緒でも、ゴールには同時に入りません」「しかられ上手であることが必要です」etc.子ど
もにかかわるすべての大人、仕事に携わるすべての職業人に、折に触れてページを開いて
読んでほしい。
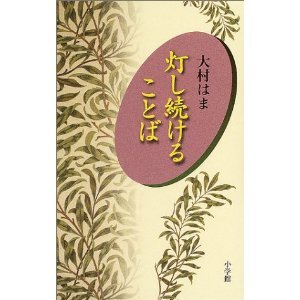
◇バケツの水を捨てるときのように
掃除の後、バケツの水を捨てるときに、ぐるぐるぐるぐる回してポイと捨てると、底の
ほうに沈んでいた澱が浮かんできて捨てられます。
でもその回転を途中でやめたら、また澱が沈んでしまいます。
人間の頭もそれと同じではないか、と子どもに話すことがありました。
ゆっくり少しずつやっていたのでは、アイディアが出てこないということがあります。
ですから、ぐるぐるかき回して、ぱっと捨てるように進めていくのです。
とくに文章を書くときなどに、そういう場面があるようです。
カードやメモに、頭に浮かぶことを次から次へと頭がからっぽになるまで、「書くこと
がない」というところまではき出していくのです。
こうやっていくと、自分でも知らなかったような自分の持っている考えが浮き上がって
きます。
そのようにしなければ、私たちは心の底に沈んでいる自分の大切な思想を引き出すこと
ができないもののようです。
それを目覚めさせるために、ぐるぐる回していくこと、からっぽになるまで頭を使い、
鉛筆を止めずに書き続けること。
そこからいい文章、いい見方が生まれて来るというのは、私の実体験でした。
◇「なんにも考えてこなかったのですが…」
教師たちの会に、俳優の森繁久弥さんを講演にお招きしたことがありました。
みんなが楽しみに待っているところへ、森繁さんが走るようにはいっていらっしゃいま
した。
「遅くなりました。いま旅から帰ってきたもので」
とおっしゃり、
「なんにも考えてこないで、先生がたの前でお話をするなんておこがましいようですけれ
ど」
というふうに話し始められました。
しかし、大変面白く、心にしみるお話でした。
さてお話が終わって、
「何かこの際、お聞きしたいことがありましたら」
となると、一人の方が
「大変おもしろいお話でした。なんにも考えてこられないのに、どうしたらそういうふう
に、のびのびと、しかし筋の通ったお話ができるようになるのでしょうか」
と尋ねられました。
そのときです。森繁さんが、瞬間キリっとした表情になりました。
すぐまた元の穏やかな表情に戻りましたが、私にはその瞬間がわかりました。
「なんにも用意してこなかった、と言いましたが、本当は、う-んと用意してきました。
みなさんに楽しんで聞いていただけるように、長い間、この話の案を練っていました。
なんにも考えてこなかったと言ったのも、それも私の案でした」
会場はシーンとなりました。
私はいろいろな案があってこそ、ないように見えるすばらしさが心にしみました。
案はいくら練っても練りすぎることはないということ、それをなんでもないように、重
い感じにならないようにして、気軽に聞いてもらうためには何倍もの苦心がいることを知
りました。
なんにも考えていないような自然さがあるからといって、なんにもないんだと思ったり
するのが、どんなに浅いものの見方か、話すことの難しさに思いを致していないことであ
るかと気づきました。
キーワード「新津」23(最終)ー「ふるさと新津」新津婦人学級 昭和57年3月5日発行(8) / 「言語学者が政治家を丸裸にする」東照二 文藝春秋 2007年 ①,②【再々掲載 2012.11】 [読書記録 郷土]
今回は、12月24日に続いて、わたしの教育ノートから、
キーワード「新津」23回目の紹介 最終です。
新津婦人学級による「ふるさと新津」8回目の紹介です。
地元の人が努力なされてまとめた本により、地域のことをよく知ることができました。
幾人か知っている方の名前もありました。
新津中学校が設立時は、現在の場所ではなく、
江戸時代に整備されたお台場の近くにあったということを本書で初めて知りました。
もう一つ、再掲載、再々掲載となりますが、東照二さんの
「言語学者が政治家を丸裸にする」①と②をのせます。
大変面白く読んだ本です。
暮れになり政治家の言葉、特に総理大臣の言葉、話し方が話題になっています。
聞きやすい口調で、具体的に、聴き手を意識して話してほしいと切に願います。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
☆子供たちの学習に
文部科学省の
「子供の学び応援サイト(臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト)」
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆キーワード「新津」23(最終)ー「ふるさと新津」新津婦人学級 昭和57年3月5日発行(8)
2.新津中学校
(1)浜名郡新津村立新津中学校
昭和22(1947)年4月1日~昭和26(1951)年
新津小学校に併設 昭和22年4月1日~
[高射砲旧兵舎に移転]昭和22年9月1日~
お台場の高射砲内兵舎に = 「浜の中学校」
校長 中村半次郎 議長・山村義雄 大工・水野さん
小楠伊吉校長
(2)浜松市立新津中学校 昭和26年3月23日~現在
昭和27(1952)年3月31日
赤屋根のスマートな校舎 平屋建て 校庭には緑の芝生
昭和36(1961)年 全日本器楽合奏コンクール第一部優勝
昭和38・39年 全国子供音楽コンクール静岡県予選優勝
◇参考資料
『浜松市史』
『浜名郡史』
『新津村沿革史』
『遠江風土記伝』
『土のいろ』
『遠南のしぶき』
『倉松考』(鈴木実著)
『浜松の史跡』(浜松史跡調査顕彰会)
『浜松近郷の隠れ地蔵』(鈴木達吉著)
『浜松風土記』(会田文彬著)
『遠州伝説集』(御手洗清)
『あの町この町』(加藤鎮毅)
『のびゆく浜松(小学校編・中学校編)』
『はままつ再発見』(読売新聞社)
『ふるさと百話』(静岡新聞社)
『郷土の史跡』(浜松市広報課)
『遠州浜』(でんでんむしの会)
◇新津婦人学級
水野多美子 西山美江子 丸山綾子 小楠道子 渭原京子
☆「言語学者が政治家を丸裸にする」東照二 文藝春秋 2007年 ①【再掲載 2012.11】
<出版社の案内>
「なぜ」の小泉、「だぜ」の麻生、「おせ」の角栄。政治家の話に、人はなぜひきつけられ
るのか。歴代首相の所信表明演説、記者のぶらさがり取材、街頭演説…社会言語学者の徹
底的な収集と分析によって、明かされた政治の本質。
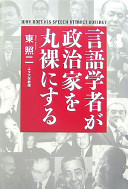
◇小泉純一郎の魔術
□言葉が政治を動かす
□「私小泉も愛する皆さんのため」
□魔術の種は夫婦の会話にある
①リポート・トーク
②ラポート・トーク
□○○(不明)の分かりにくさ
竹下登の修辞学 - 学者のように分かりにくい渦巻きスタイル
□会話の協調原理
①質
②量
③関連性
④話し方
□郵政選挙圧勝の秘密は「疑問形」にあり
□小泉 = ラポート・トークの政治家
漲る気迫,セリフをためる,疑問形を使う
「国民の皆さんに聞いてみたい」「なぜ」の繰り返し
素人の言葉を使った政治のプロ
□善悪二言論で国民を巻き込む
「~ます形」と「~だ形」
ウチを演出する
フレーミングの力
◇安倍晋三の馬脚
□国会所信表明演説
安倍の短い文節数 ←→ ダントツの長さは橋本龍之介
□文末表現から首相診断
消えゆく「~あります」
□小泉を徹底研究していた安倍晋三
「~します」
明快で斬新なイメージ
安倍のカタカナ戦略
□安倍式
①「あります」を失わない
②「~します」の多用
③カタカナ語の多用
□顔を上げて話してほしい
37回もの「改革」(小泉)眼中に徴収なし
□原稿のない即興の答弁を分析すると
がらりと変わった安倍
-答弁では「あります。「あります」「ございます」多用
□疑問形の小泉 「ございます」の安倍
※ 演説と答弁の開き
☆「言語学者が政治家を丸裸にする」東照二 文藝春秋 2007年 ②【再掲載 2012.11】
◇小沢一郎の継承
□党首討論から見えるもの
「~おります」を多用していた小沢
□やはり小泉は短く話す = グルグル渦巻きスタイル
□「ぶら下がり」取材の録音テープを分析する
= 簡潔さと饒舌さ
※「~ですね」の小泉,「~思います」の安倍
□小泉の体言止め,安倍の「ございません」
□「ね」「だ」「と」の小泉,「です」「ます」の安倍
□ポイントはスイッチを変えられるか
スイッチしない安倍,スイッチする小泉
靖国参拝とコードスイッチング
◇渡辺美智雄のポルノ
□なぜあの演説に人は群がったのか
□加藤紘一が分析する演説の極意
①ポルノ調
②情報と情緒
③リポートトークとラポートトーク
□田中角栄とそのまんま東を結ぶ線
押しと引き
地方方言 - そのまんま東
◇小泉と安倍 応援演説の聞き比べ
□小泉
直截,「~です」
切り替え,ダイナミズム
コードスイッチング有り
話の流れ
今日の聴衆についての感想
お礼
外の聴衆の言葉の引用
お礼
候補者への応援要請
自分の名前 - 自分を茶化す
□候補者への応援要請
□安倍
婉曲,「~あります」
単調な「です「ます」一本槍
コードスイッチングなし
話の流れ
あいさつ
自分の名前
天候
お礼
候補者に用意してきたようなコメント
◇田中角栄の革命
□名手達の演説術
アリストテレスの説く王道
尾崎行雄(公開演説会)
犬養毅(理路整然)
浜口雄幸(荘重)
浅沼稲次郎(人間機関車)
□「念押し」が入る角栄節
□「だぜ」の麻生太郎 - 半径2mの男(ラポートトークの落とし穴)
□薄くなった話の中身
「小泉劇場」の本当の意味
マックス・ウェーバー 「責任感,情熱,洞察力」
キーワード「新津」23回目の紹介 最終です。
新津婦人学級による「ふるさと新津」8回目の紹介です。
地元の人が努力なされてまとめた本により、地域のことをよく知ることができました。
幾人か知っている方の名前もありました。
新津中学校が設立時は、現在の場所ではなく、
江戸時代に整備されたお台場の近くにあったということを本書で初めて知りました。
もう一つ、再掲載、再々掲載となりますが、東照二さんの
「言語学者が政治家を丸裸にする」①と②をのせます。
大変面白く読んだ本です。
暮れになり政治家の言葉、特に総理大臣の言葉、話し方が話題になっています。
聞きやすい口調で、具体的に、聴き手を意識して話してほしいと切に願います。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
☆子供たちの学習に
文部科学省の
「子供の学び応援サイト(臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト)」
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆キーワード「新津」23(最終)ー「ふるさと新津」新津婦人学級 昭和57年3月5日発行(8)
2.新津中学校
(1)浜名郡新津村立新津中学校
昭和22(1947)年4月1日~昭和26(1951)年
新津小学校に併設 昭和22年4月1日~
[高射砲旧兵舎に移転]昭和22年9月1日~
お台場の高射砲内兵舎に = 「浜の中学校」
校長 中村半次郎 議長・山村義雄 大工・水野さん
小楠伊吉校長
(2)浜松市立新津中学校 昭和26年3月23日~現在
昭和27(1952)年3月31日
赤屋根のスマートな校舎 平屋建て 校庭には緑の芝生
昭和36(1961)年 全日本器楽合奏コンクール第一部優勝
昭和38・39年 全国子供音楽コンクール静岡県予選優勝
◇参考資料
『浜松市史』
『浜名郡史』
『新津村沿革史』
『遠江風土記伝』
『土のいろ』
『遠南のしぶき』
『倉松考』(鈴木実著)
『浜松の史跡』(浜松史跡調査顕彰会)
『浜松近郷の隠れ地蔵』(鈴木達吉著)
『浜松風土記』(会田文彬著)
『遠州伝説集』(御手洗清)
『あの町この町』(加藤鎮毅)
『のびゆく浜松(小学校編・中学校編)』
『はままつ再発見』(読売新聞社)
『ふるさと百話』(静岡新聞社)
『郷土の史跡』(浜松市広報課)
『遠州浜』(でんでんむしの会)
◇新津婦人学級
水野多美子 西山美江子 丸山綾子 小楠道子 渭原京子
☆「言語学者が政治家を丸裸にする」東照二 文藝春秋 2007年 ①【再掲載 2012.11】
<出版社の案内>
「なぜ」の小泉、「だぜ」の麻生、「おせ」の角栄。政治家の話に、人はなぜひきつけられ
るのか。歴代首相の所信表明演説、記者のぶらさがり取材、街頭演説…社会言語学者の徹
底的な収集と分析によって、明かされた政治の本質。
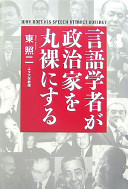
◇小泉純一郎の魔術
□言葉が政治を動かす
□「私小泉も愛する皆さんのため」
□魔術の種は夫婦の会話にある
①リポート・トーク
②ラポート・トーク
□○○(不明)の分かりにくさ
竹下登の修辞学 - 学者のように分かりにくい渦巻きスタイル
□会話の協調原理
①質
②量
③関連性
④話し方
□郵政選挙圧勝の秘密は「疑問形」にあり
□小泉 = ラポート・トークの政治家
漲る気迫,セリフをためる,疑問形を使う
「国民の皆さんに聞いてみたい」「なぜ」の繰り返し
素人の言葉を使った政治のプロ
□善悪二言論で国民を巻き込む
「~ます形」と「~だ形」
ウチを演出する
フレーミングの力
◇安倍晋三の馬脚
□国会所信表明演説
安倍の短い文節数 ←→ ダントツの長さは橋本龍之介
□文末表現から首相診断
消えゆく「~あります」
□小泉を徹底研究していた安倍晋三
「~します」
明快で斬新なイメージ
安倍のカタカナ戦略
□安倍式
①「あります」を失わない
②「~します」の多用
③カタカナ語の多用
□顔を上げて話してほしい
37回もの「改革」(小泉)眼中に徴収なし
□原稿のない即興の答弁を分析すると
がらりと変わった安倍
-答弁では「あります。「あります」「ございます」多用
□疑問形の小泉 「ございます」の安倍
※ 演説と答弁の開き
☆「言語学者が政治家を丸裸にする」東照二 文藝春秋 2007年 ②【再掲載 2012.11】
◇小沢一郎の継承
□党首討論から見えるもの
「~おります」を多用していた小沢
□やはり小泉は短く話す = グルグル渦巻きスタイル
□「ぶら下がり」取材の録音テープを分析する
= 簡潔さと饒舌さ
※「~ですね」の小泉,「~思います」の安倍
□小泉の体言止め,安倍の「ございません」
□「ね」「だ」「と」の小泉,「です」「ます」の安倍
□ポイントはスイッチを変えられるか
スイッチしない安倍,スイッチする小泉
靖国参拝とコードスイッチング
◇渡辺美智雄のポルノ
□なぜあの演説に人は群がったのか
□加藤紘一が分析する演説の極意
①ポルノ調
②情報と情緒
③リポートトークとラポートトーク
□田中角栄とそのまんま東を結ぶ線
押しと引き
地方方言 - そのまんま東
◇小泉と安倍 応援演説の聞き比べ
□小泉
直截,「~です」
切り替え,ダイナミズム
コードスイッチング有り
話の流れ
今日の聴衆についての感想
お礼
外の聴衆の言葉の引用
お礼
候補者への応援要請
自分の名前 - 自分を茶化す
□候補者への応援要請
□安倍
婉曲,「~あります」
単調な「です「ます」一本槍
コードスイッチングなし
話の流れ
あいさつ
自分の名前
天候
お礼
候補者に用意してきたようなコメント
◇田中角栄の革命
□名手達の演説術
アリストテレスの説く王道
尾崎行雄(公開演説会)
犬養毅(理路整然)
浜口雄幸(荘重)
浅沼稲次郎(人間機関車)
□「念押し」が入る角栄節
□「だぜ」の麻生太郎 - 半径2mの男(ラポートトークの落とし穴)
□薄くなった話の中身
「小泉劇場」の本当の意味
マックス・ウェーバー 「責任感,情熱,洞察力」



