「ヤクザの必勝心理術」向谷匡史 イーストプレス 2014年 /「過労死防止基本法の制定運動」大阪大学大学院教授 小野田正利 (『内外教育』2012年4月13日号「普通の教師が生きる学校-モンスター・ペアレント論を超えて」より)【再掲載 2012.4】 [読書記録 一般]
今回は、向谷匡史さんの
「ヤクザの必勝心理術」を紹介します。
出版社の案内には、
「なぜ、『ヤクザの言い分』に従ってしまうのか?その恐るべき“禁断”の心理テクニック
を完全図解化!ビジネス心理戦に絶対負けない裏ワザ!」
とあります。
勉強になりました。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「テクニック ①論点をずらす ②揚げ足を取る ③比喩を使う 名コピー」
- 国会中継でよく見聞きします。
・「第三者を引き合いに出す」
・「相手が口を開くまで待つ-沈黙にいかに耐えるか」
・「初対面で安めを売らない」
・「ワンマン上司操縦法はまず『言い分』を受け入れること
一旦受け入れてから指示を仰ぐ」
もう一つ、再掲載となりますが、
小野田正利さんの「過労死防止基本法の制定運動」を載せます。
学習指導要領が変わるたびに、次々と新しいものが取り入れられます。
「スクラップ&ビルド」ではなく、「ビルド&ビルド」、
「現行」学習指導要領の総括なしに、
新しい目玉のものを盛り込んだ次の「新」学習指導要領が示されていきます。
教員になろうという若者が減り、
教員採用選考試験の倍率低下に歯止めがかからない状況ですが当然かと感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「図解 ヤクザの必勝心理術」向谷匡史 イーストプレス 2014年
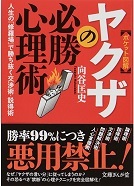
◇反論を100%封じ込めるヤクザの論理術
テクニック
① 論点をずらす
② 揚げ足を取る
③ 比喩を使う 名コピー
追い込みのテクニック
「初っ端ガツン」
- 懇願ではなく交渉
相手にノーと言わせず外堀を埋めていく
矛盾点をつく
「みなさんも…」と言う言葉の魔術
バンドワゴン効果
第三者を引き合いに出す
「オレはいいんだ。だけど組長の顔をどうしてくれる。」
断る理由にかみつく
→ 理由は言わずに「イヤです」の一点張り
次々と断る理由をいなし,それをつぶして退路を断つ
「筋」のパワーは自由自在
筋を臨機応変に使い分ける
ヤクザ式交渉術
「言質(げんち)で相手を絡み取る」
~ 社交辞令に食いつく
沈黙は金
「後の先」で主導権
相手が口を開くまで待つ - 沈黙にいかに耐えるか
後出しジャンケンが勝ち
◇強い自分を巧みに演出するヤクザの説得術
「他人の目」で自分を見る
怖い顔はパフォーマンス
= 物言わぬヤクザの迫力
第一印象がすべて
初対面で安めを売らない
ベンツ男と国産中古車
- 信用は見た目で決する
自分を「一歩上」に見せる交渉術
「多忙=有能」のイメージ利用
ダブルブッキングで忙しさを演出
世間のイメージを上手に利用
さりげないアピール
鷹揚さ・気前の良さ
身なりは内面も変える
一人歩きしてこそ生きる「伝説」や「武勇伝」
さわりのみ
悪評の人間はたった一日の全高で信用を得,善人はたった一回の悪評で信用のすべてを
失う
-「コントラスト効果」
◇相手の心を手玉に取るヤクザ交渉術
「頼み事」は頼まれた時間から頼まれた側が弱くなる
交渉の口火ははったりで
説得とは相手に納得させること
相手になるほどと思わせられるかどうか
議論は「利」を得るためのもの
「トドメ」は刺さずに「メンツ」を立たせる
震え上がらせ安堵させる妙
強面とダメ役
不確かと思わせることで信頼性をアップする
「まさかとは…」
「小耳に…」
「頼み事」はした方が有利になる不思議
頼み事をすれば相手より優位に立てる
◇どんな修羅場も一発逆転 ヤクザの問題解決術
ピンチで一発逆転
油断を見逃さない
相手の失言を待つ - 白旗を揚げない
風評(ウワサ)の効力
スケープゴート強迫術
人望を得ようとするなら「強い立場」に立った時にあえて腰を低く見せればよい。筋を
通せば無理も通る
他人の不幸は蜜の味
ウワサを広める極意
情報は虚実の確証がないから価値がある ××に叱られた
災いを転じる事後処理術
① すぐに謝りいなせ
② 言い訳するな
③ チャンスと
◇相手を一喝 人心掌握術
「自分で決断する」というスタイルを取る
返事の退路を断つ
時期を見て高飛車に
「それでどうする」失敗したものにけじめを付けさせる
↓
自分に何をすべきか
アメとムチ
「親しき仲にも恐怖あり」
ビシッと叱っておく
叱る時は名前で
「暗黙の強化」
ワンマン上司操縦法はまず「言い分」を受け入れること
一旦受け入れてから指示を仰ぐ
「では,どうしましょうか」
☆「過労死防止基本法の制定運動」大阪大学大学院教授 小野田正利 (『内外教育』2012年4月13日号「普通の教師が生きる学校-モンスター・ペアレント論を超えて」より)【再掲載 2012.4】
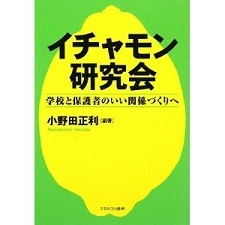
◇ポイント
① 働く意義と、人間の尊さを両立させることが難しくなってしまった国・ニッポン
② 働く教師、教え子を社会に送り出す教師として、この事実を受け止めてほしい
③ 今、過労死防止基本法の制定を求める運動が進められている
◇父さんが死んでしまう前の日に
《大きくなったら
ぼくは博士になりたい
そしてドラえもんに出てくるような
タイムマシーンをつくる
ぼくはタイムマシーンにのって
お父さんの死んでしまう
まえの日に行く
そして「仕事に行ったらあかん」ていうんや》
「ぼくの夢」と題されたこの詩は、父親を過労自殺で亡くしたマーくん(当時小学校1
年生)が書いたものだ。
これを前面に出しながら、今、全国各地で、過労死防止基本法の制定のための運動が展
開されていることをご存じだろうか。
「いのちより、家族より、大事な仕事って、何ですか?」
◇人間の尊厳のために
私は次のようなメーツセージを寄せた。
○○○○○
私は教育学者の一人として、学校や教師達の働きぶりや生活実態を調査してきました。
今の学校と教職員は過労死水準をはるかに超えています。
朝早くから夜遅くまで、土日も部活指導で馬車馬のように働いていて、アップアップの
状態にあります。
2つの数字がそのことを物語っています。
① 業務の拡大と複雑化が進行し、病み倒れていく者はあとをたちません。
公立学校に限定した数字ですが、病気休職者8000人超、うち精神性疾患5000人超の
背後には、その3倍ほどの2~3か月の病気休暇者がおり、さらに数倍の危険水域にあ
る者がいると思われます。
そして毎年100人近い教員が自殺しているとされます。
② 1971年からの教職調整手当は、残業時間はどれだけあっても、月額で本給に対して
4%上乗せをすることで打ち切りとなっています。
当時は月平均で8時間の残業だったからです。
しかし2006年の調査結果は、1日の労働時間ですら11時間。
これだけで、いかに無茶な実態であるかか分かるでしょう。
必至で善であると進められてきた矢継ぎ早の「教育改革」の嵐(教育改革病)は、確実
に教師から「子どもと触れ合い向き合う=教師としての自信を取り戻す時間」を奪って
いった。
そして、本来は協業文化で子どもを見ていたものが、個業から孤業へと移りゆきます。
極限的多忙から、疲労感、徒労感が、その身を包んでいます。
民間企業もおかしい、公務労働もおかしい状態がまかり通ることは、社会の危機と思い
ます。ぜひ「過労死防止基本法」を制定する緊急性があると強く思います。人間の尊厳の
ために
○○○○○
過労死防止基本法は、
① 過労死はあってはならないことを、国が宣言する
② 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にする
③ 国は、過労死に間する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行う
ことを求めている。
過労死防止基本法については、インターネットの検索サイトで「過労死防止基本法の制
定をめざす実行委員会」のホームページにアクセスしていただければ、詳細な情報と署名
用紙のダウンロードが可能なので、ぜひ広めていただくことをお願いしたい。
それは私たちの問題だけでなく、私たちにつながる人々の問題でもあり、これから生ま
れ来る次の世代への財産でもあると思うから。
「ヤクザの必勝心理術」を紹介します。
出版社の案内には、
「なぜ、『ヤクザの言い分』に従ってしまうのか?その恐るべき“禁断”の心理テクニック
を完全図解化!ビジネス心理戦に絶対負けない裏ワザ!」
とあります。
勉強になりました。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「テクニック ①論点をずらす ②揚げ足を取る ③比喩を使う 名コピー」
- 国会中継でよく見聞きします。
・「第三者を引き合いに出す」
・「相手が口を開くまで待つ-沈黙にいかに耐えるか」
・「初対面で安めを売らない」
・「ワンマン上司操縦法はまず『言い分』を受け入れること
一旦受け入れてから指示を仰ぐ」
もう一つ、再掲載となりますが、
小野田正利さんの「過労死防止基本法の制定運動」を載せます。
学習指導要領が変わるたびに、次々と新しいものが取り入れられます。
「スクラップ&ビルド」ではなく、「ビルド&ビルド」、
「現行」学習指導要領の総括なしに、
新しい目玉のものを盛り込んだ次の「新」学習指導要領が示されていきます。
教員になろうという若者が減り、
教員採用選考試験の倍率低下に歯止めがかからない状況ですが当然かと感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「図解 ヤクザの必勝心理術」向谷匡史 イーストプレス 2014年
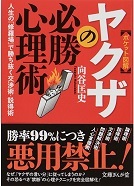
◇反論を100%封じ込めるヤクザの論理術
テクニック
① 論点をずらす
② 揚げ足を取る
③ 比喩を使う 名コピー
追い込みのテクニック
「初っ端ガツン」
- 懇願ではなく交渉
相手にノーと言わせず外堀を埋めていく
矛盾点をつく
「みなさんも…」と言う言葉の魔術
バンドワゴン効果
第三者を引き合いに出す
「オレはいいんだ。だけど組長の顔をどうしてくれる。」
断る理由にかみつく
→ 理由は言わずに「イヤです」の一点張り
次々と断る理由をいなし,それをつぶして退路を断つ
「筋」のパワーは自由自在
筋を臨機応変に使い分ける
ヤクザ式交渉術
「言質(げんち)で相手を絡み取る」
~ 社交辞令に食いつく
沈黙は金
「後の先」で主導権
相手が口を開くまで待つ - 沈黙にいかに耐えるか
後出しジャンケンが勝ち
◇強い自分を巧みに演出するヤクザの説得術
「他人の目」で自分を見る
怖い顔はパフォーマンス
= 物言わぬヤクザの迫力
第一印象がすべて
初対面で安めを売らない
ベンツ男と国産中古車
- 信用は見た目で決する
自分を「一歩上」に見せる交渉術
「多忙=有能」のイメージ利用
ダブルブッキングで忙しさを演出
世間のイメージを上手に利用
さりげないアピール
鷹揚さ・気前の良さ
身なりは内面も変える
一人歩きしてこそ生きる「伝説」や「武勇伝」
さわりのみ
悪評の人間はたった一日の全高で信用を得,善人はたった一回の悪評で信用のすべてを
失う
-「コントラスト効果」
◇相手の心を手玉に取るヤクザ交渉術
「頼み事」は頼まれた時間から頼まれた側が弱くなる
交渉の口火ははったりで
説得とは相手に納得させること
相手になるほどと思わせられるかどうか
議論は「利」を得るためのもの
「トドメ」は刺さずに「メンツ」を立たせる
震え上がらせ安堵させる妙
強面とダメ役
不確かと思わせることで信頼性をアップする
「まさかとは…」
「小耳に…」
「頼み事」はした方が有利になる不思議
頼み事をすれば相手より優位に立てる
◇どんな修羅場も一発逆転 ヤクザの問題解決術
ピンチで一発逆転
油断を見逃さない
相手の失言を待つ - 白旗を揚げない
風評(ウワサ)の効力
スケープゴート強迫術
人望を得ようとするなら「強い立場」に立った時にあえて腰を低く見せればよい。筋を
通せば無理も通る
他人の不幸は蜜の味
ウワサを広める極意
情報は虚実の確証がないから価値がある ××に叱られた
災いを転じる事後処理術
① すぐに謝りいなせ
② 言い訳するな
③ チャンスと
◇相手を一喝 人心掌握術
「自分で決断する」というスタイルを取る
返事の退路を断つ
時期を見て高飛車に
「それでどうする」失敗したものにけじめを付けさせる
↓
自分に何をすべきか
アメとムチ
「親しき仲にも恐怖あり」
ビシッと叱っておく
叱る時は名前で
「暗黙の強化」
ワンマン上司操縦法はまず「言い分」を受け入れること
一旦受け入れてから指示を仰ぐ
「では,どうしましょうか」
☆「過労死防止基本法の制定運動」大阪大学大学院教授 小野田正利 (『内外教育』2012年4月13日号「普通の教師が生きる学校-モンスター・ペアレント論を超えて」より)【再掲載 2012.4】
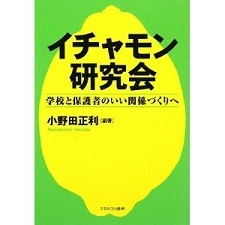
◇ポイント
① 働く意義と、人間の尊さを両立させることが難しくなってしまった国・ニッポン
② 働く教師、教え子を社会に送り出す教師として、この事実を受け止めてほしい
③ 今、過労死防止基本法の制定を求める運動が進められている
◇父さんが死んでしまう前の日に
《大きくなったら
ぼくは博士になりたい
そしてドラえもんに出てくるような
タイムマシーンをつくる
ぼくはタイムマシーンにのって
お父さんの死んでしまう
まえの日に行く
そして「仕事に行ったらあかん」ていうんや》
「ぼくの夢」と題されたこの詩は、父親を過労自殺で亡くしたマーくん(当時小学校1
年生)が書いたものだ。
これを前面に出しながら、今、全国各地で、過労死防止基本法の制定のための運動が展
開されていることをご存じだろうか。
「いのちより、家族より、大事な仕事って、何ですか?」
◇人間の尊厳のために
私は次のようなメーツセージを寄せた。
○○○○○
私は教育学者の一人として、学校や教師達の働きぶりや生活実態を調査してきました。
今の学校と教職員は過労死水準をはるかに超えています。
朝早くから夜遅くまで、土日も部活指導で馬車馬のように働いていて、アップアップの
状態にあります。
2つの数字がそのことを物語っています。
① 業務の拡大と複雑化が進行し、病み倒れていく者はあとをたちません。
公立学校に限定した数字ですが、病気休職者8000人超、うち精神性疾患5000人超の
背後には、その3倍ほどの2~3か月の病気休暇者がおり、さらに数倍の危険水域にあ
る者がいると思われます。
そして毎年100人近い教員が自殺しているとされます。
② 1971年からの教職調整手当は、残業時間はどれだけあっても、月額で本給に対して
4%上乗せをすることで打ち切りとなっています。
当時は月平均で8時間の残業だったからです。
しかし2006年の調査結果は、1日の労働時間ですら11時間。
これだけで、いかに無茶な実態であるかか分かるでしょう。
必至で善であると進められてきた矢継ぎ早の「教育改革」の嵐(教育改革病)は、確実
に教師から「子どもと触れ合い向き合う=教師としての自信を取り戻す時間」を奪って
いった。
そして、本来は協業文化で子どもを見ていたものが、個業から孤業へと移りゆきます。
極限的多忙から、疲労感、徒労感が、その身を包んでいます。
民間企業もおかしい、公務労働もおかしい状態がまかり通ることは、社会の危機と思い
ます。ぜひ「過労死防止基本法」を制定する緊急性があると強く思います。人間の尊厳の
ために
○○○○○
過労死防止基本法は、
① 過労死はあってはならないことを、国が宣言する
② 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にする
③ 国は、過労死に間する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行う
ことを求めている。
過労死防止基本法については、インターネットの検索サイトで「過労死防止基本法の制
定をめざす実行委員会」のホームページにアクセスしていただければ、詳細な情報と署名
用紙のダウンロードが可能なので、ぜひ広めていただくことをお願いしたい。
それは私たちの問題だけでなく、私たちにつながる人々の問題でもあり、これから生ま
れ来る次の世代への財産でもあると思うから。



