「小林秀雄学生との対談」国民文化研究会 新潮社 2014年 /「社会主義行政を全面的に見直すこと」 榊原英資 (『教育改革は改革か』土居建郎編 PHP 2001年より ④)【再掲載 2011.10】 [読書記録 一般]
今回は、国民文化研究所の
「小林秀雄との対談」を紹介します。
小林秀雄さんと聞くと「受験」を思い出します。
入学試験、模擬試験の問題によく出されていました。
難しいというイメージをもっていましたが、
この本はわかりやすく感じました。
自分が成長したのか、対話形式だからか… もちろん後者でしょうが。
出版社の案内には、
「『さあ、何でも聞いて下さい』と〈批評の神様〉は語りかけた。伝説の対話、初の公刊! 『僕ばかりに喋らさないで、諸君と少し対話しようじゃないか』――。昭和36年から
53年にかけて、小林秀雄は真夏の九州の『学生合宿』に5回訪れた。そこで行われた
火の出るような講義と真摯極まる質疑応答。〈人生の教室〉の全貌がいま明らかになる。
小林秀雄はかくも親切で、熱く、面白く、分かりやすかった!」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「大和魂をもった人 とは 人間のことをよく知った優しい正直な人」
・「もともと大和心は『もののあはれ』←→大和魂と武士道を結び付けたのは平田篤胤」
・「理性は科学をいつも批判しなければいけない。科学は人間が思いついた1つにしか過
ぎない」
・「パスカルの『人間は考える葦である』とは、人間は葦のごとく弱い存在だが、そうい
う人間の分際であるというものを忘れずにものを考えなければならぬということ」
・「苦しくない喜びなんてありませんよ。困難があるから面白いのです」
もう一つ、再掲載となりますが、榊原英資さんの
「社会主義行政を全面的に見直すこと」((『教育改革は改革か』PHP 2001年④)
を載せます。
中央集権、全面規制の体質は20年経っても変わっていないように感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「小林秀雄学生との対談」国民文化研究会 新潮社 2014年
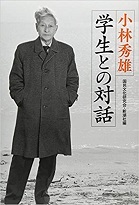
◇はじめに
「うまく問題を出す訓練」
-「うまく質問する」
「意味と同時に言葉を植え付ける」会話
「会話教育」と「質問教育」
S36~S53 九州各地「全国学生合宿」
◇文学の雑感
□本居宣長
「古事記伝」に35年間 出版は死後
「敷島の大和心を人問わば朝日に匂う山桜花」
山桜 - 花と葉が一緒に出る
88%がソメイヨシノ - 明治になってから 育てやすい
一流の山桜を希望
「大和心」平安期の言葉 学問ではなく、もっと生活的な知恵を言う
= 生きた知恵、常識をもつこと
大和魂をもった人 = 人間のことをよく知った優しい正直な人
□「源氏物語」
- 女性の手
男は学問にかまいて大和心をなくしてしまっていた
□「古事記伝」
訳は宣長の直感力と想像力
もともと大和心は「もののあはれ」
大和魂と武士道を結び付けたのは平田篤胤
宣長の学問の目的
= 古の手ぶり口ぶりを目の当たりに見ることができる
現在の心の中に生きなければ歴史ではない
◇信ずること知ること
□現代のインテリは不思議を不思議とする素直な心を失っている
|
科学は始まってからまだ3000,4000年しか経っていない
科学の言う経験は「合理的経験」
| 感情もイマジネーションも道徳的な経験も外している
◎ 科学は数学がなければ成り立たない
□ベルグゾン
「精神と脳髄の運動は並行しない」
~ 指揮棒が脳髄の動きで音は精神
人間の脳髄は現実世界に対する注意の器官
→ 便利な記憶だけ選んで選んで思い出させるようにしている
無意識はいつでも人間の中にかくれている
記憶と脳髄の運動は並列していない - 独立
科学は進歩したけれども
「僕らが生きていくための知恵というものはどれだけ進歩していますか?」
|
◎ 理性は科学をいつも批判しなければいけない
◎ 科学は人間が思いついた1つにしか過ぎない
□柳田國男「故郷七十年」
科学の方法みたいな狭苦しい方法では民俗学という学問はできない
|
ひよどりが鳴かなかったら発狂するというような神経をもたなければ民俗学はできない
∥
感受性
◎「諸君はみんな自分の親しい人の魂をもって生きています」
平凡だけどリアルなこと
|
◎ 現代のインテリにはなかなかこういう健全な思想がもてない
柳田國男「山の人生」
あまりに言葉が多すぎる現代
|
○信ずるということは自分流に信ずるということ
○責任をとること
↓
◎信ずる心を失うと責任をとらなくなる
集団的になる
□本居宣長 「物知り(インテリ)」人を実に嫌っている
◎ 日本というのはぼくの心の中にある
◎ 自分に都合がよいことだけを考えるのがインテリ。インテリには反省がない。信ず
る能力を失った。
「考える」 = かむかふ
身 変わる
自分が身をもって相手と交わる = 付き合う
パスカル 「人間は考える葦である」
※ 人間は葦のごとく弱い存在だが、そういう人間の分際であるというものを忘れ
ずにものを考えなければならぬ。
◇「現代思想について」後の学生との対話
無意識心理学
精神現象と物理現象は違うが、密接な関係がある
実在の<関係性>を調べるのが科学
ベルグゾン
8年間 精神と肉体との関係を考えた
宣長の信念
「古人のような考え方でこの世を生きることが正しいのではないか」
武士道というのは「いいかおまえはインテリなのだ」という思想
インテリ = 特権階級 - 責任をもった階級
学問をしたいというのは人間の本能
|
伊藤仁斎
独学 -京都で塾
アカデミーの学問に大反対
「学問とは人間がどうやって生活するか生きざまを教えるもの」
|
「教師が現れる」こと
◎ 魂はうつるんだよ
◎直感 → 分析
×分析 → 直感
◇「常識について」後の学生との対話
現代の教育に一番欠けているのは感情の教育(情操教育)
「苦しくない喜びなんてありませんよ。困難があるから面白いのです」
学問には必ず自得しなければいけないものがある
☆「社会主義行政を全面的に見直すこと」 榊原英資 (『教育改革は改革か』土居建郎編 PHP 2001年より ④)【再掲載 2011.10】
[出版社の案内]
「教育改革」と叫ばれて久しいが、何をどう変えればよいのか。現下の教育問題を10大論
点に分け、10人の識者が独自の分析・提言を行う。
学級崩壊、少年犯罪、不登校、ひきこもり、文部科学行政、学力低下、大学再建、教師改
革、偏向教育、宗教教育、道徳教育・・・。文部科学省や教育学者には、もう任せておけ
ない!各界の識者が、子どもを救うため大論争を繰り広げる。

<文部科学行政>
◇「社会主義行政」を全面的に見直すこと 榊原英資
□榊原英資
1941年神奈川県生 東京大学経済学部卒 1965 年大蔵省入り
現在慶応大学教授「ミスター円」
□イデオロギー論争のせいで無視されてきた制度問題
□法令改革にエネルギーを集中すべき
学校教育法 - 行政分野の基本法
教育基本法 - 準憲法、憲法付属法の性格
教基法の改革は憲法改正の一部として行われるべき
↓
◎教育改革 - 学校教育法等にエネルギー集中が得策
□中央集権、全面規制でよいのか?
「どの程度の規制と監督が大切か」
① どのような規制監督を中央が行い、どこまでを地方教育委員会に委ねるか
地方教育委員会からどの程度校長等に委ねるか
② どの程度を市場の原理、市場の競争に委ねるか - イギリス
<英米>
全国レベルでの教育スタンダードを設定し、それを達成するという結果責任(アカウン
タビリティ)を課した上で、徹底的分権と規制を緩和するといった方式
↑↓
<日本>
全国標準の設定は英米に先行しているが、ここ20年弱この標準レベルを継続的に低下
させ、またそれが達成されているかどうかの評価が全くされていない
△(全国レベルでの試験が全くされていない)点が大きな問題点
|
さらに問題なのは、こうした標準を達成するための手段(例えば教科の詳細、教科書の
検定等)を細部に渡って規制し、各地域あるいは各学校の独自性を限られた範囲でしか認
めていない
|
(榊原の評価)
全国一律のスタンダードを創りながら、その成果についての評価をすることもなく、ス
タンダードのレベルを継続的且つ大幅に削減せざるを得ないというのは、日本の教育シス
テムが破綻している、しつつある明確な証拠
∥
全国的な規制システムのもとで成果が上がっているというのなら、イデオロギー的に市
場メカニズムの利用を説く必要はない。しかし、中央集権、全面規制というシステムが機
能不全を起こしつつあるのなら話は別である
↓
◎文部科学省の社会主義行政もまた全面的に見直されなければならない
□学校教育の目的は「勉強させること」
◎学校教育の改革に限定すべき!
家庭や職場、コミュニティで行われる教育は当面改革の対象とはしない
学校教育の目的「生きる力の育成」は的はずれ
※的はずれだという理由
①「生きる力」が具体的に何であるか明確に定義できない
= 達成が確認できない 評価ができない
↓
◎ 現状を具体的には何も変えたくないと言う潜在的願望の表れ
②「生きる力」という概念が反知育的勉強否定論のニュアンスを多分に持っている
|
文部科学省
「知育に費やす時間とエネルギーを他に向ける」
<学校教育の本来の目的> - 榊原
日本という国家において社会生活を送るために最低限必要な知識を身に付け(主として
初等中等教育)、さらにその知識をベースに自ら学び、ものを考える習慣(主として高等教
育)を付けさせることである
∥
◎ 学校教育の目的は、主として知識を身に付けさせることであり、学力を付け、さらに
その水準を向上させることでなくてはならない。要するに勉強させることであり、徳育
も体育も勉強の一部である。
□分権 + 規制緩和 + 文科省の役割強化を!
教育改革の目的を知育と学力の水準の向上に絞る
・日本の教育行政をどう変えていくのか
・学校教育法及びその関連法令をどのように変えていったらよいのか
↓
ナショナルスタンダードを明確にし、定期的に全国試験を実施し、その結果を県市町村の教育委員会ごと、また個別の学校ごとに公表することが適切であろう
∥
◎ 徹底的な分権と規制の緩和を行う反面、スタンダードの設定とそれに基づく評価につ
いては文科省の役割を強化する
|
◎ 小中教科について文科大臣がこれを定めるという規定を削除し、これを各教委あるい
は学校に任せることにするのが適切であろう。ただし、文科省は最低基準としての学習
指導要領を作成し、全国試験をそれに基づいて実施し評価すればよい
◎ 教員の人事権は各学校に委任すべき
|
経営陣のチェックは別途評議会が行う、また文科省も透明な評価基準を策定し、それ
ぞれの大学の評価を基準に基づいて行い公表する
「小林秀雄との対談」を紹介します。
小林秀雄さんと聞くと「受験」を思い出します。
入学試験、模擬試験の問題によく出されていました。
難しいというイメージをもっていましたが、
この本はわかりやすく感じました。
自分が成長したのか、対話形式だからか… もちろん後者でしょうが。
出版社の案内には、
「『さあ、何でも聞いて下さい』と〈批評の神様〉は語りかけた。伝説の対話、初の公刊! 『僕ばかりに喋らさないで、諸君と少し対話しようじゃないか』――。昭和36年から
53年にかけて、小林秀雄は真夏の九州の『学生合宿』に5回訪れた。そこで行われた
火の出るような講義と真摯極まる質疑応答。〈人生の教室〉の全貌がいま明らかになる。
小林秀雄はかくも親切で、熱く、面白く、分かりやすかった!」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「大和魂をもった人 とは 人間のことをよく知った優しい正直な人」
・「もともと大和心は『もののあはれ』←→大和魂と武士道を結び付けたのは平田篤胤」
・「理性は科学をいつも批判しなければいけない。科学は人間が思いついた1つにしか過
ぎない」
・「パスカルの『人間は考える葦である』とは、人間は葦のごとく弱い存在だが、そうい
う人間の分際であるというものを忘れずにものを考えなければならぬということ」
・「苦しくない喜びなんてありませんよ。困難があるから面白いのです」
もう一つ、再掲載となりますが、榊原英資さんの
「社会主義行政を全面的に見直すこと」((『教育改革は改革か』PHP 2001年④)
を載せます。
中央集権、全面規制の体質は20年経っても変わっていないように感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「小林秀雄学生との対談」国民文化研究会 新潮社 2014年
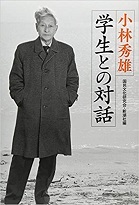
◇はじめに
「うまく問題を出す訓練」
-「うまく質問する」
「意味と同時に言葉を植え付ける」会話
「会話教育」と「質問教育」
S36~S53 九州各地「全国学生合宿」
◇文学の雑感
□本居宣長
「古事記伝」に35年間 出版は死後
「敷島の大和心を人問わば朝日に匂う山桜花」
山桜 - 花と葉が一緒に出る
88%がソメイヨシノ - 明治になってから 育てやすい
一流の山桜を希望
「大和心」平安期の言葉 学問ではなく、もっと生活的な知恵を言う
= 生きた知恵、常識をもつこと
大和魂をもった人 = 人間のことをよく知った優しい正直な人
□「源氏物語」
- 女性の手
男は学問にかまいて大和心をなくしてしまっていた
□「古事記伝」
訳は宣長の直感力と想像力
もともと大和心は「もののあはれ」
大和魂と武士道を結び付けたのは平田篤胤
宣長の学問の目的
= 古の手ぶり口ぶりを目の当たりに見ることができる
現在の心の中に生きなければ歴史ではない
◇信ずること知ること
□現代のインテリは不思議を不思議とする素直な心を失っている
|
科学は始まってからまだ3000,4000年しか経っていない
科学の言う経験は「合理的経験」
| 感情もイマジネーションも道徳的な経験も外している
◎ 科学は数学がなければ成り立たない
□ベルグゾン
「精神と脳髄の運動は並行しない」
~ 指揮棒が脳髄の動きで音は精神
人間の脳髄は現実世界に対する注意の器官
→ 便利な記憶だけ選んで選んで思い出させるようにしている
無意識はいつでも人間の中にかくれている
記憶と脳髄の運動は並列していない - 独立
科学は進歩したけれども
「僕らが生きていくための知恵というものはどれだけ進歩していますか?」
|
◎ 理性は科学をいつも批判しなければいけない
◎ 科学は人間が思いついた1つにしか過ぎない
□柳田國男「故郷七十年」
科学の方法みたいな狭苦しい方法では民俗学という学問はできない
|
ひよどりが鳴かなかったら発狂するというような神経をもたなければ民俗学はできない
∥
感受性
◎「諸君はみんな自分の親しい人の魂をもって生きています」
平凡だけどリアルなこと
|
◎ 現代のインテリにはなかなかこういう健全な思想がもてない
柳田國男「山の人生」
あまりに言葉が多すぎる現代
|
○信ずるということは自分流に信ずるということ
○責任をとること
↓
◎信ずる心を失うと責任をとらなくなる
集団的になる
□本居宣長 「物知り(インテリ)」人を実に嫌っている
◎ 日本というのはぼくの心の中にある
◎ 自分に都合がよいことだけを考えるのがインテリ。インテリには反省がない。信ず
る能力を失った。
「考える」 = かむかふ
身 変わる
自分が身をもって相手と交わる = 付き合う
パスカル 「人間は考える葦である」
※ 人間は葦のごとく弱い存在だが、そういう人間の分際であるというものを忘れ
ずにものを考えなければならぬ。
◇「現代思想について」後の学生との対話
無意識心理学
精神現象と物理現象は違うが、密接な関係がある
実在の<関係性>を調べるのが科学
ベルグゾン
8年間 精神と肉体との関係を考えた
宣長の信念
「古人のような考え方でこの世を生きることが正しいのではないか」
武士道というのは「いいかおまえはインテリなのだ」という思想
インテリ = 特権階級 - 責任をもった階級
学問をしたいというのは人間の本能
|
伊藤仁斎
独学 -京都で塾
アカデミーの学問に大反対
「学問とは人間がどうやって生活するか生きざまを教えるもの」
|
「教師が現れる」こと
◎ 魂はうつるんだよ
◎直感 → 分析
×分析 → 直感
◇「常識について」後の学生との対話
現代の教育に一番欠けているのは感情の教育(情操教育)
「苦しくない喜びなんてありませんよ。困難があるから面白いのです」
学問には必ず自得しなければいけないものがある
☆「社会主義行政を全面的に見直すこと」 榊原英資 (『教育改革は改革か』土居建郎編 PHP 2001年より ④)【再掲載 2011.10】
[出版社の案内]
「教育改革」と叫ばれて久しいが、何をどう変えればよいのか。現下の教育問題を10大論
点に分け、10人の識者が独自の分析・提言を行う。
学級崩壊、少年犯罪、不登校、ひきこもり、文部科学行政、学力低下、大学再建、教師改
革、偏向教育、宗教教育、道徳教育・・・。文部科学省や教育学者には、もう任せておけ
ない!各界の識者が、子どもを救うため大論争を繰り広げる。

<文部科学行政>
◇「社会主義行政」を全面的に見直すこと 榊原英資
□榊原英資
1941年神奈川県生 東京大学経済学部卒 1965 年大蔵省入り
現在慶応大学教授「ミスター円」
□イデオロギー論争のせいで無視されてきた制度問題
□法令改革にエネルギーを集中すべき
学校教育法 - 行政分野の基本法
教育基本法 - 準憲法、憲法付属法の性格
教基法の改革は憲法改正の一部として行われるべき
↓
◎教育改革 - 学校教育法等にエネルギー集中が得策
□中央集権、全面規制でよいのか?
「どの程度の規制と監督が大切か」
① どのような規制監督を中央が行い、どこまでを地方教育委員会に委ねるか
地方教育委員会からどの程度校長等に委ねるか
② どの程度を市場の原理、市場の競争に委ねるか - イギリス
<英米>
全国レベルでの教育スタンダードを設定し、それを達成するという結果責任(アカウン
タビリティ)を課した上で、徹底的分権と規制を緩和するといった方式
↑↓
<日本>
全国標準の設定は英米に先行しているが、ここ20年弱この標準レベルを継続的に低下
させ、またそれが達成されているかどうかの評価が全くされていない
△(全国レベルでの試験が全くされていない)点が大きな問題点
|
さらに問題なのは、こうした標準を達成するための手段(例えば教科の詳細、教科書の
検定等)を細部に渡って規制し、各地域あるいは各学校の独自性を限られた範囲でしか認
めていない
|
(榊原の評価)
全国一律のスタンダードを創りながら、その成果についての評価をすることもなく、ス
タンダードのレベルを継続的且つ大幅に削減せざるを得ないというのは、日本の教育シス
テムが破綻している、しつつある明確な証拠
∥
全国的な規制システムのもとで成果が上がっているというのなら、イデオロギー的に市
場メカニズムの利用を説く必要はない。しかし、中央集権、全面規制というシステムが機
能不全を起こしつつあるのなら話は別である
↓
◎文部科学省の社会主義行政もまた全面的に見直されなければならない
□学校教育の目的は「勉強させること」
◎学校教育の改革に限定すべき!
家庭や職場、コミュニティで行われる教育は当面改革の対象とはしない
学校教育の目的「生きる力の育成」は的はずれ
※的はずれだという理由
①「生きる力」が具体的に何であるか明確に定義できない
= 達成が確認できない 評価ができない
↓
◎ 現状を具体的には何も変えたくないと言う潜在的願望の表れ
②「生きる力」という概念が反知育的勉強否定論のニュアンスを多分に持っている
|
文部科学省
「知育に費やす時間とエネルギーを他に向ける」
<学校教育の本来の目的> - 榊原
日本という国家において社会生活を送るために最低限必要な知識を身に付け(主として
初等中等教育)、さらにその知識をベースに自ら学び、ものを考える習慣(主として高等教
育)を付けさせることである
∥
◎ 学校教育の目的は、主として知識を身に付けさせることであり、学力を付け、さらに
その水準を向上させることでなくてはならない。要するに勉強させることであり、徳育
も体育も勉強の一部である。
□分権 + 規制緩和 + 文科省の役割強化を!
教育改革の目的を知育と学力の水準の向上に絞る
・日本の教育行政をどう変えていくのか
・学校教育法及びその関連法令をどのように変えていったらよいのか
↓
ナショナルスタンダードを明確にし、定期的に全国試験を実施し、その結果を県市町村の教育委員会ごと、また個別の学校ごとに公表することが適切であろう
∥
◎ 徹底的な分権と規制の緩和を行う反面、スタンダードの設定とそれに基づく評価につ
いては文科省の役割を強化する
|
◎ 小中教科について文科大臣がこれを定めるという規定を削除し、これを各教委あるい
は学校に任せることにするのが適切であろう。ただし、文科省は最低基準としての学習
指導要領を作成し、全国試験をそれに基づいて実施し評価すればよい
◎ 教員の人事権は各学校に委任すべき
|
経営陣のチェックは別途評議会が行う、また文科省も透明な評価基準を策定し、それ
ぞれの大学の評価を基準に基づいて行い公表する



