林間学校・野外活動① -『野外活動プログラム集』齋藤哲瑯 船橋明男 黎明書房 1991 『野外活動の計画と展開』全国少年自然の家連絡協議会 第一法規1980、『野外活動』日本野外教育研究会 杏林書院 2001 などから / 「考える日々Ⅱ」池田晶子 毎日新聞社 1999年【再掲載 2012.1】 [読書記録 教育]
今回は、8月15日に続いて、
「林間学校 野外活動」の紹介 2回目です。
読書した本を要約した、わたしの「教育ノート」からの記事です。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「空間的なゆとりと時間的ゆとりを!」
・「生活はゆったり,食事はおいしく,睡眠は十分に,そして活動は厳しく」
・「野外活動施設は『子どもの放牧場』 = 過保護からの脱却」
・「小学生の発達課題は活動性、中学生の発達課題は自発性」
もう一つ、再掲載となりますが、池田晶子さんの
「考える日々Ⅱ」を載せます。
-幸福は欲するものではなく気が付くものだ
そうだなあと感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆林間学校・野外活動① -『野外活動プログラム集』齋藤哲瑯 船橋明男 黎明書房 1991 『野外活動の計画と展開』全国少年自然の家連絡協議会 第一法規1980、『野外活動』日本野外教育研究会 杏林書院 2001 などから
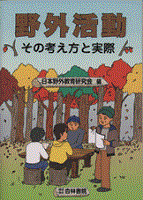
◇楽しい野外活動プログラムを作ろう
□野外活動の目的
① 普段,家庭や学校では体験できない多くのことを体験させる
キャンプ,奉仕活動など
② 自然と接触することによって心身のリフレッシュができること
日の出の観察,バード・ウォッチングなど
③ 集団による宿泊生活を通して人間関係の醸成を図ること
共同宿泊,野外炊飯,入浴
④ 人間と自然との関係を知り,環境を大事にする心を育てること
森林と水との関係,自然観察など
1 子どもが主役
2 自然は子ども達の情感を刺激する
3 小グループによる活動が体験を豊かにする
「空間的なゆとり」 と 「時間的ゆとり」 を
4「生活はゆったり,食事はおいしく,睡眠は十分に,そして活動は厳しく」
5 子ども達の体験の実態や能力を事前に知ること
地図の読み方
6 野外活動は総合的な教育活動
□プログラムの分類
① 自然体験的学習活動
② 勤労体験的学習活動
③ 歴史・文化的学習活動
④ 生活体験的学習活動
⑤ スポーツ・レクリエーション的学習活動
[例]
・手紙を書いたことがない
→ 親に手紙を
・ハイキング
身体的活動主か自然観察主か
・夜道歩行
暗闇懐中電灯で歩行
◇野外活動
野外活動施設は「子どもの放牧場」
→ 過保護からの脱却
発達課題
小学生 = 「活動性」
→ 自分から体を動かす
中学生 = 「自発性」
→ 目的意識を明確に
◇野外活動のマネジメント
「マネジメント イズ オール」
<事前マネジメント>
○ 活動場所の選定
○ 活動場所の安全チェック
○ 交通手段の決定と手配
○ 備品の手配とチェック
備品の個数,種類等のチェック
貸し出し返品等の管理運営方法の手配
○ 食事の計画と手配
○ 記録の手配
○ 実施要録(案内・ガイドブック)の作成
○ 全体費用の概算及び個人参加費の算出
○ 医療関係の手配及び旅行傷害保険加入の手続き
○ 参加申込書や個人調査書,必要に応じてアンケート等の作成
○ 参加者名簿の作成
(詳細な個人内容も,必要に応じて一覧表にする)
<活動直前から活動中のマネジメント>
○ マネジメントセンターや備品庫の設置
○ 活動センター(本部・医務センターなど)の設置
○ 備品の搬入,配置
○ 備品使用に関する指導
○ 安全指導と管理
○ 医務関係の手配とインフォメーションおよび指導
○ 各活動のエリア確保
○ 各活動別の備品の準備と使用上の注意
○ 安全な飲料水の確保
○ 燃料の手配とその指導
○ 生ゴミなど様々なごみ処理の手配とその指導
○ トイレの清掃と手洗いの指導
○ 夜間照明のチェックと手配
○ 食料の買い出しと管理,配布などの手配と指導
<活動後のマネジメント>
○ 備品の清掃とチェック,収納
○ 医務関係の在庫や薬効期限などのチェック及び引き継ぎメモの作成
○ 会計決算,報告
○ 記録の整理
○ 報告書の作成
☆「考える日々Ⅱ」池田晶子 毎日新聞社 1999年【再掲載 2012.1】
<出版社の案内>
生が存在するのはなぜなのか。それは考えているからだ。世は謎を巡る。千年紀の終わり、
通り過ぎた日々へ、今いちど。哲学=考えることの光を。
いったい何が悲しうてわれわれは、この惑星の、この人生にしがみついているのだろうか。
われわれはいったい「何を」欲して、「何を」しているのだろうか…。『サンデー毎日』
連載中の、「形而上時評」の単行本化。
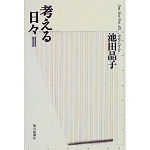
◇池田晶子さん
1960年東京生 文筆家 慶大哲学科卒
専門用語によらない哲学実践の表現開拓
◇幸福は欲するのではなく
欲すると言うことが不幸
= 幸福は欲するものではなく気が付くものだ
◎ 自分が誰だか分からないと気が付くことこそ幸福である。そのとき,自分が宇宙そ
のものだと知るから…。
◇団結したのは資本であった
21世紀は壮大なる大失敗
IT化
→ 便利になった時間は愚劣なレジャーに使うぐらいしかない
= 人間の痴呆化
※ 夢のインターネットの時代は知能の暗黒時代である。
人間の条件は「生きて死ぬこと」
◇廃棄大処分の悦び
不要なものを捨てること
不要な人は廃棄する
→ 人から廃棄されないように努める
↑
◎ 各自にそういう覚悟が
◇「世代論」の腹立たしさ
団塊の世代 - 全共闘世代
◎「われわれは」か?「私は」か?
◇お金を巡る「普通」の心証
金がほしい
→ 働く ○
→ 殺人する ×
◇生きることに「理由」があるか
なぜ生きているのか
→ 生まれたからだ
◇金
マネーでなくお金
= ものと遊離すべきではない
◇教育
教育が変わらなければ社会は変わり得ない。しかし,社会が変わらなければ教育も変わ
らない。
◎ 教育 = 社会
◇「見える死」を見せてみろ
脳死は死 と 脳死は人の死
↓
見えないもの
死は言葉である
◇少子化とは誰の問題か
「産み損」
- 計算 出産が損得になってしまった
↓
◎ 生まれた子も損得に生きる
◎ 死ぬときは一人で死ねばいいではないか
= だからこそ生きることが自由
「林間学校 野外活動」の紹介 2回目です。
読書した本を要約した、わたしの「教育ノート」からの記事です。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「空間的なゆとりと時間的ゆとりを!」
・「生活はゆったり,食事はおいしく,睡眠は十分に,そして活動は厳しく」
・「野外活動施設は『子どもの放牧場』 = 過保護からの脱却」
・「小学生の発達課題は活動性、中学生の発達課題は自発性」
もう一つ、再掲載となりますが、池田晶子さんの
「考える日々Ⅱ」を載せます。
-幸福は欲するものではなく気が付くものだ
そうだなあと感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆林間学校・野外活動① -『野外活動プログラム集』齋藤哲瑯 船橋明男 黎明書房 1991 『野外活動の計画と展開』全国少年自然の家連絡協議会 第一法規1980、『野外活動』日本野外教育研究会 杏林書院 2001 などから
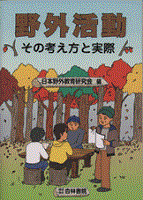
◇楽しい野外活動プログラムを作ろう
□野外活動の目的
① 普段,家庭や学校では体験できない多くのことを体験させる
キャンプ,奉仕活動など
② 自然と接触することによって心身のリフレッシュができること
日の出の観察,バード・ウォッチングなど
③ 集団による宿泊生活を通して人間関係の醸成を図ること
共同宿泊,野外炊飯,入浴
④ 人間と自然との関係を知り,環境を大事にする心を育てること
森林と水との関係,自然観察など
1 子どもが主役
2 自然は子ども達の情感を刺激する
3 小グループによる活動が体験を豊かにする
「空間的なゆとり」 と 「時間的ゆとり」 を
4「生活はゆったり,食事はおいしく,睡眠は十分に,そして活動は厳しく」
5 子ども達の体験の実態や能力を事前に知ること
地図の読み方
6 野外活動は総合的な教育活動
□プログラムの分類
① 自然体験的学習活動
② 勤労体験的学習活動
③ 歴史・文化的学習活動
④ 生活体験的学習活動
⑤ スポーツ・レクリエーション的学習活動
[例]
・手紙を書いたことがない
→ 親に手紙を
・ハイキング
身体的活動主か自然観察主か
・夜道歩行
暗闇懐中電灯で歩行
◇野外活動
野外活動施設は「子どもの放牧場」
→ 過保護からの脱却
発達課題
小学生 = 「活動性」
→ 自分から体を動かす
中学生 = 「自発性」
→ 目的意識を明確に
◇野外活動のマネジメント
「マネジメント イズ オール」
<事前マネジメント>
○ 活動場所の選定
○ 活動場所の安全チェック
○ 交通手段の決定と手配
○ 備品の手配とチェック
備品の個数,種類等のチェック
貸し出し返品等の管理運営方法の手配
○ 食事の計画と手配
○ 記録の手配
○ 実施要録(案内・ガイドブック)の作成
○ 全体費用の概算及び個人参加費の算出
○ 医療関係の手配及び旅行傷害保険加入の手続き
○ 参加申込書や個人調査書,必要に応じてアンケート等の作成
○ 参加者名簿の作成
(詳細な個人内容も,必要に応じて一覧表にする)
<活動直前から活動中のマネジメント>
○ マネジメントセンターや備品庫の設置
○ 活動センター(本部・医務センターなど)の設置
○ 備品の搬入,配置
○ 備品使用に関する指導
○ 安全指導と管理
○ 医務関係の手配とインフォメーションおよび指導
○ 各活動のエリア確保
○ 各活動別の備品の準備と使用上の注意
○ 安全な飲料水の確保
○ 燃料の手配とその指導
○ 生ゴミなど様々なごみ処理の手配とその指導
○ トイレの清掃と手洗いの指導
○ 夜間照明のチェックと手配
○ 食料の買い出しと管理,配布などの手配と指導
<活動後のマネジメント>
○ 備品の清掃とチェック,収納
○ 医務関係の在庫や薬効期限などのチェック及び引き継ぎメモの作成
○ 会計決算,報告
○ 記録の整理
○ 報告書の作成
☆「考える日々Ⅱ」池田晶子 毎日新聞社 1999年【再掲載 2012.1】
<出版社の案内>
生が存在するのはなぜなのか。それは考えているからだ。世は謎を巡る。千年紀の終わり、
通り過ぎた日々へ、今いちど。哲学=考えることの光を。
いったい何が悲しうてわれわれは、この惑星の、この人生にしがみついているのだろうか。
われわれはいったい「何を」欲して、「何を」しているのだろうか…。『サンデー毎日』
連載中の、「形而上時評」の単行本化。
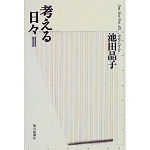
◇池田晶子さん
1960年東京生 文筆家 慶大哲学科卒
専門用語によらない哲学実践の表現開拓
◇幸福は欲するのではなく
欲すると言うことが不幸
= 幸福は欲するものではなく気が付くものだ
◎ 自分が誰だか分からないと気が付くことこそ幸福である。そのとき,自分が宇宙そ
のものだと知るから…。
◇団結したのは資本であった
21世紀は壮大なる大失敗
IT化
→ 便利になった時間は愚劣なレジャーに使うぐらいしかない
= 人間の痴呆化
※ 夢のインターネットの時代は知能の暗黒時代である。
人間の条件は「生きて死ぬこと」
◇廃棄大処分の悦び
不要なものを捨てること
不要な人は廃棄する
→ 人から廃棄されないように努める
↑
◎ 各自にそういう覚悟が
◇「世代論」の腹立たしさ
団塊の世代 - 全共闘世代
◎「われわれは」か?「私は」か?
◇お金を巡る「普通」の心証
金がほしい
→ 働く ○
→ 殺人する ×
◇生きることに「理由」があるか
なぜ生きているのか
→ 生まれたからだ
◇金
マネーでなくお金
= ものと遊離すべきではない
◇教育
教育が変わらなければ社会は変わり得ない。しかし,社会が変わらなければ教育も変わ
らない。
◎ 教育 = 社会
◇「見える死」を見せてみろ
脳死は死 と 脳死は人の死
↓
見えないもの
死は言葉である
◇少子化とは誰の問題か
「産み損」
- 計算 出産が損得になってしまった
↓
◎ 生まれた子も損得に生きる
◎ 死ぬときは一人で死ねばいいではないか
= だからこそ生きることが自由



