「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」 毎日新聞社 2003年 / 「米津浜の松風」井口周治 著者私家版 2006年 ①②【再掲載 2014.12】 [読書記録 一般]
今回は、毎日新聞出版の
「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」を紹介します。
滋賀県の和菓子やさん「たねや」はよく知られていますね。
もともとは種を販売する「種屋」さんだったそうですが、
今では洋菓子でも知られています。
「ふくみ天平」最中が好きです。
創業地は近江八幡市。言われて気が付く近江商人ということですね。
たねや社長の山本徳次さんの言葉を集めた本ですが、おもしろく読みました。
メモにとっておいた、覚えておきたいいくつかの言葉を紹介します。
出版社の案内には
「すべては最善のおもてなしのために-。近江八幡から全国へと躍進した和菓子メーカー
『たねや』の、こだわりの商道を紹介する。」
とあります。
もう一つ、再掲載となりますが、井口周治さんの
「米津浜の松風」を載せます。
地域にある図書館の郷土コーナーで見つけて読みました。
郷土の話だけに、たいへん勉強になった本です。
以前2回に分けて紹介したものを、一つにまとめました。
井口周治さんの私家版で、地元の図書館に寄贈されたものです。
地域の話を本に著してくださったおかげで、読むことができました。
ありがたいことです。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」 毎日新聞社 2003年

デザイナーではなくアーティストになれ
経営者はばい菌をばらまいているようなもの
お菓子には物語がないといかん
農家が元気になってもらわんと困るのや
安心安全健康的ということ
店づくりはどこまでも本物志向
その地域で絶対的な信頼と支持を得る店
儲け急ぎはダメ すぐ数字に酔うてしまう
マイナス部分をいち早く報告すること
開発力・企画力が○○と販売とを橋渡しする
表の非効率と裏の効率化を柔軟に
情報は公開し共有により新たな情報を作り出す
中途半端な金を使うな
恥ずかしさが原点
経営者は孤独
人と反対の方へ行け
現場にヒントがあり改善点がある
母さん、おばあちゃんのおはぎがいちばん
若いときは特に汗を惜しむな
和菓子は水を洋菓子は空気を売りなさい
値を下げるな
五歳までに善悪を教え込む
無駄がプラスになる
迷ったらやめる
菓子は総合芸術
人にはばかることはしてはいかん
経営者に美意識がなかったらあかん
今日できたものは過去のもの 必ず欠点がある
こつこつの中に人間の信念が生まれてくる
季節には季節の物語がある
頭ばかり大きくなるな足が…?
迷ったら白に戻れ
雅ではなく鄙び
製造で儲けるは○?
原価積み上げはやめろ
総合力で販売
販売は非合理化 工場は合理化
鎧を着ては商売できない
商道は人道
ものを売る前に自分を売る
イノベーターになる
本式経営は近江商人が原点
後追いは絶対ダメ
名前を売りたいだけの広告ならやめる
人にだまされても自分からだますな
先義後利売れてるときがいちばんこわい
あるがままがいちばん
人の顔は人生の積み木
川下産業になりきること
◇たねや物語
近江八幡市和菓子メーカー「たねや」1872(明治5)創業
☆「米津浜の松風」井口周治 著者私家版 2006年 ①②【再掲載 2014.12】
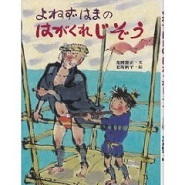
◇はじめに
<魚は獲れ>
□山を立てる
~ 遠方の山に目標物を重ねた延長線上に魚のよく獲れる漁場
□地引き網
(半農半漁=ハマコウ註)
□森茉莉
鴎外長女 「本当に金を使ってやる贅沢には空想と想像の歓びがない」
□貧乏 ~ 金銭に縁のない生活
その時あるものを食べ命を繋ぐことで,ある程度の満足を覚えることができれば,人間
に悩みも迷いも社会に
◇米津浜(よねづはま)の松風
□米津浜
花崗岩の砂 石英の粒,長石の粒,雲母の粒
□天竜川
かつては鹿島で二筋
東は「小天竜」
西は「大天竜」(現在の馬込川筋)
船越(渡船)地名が残る
↓
◎ 一筋になったのは江戸初期・慶安年中(1648-1651)
「彦助堤」による
□米津浜
~ 米津浜の権利は300mほど
□新津村米津海岸
大正14(1925)年5月
豊橋高射砲第一連隊の演習場に
昭和3(1928)年3月20日
豊橋第一連隊が和地山(浜松市)に
→ やがて御台場北に兵舎
昭和22(197)年9月より
「浜の中学校」 = 新津中学校
(~昭和27年3月まで浜に、それ以後現在の地に)
◇米津浜安泉寺と太田備中守資宗
□安泉寺
8代城主・太田備中守資宗を開祖 - 庇護
正保元(1644)~寛文11(1671) 27年間
「御前道」 → 「御台場道」 → 高射砲道路
御前=資宗?
堤の好徳寺より太田資宗の位牌が発見された
□安泉寺境内の地蔵堂
昭和55(1980)年3月に築造された「江戸送り地蔵尊」
白羽町の太田泰次氏が地蔵堂を無償で建立
◇米津の江戸送り地蔵
□安永2(1773)年秋
無実の罪で6人が江戸小塚原の刑場の露に
= 米津の義民
□昭和10(1935)年10月
安泉寺住職13世小林鶴洲師が土中より発見
台座に「安永2巳年難船ニ付江戸総代為菩提村中に…」
土中に160余年埋もれていた
総代 又三郎(隠居船) 半五郎(本船) 仙之助(六軒)
権兵衛(清三) 仁左衛門(中船) 寅之助(新船)
□安永の大難
安永2(1773)年の初秋
紀州御用船が座礁 不幸 = 紀州船だったこと
→ 荷の不足を訴えられる
古老の言い伝え
「下田港で豪遊し積み荷に手を付けたため,暴風雨のあったことをよいことに米津海
岸に座礁した」(口伝)
字名 - 地引き網船の名が小字名に転化した
※ 権力の前に否応なしに下手人を仕立てた
→ 「救うために200両調達せよ」(浜松藩)
◎ 63軒で200両を作った(それにもかかわらず全員刑場の露に)
※ 村人 ~ 土中で陰まつり (紛失)
↓
◎ 米津浜の自浜が狭いのは難破船を恐れて浜の権利を譲った
(漂着物届出の義務を避けるため)
□昭和29年10月6日
市史編纂室 馬渕紫陽「米津地蔵由来記」「夢枕」
□昭和33年10月
渥美実「土のいろ」
※松島町(浜松市)でも同様のことが‥
寛政12(1799)年正月
紀州船が松嶋村の海岸に漂着した際,荷物を内分にて処理したという理由で庄屋,
組頭,百姓代の三人が江戸に送られ,米津のように亡くなっている。
|
◎しかし,松嶋村ではすでに風化してしまっている
□新津小元校長(昭和16~19)阿部一夫先生のみ賛同
「君,調べた物があるなら書物を村中に配ろう」
→ 「米津の江戸送り地蔵」小冊子を450戸全戸に
□昭和48(1973)年8月13日
寺施餓鬼の後 御遺族,阿部一夫氏とほんの数人で…
「江戸送り地蔵尊二百年祭」
第14世磯谷光山師 地蔵尊小祠の前で
↓
昭和55(1980)年春 篤志家…太田泰次氏により地蔵堂が建立
平成13年より8月24日に近い日曜日に開催
↓
◎ 昭和56(1981)年 「劇団たんぽぽ」の小百合葉子さんが劇化
◇米津の御台場
□昭和34(1959)年6月18日 浜松市指定史跡「米津台場跡」
安政3(1856)年浜松城主・井上河内守正直が三基建立
幕末には全国で一千か所も御台場が築かれた
米津に三つの史跡 台場跡 現台場跡の東西150mのところ
当時 高さ27m 海への前面には石積み(大知波村の石)
内部に砲弾・砲弾を貯蔵する穴蔵
後方は円形
□砲弾
米津庄屋 鳥居太郎左右衛門家の大威助氏が新津小に寄贈
平成5年7月 浜松市博物館より里帰り(現在新津小に有=ハマコウ註)
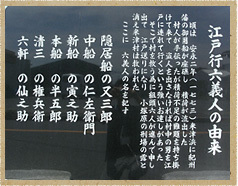
※写真は「わがまち倉松」より

米津のお台場
※浜松市HPより
「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」を紹介します。
滋賀県の和菓子やさん「たねや」はよく知られていますね。
もともとは種を販売する「種屋」さんだったそうですが、
今では洋菓子でも知られています。
「ふくみ天平」最中が好きです。
創業地は近江八幡市。言われて気が付く近江商人ということですね。
たねや社長の山本徳次さんの言葉を集めた本ですが、おもしろく読みました。
メモにとっておいた、覚えておきたいいくつかの言葉を紹介します。
出版社の案内には
「すべては最善のおもてなしのために-。近江八幡から全国へと躍進した和菓子メーカー
『たねや』の、こだわりの商道を紹介する。」
とあります。
もう一つ、再掲載となりますが、井口周治さんの
「米津浜の松風」を載せます。
地域にある図書館の郷土コーナーで見つけて読みました。
郷土の話だけに、たいへん勉強になった本です。
以前2回に分けて紹介したものを、一つにまとめました。
井口周治さんの私家版で、地元の図書館に寄贈されたものです。
地域の話を本に著してくださったおかげで、読むことができました。
ありがたいことです。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「商いはたねやに訊け-近江商人山本徳次語録」 毎日新聞社 2003年

デザイナーではなくアーティストになれ
経営者はばい菌をばらまいているようなもの
お菓子には物語がないといかん
農家が元気になってもらわんと困るのや
安心安全健康的ということ
店づくりはどこまでも本物志向
その地域で絶対的な信頼と支持を得る店
儲け急ぎはダメ すぐ数字に酔うてしまう
マイナス部分をいち早く報告すること
開発力・企画力が○○と販売とを橋渡しする
表の非効率と裏の効率化を柔軟に
情報は公開し共有により新たな情報を作り出す
中途半端な金を使うな
恥ずかしさが原点
経営者は孤独
人と反対の方へ行け
現場にヒントがあり改善点がある
母さん、おばあちゃんのおはぎがいちばん
若いときは特に汗を惜しむな
和菓子は水を洋菓子は空気を売りなさい
値を下げるな
五歳までに善悪を教え込む
無駄がプラスになる
迷ったらやめる
菓子は総合芸術
人にはばかることはしてはいかん
経営者に美意識がなかったらあかん
今日できたものは過去のもの 必ず欠点がある
こつこつの中に人間の信念が生まれてくる
季節には季節の物語がある
頭ばかり大きくなるな足が…?
迷ったら白に戻れ
雅ではなく鄙び
製造で儲けるは○?
原価積み上げはやめろ
総合力で販売
販売は非合理化 工場は合理化
鎧を着ては商売できない
商道は人道
ものを売る前に自分を売る
イノベーターになる
本式経営は近江商人が原点
後追いは絶対ダメ
名前を売りたいだけの広告ならやめる
人にだまされても自分からだますな
先義後利売れてるときがいちばんこわい
あるがままがいちばん
人の顔は人生の積み木
川下産業になりきること
◇たねや物語
近江八幡市和菓子メーカー「たねや」1872(明治5)創業
☆「米津浜の松風」井口周治 著者私家版 2006年 ①②【再掲載 2014.12】
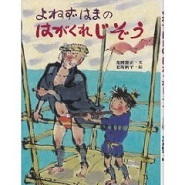
◇はじめに
<魚は獲れ>
□山を立てる
~ 遠方の山に目標物を重ねた延長線上に魚のよく獲れる漁場
□地引き網
(半農半漁=ハマコウ註)
□森茉莉
鴎外長女 「本当に金を使ってやる贅沢には空想と想像の歓びがない」
□貧乏 ~ 金銭に縁のない生活
その時あるものを食べ命を繋ぐことで,ある程度の満足を覚えることができれば,人間
に悩みも迷いも社会に
◇米津浜(よねづはま)の松風
□米津浜
花崗岩の砂 石英の粒,長石の粒,雲母の粒
□天竜川
かつては鹿島で二筋
東は「小天竜」
西は「大天竜」(現在の馬込川筋)
船越(渡船)地名が残る
↓
◎ 一筋になったのは江戸初期・慶安年中(1648-1651)
「彦助堤」による
□米津浜
~ 米津浜の権利は300mほど
□新津村米津海岸
大正14(1925)年5月
豊橋高射砲第一連隊の演習場に
昭和3(1928)年3月20日
豊橋第一連隊が和地山(浜松市)に
→ やがて御台場北に兵舎
昭和22(197)年9月より
「浜の中学校」 = 新津中学校
(~昭和27年3月まで浜に、それ以後現在の地に)
◇米津浜安泉寺と太田備中守資宗
□安泉寺
8代城主・太田備中守資宗を開祖 - 庇護
正保元(1644)~寛文11(1671) 27年間
「御前道」 → 「御台場道」 → 高射砲道路
御前=資宗?
堤の好徳寺より太田資宗の位牌が発見された
□安泉寺境内の地蔵堂
昭和55(1980)年3月に築造された「江戸送り地蔵尊」
白羽町の太田泰次氏が地蔵堂を無償で建立
◇米津の江戸送り地蔵
□安永2(1773)年秋
無実の罪で6人が江戸小塚原の刑場の露に
= 米津の義民
□昭和10(1935)年10月
安泉寺住職13世小林鶴洲師が土中より発見
台座に「安永2巳年難船ニ付江戸総代為菩提村中に…」
土中に160余年埋もれていた
総代 又三郎(隠居船) 半五郎(本船) 仙之助(六軒)
権兵衛(清三) 仁左衛門(中船) 寅之助(新船)
□安永の大難
安永2(1773)年の初秋
紀州御用船が座礁 不幸 = 紀州船だったこと
→ 荷の不足を訴えられる
古老の言い伝え
「下田港で豪遊し積み荷に手を付けたため,暴風雨のあったことをよいことに米津海
岸に座礁した」(口伝)
字名 - 地引き網船の名が小字名に転化した
※ 権力の前に否応なしに下手人を仕立てた
→ 「救うために200両調達せよ」(浜松藩)
◎ 63軒で200両を作った(それにもかかわらず全員刑場の露に)
※ 村人 ~ 土中で陰まつり (紛失)
↓
◎ 米津浜の自浜が狭いのは難破船を恐れて浜の権利を譲った
(漂着物届出の義務を避けるため)
□昭和29年10月6日
市史編纂室 馬渕紫陽「米津地蔵由来記」「夢枕」
□昭和33年10月
渥美実「土のいろ」
※松島町(浜松市)でも同様のことが‥
寛政12(1799)年正月
紀州船が松嶋村の海岸に漂着した際,荷物を内分にて処理したという理由で庄屋,
組頭,百姓代の三人が江戸に送られ,米津のように亡くなっている。
|
◎しかし,松嶋村ではすでに風化してしまっている
□新津小元校長(昭和16~19)阿部一夫先生のみ賛同
「君,調べた物があるなら書物を村中に配ろう」
→ 「米津の江戸送り地蔵」小冊子を450戸全戸に
□昭和48(1973)年8月13日
寺施餓鬼の後 御遺族,阿部一夫氏とほんの数人で…
「江戸送り地蔵尊二百年祭」
第14世磯谷光山師 地蔵尊小祠の前で
↓
昭和55(1980)年春 篤志家…太田泰次氏により地蔵堂が建立
平成13年より8月24日に近い日曜日に開催
↓
◎ 昭和56(1981)年 「劇団たんぽぽ」の小百合葉子さんが劇化
◇米津の御台場
□昭和34(1959)年6月18日 浜松市指定史跡「米津台場跡」
安政3(1856)年浜松城主・井上河内守正直が三基建立
幕末には全国で一千か所も御台場が築かれた
米津に三つの史跡 台場跡 現台場跡の東西150mのところ
当時 高さ27m 海への前面には石積み(大知波村の石)
内部に砲弾・砲弾を貯蔵する穴蔵
後方は円形
□砲弾
米津庄屋 鳥居太郎左右衛門家の大威助氏が新津小に寄贈
平成5年7月 浜松市博物館より里帰り(現在新津小に有=ハマコウ註)
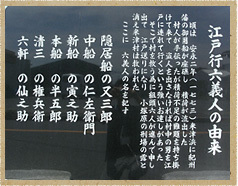
※写真は「わがまち倉松」より

米津のお台場
※浜松市HPより



