「新時代の教育をどう構想するのか」藤田英典 岩波ブックレット№533 2001年 ③ /「忘れられた日本人を読む」網野善彦 岩波セミナーブックス2003年 ①【再掲載 2014.8】 [読書記録 教育]
今回は、1月16日に続いて、藤田英典さんの
「新時代の教育をどう構想するのか」の紹介 3回目です。
出版社の案内には、
「首相の私的諮問機関として各界の識者を集め、集中的な討議をへて発表された教育改革
国民会議の報告は、教育基本法の見直し・奉仕活動の必要性など、大きな関心を呼び、
今後の政策に反映必至の重大な提案を含んでいた。委員として参加・発言した教育学者
が提案内容を検証・批判しながら『いま本当に必要な教育改革とは』を訴える。」
とあります。
- 日本の教育は能力主義的・エリート主義的に再編され,教育の制度的差別化と分断化
が進み,子供の生活は地域からますます切り離され,個人化されていく(ことになる)
この文章を見て、びくっとしました。生きる意欲をなくし関係のないたまたまそこに居合わせた人を巻き込んでしまう事件を思ったからです。
学区制をとらない公立義務教育学校は…。
地域の自治会組織への参加については…。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「不満点は、理論的・実証的な検討が殆ど行われなかったこと、過半数の委員は殆ど何
も発言しなかったこと、少数意見の取り扱いが不備なことの3点。」
・「国民会議は、選択の自由や市場的競争原理を重視したエリート主義的・能力主義的な
制度改革をさらに推し進めようとしている。日本の教育は能力主義的・エリート主義
的に再編され,教育の制度的差別化と分断化が進み,子供の生活は地域からますます
切り離され,個人化されていく」
・「国民会議は軌道修正し、これまでのように子供の側に歩み寄り,子供を甘やかすとい
うのではなく,大人や教える側の論理と姿勢を立て直し,道徳教育・全人教育を充実
しようと言う」
・「政策担当者も知識人も時流に流され,良識と専門性に基づく賢明な判断ができなくな
っている」
もう一つ、再掲載となりますが、網野善彦さんの
「忘れられた日本人を読む」①を載せます。
わたしには、網野史学と宮本民俗学のつながりが少し分かるようでした。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「新時代の教育をどう構想するのか」藤田英典 岩波ブックレット№533 2001年 ③

Ⅱ 1章 審議の展開と最終報告の概要
◇国民会議の審議の展開
□2000年3月発足
全体会13回
分科会で6~7回(3分科会)
公聴会 4回
学校視察 3回
企画委員会16回
合計 56回もの会合
□筆者の不満
① 理論的・実証的な検討が殆ど行われなかった
② 過半数の委員は殆ど何も発言しなかった
③ 少数意見の取り扱いが不備
◇最終報告の評価
□筆者の評価「30点」
- ・「報告の基調が分裂した危険なもの」
・「独善的で無責任な提案が少なくない」
□大宅映子「50点」
- ・「議論とは言えない」
◇分裂した改革案の基調
□二つの考え方で報告基調すらが引き裂かれたものになっている
① 選択の自由や市場的競争原理を重視したエリート主義的・能力主義的な制度改革
② 道徳性,奉仕の精神,家族愛・郷土愛・祖国愛の涵養などを強調する復古主義的・
全体主義的傾向を宿した改革
□国民会議
※ ①をさらに推し進めようとしている
→ 日本の教育は能力主義的・エリート主義的に再編され,教育の制度的差別化と分
断化が進み,子供の生活は地域からますます切り離され,個人化されていく
※ ②の背景
いじめ・学級崩壊・青少年の暴力や犯罪 = 改善されない学校子供問題
↑
子供の側に歩み寄る改革を進めてきたが、国民会議は軌道修正
→ これまでのように子供の側に歩み寄り,子供を甘やかすというのではなく,大人
や教える側の論理と姿勢を立て直し,道徳教育・全人教育を充実しようと言う
□なぜこういう提案がされたのか
筆者(藤田)の考え
①の背景にはバブル経済崩壊以降の政治経済状況や文化社会状況がある
政経状況 財政赤字削減,規制緩和と構造改革による経済の再活性化
行政の効率化とアカウンタビリティ(説明責任)重視
文社状況 生活様式や価値観の多様化,選択の自由を重視する風潮
利己主義を個性の尊重として正当化するレトリック
↓
◎ 政策担当者も知識人も時流に流され,良識と専門性に基づく賢明な判断ができ
なくなっている
②の背景
・相次いで起こった青少年の凶悪犯罪や学級崩壊などへのセンセーショナルな対応
・ 利己主義的で傍若無人な青少年への大人の怒りと危機感
・ この十数年の子供を甘やかしがちな改革動向への反動
↓
◎ 次の点の確認を!
(次回に続きます)
☆「忘れられた日本人を読む」網野善彦 岩波セミナーブックス2003年 ①【再掲載 2014.8】
<出版社の案内>
既存の日本像に鋭く切り込んでいる日本中世史家が、宮本常一の代表作『忘れられた日本
人』を、用いられている民族語彙に注目しながら読みぬき、日本論におけるその先駆性を
明らかにする。歴史の中の老人・女性・子ども・遍歴民の役割や東日本と西日本との間の
大きな差異に早くから着目した点を浮き彫りにし、宮本民俗学の真髄に迫る。
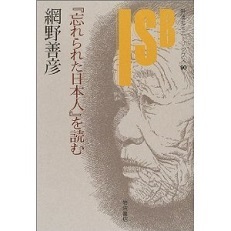
◇宮本常一との出会い 民俗語彙の再発見(1)
□網野善彦
1950(昭和25)年4月 日本常民文化研究所に入所 → 月島分室に
宇野脩平 「文書はすべて借りてこい」
↑↓
宮本常一 「本当に必要なものだけ借りる」 → 最後まで責任
◎「存在だけでまわりが明るく生き生きするような特異な力」
□宮本常一の中世史像
- 清水三男への高い評価
宮本常一「石母田正や藤間生大の学問はだめだ」
「清水はすばらしい」
「松本新八郎もおもしろいところがある」
1950年代「民話の会」
清水三男 共産党員からの転向
「天皇に対する見方、庶民、百姓、村に対するとらえ方」
= 天皇に対する親愛感
□宮本常一の学問
日本常民文化研究所月島分室閉鎖 → 都立北園高校に勤務
河村武春から宮本の話
□強烈な(宮本常一の)人格
大変な迫力 - 強烈な人格
日本常民文化研究所が神奈川大学に移る。
※主に古文書の返却の仕事
宮本常一
◎「あなたが行ってくれて、自分は地獄からはい上がれたような気がする」(1980年)
(地域から借りっぱなしになっていた古文書がまだ多数残っていた)
□宮本常一と渋澤敬三
佐野眞一「旅する巨人」「渋澤家三代」
□海から日本社会を見る
「日本文化の形成」(そしえて) → ちくま学芸文庫
= 海から日本の社会を見る
□東・西日本の文化の差異と「民具」研究の提唱
□進歩とは何か? 発展とは何か?
◎「進歩とは、発展とは何なのか、そこで切り落とされてきたものの中に非常に大事な
ものがある」
1980年 網野善彦
名古屋大学から神奈川大学短期大学部に移る。日本常民文化研究所員でもある
→ 古文書返却の旅
□短大のテキストに「忘れられた日本人」
大変な文化的・生活的な断絶
□「もののけ姫」とアジール
宮崎駿と鈴木敏夫プロデューサー
□民俗語彙の再発見
お辞儀 -「時宜」 時宜に対して頭を下げる意
朋輩(ホウバイ)-中世「傍輩」 対等な関係(単純な友達ではない)
えっと - ある限度を超えた誤り、過失
おとし宿-「おとす」とは人間のものではなくなってしまうこと
= 無縁、神仏のもの「無主物」
→ 落とされて初めて奪い取ることが可能になる
中世
-◎山の神によって山の中に入った人の持ち物はすべて「落ちて」しまうので、狩人が
山の中を通る人の物を奪うことが不法とならない
= 落ち穂拾い 誰が拾っても構わない
= 神仏からの贈り物
落ちてしまえば山賊にならない
「おとし宿」= 無縁の場
「宿」には無縁の場の性格がある
□善根宿の役割
□狂言「かくしだぬき」の世界
「いちは」(市庭=市場)14世紀初までは都市へ
たぬきが市場で売買されていた
荘園代官 国司・守護に接待し、文句を言わせない
百姓には正月・祭りの時、年貢納めの時酒宴
|
必要経費としている
○ 京都に年貢を送るときは銭を為替に替えて手形で送る 14ct初より
= 13ct後半以降 信用経済
<備中国新貝荘領家方所下帳>良資料
・せがき(施餓鬼)
・ゑとき(絵解き)
・千寿万歳(万歳)
・とひ(とび=贈り物)
・はうとう(保頭-保の頭)
・あいさつに来た物には八文出すのが相場
・「おおとびでございす」「もっておんだされ」
= 神に対しての贈答
・ありきそ女(村の使い走り)
→ 代官宣深の接待のやりすぎがばれて免職に(東寺)
・百姓 = 農民は江戸時代後期から(それまでは百姓=農民ではなかった)
「新時代の教育をどう構想するのか」の紹介 3回目です。
出版社の案内には、
「首相の私的諮問機関として各界の識者を集め、集中的な討議をへて発表された教育改革
国民会議の報告は、教育基本法の見直し・奉仕活動の必要性など、大きな関心を呼び、
今後の政策に反映必至の重大な提案を含んでいた。委員として参加・発言した教育学者
が提案内容を検証・批判しながら『いま本当に必要な教育改革とは』を訴える。」
とあります。
- 日本の教育は能力主義的・エリート主義的に再編され,教育の制度的差別化と分断化
が進み,子供の生活は地域からますます切り離され,個人化されていく(ことになる)
この文章を見て、びくっとしました。生きる意欲をなくし関係のないたまたまそこに居合わせた人を巻き込んでしまう事件を思ったからです。
学区制をとらない公立義務教育学校は…。
地域の自治会組織への参加については…。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「不満点は、理論的・実証的な検討が殆ど行われなかったこと、過半数の委員は殆ど何
も発言しなかったこと、少数意見の取り扱いが不備なことの3点。」
・「国民会議は、選択の自由や市場的競争原理を重視したエリート主義的・能力主義的な
制度改革をさらに推し進めようとしている。日本の教育は能力主義的・エリート主義
的に再編され,教育の制度的差別化と分断化が進み,子供の生活は地域からますます
切り離され,個人化されていく」
・「国民会議は軌道修正し、これまでのように子供の側に歩み寄り,子供を甘やかすとい
うのではなく,大人や教える側の論理と姿勢を立て直し,道徳教育・全人教育を充実
しようと言う」
・「政策担当者も知識人も時流に流され,良識と専門性に基づく賢明な判断ができなくな
っている」
もう一つ、再掲載となりますが、網野善彦さんの
「忘れられた日本人を読む」①を載せます。
わたしには、網野史学と宮本民俗学のつながりが少し分かるようでした。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「新時代の教育をどう構想するのか」藤田英典 岩波ブックレット№533 2001年 ③

Ⅱ 1章 審議の展開と最終報告の概要
◇国民会議の審議の展開
□2000年3月発足
全体会13回
分科会で6~7回(3分科会)
公聴会 4回
学校視察 3回
企画委員会16回
合計 56回もの会合
□筆者の不満
① 理論的・実証的な検討が殆ど行われなかった
② 過半数の委員は殆ど何も発言しなかった
③ 少数意見の取り扱いが不備
◇最終報告の評価
□筆者の評価「30点」
- ・「報告の基調が分裂した危険なもの」
・「独善的で無責任な提案が少なくない」
□大宅映子「50点」
- ・「議論とは言えない」
◇分裂した改革案の基調
□二つの考え方で報告基調すらが引き裂かれたものになっている
① 選択の自由や市場的競争原理を重視したエリート主義的・能力主義的な制度改革
② 道徳性,奉仕の精神,家族愛・郷土愛・祖国愛の涵養などを強調する復古主義的・
全体主義的傾向を宿した改革
□国民会議
※ ①をさらに推し進めようとしている
→ 日本の教育は能力主義的・エリート主義的に再編され,教育の制度的差別化と分
断化が進み,子供の生活は地域からますます切り離され,個人化されていく
※ ②の背景
いじめ・学級崩壊・青少年の暴力や犯罪 = 改善されない学校子供問題
↑
子供の側に歩み寄る改革を進めてきたが、国民会議は軌道修正
→ これまでのように子供の側に歩み寄り,子供を甘やかすというのではなく,大人
や教える側の論理と姿勢を立て直し,道徳教育・全人教育を充実しようと言う
□なぜこういう提案がされたのか
筆者(藤田)の考え
①の背景にはバブル経済崩壊以降の政治経済状況や文化社会状況がある
政経状況 財政赤字削減,規制緩和と構造改革による経済の再活性化
行政の効率化とアカウンタビリティ(説明責任)重視
文社状況 生活様式や価値観の多様化,選択の自由を重視する風潮
利己主義を個性の尊重として正当化するレトリック
↓
◎ 政策担当者も知識人も時流に流され,良識と専門性に基づく賢明な判断ができ
なくなっている
②の背景
・相次いで起こった青少年の凶悪犯罪や学級崩壊などへのセンセーショナルな対応
・ 利己主義的で傍若無人な青少年への大人の怒りと危機感
・ この十数年の子供を甘やかしがちな改革動向への反動
↓
◎ 次の点の確認を!
(次回に続きます)
☆「忘れられた日本人を読む」網野善彦 岩波セミナーブックス2003年 ①【再掲載 2014.8】
<出版社の案内>
既存の日本像に鋭く切り込んでいる日本中世史家が、宮本常一の代表作『忘れられた日本
人』を、用いられている民族語彙に注目しながら読みぬき、日本論におけるその先駆性を
明らかにする。歴史の中の老人・女性・子ども・遍歴民の役割や東日本と西日本との間の
大きな差異に早くから着目した点を浮き彫りにし、宮本民俗学の真髄に迫る。
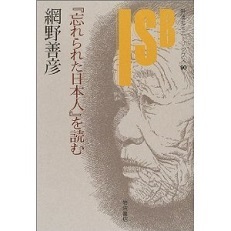
◇宮本常一との出会い 民俗語彙の再発見(1)
□網野善彦
1950(昭和25)年4月 日本常民文化研究所に入所 → 月島分室に
宇野脩平 「文書はすべて借りてこい」
↑↓
宮本常一 「本当に必要なものだけ借りる」 → 最後まで責任
◎「存在だけでまわりが明るく生き生きするような特異な力」
□宮本常一の中世史像
- 清水三男への高い評価
宮本常一「石母田正や藤間生大の学問はだめだ」
「清水はすばらしい」
「松本新八郎もおもしろいところがある」
1950年代「民話の会」
清水三男 共産党員からの転向
「天皇に対する見方、庶民、百姓、村に対するとらえ方」
= 天皇に対する親愛感
□宮本常一の学問
日本常民文化研究所月島分室閉鎖 → 都立北園高校に勤務
河村武春から宮本の話
□強烈な(宮本常一の)人格
大変な迫力 - 強烈な人格
日本常民文化研究所が神奈川大学に移る。
※主に古文書の返却の仕事
宮本常一
◎「あなたが行ってくれて、自分は地獄からはい上がれたような気がする」(1980年)
(地域から借りっぱなしになっていた古文書がまだ多数残っていた)
□宮本常一と渋澤敬三
佐野眞一「旅する巨人」「渋澤家三代」
□海から日本社会を見る
「日本文化の形成」(そしえて) → ちくま学芸文庫
= 海から日本の社会を見る
□東・西日本の文化の差異と「民具」研究の提唱
□進歩とは何か? 発展とは何か?
◎「進歩とは、発展とは何なのか、そこで切り落とされてきたものの中に非常に大事な
ものがある」
1980年 網野善彦
名古屋大学から神奈川大学短期大学部に移る。日本常民文化研究所員でもある
→ 古文書返却の旅
□短大のテキストに「忘れられた日本人」
大変な文化的・生活的な断絶
□「もののけ姫」とアジール
宮崎駿と鈴木敏夫プロデューサー
□民俗語彙の再発見
お辞儀 -「時宜」 時宜に対して頭を下げる意
朋輩(ホウバイ)-中世「傍輩」 対等な関係(単純な友達ではない)
えっと - ある限度を超えた誤り、過失
おとし宿-「おとす」とは人間のものではなくなってしまうこと
= 無縁、神仏のもの「無主物」
→ 落とされて初めて奪い取ることが可能になる
中世
-◎山の神によって山の中に入った人の持ち物はすべて「落ちて」しまうので、狩人が
山の中を通る人の物を奪うことが不法とならない
= 落ち穂拾い 誰が拾っても構わない
= 神仏からの贈り物
落ちてしまえば山賊にならない
「おとし宿」= 無縁の場
「宿」には無縁の場の性格がある
□善根宿の役割
□狂言「かくしだぬき」の世界
「いちは」(市庭=市場)14世紀初までは都市へ
たぬきが市場で売買されていた
荘園代官 国司・守護に接待し、文句を言わせない
百姓には正月・祭りの時、年貢納めの時酒宴
|
必要経費としている
○ 京都に年貢を送るときは銭を為替に替えて手形で送る 14ct初より
= 13ct後半以降 信用経済
<備中国新貝荘領家方所下帳>良資料
・せがき(施餓鬼)
・ゑとき(絵解き)
・千寿万歳(万歳)
・とひ(とび=贈り物)
・はうとう(保頭-保の頭)
・あいさつに来た物には八文出すのが相場
・「おおとびでございす」「もっておんだされ」
= 神に対しての贈答
・ありきそ女(村の使い走り)
→ 代官宣深の接待のやりすぎがばれて免職に(東寺)
・百姓 = 農民は江戸時代後期から(それまでは百姓=農民ではなかった)



