小浜逸郎さんはこんなことを⑲-「間違いだらけのいじめ論議」小浜逸郎・諏訪哲二 宝島社 1995年(1) /「土のいろ」集成 第十一巻 101~106号 (前半)【再掲載 2017.3】 [読書記録 教育]
今回は、1月12日に続いて、
「小浜逸郎さんはこんなことを」19回目、
「間違いだらけのいじめ論議」3回目の紹介です。
いじめについての報道はなくなりません。
さまざまな意見が出て、さまざまな手立てがうたれているのにもかかわらず。
出版社の案内には
「今、いじめが犯罪のレベルにまで達しつつある。いじめについて7人の専門家が考えに
考え抜いて執筆した本。学校認識・教育認識のリヴィジョナリスト(認識修正主義者)の
警世の書。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「学校が強気に出る時には何かを握っている時」
・「メディアは自分に都合のいい物語を作るためにはいくらでも事実をねじ曲げる」
「誘惑されたメディア =『言いっぱなし,書きっぱなし,垂れ流し』」
・「『子供は善 大人は悪』という幼稚な解釈→情緒的メッセージは見ていて恥ずかしい」
・「辛くも光る論点
①公教育は今よりも縮小されるべき
② 学校依存心を捨てて,自分たちの責任に於いて担っていく態度を身につけなくては
ならない」
もう一つ、再掲載となりますが、
「土のいろ」集成第十一巻(前半)を載せます。
『土のいろ』は、大正13年から、戦争による休刊をはさんで戦後の一時期復刊された、
遠州地方では古い郷土研究雑誌です。
参考 「土のいろの刊行」(浜松市立中央図書館/浜松市文化遺産デジタルアーカイブ)
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆小浜逸郎さんはこんなことを⑲-「間違いだらけのいじめ論議」小浜逸郎・諏訪哲二 宝島社 1995年(1)

◇「いじめ」を巡る七つの逆説
①「子供がいじめの実態を教師や親に告げないのは報復が恐ろしい」からではない。
②「仲が悪い子供同士の間でいじめが発生する」というのはウソだ。
③「喧嘩の強い子はいじめられない」というのは事実に反する。
④「偏差値教育や管理教育がいじめの原因だ」という指摘は的はずれだ。
⑤「みんなで仲良く」という発想こそがいじめの温床になる。
⑥「子供の人権擁護や話し合い説得」はかえっていじめを激化させる。
⑦「自由な校風や子供の自主性を尊重するクラスは荒れる」
◇学校をいじめてもいじめはなくならない
□中学生いじめ
1994年11月27日
→ 12月 2日 中日新聞スクープ
大河内清輝君 西尾市立東部中学校
→ 12月13日 岡崎市立福岡中学校
○校長バッシング
「メディアは自分に都合のいい物語を作るためにはいくらでも事実をねじ曲げる」
↑↓
◎ 学校が強気に出る時には何かを握っている時
|
浮かび上がってきたのは「いじめはなかった」
自分の方から悪戯してちょっかいを出していた子
原因:成績の問題,父親との関係
|
父親がトーンダウン ←→ 加藤校長は首尾一貫
加藤校長の反論
→ 名古屋タイムス 煽った アンカーマンシステム
∥
△誘惑されたメディア
「言いっぱなし,書きっぱなし,垂れ流し」
◇識者の不毛な発言を斬る
□情報社会の宿命
「子供は善 大人は悪」という幼稚な解釈
情緒的メッセージは見ていて恥ずかしい
毒にも薬にもならぬ優等生的発言,人生相談的忠告
認識の錯誤,概念の混乱,没論理的思いこみ
おざなりの比較文化的観念,欧米人の日本理解の限界
◎辛くも光る論点
野坂昭如 新堀通也 山岸駿介 山下恒男(茨城大)
↓
① 公教育は今よりも縮小されるべき
② 学校依存心を捨てて,自分たちの責任に於いて担っていく態度を身につけな
くてはならない
☆「土のいろ」集成 第十一巻 101~106号 (前半)【再掲載 2017.3】
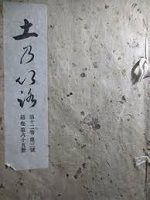
◇復刊第18号 通刊101号 昭和37年11月
「遠州大念仏」特集号 後編
◇復刊第19号 通刊102号 昭和38年1月
法多山思玄上人(上) 山口直蔵
□浜松特産「足袋のあれこれ」 須部弥一郎
徳川中期より
特産地 = 浜松と松本
足袋と旅
紺染めと厚地木綿 紺屋
□竜禅寺の不動堂 市川象三郎
□浜松の「リズム社」について 渥美 実
大正末
浜松の音楽結社「リズム社」 ~ 「赤い鳥」運動
小学校教師同人として発足
県善三郎,松井多聞,関川美作雄,水谷正義,仲野静
30号まで 大正11年5月~大正13年11月
◇復刊第20号 通刊103号 昭和38年5月
□西浦田楽はね能の詞章について 鈴木進
□法多山思玄上人(下) 山口直蔵
□新居の民俗覚え書き 山口幸洋
○大倉戸のこと
大倉戸 - 古代の屯倉に由来
「お倉が崎」-三宅性が多い
○戸 = 河や海の入り口の意味
湊は水の戸 大和は山の戸
○節分 ヤイカガシとナタもち(炒り豆を臼でつぶし,つきたての餅)
○五月一日
虫除け = イチジクの葉を一枚敷いて線香
○すわま
三月節句
→ 米の粉に黒砂糖と溜まりを加えて練って蒸す
はんぺんの形,波形
□持統天皇と引馬野 川見駒太郎
697年8月1日
702年秋 参河御幸「続日本紀」
□嫁たたきの大の子について 渥美静一
◇復刊第21号 通刊104号 昭和38年9月
□浜松通信事業の90年 鈴木犀十郎
浜松宿「遠州浜松広いようで狭い 横に車が二丁立たぬ」
□湖東地方の風俗と言語 鈴木敏
◇復刊第22号 通刊105号 昭和39年1月
□浜松・金原氏の起こり 小山正
○蒲の庄
藤原静並が越後から国司役人として3番目 大像(だいしょう)開拓
↓
伊勢神宮をお祀り
→ 神宮領に捧げた = 蒲の御厨(みくり)
24郷→43か村(寛政期)
○金原将監晴時 金原法橋(寺の住職)が領主に
鎌倉期 ・朝廷からの役人(国司)の治めている国に守護
・私有地の庄園には地頭
↓
○蒲庄に遠藤氏来る
遠江の藤原 = 遠藤 1185~1300年頃
↓ 鎌倉武士 本拠屋敷は鎌倉
任地には第二の屋敷
○遠藤氏の次に金原晴時 1300~1580年頃
金原法橋 「妙恩寺略縁起」
大野の政清の子供
下総国金原大宮の別当職
→ 鎌倉期に抜擢され遠州に
知行1万8千石 28か村領す 左近将監
↓
家康入城の翌年
台場に新居 → 帰農
庄屋や神官
□蜆塚発掘調査の総まとめ 鈴木謹一
□大手前から成子坂まで 須部弥一郎
○大手前 - 元城小前 伊勢屋文具店,川瀬文明堂,松柏堂文具店
○榎木町 - 大木屋,山本屋呉服店,木綿屋洋服店,道惣金物店
○連尺 - 谷島屋書店,文泉堂,鴻池屋
○大手前 - 山口屋菓子店,伝馬町巌邑堂
□子供の遊戯抄 小池誠二
てんつば,おたたき,あなどち,ギッコンバッタン
「小浜逸郎さんはこんなことを」19回目、
「間違いだらけのいじめ論議」3回目の紹介です。
いじめについての報道はなくなりません。
さまざまな意見が出て、さまざまな手立てがうたれているのにもかかわらず。
出版社の案内には
「今、いじめが犯罪のレベルにまで達しつつある。いじめについて7人の専門家が考えに
考え抜いて執筆した本。学校認識・教育認識のリヴィジョナリスト(認識修正主義者)の
警世の書。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「学校が強気に出る時には何かを握っている時」
・「メディアは自分に都合のいい物語を作るためにはいくらでも事実をねじ曲げる」
「誘惑されたメディア =『言いっぱなし,書きっぱなし,垂れ流し』」
・「『子供は善 大人は悪』という幼稚な解釈→情緒的メッセージは見ていて恥ずかしい」
・「辛くも光る論点
①公教育は今よりも縮小されるべき
② 学校依存心を捨てて,自分たちの責任に於いて担っていく態度を身につけなくては
ならない」
もう一つ、再掲載となりますが、
「土のいろ」集成第十一巻(前半)を載せます。
『土のいろ』は、大正13年から、戦争による休刊をはさんで戦後の一時期復刊された、
遠州地方では古い郷土研究雑誌です。
参考 「土のいろの刊行」(浜松市立中央図書館/浜松市文化遺産デジタルアーカイブ)
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆小浜逸郎さんはこんなことを⑲-「間違いだらけのいじめ論議」小浜逸郎・諏訪哲二 宝島社 1995年(1)

◇「いじめ」を巡る七つの逆説
①「子供がいじめの実態を教師や親に告げないのは報復が恐ろしい」からではない。
②「仲が悪い子供同士の間でいじめが発生する」というのはウソだ。
③「喧嘩の強い子はいじめられない」というのは事実に反する。
④「偏差値教育や管理教育がいじめの原因だ」という指摘は的はずれだ。
⑤「みんなで仲良く」という発想こそがいじめの温床になる。
⑥「子供の人権擁護や話し合い説得」はかえっていじめを激化させる。
⑦「自由な校風や子供の自主性を尊重するクラスは荒れる」
◇学校をいじめてもいじめはなくならない
□中学生いじめ
1994年11月27日
→ 12月 2日 中日新聞スクープ
大河内清輝君 西尾市立東部中学校
→ 12月13日 岡崎市立福岡中学校
○校長バッシング
「メディアは自分に都合のいい物語を作るためにはいくらでも事実をねじ曲げる」
↑↓
◎ 学校が強気に出る時には何かを握っている時
|
浮かび上がってきたのは「いじめはなかった」
自分の方から悪戯してちょっかいを出していた子
原因:成績の問題,父親との関係
|
父親がトーンダウン ←→ 加藤校長は首尾一貫
加藤校長の反論
→ 名古屋タイムス 煽った アンカーマンシステム
∥
△誘惑されたメディア
「言いっぱなし,書きっぱなし,垂れ流し」
◇識者の不毛な発言を斬る
□情報社会の宿命
「子供は善 大人は悪」という幼稚な解釈
情緒的メッセージは見ていて恥ずかしい
毒にも薬にもならぬ優等生的発言,人生相談的忠告
認識の錯誤,概念の混乱,没論理的思いこみ
おざなりの比較文化的観念,欧米人の日本理解の限界
◎辛くも光る論点
野坂昭如 新堀通也 山岸駿介 山下恒男(茨城大)
↓
① 公教育は今よりも縮小されるべき
② 学校依存心を捨てて,自分たちの責任に於いて担っていく態度を身につけな
くてはならない
☆「土のいろ」集成 第十一巻 101~106号 (前半)【再掲載 2017.3】
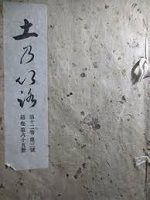
◇復刊第18号 通刊101号 昭和37年11月
「遠州大念仏」特集号 後編
◇復刊第19号 通刊102号 昭和38年1月
法多山思玄上人(上) 山口直蔵
□浜松特産「足袋のあれこれ」 須部弥一郎
徳川中期より
特産地 = 浜松と松本
足袋と旅
紺染めと厚地木綿 紺屋
□竜禅寺の不動堂 市川象三郎
□浜松の「リズム社」について 渥美 実
大正末
浜松の音楽結社「リズム社」 ~ 「赤い鳥」運動
小学校教師同人として発足
県善三郎,松井多聞,関川美作雄,水谷正義,仲野静
30号まで 大正11年5月~大正13年11月
◇復刊第20号 通刊103号 昭和38年5月
□西浦田楽はね能の詞章について 鈴木進
□法多山思玄上人(下) 山口直蔵
□新居の民俗覚え書き 山口幸洋
○大倉戸のこと
大倉戸 - 古代の屯倉に由来
「お倉が崎」-三宅性が多い
○戸 = 河や海の入り口の意味
湊は水の戸 大和は山の戸
○節分 ヤイカガシとナタもち(炒り豆を臼でつぶし,つきたての餅)
○五月一日
虫除け = イチジクの葉を一枚敷いて線香
○すわま
三月節句
→ 米の粉に黒砂糖と溜まりを加えて練って蒸す
はんぺんの形,波形
□持統天皇と引馬野 川見駒太郎
697年8月1日
702年秋 参河御幸「続日本紀」
□嫁たたきの大の子について 渥美静一
◇復刊第21号 通刊104号 昭和38年9月
□浜松通信事業の90年 鈴木犀十郎
浜松宿「遠州浜松広いようで狭い 横に車が二丁立たぬ」
□湖東地方の風俗と言語 鈴木敏
◇復刊第22号 通刊105号 昭和39年1月
□浜松・金原氏の起こり 小山正
○蒲の庄
藤原静並が越後から国司役人として3番目 大像(だいしょう)開拓
↓
伊勢神宮をお祀り
→ 神宮領に捧げた = 蒲の御厨(みくり)
24郷→43か村(寛政期)
○金原将監晴時 金原法橋(寺の住職)が領主に
鎌倉期 ・朝廷からの役人(国司)の治めている国に守護
・私有地の庄園には地頭
↓
○蒲庄に遠藤氏来る
遠江の藤原 = 遠藤 1185~1300年頃
↓ 鎌倉武士 本拠屋敷は鎌倉
任地には第二の屋敷
○遠藤氏の次に金原晴時 1300~1580年頃
金原法橋 「妙恩寺略縁起」
大野の政清の子供
下総国金原大宮の別当職
→ 鎌倉期に抜擢され遠州に
知行1万8千石 28か村領す 左近将監
↓
家康入城の翌年
台場に新居 → 帰農
庄屋や神官
□蜆塚発掘調査の総まとめ 鈴木謹一
□大手前から成子坂まで 須部弥一郎
○大手前 - 元城小前 伊勢屋文具店,川瀬文明堂,松柏堂文具店
○榎木町 - 大木屋,山本屋呉服店,木綿屋洋服店,道惣金物店
○連尺 - 谷島屋書店,文泉堂,鴻池屋
○大手前 - 山口屋菓子店,伝馬町巌邑堂
□子供の遊戯抄 小池誠二
てんつば,おたたき,あなどち,ギッコンバッタン



