「どこからお話ししましょうか 柳家小三治自伝」柳家小三治 岩波書店 2019年 ② /「一斉授業の復権」 久保齋 子どもの未来社 2005年 ③【再掲載 2014.7】 [読書記録 一般]
今回は、1月18日に続いて、柳家小三治さんの
「どこからお話ししましょうか 柳家小三治自伝」の紹介 2回目です。
出版社の案内には、
「円熟の古典落語、軽妙なマクラで、聴くものを魅了してやまない噺家・柳家小三治。本
書では、生い立ち、初恋、入門、修業時代、落語論から、バイク、クラシック音楽、俳
句、忘れじの人々まで、すべてをたっぷり語り下ろす。独特の語り口もそのままに、ま
さに読む独演会。芸と人生に対する真摯な姿勢が、初めて明らかに。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「何も考えがなくてきれいにやっているやつを私はいいと思わない」
「自分の心のない人は成功できないね」
・「自分の言葉で自分を追い込む」
・「小沢昭一が新宿末廣亭で落語 2005.6 夜の部」
- 過去記事へ→「『小沢昭一的新宿末廣亭十夜』小沢昭一 講談社 2012.5.29
・「笑いの陰に必ず悲しいとか寂しいとかってものがついてまわる。それが、日本の芸能
のもっているひとつの基本かもしれない。」
もう一つ、再掲載となりますが、久保齋さんの
「一斉授業の復権」③を載せます。
「一斉授業は古い」という教員もいますが、担任一人で授業を行うには、大切だと考えま
す。よりよい授業の組み立てさえできれば、高い効果が得ることができます。
その一助となる本だと思います。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「どこからお話ししましょうか 柳家小三治自伝」柳家小三治 岩波書店 2019年 ②
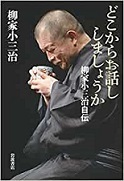
◇私の北海道
1963.4 二つ目
□丹野信吾さん(電通)
旭川の時は社員 - 札幌に
ボーナスはたいて「話聞いてやってくれませんか」
2006 丹野さんが亡くなられた しかし連絡つかず
2017 マネージャー(倉田美紀)手がかり
□東海ラジオ
嵯峨道夫 ミッドナイト東海
→ FM北海道に移る
→ 番組 スポンサーは六花亭
◇真打ち昇進
◎郡山和世著『噺家カミサン繁盛記』講談社文庫
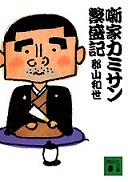
沼津の笑子さん「ちゃんと落語やってください」
◇うまくやってどうする?
□最初のクラシック
「軽騎兵」序曲 スッペ作曲
□自分でこうと思うものにはまっしぐらに進んでいく
□「なぜうまく歌うのか」
◎ 何も考えがなくてきれいにやっているやつを私はいいと思わない
→ 自分の心のない人は成功できないね
「本当にうまいのか、逆に嘘っぽいと思った」
|
作曲家の宅孝司さん 孤高の人
□「週間FM」6か月連載対談
◎8代目桂文楽
□枕が長くなった
「ミッドナイト東海」日曜 0:10-3:00
自分の言葉で! ← 自分を追い込む 「私のルネッサンス」
◇東京やなぎ句会 小沢昭一さんと入船亭扇橋さん
□東京やなぎ句会 1969.1 ~ 人間はみんなヘンなんだな
永六輔 江国滋 大西信行 小沢昭一 桂米朝 加藤武 神吉拓郎 永井啓夫
三田純一 矢野誠一 柳家さん八(入船亭扇橋)
◎やなぎ句会編『佐渡新発見 伝統と文化』三一書房
小沢昭一『日々談笑』ちくま文庫
小沢昭一とのオモシロ対談
□小沢昭一
とってもわがままな人
[ スナックに 煮凝りのある ママの過去 ]
新宿末廣亭
2005.6 夜の部に小沢昭一が登場 → お客の狂気
□扇橋
[ いばらない 母の日の 袋物屋を のぞきけり ]
「ちはやふる」の噺を聞いて涙
「落語って悲しいね」
|
◎ 笑いの陰に必ず悲しいとか寂しいとかってものがついてまわる
(日本の芸能のもっているひとつの基本かもしれない)
☆「一斉授業の復権」 久保齋 子どもの未来社 2005年 ③【再掲載 2014.7】
<出版社の案内>
学力低下・学級崩壊を救うのは一斉授業だ!学力を真に鍛え、子ども一人ひとりをいきい
きさせる、その驚くべき“教育力”を示す理論と実践の書。」
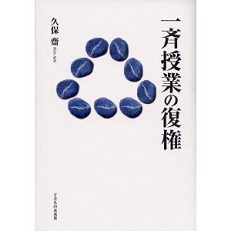
◇一斉授業の意味と価値
□「どの子も伸ばす」習得主義に立つ
危機の要因
① 教師の一斉授業の力量が落ちてきている
② 子どもたちの学力格差が広がっている
↑
◎支配層による意図
70~50代の教師(元教師)
「一斉授業でどの子も伸ばすことへの確信と気概」を持っていた
□<支配層>の意図
教員免許を有名無実化し,無権利で柔順で安上がりの教師をつくること
→ 義務教育の内容的・質的な切り下げ
□「新しい学力観」=履修主義
履修主義 = 体験させ,あとは好きに学べ主義
↓
一斉授業 「どの子も伸ばす」習得主義に
□一斉授業という形態の本質
一斉授業
= 一人の指導者のもとに多数の児童生徒が課題に取り組み,その結果を交流し,互い
に深め合っていく学習形態
|
◎本質 個と集団の双方が位置づけられていること
<凛々しい個> と <ゆたかな交流>
一斉授業のポイント
① 教師の指示・発問 子どもに「自分に指示・発問しているのだ」と思わせる
② 自分なりの結論を出せる <凛々しい個別化>
③ 自分の結論をもとに<ゆたかな交流>をする (学力の社会化)
④ 子どもたちの未熟さ 間違いが深い認識に結び付く
□クラスの中の教師の位置 - 教師はボスザル
担任は「猿ヶ島」のボスザル
= 常に自分の権威のレベルに敏感でなければならない
「授業時間は先生が仕切ります。授業時間は先生の指示に従いなさい。遊び時間や放課
後は君たちの時間ですから自由にどうぞ。」
二つに分ける ① 授業あるいは公の場
② 遊び時間や放課後の自由な中での遊び
発問・板書・ノート指導は三つの神器
◎「発問」 教師は発問を通して子どもたちの対立物になるべき
発問 = 子どもたちが考えられないことを質問すること
= 一人で考えられる半歩先
クラス全員が自分のノートに答えが書けたら<ゆたかな交流>
= 集団思考の始まり
↓
◎「板書」 子どもたちの思考の集中点
↓
一定の結論 - 教師がまとめのコメント
↓
次時の課題
↓
2~3人に「授業について考えたこと」を発表させる
↓
◎「ノート」
全員がノートに「今日学んだこと」を書き込む
(内容+感想+自己評価)
※ 書けた子から起立して,みんなに聞こえるように「今日学んだこと」を
読んでいく。
◎(低位な子が聞く = 書くヒントになる)
→ 教師が一言コメント
□学習規律と<学力の社会化>
学習規律の到達度(=一斉授業をつくりあげていくための設計図)
○ステップ1
立ち歩き・私語がなく授業が受けられる
○ステップ2
教師の発問に全員が反応し,素直に指示に従い,授業が受けられる
○ステップ3
教師の発問に一人一人が答えを用意し,友だちの意見に反応しながら授業が受
けられる
○ステップ4
その場その場の学習課題を理解し,教師の発問や友だちの意見と響き合った発
言ができ,自分の活躍についての自己評価ができる。
○ステップ5
学習課題を持って授業に参加し,教師・友だちとともに授業をつくることがで
きる。自分の意見・友だちの意見を大切にし課題を深める発言ができ,授業づく
りについての評価ができる。
「どこからお話ししましょうか 柳家小三治自伝」の紹介 2回目です。
出版社の案内には、
「円熟の古典落語、軽妙なマクラで、聴くものを魅了してやまない噺家・柳家小三治。本
書では、生い立ち、初恋、入門、修業時代、落語論から、バイク、クラシック音楽、俳
句、忘れじの人々まで、すべてをたっぷり語り下ろす。独特の語り口もそのままに、ま
さに読む独演会。芸と人生に対する真摯な姿勢が、初めて明らかに。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「何も考えがなくてきれいにやっているやつを私はいいと思わない」
「自分の心のない人は成功できないね」
・「自分の言葉で自分を追い込む」
・「小沢昭一が新宿末廣亭で落語 2005.6 夜の部」
- 過去記事へ→「『小沢昭一的新宿末廣亭十夜』小沢昭一 講談社 2012.5.29
・「笑いの陰に必ず悲しいとか寂しいとかってものがついてまわる。それが、日本の芸能
のもっているひとつの基本かもしれない。」
もう一つ、再掲載となりますが、久保齋さんの
「一斉授業の復権」③を載せます。
「一斉授業は古い」という教員もいますが、担任一人で授業を行うには、大切だと考えま
す。よりよい授業の組み立てさえできれば、高い効果が得ることができます。
その一助となる本だと思います。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「どこからお話ししましょうか 柳家小三治自伝」柳家小三治 岩波書店 2019年 ②
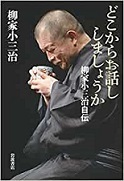
◇私の北海道
1963.4 二つ目
□丹野信吾さん(電通)
旭川の時は社員 - 札幌に
ボーナスはたいて「話聞いてやってくれませんか」
2006 丹野さんが亡くなられた しかし連絡つかず
2017 マネージャー(倉田美紀)手がかり
□東海ラジオ
嵯峨道夫 ミッドナイト東海
→ FM北海道に移る
→ 番組 スポンサーは六花亭
◇真打ち昇進
◎郡山和世著『噺家カミサン繁盛記』講談社文庫
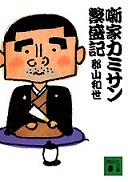
沼津の笑子さん「ちゃんと落語やってください」
◇うまくやってどうする?
□最初のクラシック
「軽騎兵」序曲 スッペ作曲
□自分でこうと思うものにはまっしぐらに進んでいく
□「なぜうまく歌うのか」
◎ 何も考えがなくてきれいにやっているやつを私はいいと思わない
→ 自分の心のない人は成功できないね
「本当にうまいのか、逆に嘘っぽいと思った」
|
作曲家の宅孝司さん 孤高の人
□「週間FM」6か月連載対談
◎8代目桂文楽
□枕が長くなった
「ミッドナイト東海」日曜 0:10-3:00
自分の言葉で! ← 自分を追い込む 「私のルネッサンス」
◇東京やなぎ句会 小沢昭一さんと入船亭扇橋さん
□東京やなぎ句会 1969.1 ~ 人間はみんなヘンなんだな
永六輔 江国滋 大西信行 小沢昭一 桂米朝 加藤武 神吉拓郎 永井啓夫
三田純一 矢野誠一 柳家さん八(入船亭扇橋)
◎やなぎ句会編『佐渡新発見 伝統と文化』三一書房
小沢昭一『日々談笑』ちくま文庫
小沢昭一とのオモシロ対談
□小沢昭一
とってもわがままな人
[ スナックに 煮凝りのある ママの過去 ]
新宿末廣亭
2005.6 夜の部に小沢昭一が登場 → お客の狂気
□扇橋
[ いばらない 母の日の 袋物屋を のぞきけり ]
「ちはやふる」の噺を聞いて涙
「落語って悲しいね」
|
◎ 笑いの陰に必ず悲しいとか寂しいとかってものがついてまわる
(日本の芸能のもっているひとつの基本かもしれない)
☆「一斉授業の復権」 久保齋 子どもの未来社 2005年 ③【再掲載 2014.7】
<出版社の案内>
学力低下・学級崩壊を救うのは一斉授業だ!学力を真に鍛え、子ども一人ひとりをいきい
きさせる、その驚くべき“教育力”を示す理論と実践の書。」
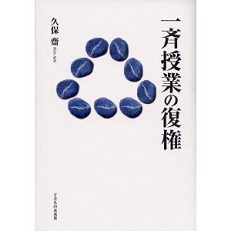
◇一斉授業の意味と価値
□「どの子も伸ばす」習得主義に立つ
危機の要因
① 教師の一斉授業の力量が落ちてきている
② 子どもたちの学力格差が広がっている
↑
◎支配層による意図
70~50代の教師(元教師)
「一斉授業でどの子も伸ばすことへの確信と気概」を持っていた
□<支配層>の意図
教員免許を有名無実化し,無権利で柔順で安上がりの教師をつくること
→ 義務教育の内容的・質的な切り下げ
□「新しい学力観」=履修主義
履修主義 = 体験させ,あとは好きに学べ主義
↓
一斉授業 「どの子も伸ばす」習得主義に
□一斉授業という形態の本質
一斉授業
= 一人の指導者のもとに多数の児童生徒が課題に取り組み,その結果を交流し,互い
に深め合っていく学習形態
|
◎本質 個と集団の双方が位置づけられていること
<凛々しい個> と <ゆたかな交流>
一斉授業のポイント
① 教師の指示・発問 子どもに「自分に指示・発問しているのだ」と思わせる
② 自分なりの結論を出せる <凛々しい個別化>
③ 自分の結論をもとに<ゆたかな交流>をする (学力の社会化)
④ 子どもたちの未熟さ 間違いが深い認識に結び付く
□クラスの中の教師の位置 - 教師はボスザル
担任は「猿ヶ島」のボスザル
= 常に自分の権威のレベルに敏感でなければならない
「授業時間は先生が仕切ります。授業時間は先生の指示に従いなさい。遊び時間や放課
後は君たちの時間ですから自由にどうぞ。」
二つに分ける ① 授業あるいは公の場
② 遊び時間や放課後の自由な中での遊び
発問・板書・ノート指導は三つの神器
◎「発問」 教師は発問を通して子どもたちの対立物になるべき
発問 = 子どもたちが考えられないことを質問すること
= 一人で考えられる半歩先
クラス全員が自分のノートに答えが書けたら<ゆたかな交流>
= 集団思考の始まり
↓
◎「板書」 子どもたちの思考の集中点
↓
一定の結論 - 教師がまとめのコメント
↓
次時の課題
↓
2~3人に「授業について考えたこと」を発表させる
↓
◎「ノート」
全員がノートに「今日学んだこと」を書き込む
(内容+感想+自己評価)
※ 書けた子から起立して,みんなに聞こえるように「今日学んだこと」を
読んでいく。
◎(低位な子が聞く = 書くヒントになる)
→ 教師が一言コメント
□学習規律と<学力の社会化>
学習規律の到達度(=一斉授業をつくりあげていくための設計図)
○ステップ1
立ち歩き・私語がなく授業が受けられる
○ステップ2
教師の発問に全員が反応し,素直に指示に従い,授業が受けられる
○ステップ3
教師の発問に一人一人が答えを用意し,友だちの意見に反応しながら授業が受
けられる
○ステップ4
その場その場の学習課題を理解し,教師の発問や友だちの意見と響き合った発
言ができ,自分の活躍についての自己評価ができる。
○ステップ5
学習課題を持って授業に参加し,教師・友だちとともに授業をつくることがで
きる。自分の意見・友だちの意見を大切にし課題を深める発言ができ,授業づく
りについての評価ができる。



