鷲田小彌太さんはこんなことを ⑦-「本はこう買えこう読めこう使え」大和書房 1996年(7)(最終) /「子ども集団を動かす魔法のワザ」杉渕鐵良 学陽書房 2010年 ①【再掲載 2013.7】 [読書記録 一般]
今回は、7月28日に続いてわたしの読書ノートから、
「鷲田小彌太さんはこんなことを」7回目、
「本はこう買えこう読めこう使え」の紹介7回目 最終です。
出版社の案内には
「道具として役に立つ読書。元気が出る読書。普段着の読書。この三つ
のテーマのもとに、情報化社会の現代のための実践的『本』の活用法
を説く。明るく、迅速かつ積極的に生きるための読書術。」
とあります。
1996年、出版された年を感じさせる読書案内であるように感じます。
もう一つ、再掲載となりますが、杉渕鐵良さんの
「子ども集団を動かす魔法のワザ」①を載せます。
教員、特に担任が知っておくとよいワザですが、読み直してみて
この10年間で子どもが大きく変わってきていることを感じています。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆鷲田小彌太さんはこんなことを ⑦-「本はこう買えこう読めこう使え」大和書房 1996年(7)(最終)

◇教養を手軽に学ぶ
□知的生活のすすめ
ちょっとかっこよく生きる
渡部昇一『知的生活の方法』講談社現代新書
努力の意味
竹内洋『受験生の社会史』『立志・哲学・出世』現代新書
大人の読書
向井敏『贅沢な読書』現代新書
『文章読本』文藝春秋
□思想と科学に強くなる
思想に手がかりを求める
今村仁司『現代思想のキーワード』現代新書
科学と技術の怖さと豊かさ
坂本賢三『現代科学をどうとらえるか』現代新書
最前線を知る
米本昌平『バイオエシックス』現代新書
資本主義社会と人間の欲望
日本は進んでいる
飯田経夫『豊かさとは何か』現代新書
ガルブレイス『豊かな社会』岩波書店
欲望の起源
丸山圭三郎『言葉・狂気・エロス』現代新書
資本主義を動かすものとその行方
佐伯啓思『欲望と資本主義』現代新書
☆「子ども集団を動かす魔法のワザ」杉渕鐵良 学陽書房 2010年 ①【再掲載 2013.7】
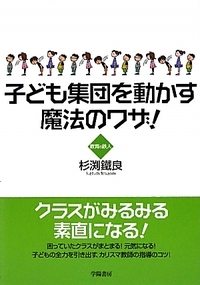
◇杉渕鐵良
1959年 東京生 現在(2010年3月)足立区立綾瀬小学校
「どの子もひとり残らず伸ばす」
「一人も落ちこぼれをつくらない」
クラスをまとめていくこと、子どもを変えていくことができるのは、
教師の覚悟と情熱が決め手
◇子ども集団に基本を教える魔法のワザ!(前半)
基本こそがクラスを変える
基本を全力でやることが大切
あいさつ、返事、学習態度
杉渕指導モットー
「あたりまえのことを究極まで高める」
あいさつや返事は全力で声を出させることが大事
|
例えば返事をさせるときも子どもに全力を出させる
一週間でも頑張って続けると…子どもの表情、クラスの雰囲気が変わる
基本をできるようにするのは教師の一番の仕事
起立の仕方、座り方、立ち方(限界をひいてはいけない)
教師は叱るべき時には叱るが、いつもはユーモアで
こども一人一人に合った指導を考え、うまく子どもを誘導することが
必要
=毎日、何度もそのことを繰り返したり、練習させたりすることが大切
やり直し
~ほめたり、ユーモアを交えながら面白くテンポよく
「覚悟をもって」
ユーモア満載、テンポよく、しつこく指導
1 子どもがみるみるあいさつできる子に!
○子どもにあいさつを教えるには
「ありがとう」を言えない子
◎ 子どもの意識があいさつに向くのを待ってあげる余裕が大事。教
師から声を掛け、「○○君」と名前を言ってからあいさつしよう。
2 大きな声であいさつさせるには?
○教師が手本を見せる
全員あいさつ → 個人全員 → 全員
◎ スピードとテンポが大事。ダラダラしていると効果なし。声を出
せた子には、「○○君、いいねえ」と褒める。声を出せる子を一人
ずつ増やしていこう。
3 大きな返事が子どもの意識を変える!
○返事をする場面をとにかくたくさん設定する
「出席をとります」 「はい」
「プリントを配ります」 「はい」
「短時間掛ける多回数」
みんなで返事をする場をたくさんつくる
◎ 一斉に返事をさせる場面をたくさん設定する
集団の中で声を出す いい練習になる
◎ 1日に何度も返事をする場を設定しよう
「短時間×多回数」は上達の大原則
4 子どもたちの授業態度が劇的に変わるポイント
○授業態度で困ったとき
→ 授業のスタートの仕方を変える
授業の始まりのあいさつは全力で
自分が歯切れよく手本を
→ 3回やらせればできるようになる
さっさと立つことも指導のポイント
「起立と言われたらさっさと立ちましょう」
→ さっさと立てるまで何度か練習させる
そしてあいさつまでをつなげる
「先生がみんなの前に立ったら、さっと立ち上がってあいさつしよう」
すぐあいさつ、腰掛ける、
2秒 - すぐに
◎ グズグズしている子を待たないですぐに始めることが大切。
さっと取りかかることにより、授業がしまってくる。
5 教科書の出し方でクラスが変わる!
○教科書の出し方一つでクラスが変わる
気持ちを素早く切り替えられるようになる
教科書の出し方を指導するポイント
「パッと出せるようになりましょう」
「国語の教科書を出してと言うから用意しておきましょう」
予告をしておく ~ 練習
数日で全員できるようになる ~ 成功体験
◎「パッと出せることができました。すばらしい。立派ですね」
「次は音を出さないようにしましょう」
◎ 高速スタートですべての面がスピードアップする。
すばやく行動できる技(段取り)を教えよう
「鷲田小彌太さんはこんなことを」7回目、
「本はこう買えこう読めこう使え」の紹介7回目 最終です。
出版社の案内には
「道具として役に立つ読書。元気が出る読書。普段着の読書。この三つ
のテーマのもとに、情報化社会の現代のための実践的『本』の活用法
を説く。明るく、迅速かつ積極的に生きるための読書術。」
とあります。
1996年、出版された年を感じさせる読書案内であるように感じます。
もう一つ、再掲載となりますが、杉渕鐵良さんの
「子ども集団を動かす魔法のワザ」①を載せます。
教員、特に担任が知っておくとよいワザですが、読み直してみて
この10年間で子どもが大きく変わってきていることを感じています。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆鷲田小彌太さんはこんなことを ⑦-「本はこう買えこう読めこう使え」大和書房 1996年(7)(最終)

◇教養を手軽に学ぶ
□知的生活のすすめ
ちょっとかっこよく生きる
渡部昇一『知的生活の方法』講談社現代新書
努力の意味
竹内洋『受験生の社会史』『立志・哲学・出世』現代新書
大人の読書
向井敏『贅沢な読書』現代新書
『文章読本』文藝春秋
□思想と科学に強くなる
思想に手がかりを求める
今村仁司『現代思想のキーワード』現代新書
科学と技術の怖さと豊かさ
坂本賢三『現代科学をどうとらえるか』現代新書
最前線を知る
米本昌平『バイオエシックス』現代新書
資本主義社会と人間の欲望
日本は進んでいる
飯田経夫『豊かさとは何か』現代新書
ガルブレイス『豊かな社会』岩波書店
欲望の起源
丸山圭三郎『言葉・狂気・エロス』現代新書
資本主義を動かすものとその行方
佐伯啓思『欲望と資本主義』現代新書
☆「子ども集団を動かす魔法のワザ」杉渕鐵良 学陽書房 2010年 ①【再掲載 2013.7】
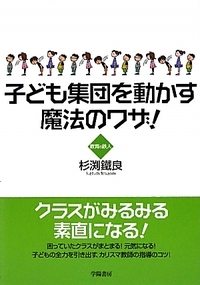
◇杉渕鐵良
1959年 東京生 現在(2010年3月)足立区立綾瀬小学校
「どの子もひとり残らず伸ばす」
「一人も落ちこぼれをつくらない」
クラスをまとめていくこと、子どもを変えていくことができるのは、
教師の覚悟と情熱が決め手
◇子ども集団に基本を教える魔法のワザ!(前半)
基本こそがクラスを変える
基本を全力でやることが大切
あいさつ、返事、学習態度
杉渕指導モットー
「あたりまえのことを究極まで高める」
あいさつや返事は全力で声を出させることが大事
|
例えば返事をさせるときも子どもに全力を出させる
一週間でも頑張って続けると…子どもの表情、クラスの雰囲気が変わる
基本をできるようにするのは教師の一番の仕事
起立の仕方、座り方、立ち方(限界をひいてはいけない)
教師は叱るべき時には叱るが、いつもはユーモアで
こども一人一人に合った指導を考え、うまく子どもを誘導することが
必要
=毎日、何度もそのことを繰り返したり、練習させたりすることが大切
やり直し
~ほめたり、ユーモアを交えながら面白くテンポよく
「覚悟をもって」
ユーモア満載、テンポよく、しつこく指導
1 子どもがみるみるあいさつできる子に!
○子どもにあいさつを教えるには
「ありがとう」を言えない子
◎ 子どもの意識があいさつに向くのを待ってあげる余裕が大事。教
師から声を掛け、「○○君」と名前を言ってからあいさつしよう。
2 大きな声であいさつさせるには?
○教師が手本を見せる
全員あいさつ → 個人全員 → 全員
◎ スピードとテンポが大事。ダラダラしていると効果なし。声を出
せた子には、「○○君、いいねえ」と褒める。声を出せる子を一人
ずつ増やしていこう。
3 大きな返事が子どもの意識を変える!
○返事をする場面をとにかくたくさん設定する
「出席をとります」 「はい」
「プリントを配ります」 「はい」
「短時間掛ける多回数」
みんなで返事をする場をたくさんつくる
◎ 一斉に返事をさせる場面をたくさん設定する
集団の中で声を出す いい練習になる
◎ 1日に何度も返事をする場を設定しよう
「短時間×多回数」は上達の大原則
4 子どもたちの授業態度が劇的に変わるポイント
○授業態度で困ったとき
→ 授業のスタートの仕方を変える
授業の始まりのあいさつは全力で
自分が歯切れよく手本を
→ 3回やらせればできるようになる
さっさと立つことも指導のポイント
「起立と言われたらさっさと立ちましょう」
→ さっさと立てるまで何度か練習させる
そしてあいさつまでをつなげる
「先生がみんなの前に立ったら、さっと立ち上がってあいさつしよう」
すぐあいさつ、腰掛ける、
2秒 - すぐに
◎ グズグズしている子を待たないですぐに始めることが大切。
さっと取りかかることにより、授業がしまってくる。
5 教科書の出し方でクラスが変わる!
○教科書の出し方一つでクラスが変わる
気持ちを素早く切り替えられるようになる
教科書の出し方を指導するポイント
「パッと出せるようになりましょう」
「国語の教科書を出してと言うから用意しておきましょう」
予告をしておく ~ 練習
数日で全員できるようになる ~ 成功体験
◎「パッと出せることができました。すばらしい。立派ですね」
「次は音を出さないようにしましょう」
◎ 高速スタートですべての面がスピードアップする。
すばやく行動できる技(段取り)を教えよう



