鷲田小彌太さんはこんなことを ⑩-「現代知識人の作法」青弓社 1995年 (3) /「先生が忙しすぎるをあきらめない」妹尾昌俊 教育開発研究所2017年 ③【再掲載 2019.2】 [読書記録 一般]
今回は、8月8日に続いてわたしの読書ノートから、
「鷲田小彌太さんはこんなことを」10回目、
「現代知識人の作法」3回目の紹介です。
出版社の案内には
「知が社会と切り結ぶための有効な作法とは? アカデミズムとジャー
ナリズムが異種交配する現代知の変容やその系譜を分析し、大衆知識
社会と化した時代における新しい知識人の発現する可能態を、新教養
主義=知的ゼネラリズムとして導き出す。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「知識人が変わった。文体が変わった」
・「大衆と知識人の間に乗り換え不能な壁は存在しない
知が大衆化した」
・「教育のビジネス化『大学にはビジネスチャンスが落ちている』」
もう一つ、再掲載となりますが、妹尾昌俊さんの
「先生が忙しすぎるをあきらめない」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆鷲田小彌太さんはこんなことを ⑩-「現代知識人の作法」青弓社 1995年 (3)
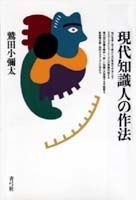
◇現代知識人の変容 教養知の可能性(2)
□現代知識人の類型
研究・教育・行政の三位一体 - 梅棹忠夫
梅棹忠夫(1920~)『知的生産の技術』岩波新書
政治と文芸の拮抗 - 江藤淳
江藤淳(1932~) ジャーナルの人
政治が好きでたまらない
アカデミズムのジャーナリズムの絶対矛盾的自己統一 - 小室直樹
小室直樹(1932~)正統であり奇である
京大理学部数学科
フルブライト留学
ミシガン大 - スーツから計量経済学
ハーバード大 - スキナーから心理学
- パーソンズから社会学
MIT - サミュエルソン 理論経済学
1963 東大大学院政治学科
丸山真男から政治学
川島武宜から法社会学
中根千枝から文化人類学
大塚久雄からウェーバー
□新教養主義の宣揚のために
情報と生活技術の多様化
知識人の変化
① 知識人が変わった
② 文体が変わった
現在
~ 知識を対価に生きる人
大衆が変わった かつて大学 学術論文以外は雑文
↓
現在大衆に了解不能なものはお蔵入り
大衆と知識人の間に乗り換え不能な壁は存在しない
→ 知の大衆化
消費への中心価値移動
個人消費中心
浪費のすすめの倫理学
□教育とビジネスの高度化
高学歴社会
個人消費の半分以上が選択消費
大学
かつては 専門を修養する場 専門学
今は 専門学のための入り口 教養学
∥
◎ 世界市民として広い見地に立って知識・技術・マナー
高度知識高度技術社会
知識の高速化=国際化
個人化とネットワークの拡大化が極限まで進む
教育のビジネス化
大学 研究と教育の機関 → ビジネス原理(大学の自由化)
∥
◎「大学にはビジネスチャンスが落ちている」
□専門的教養こそ知の主戦場である
教養の新旧定義
旧 教養ある人=職業的な活動をする必要のない人
有閑人(スカラー)=知識人 「君子」
読書人-本の人
↓
◎ 実学化
教養の廃止が問題か?
戦後 一般教養(戦後教育)見直された
旧教養学は廃棄 → しかし廃止しないで
① 総合知が重要になる
スペシャリストであるためにはゼネラリスト
② 習得に手間も時間も掛かる
学の全体像
新総合知のシステムが登場した
新総合知の誕生の要求
総合学部 + 学部のない大学院大学
☆「先生が忙しすぎるをあきらめない」妹尾昌俊 教育開発研究所2017年 ③【再掲載 2019.2】
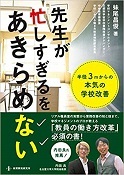
◇本気の学校改善 あきらめる前にできる半径3mからの実践
[基本方針1]
現実を見よ。本当にこのままでよいのかという対話を!
□忙しすぎる学校をあきらめているあなたへ
□そもそも法律上は残業なしが原則
教職員調整手当4%(月8時間分)がつく
= 今の実態から大きく乖離
超勤4項目
① 生徒の実習
② 学校行事
③ 職員会議
④ 非常災害
|
◎ 残業なしが原則中の原則
□校長は人がいいだけでは×
校長は労務管理の現場責任者
□まず超勤勤務の見える化を
<具体案1-1>
タイムカード・ICカードで労働実態を把握する
京田辺市 - パソコンのログオフ把握 → 管理職のPC上に
□教員は自分のためにも時間を把握しよう
<具体案1-2>
養護教諭、事務職員の○○
<具体案1-3>
弊害について気付き振り返る場を
[基本方針2]
「子どものため」ばかり言うな
□6つの神話を疑って掛かろう
<具体案2-1>
目標の重点化の前に課題の重点化を
重要課題トップ3について教職員等の義務を出す
<具体案2-4>
振り返りシート チェックシート式
◎提出物等の丁寧なチェックも、もう少し楽にしてみる
[基本方針3]
教員でなくてもできることは他にさせるとともにチームで対応できる
ようにする
□その仕事はあなたでなくてもできない?
<具体案3-1>
学習アシスタントの活用(岡山県)
□教員がお金を扱う仕事を大幅に減らす
<具体案3-2>
役割分担の見直しにとどまらず、学習プロセス自体の見直しをする
□日常的な不満と疑問が背改善のヒント
<具体案3-3>
何でも自前はやめ、過去や全国の実践等から真似て学ぶ
玉置崇教授「仕事が速い人は模倣…」
<具体案3-4>
仕事を任せきりにせず、進捗を確認し悩みを打ち明けられる場を作る
「鷲田小彌太さんはこんなことを」10回目、
「現代知識人の作法」3回目の紹介です。
出版社の案内には
「知が社会と切り結ぶための有効な作法とは? アカデミズムとジャー
ナリズムが異種交配する現代知の変容やその系譜を分析し、大衆知識
社会と化した時代における新しい知識人の発現する可能態を、新教養
主義=知的ゼネラリズムとして導き出す。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「知識人が変わった。文体が変わった」
・「大衆と知識人の間に乗り換え不能な壁は存在しない
知が大衆化した」
・「教育のビジネス化『大学にはビジネスチャンスが落ちている』」
もう一つ、再掲載となりますが、妹尾昌俊さんの
「先生が忙しすぎるをあきらめない」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆鷲田小彌太さんはこんなことを ⑩-「現代知識人の作法」青弓社 1995年 (3)
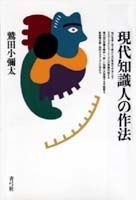
◇現代知識人の変容 教養知の可能性(2)
□現代知識人の類型
研究・教育・行政の三位一体 - 梅棹忠夫
梅棹忠夫(1920~)『知的生産の技術』岩波新書
政治と文芸の拮抗 - 江藤淳
江藤淳(1932~) ジャーナルの人
政治が好きでたまらない
アカデミズムのジャーナリズムの絶対矛盾的自己統一 - 小室直樹
小室直樹(1932~)正統であり奇である
京大理学部数学科
フルブライト留学
ミシガン大 - スーツから計量経済学
ハーバード大 - スキナーから心理学
- パーソンズから社会学
MIT - サミュエルソン 理論経済学
1963 東大大学院政治学科
丸山真男から政治学
川島武宜から法社会学
中根千枝から文化人類学
大塚久雄からウェーバー
□新教養主義の宣揚のために
情報と生活技術の多様化
知識人の変化
① 知識人が変わった
② 文体が変わった
現在
~ 知識を対価に生きる人
大衆が変わった かつて大学 学術論文以外は雑文
↓
現在大衆に了解不能なものはお蔵入り
大衆と知識人の間に乗り換え不能な壁は存在しない
→ 知の大衆化
消費への中心価値移動
個人消費中心
浪費のすすめの倫理学
□教育とビジネスの高度化
高学歴社会
個人消費の半分以上が選択消費
大学
かつては 専門を修養する場 専門学
今は 専門学のための入り口 教養学
∥
◎ 世界市民として広い見地に立って知識・技術・マナー
高度知識高度技術社会
知識の高速化=国際化
個人化とネットワークの拡大化が極限まで進む
教育のビジネス化
大学 研究と教育の機関 → ビジネス原理(大学の自由化)
∥
◎「大学にはビジネスチャンスが落ちている」
□専門的教養こそ知の主戦場である
教養の新旧定義
旧 教養ある人=職業的な活動をする必要のない人
有閑人(スカラー)=知識人 「君子」
読書人-本の人
↓
◎ 実学化
教養の廃止が問題か?
戦後 一般教養(戦後教育)見直された
旧教養学は廃棄 → しかし廃止しないで
① 総合知が重要になる
スペシャリストであるためにはゼネラリスト
② 習得に手間も時間も掛かる
学の全体像
新総合知のシステムが登場した
新総合知の誕生の要求
総合学部 + 学部のない大学院大学
☆「先生が忙しすぎるをあきらめない」妹尾昌俊 教育開発研究所2017年 ③【再掲載 2019.2】
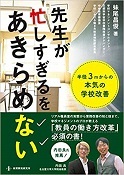
◇本気の学校改善 あきらめる前にできる半径3mからの実践
[基本方針1]
現実を見よ。本当にこのままでよいのかという対話を!
□忙しすぎる学校をあきらめているあなたへ
□そもそも法律上は残業なしが原則
教職員調整手当4%(月8時間分)がつく
= 今の実態から大きく乖離
超勤4項目
① 生徒の実習
② 学校行事
③ 職員会議
④ 非常災害
|
◎ 残業なしが原則中の原則
□校長は人がいいだけでは×
校長は労務管理の現場責任者
□まず超勤勤務の見える化を
<具体案1-1>
タイムカード・ICカードで労働実態を把握する
京田辺市 - パソコンのログオフ把握 → 管理職のPC上に
□教員は自分のためにも時間を把握しよう
<具体案1-2>
養護教諭、事務職員の○○
<具体案1-3>
弊害について気付き振り返る場を
[基本方針2]
「子どものため」ばかり言うな
□6つの神話を疑って掛かろう
<具体案2-1>
目標の重点化の前に課題の重点化を
重要課題トップ3について教職員等の義務を出す
<具体案2-4>
振り返りシート チェックシート式
◎提出物等の丁寧なチェックも、もう少し楽にしてみる
[基本方針3]
教員でなくてもできることは他にさせるとともにチームで対応できる
ようにする
□その仕事はあなたでなくてもできない?
<具体案3-1>
学習アシスタントの活用(岡山県)
□教員がお金を扱う仕事を大幅に減らす
<具体案3-2>
役割分担の見直しにとどまらず、学習プロセス自体の見直しをする
□日常的な不満と疑問が背改善のヒント
<具体案3-3>
何でも自前はやめ、過去や全国の実践等から真似て学ぶ
玉置崇教授「仕事が速い人は模倣…」
<具体案3-4>
仕事を任せきりにせず、進捗を確認し悩みを打ち明けられる場を作る



