「幸田露伴の語録に学ぶ自己修養法」渡部昇一 致知出版社 2011年 ⑤(最終) / 有田和正さんはこんなことを ⑦ 「このユーモアが明るい子を育てる」 有田和正 企画室 1999年 (1)【再掲載 2012.10】 [読書記録 一般]
今回は、8月20日に続いて、渡部昇一さんの
「幸田露伴の語録に学ぶ自己修養法」5回目 最終の紹介です。
出版社の案内には、
「第一回文化勲章受章者であり、代表作『五重塔』で知られる作家・幸田
露伴(1867~1947)。かつて慶大塾長小泉信三博士に『百年に一度の頭脳』
と言わしめた露伴の実績は、現在、全42巻の『幸田露伴全集』として
結実している。その昔、若き露伴は電信技師として北海道へ赴任する。
しかし、文学への思いを断ち難く帰京を決意。連絡船で青森へ渡った後、
徒歩にて帰京をするが餓死寸前にまで至る。その間の野宿で、露を伴っ
て寝たので『露伴』と名乗った。所謂出世コースとは無縁だった露伴は、
その人生航路において、自己修養の重要性を認識し実践していたのであ
る。本書は、当代随一の論客として活躍を続ける渡部氏が、露伴の思想
と実践とに、自らの実体験を重ね合わせて綴った、すべての現代人に贈
る自己修養論である。本書で取り上げている作品は、『努力論』『修省論』
『靄護精舎雑筆』の3作。渡部氏はこれらの作品を文字通り座右に置き、
数え切れないほど読み返してきたというが、そのいずれにも、露伴独特
の味わいのある文章中に、万人に共通する人生の機微、生き方の極意が
述べられている。そして、それらは今日のような時代状況の中では、前
途に立ちはだかる困難を、自らの手で切り開かんとする人たちの心を奮
い立たせ、充実した気を注入するものとして大いに役立つに違いない。
露伴の『生き方の原理原則の言葉』に心底から共鳴し、露伴を敬愛して
やまぬ渡部氏の手になる本書には、明治から昭和の文壇の巨匠、そして
現代の碩学が実践してきた自己修養法、生き方のエッセンスがぎっしり
と詰まっている。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は‥
・「うんと時間が掛からないとわからないことが世の中には非常に多い。
合理的なものは文明として残っているし、役に立たないものは自然に
滅びる - ハイエク」
・「特攻隊とは自ら進んで特攻に出ようとする人は尊いが、上からの命令
にしたがってしまった人。一番上の人が和平交渉を嫌がったから特攻
隊が生まれた。上の人のエゴイズム」
・「人間は生まれながらの上下はなく、その後の努力によって価値が決ま
る - スペンサー思想」
もう一つ、再掲載となりますが、
「有田和正さんはこんなことを」⑦を載せます。
有田さんのエネルギッシュな実践を思い出しました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「幸田露伴の語録に学ぶ自己修養法」渡部昇一 致知出版社 2011年 ⑤(最終)

<今日本に求められる修養の力>
1子どもの減少は日本の急速な退潮を証明している
張る気を失った日本の危機
今こそ形式の重要性を見直すべきである
形を捨て去ることは心を捨て去ることにつながる
伝統が残るにはしかるべき理由がある
結論をいそぐな時間を掛けないと分からないこともある
ハイエク
「うんと時間が掛からないとわからないことが世の中には非常に
多い。合理的なものは文明として残っているし、役に立たない
ものは自然に滅びる」
チェスタトン
「オーソドクシー(正統)」
伝統はタテにつながったデモクラシー
4なぜ日本に犠牲的精神が失われてしまったのか
犠牲は強いるものであってはならない
犠牲 = いちばん崇高なものでありいちばん下劣なものである
特攻隊 = 自ら進んで特攻に出ようとする人は尊いが上からの
命令にしたがってしまった人
↓
◎ 一番上の人が和平交渉を嫌がったから =エゴイズム
ハーマン・ウォーク
「戦争と記憶」
|
◎崇高なものほど、その極としていちばん残酷になりかねない
5自己責任の時代とは「修養の時代」である
講談社「修養全集」
自助論思想
渡部「ヒルティに学ぶ心術」(致知出版社)
↑↓
社会主義
「人のやっていることをあてにする」制度
人任せ
◇おわりに 修養時代の復活
社会主義とは何だったのか
マルクス主義・社会主義
① 私有財産は悪いものである
② 金持ちが生まれるようなものは許すべきではない
③ 土地の所有を認めない
∥
◎ 個人が絶対に富めるようにしない制度
貧しい人々の嫉妬心に訴えた
イギリス
20世紀初
ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス・アンド・ポリティカル・サイエンス LSED
ウェッブ夫妻創設
社会主義的立法行政
のちのロンドン大学経済学部
1917 ロシア革命の引き金
↓
日本でも社会主義の力が強大に → 軍隊を巻き込んだ右翼
大川周名も北一輝も
社会主義は何ももたらさなかった
再び脚光を浴びるスペンサーの思想
スペンサー
社会進化論
- 適者生存優勝劣敗思想
∥
明治維新政治家
富国強兵 殖産興業思想
∥
明治日本を形どった思想はスペンサーの思想
国力を充実しアジア唯一の近代国家に
中村正直(敬宇)「西国立志編」
福沢諭吉「学問のすすめ」
→ 人間は生まれながらの上下はなく、その後の努力によって価値
が決まる
↓
スペンサー思想 ◎本多静六博士 日本林学創始者 日比谷公園
◎幸田露伴
ノーマン・v・ピール
「ポジィティブ・シンキング」の世界
幸田露伴 新渡戸稲造 本多静六の修養の世界
サッチャー ビール牧師
幸田露伴は修養の人
→ 古く見えるが本来に向けての新しい考え方になりうる
◇幸田露伴
慶応3(1867)年 江戸 下谷生 小説家・随筆家
電信修技学校卒
電信技手として北海道に赴任するも文学へと明治20(1887)年帰京
明治22(1889)年 作家の地位確立 「露団々」「風流仏」
理想詩人 「五重塔」明治25が代表作
昭和12(1937)年 第1回文化勲章受章
昭和22(1947)年没
次女-幸田文 その娘は青木玉
2002.12.22
☆有田和正さんはこんなことを ⑦ 「このユーモアが明るい子を育てる」 有田和正 企画室 1999年 (1)【再掲載 2012.10】
<出版社の案内>
親のユーモアある対応が子どものピンチを救い、いきいきとした明るい子
に変えていく。教室に笑いを巻き起こしてきた著者が、親子が一緒に笑っ
て暮らす明るい家庭を作るためのノウハウを紹介する。
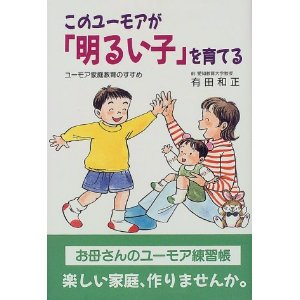
◇「どうぞ(おもいやり)」「ありがとう(感謝)がユーモアを生む
□「どうぞ」(思いやり)という心がユーモアを生む
「どうぞ」の一言が人の心を和ませる
「どうぞ」と言うと笑顔になる
「鉛筆貸して!」「どうぞ!」
「友達っていいな」
友達の良さが見える子供
自分の子供の良さが見えるお母さんに
◎子供の逃げ場を作ってあげる
「おじさん お茶の時間ですよ」
「どうぞ」は極楽で生きている
□木村博『モラロジー教育№75 1999.5.20』
「ありがとう」(感謝)と思う気持ちがユーモアを生む
「ありがたい」と思う人思わない人
「子供の七光で役員をさせてもらっています」
「おかげさまで」と言える心を
「死んでも元気でいてください」
「ありがとう」はユーモアです 簡単なことほどできない
「ハイ!」の返事ができない
身の回りをおもしろく見る
「うんこのホテルにはプールがあるよ」
「お母さん、うんこの先生だよ!」
□お母さん、少し派手な服装を!
教師はやや派手な服装で綺麗に見えた方が良い
少し派手なくらいがよい
エコノミー焼きは安くておいしい!
拝啓犬殿
「食べるのはやめた方がいい」「こんな断り方もあるね」
□「握手」しながらモノを見る子供
手に「目」がある小さい子供
子供は手に目があるから何にでもさわる
∥
◎さわれないものは見えない
あくしゅしながらものを見る
花や植物と握手
聴診器 - 木が生きている音が聞こえる
いろんな人と握手をしましょう
「握手しながら見るのよ!」
子供はさわっていけないと言っても触る
「花で握手をしなさい」
「見ること」(目で握手)は楽しいね
一見を生かすには百聞 = 予想が必要
◇子供を輝かせるには
□子供は太鼓だ
太鼓は叩き方によって鳴り方が違う(龍馬の西郷評)
マイナスをプラスを変えるユーモア精神
「いいことを見つけたら、メモしなさい」
テレビもいいこと見つけたらメモ
テレビを見ながら地図帳で調べたりメモして見せたりする
→ 親子でメモ競争
子供の話を良く聞いてあげる
「今日、どんなおもしろいことがあったの?」
人間には「いい系」と「悪い系」の二本ある
「楽しかったことだけ話なさい」
話は短くおもしろく
□子供は結構へそ曲がり
「君の頭では無理だぞ」
「むし歯になる方法を教えてあげよう」
上学年 ~ 逆説的な話も有効 どちらが親なの?
□ユーモア小説を集めるお母さん
「おもしろい」と思って読む癖をつける
→ 毎日の新聞に
ネタを作り替えておもしろくする
「ぼくもおもしろい話(笑い話)を集めたい」
努力によって性格も変えられる
笑い話を集めて自分が笑い子供にも話す
□<教師>
・いつも笑い話を集める、求める
・いつもニコニコする努力 → ネアカに
・大げさに笑う努力
□ユーモアを集める子供に
おもしろい小話をして笑わせる
講演用スクラップブック
おもしろいことをおもしろいと感じる心
「お母さんずるい!」
「こんな話見つけたよ」
◎ユーモアのセンスは財産 表現力が大切
不幸なできごとが笑える子供
□子供が輝けば親も輝く
「偉いね、電話かけてあげるのね!」
「休んだ子供に電話を掛けなさい」
□子供に教わった電話作戦 子供は偉いものです
子供は担任からの電話を待っている
自分の親を「バカ母ちゃん」と言える「子供」
相川浩『ユーモア話術』(KKロングセラーズ)
□ユーモア溢れる子供たち
一年生の子供に脱帽
いろいろな店の春
スーパーの春
薬屋さんの春
パン屋さんの春
資生堂の春
おもしろい実験をする子供
◎「子供にしか見えない世界」がある
叱る前に子供の話を聞く
長岡文雄『学習研究』
葉っぱに描いたへのへのもへじ
◇ユーモアのセンスを磨こう
□モノをよく見る癖をつける
モノを見るということ
本当に見ることは大変なこと
赤福25段積み → 何故か
□見方によって見えるものが違う
「坊や一寸座らせて」
ワルの電車
良いところを見ようという見方で!
「良いところが見える眼鏡」を掛けよう
「おもしろいところが見える眼鏡」を掛けよう
□失敗を笑いの材料にする
「しっ、お父さんが欲しがるんじゃないの?」
子供の頃の失敗話をする
こんないたずらもしたよ
□「お話のあいうえお」の体得
お話のあいうえお
あ 明るく
い 生き生きと
う うれしそうに あいうえおの手紙
え 笑顔で
お おもしろい内容を
◇お母さんは「お釈迦様の指」
□お釈迦様の指の話
ぼけてみせるお母さん
一流の教師
子供に「自分一人の力で育ったのだ」と思わせることのできる教師です
三流の教師
「先生が教えてあげたから成長できたのだ」と思わせる教師
∥
◎ 見えない手で支援する
「大丈夫だ」は大丈夫ではない
□暗示を掛けてその気にさせる
「あなたって本当におもしろいね」
子供を楽しませる努力
ユーモアは技術でもある
自分の家庭はいい家庭だと思わせる
教師、自分の教室はいい教室だと思わせる
→ 自分程幸せな者はいない!
□ユーモアの達人は人生の達人(鉄人)
ユーモアは人間性そのもの
ヒューマンからユーモア
「幸田露伴の語録に学ぶ自己修養法」5回目 最終の紹介です。
出版社の案内には、
「第一回文化勲章受章者であり、代表作『五重塔』で知られる作家・幸田
露伴(1867~1947)。かつて慶大塾長小泉信三博士に『百年に一度の頭脳』
と言わしめた露伴の実績は、現在、全42巻の『幸田露伴全集』として
結実している。その昔、若き露伴は電信技師として北海道へ赴任する。
しかし、文学への思いを断ち難く帰京を決意。連絡船で青森へ渡った後、
徒歩にて帰京をするが餓死寸前にまで至る。その間の野宿で、露を伴っ
て寝たので『露伴』と名乗った。所謂出世コースとは無縁だった露伴は、
その人生航路において、自己修養の重要性を認識し実践していたのであ
る。本書は、当代随一の論客として活躍を続ける渡部氏が、露伴の思想
と実践とに、自らの実体験を重ね合わせて綴った、すべての現代人に贈
る自己修養論である。本書で取り上げている作品は、『努力論』『修省論』
『靄護精舎雑筆』の3作。渡部氏はこれらの作品を文字通り座右に置き、
数え切れないほど読み返してきたというが、そのいずれにも、露伴独特
の味わいのある文章中に、万人に共通する人生の機微、生き方の極意が
述べられている。そして、それらは今日のような時代状況の中では、前
途に立ちはだかる困難を、自らの手で切り開かんとする人たちの心を奮
い立たせ、充実した気を注入するものとして大いに役立つに違いない。
露伴の『生き方の原理原則の言葉』に心底から共鳴し、露伴を敬愛して
やまぬ渡部氏の手になる本書には、明治から昭和の文壇の巨匠、そして
現代の碩学が実践してきた自己修養法、生き方のエッセンスがぎっしり
と詰まっている。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は‥
・「うんと時間が掛からないとわからないことが世の中には非常に多い。
合理的なものは文明として残っているし、役に立たないものは自然に
滅びる - ハイエク」
・「特攻隊とは自ら進んで特攻に出ようとする人は尊いが、上からの命令
にしたがってしまった人。一番上の人が和平交渉を嫌がったから特攻
隊が生まれた。上の人のエゴイズム」
・「人間は生まれながらの上下はなく、その後の努力によって価値が決ま
る - スペンサー思想」
もう一つ、再掲載となりますが、
「有田和正さんはこんなことを」⑦を載せます。
有田さんのエネルギッシュな実践を思い出しました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「幸田露伴の語録に学ぶ自己修養法」渡部昇一 致知出版社 2011年 ⑤(最終)

<今日本に求められる修養の力>
1子どもの減少は日本の急速な退潮を証明している
張る気を失った日本の危機
今こそ形式の重要性を見直すべきである
形を捨て去ることは心を捨て去ることにつながる
伝統が残るにはしかるべき理由がある
結論をいそぐな時間を掛けないと分からないこともある
ハイエク
「うんと時間が掛からないとわからないことが世の中には非常に
多い。合理的なものは文明として残っているし、役に立たない
ものは自然に滅びる」
チェスタトン
「オーソドクシー(正統)」
伝統はタテにつながったデモクラシー
4なぜ日本に犠牲的精神が失われてしまったのか
犠牲は強いるものであってはならない
犠牲 = いちばん崇高なものでありいちばん下劣なものである
特攻隊 = 自ら進んで特攻に出ようとする人は尊いが上からの
命令にしたがってしまった人
↓
◎ 一番上の人が和平交渉を嫌がったから =エゴイズム
ハーマン・ウォーク
「戦争と記憶」
|
◎崇高なものほど、その極としていちばん残酷になりかねない
5自己責任の時代とは「修養の時代」である
講談社「修養全集」
自助論思想
渡部「ヒルティに学ぶ心術」(致知出版社)
↑↓
社会主義
「人のやっていることをあてにする」制度
人任せ
◇おわりに 修養時代の復活
社会主義とは何だったのか
マルクス主義・社会主義
① 私有財産は悪いものである
② 金持ちが生まれるようなものは許すべきではない
③ 土地の所有を認めない
∥
◎ 個人が絶対に富めるようにしない制度
貧しい人々の嫉妬心に訴えた
イギリス
20世紀初
ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス・アンド・ポリティカル・サイエンス LSED
ウェッブ夫妻創設
社会主義的立法行政
のちのロンドン大学経済学部
1917 ロシア革命の引き金
↓
日本でも社会主義の力が強大に → 軍隊を巻き込んだ右翼
大川周名も北一輝も
社会主義は何ももたらさなかった
再び脚光を浴びるスペンサーの思想
スペンサー
社会進化論
- 適者生存優勝劣敗思想
∥
明治維新政治家
富国強兵 殖産興業思想
∥
明治日本を形どった思想はスペンサーの思想
国力を充実しアジア唯一の近代国家に
中村正直(敬宇)「西国立志編」
福沢諭吉「学問のすすめ」
→ 人間は生まれながらの上下はなく、その後の努力によって価値
が決まる
↓
スペンサー思想 ◎本多静六博士 日本林学創始者 日比谷公園
◎幸田露伴
ノーマン・v・ピール
「ポジィティブ・シンキング」の世界
幸田露伴 新渡戸稲造 本多静六の修養の世界
サッチャー ビール牧師
幸田露伴は修養の人
→ 古く見えるが本来に向けての新しい考え方になりうる
◇幸田露伴
慶応3(1867)年 江戸 下谷生 小説家・随筆家
電信修技学校卒
電信技手として北海道に赴任するも文学へと明治20(1887)年帰京
明治22(1889)年 作家の地位確立 「露団々」「風流仏」
理想詩人 「五重塔」明治25が代表作
昭和12(1937)年 第1回文化勲章受章
昭和22(1947)年没
次女-幸田文 その娘は青木玉
2002.12.22
☆有田和正さんはこんなことを ⑦ 「このユーモアが明るい子を育てる」 有田和正 企画室 1999年 (1)【再掲載 2012.10】
<出版社の案内>
親のユーモアある対応が子どものピンチを救い、いきいきとした明るい子
に変えていく。教室に笑いを巻き起こしてきた著者が、親子が一緒に笑っ
て暮らす明るい家庭を作るためのノウハウを紹介する。
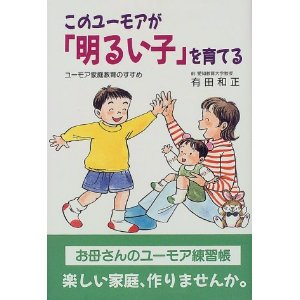
◇「どうぞ(おもいやり)」「ありがとう(感謝)がユーモアを生む
□「どうぞ」(思いやり)という心がユーモアを生む
「どうぞ」の一言が人の心を和ませる
「どうぞ」と言うと笑顔になる
「鉛筆貸して!」「どうぞ!」
「友達っていいな」
友達の良さが見える子供
自分の子供の良さが見えるお母さんに
◎子供の逃げ場を作ってあげる
「おじさん お茶の時間ですよ」
「どうぞ」は極楽で生きている
□木村博『モラロジー教育№75 1999.5.20』
「ありがとう」(感謝)と思う気持ちがユーモアを生む
「ありがたい」と思う人思わない人
「子供の七光で役員をさせてもらっています」
「おかげさまで」と言える心を
「死んでも元気でいてください」
「ありがとう」はユーモアです 簡単なことほどできない
「ハイ!」の返事ができない
身の回りをおもしろく見る
「うんこのホテルにはプールがあるよ」
「お母さん、うんこの先生だよ!」
□お母さん、少し派手な服装を!
教師はやや派手な服装で綺麗に見えた方が良い
少し派手なくらいがよい
エコノミー焼きは安くておいしい!
拝啓犬殿
「食べるのはやめた方がいい」「こんな断り方もあるね」
□「握手」しながらモノを見る子供
手に「目」がある小さい子供
子供は手に目があるから何にでもさわる
∥
◎さわれないものは見えない
あくしゅしながらものを見る
花や植物と握手
聴診器 - 木が生きている音が聞こえる
いろんな人と握手をしましょう
「握手しながら見るのよ!」
子供はさわっていけないと言っても触る
「花で握手をしなさい」
「見ること」(目で握手)は楽しいね
一見を生かすには百聞 = 予想が必要
◇子供を輝かせるには
□子供は太鼓だ
太鼓は叩き方によって鳴り方が違う(龍馬の西郷評)
マイナスをプラスを変えるユーモア精神
「いいことを見つけたら、メモしなさい」
テレビもいいこと見つけたらメモ
テレビを見ながら地図帳で調べたりメモして見せたりする
→ 親子でメモ競争
子供の話を良く聞いてあげる
「今日、どんなおもしろいことがあったの?」
人間には「いい系」と「悪い系」の二本ある
「楽しかったことだけ話なさい」
話は短くおもしろく
□子供は結構へそ曲がり
「君の頭では無理だぞ」
「むし歯になる方法を教えてあげよう」
上学年 ~ 逆説的な話も有効 どちらが親なの?
□ユーモア小説を集めるお母さん
「おもしろい」と思って読む癖をつける
→ 毎日の新聞に
ネタを作り替えておもしろくする
「ぼくもおもしろい話(笑い話)を集めたい」
努力によって性格も変えられる
笑い話を集めて自分が笑い子供にも話す
□<教師>
・いつも笑い話を集める、求める
・いつもニコニコする努力 → ネアカに
・大げさに笑う努力
□ユーモアを集める子供に
おもしろい小話をして笑わせる
講演用スクラップブック
おもしろいことをおもしろいと感じる心
「お母さんずるい!」
「こんな話見つけたよ」
◎ユーモアのセンスは財産 表現力が大切
不幸なできごとが笑える子供
□子供が輝けば親も輝く
「偉いね、電話かけてあげるのね!」
「休んだ子供に電話を掛けなさい」
□子供に教わった電話作戦 子供は偉いものです
子供は担任からの電話を待っている
自分の親を「バカ母ちゃん」と言える「子供」
相川浩『ユーモア話術』(KKロングセラーズ)
□ユーモア溢れる子供たち
一年生の子供に脱帽
いろいろな店の春
スーパーの春
薬屋さんの春
パン屋さんの春
資生堂の春
おもしろい実験をする子供
◎「子供にしか見えない世界」がある
叱る前に子供の話を聞く
長岡文雄『学習研究』
葉っぱに描いたへのへのもへじ
◇ユーモアのセンスを磨こう
□モノをよく見る癖をつける
モノを見るということ
本当に見ることは大変なこと
赤福25段積み → 何故か
□見方によって見えるものが違う
「坊や一寸座らせて」
ワルの電車
良いところを見ようという見方で!
「良いところが見える眼鏡」を掛けよう
「おもしろいところが見える眼鏡」を掛けよう
□失敗を笑いの材料にする
「しっ、お父さんが欲しがるんじゃないの?」
子供の頃の失敗話をする
こんないたずらもしたよ
□「お話のあいうえお」の体得
お話のあいうえお
あ 明るく
い 生き生きと
う うれしそうに あいうえおの手紙
え 笑顔で
お おもしろい内容を
◇お母さんは「お釈迦様の指」
□お釈迦様の指の話
ぼけてみせるお母さん
一流の教師
子供に「自分一人の力で育ったのだ」と思わせることのできる教師です
三流の教師
「先生が教えてあげたから成長できたのだ」と思わせる教師
∥
◎ 見えない手で支援する
「大丈夫だ」は大丈夫ではない
□暗示を掛けてその気にさせる
「あなたって本当におもしろいね」
子供を楽しませる努力
ユーモアは技術でもある
自分の家庭はいい家庭だと思わせる
教師、自分の教室はいい教室だと思わせる
→ 自分程幸せな者はいない!
□ユーモアの達人は人生の達人(鉄人)
ユーモアは人間性そのもの
ヒューマンからユーモア



