「京都御所西一松町物語」杉山正明 日本経済新聞出版社 2011年 ④ /「魂にうったえる授業」伊藤功一 NHKBOOKS 1992年 ②【再掲載 2011.7】 [読書記録 一般]
今回は10月24日に続いて、杉山正明さんの
「京都御所西一松町物語」4回目の紹介です。
出版社の案内には、
「京都御所の西にある小さな街区「一松町」から定点観測すれば、京都1200
年の出来事が鮮やかによみがえる。この町の住人でもある歴史家が、ロー
カル&グローバルな視点で語る、まったく新しい京都歴史読本。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は‥
・「一条小川のはじまりは667年恐るべき古さの誓願寺(今は新京極)か」
・「兼好が語る「こかわ」と一条室町
89段の「奥山に猫またというもの」は小川のほとり。魔女のウワサも」
・「『下民からの成り上がり』という秀吉への悪口はうさんくささをごまか
すため。秀吉は時代の魔術師であり、パタパタと扇を仰ぐように日本を
とりまとめた」
・「秀吉による聚楽第とお土居。お土居は日本史上唯一の王城を囲む全長
23㎞の壁。幻の聚楽第。上京中学・新町小学校から金箔瓦が出土」
もう一つ、再掲載になりますが、伊藤功一さんの
「魂にうったえる授業」②を載せます。
この30年間の間にITが多く取り入れられるようになり、
研修も少しずつ変わってきました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「京都御所西一松町物語」杉山正明 日本経済新聞出版社 2011年 ④
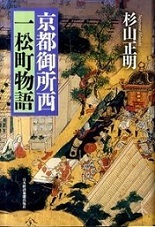
Ⅵ 過ぎし日の一条小川の記憶 京外の祈りと楽しみの場
1.はじまりは誓願寺か
恐るべき古さ
667年 誓願寺(今は新京極)
2.小川と誓願寺に関わる二人
清少納言と和泉式部
才女たちの時代
二人の女人伝説
3.女人往生の寺と和泉式部伝説
誓願寺と法然
浄土宗
和泉式部と一遍
そして謡曲
時空を超えて生きる和泉式部
4.兼好が語る「こかわ」と一条室町
89段 「奥山に猫またというもの」
小川のほとり
小川と革堂
魔女のウワサ
5.故書が伝える小川の姿
「小河」の水上レストラン
~ 鴨川・納涼床のはしり?
小川一町
~ 小川うつぼや町(靫屋町)
Ⅶ 秀吉が開いた近世京都 豪奢絢爛たる時代
1.信長から始まる次なる京への道
信長と京都
信長と一松町界隈
1559年
上洛
- 寄宿先 室町通上京うら辻
1570年
上洛(義昭を奉じて)「上京・ろ庵」に投宿
「元ろあん町」と武者小路での築城プラン
「上京ろ庵」
~「半井馬廬庵」名高い医師
上京中学の北側
一松町の南端辺り
|
信長 自分の城を計画
- 武者小路通辺りに
2.幻の信長の居城 そして京都御苑
一松町には一条殿と日野殿の公家屋敷
3.稀代(きたい)のイリュージョナリスト秀吉
秀吉への悪口は徳川家へのコンプレックスの裏返し
徳川・松平
~ もともと新田・足利近辺時宗の破れ坊主の流れ者
三河の土豪程度の未亡人の入り婿が始まり
|
※ 「下民からの成り上がり」という秀吉への悪口はうさんくささ
をごまかすため
- 秀吉は時代の魔術師
パタパタと扇を仰ぐように日本をとりまとめた
~ 急ごしらえ
4.秀吉の京都大改造と聚楽第の出現
秀吉 京都大改造
伏見城 聚楽第 お土居
大航海時代というナンセンスな考え
小さな船
巨大な外城・外郭・団郭をもつ
5.聚楽第とお土居
日本史上唯一の王城を囲む壁
1591年 全長23㎞羅城-京廻ノ堤
高さ3.6~5.4m 厚さ18~20m
幻の聚楽第
上京中学・新町小学校から金箔瓦
6.京極竜子の光と影
京極家のお姫様
信長・光秀・そして秀吉
7.秀吉が憧れた京極竜子
おねと京極竜子
京極竜子と誓願寺
洛中の寺院を寺町通に移させた
☆「魂にうったえる授業」伊藤功一 NHKBOOKS 1992年 ②【再掲載 2011.7】

◇私の授業
□校長と授業
校長自らが授業実践を通して,その困難さや教材研究の労苦を,担任教
師たちと共感できる能力を指していて,そのことが校長として必要
[授業] 家族 浅間山噴火-遺跡に神社階段前逃げ遅れた二人
[授業] 屋根
林竹二
「子供は学びたがっている。教師はパンを欲しがっている子供に石を
与えている」
◎ 大切なのは「教師の内に伝えたいものがある」
∥
※ 集中とは?
◇開放的な研修を
授業を問い直すことの重要さ
= 教えるためにまず教師が学ばなければならない
↓
◎ 学問的根拠の必要性に目覚め,自信の授業を問い直すことによって
授業の再創造に取り組む
「授業の再創造」
□開放的な研修を
校外から優れた実践者や識見の持ち主を招いて共同による研修へと変
えていく
∥
学校外の優れた人との共同による解放的研修
□現職教育の現状
① 研修機会の不足
回数・人員に制限
旅費不足 → 自費参加研修
② 研修参加
授業補欠が思うように行かない
補欠 - 教務・教頭・校長
↑
◎ 人に迷惑をかけるとおっくうに
= 機会はあるが参加条件整備は不十分
↓
◎ 校内研修重視
□校内研修の問題点
① 義務として行われている
あまりにも義務的
毎年同じことの繰り返し,飽くことなく続ける
パターン化された研修主題と手順
→ 消極的な姿勢
↑
研修が自分自身のためのものでなく,いつも,子供のためにと
か教育公務員としての義務だからという発想
② 研修主題の設定にあたって教師自身を問うことが殆どない
研究の過程で最小の努力で最大の効果を上げるための方法が形
式的にやってみる程度のものにすり替わってしまう
↓
効率化の名の下に,最小限の努力しか払わずに,子供たちには
最大の変容を期待することになる
◎ 教師はいつでも他人をどうするかということばかりに目を向けて,
自分自身の資質をどのように向上させていくか,自分をどのように
変容させるかについてはほとんど無視され続けてきた。
↓
◎ 変革を
◎ 小学校と教員養成大学が共同して研究を!
授業に一般的な法則などない
究極は「取り返しのつかない出会いの場」
↓
◎自らを常に問題にする教師の誠実さ
NHK特集「若き教師たちへ」1991.4.29放送
「京都御所西一松町物語」4回目の紹介です。
出版社の案内には、
「京都御所の西にある小さな街区「一松町」から定点観測すれば、京都1200
年の出来事が鮮やかによみがえる。この町の住人でもある歴史家が、ロー
カル&グローバルな視点で語る、まったく新しい京都歴史読本。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は‥
・「一条小川のはじまりは667年恐るべき古さの誓願寺(今は新京極)か」
・「兼好が語る「こかわ」と一条室町
89段の「奥山に猫またというもの」は小川のほとり。魔女のウワサも」
・「『下民からの成り上がり』という秀吉への悪口はうさんくささをごまか
すため。秀吉は時代の魔術師であり、パタパタと扇を仰ぐように日本を
とりまとめた」
・「秀吉による聚楽第とお土居。お土居は日本史上唯一の王城を囲む全長
23㎞の壁。幻の聚楽第。上京中学・新町小学校から金箔瓦が出土」
もう一つ、再掲載になりますが、伊藤功一さんの
「魂にうったえる授業」②を載せます。
この30年間の間にITが多く取り入れられるようになり、
研修も少しずつ変わってきました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「京都御所西一松町物語」杉山正明 日本経済新聞出版社 2011年 ④
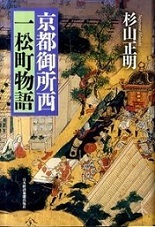
Ⅵ 過ぎし日の一条小川の記憶 京外の祈りと楽しみの場
1.はじまりは誓願寺か
恐るべき古さ
667年 誓願寺(今は新京極)
2.小川と誓願寺に関わる二人
清少納言と和泉式部
才女たちの時代
二人の女人伝説
3.女人往生の寺と和泉式部伝説
誓願寺と法然
浄土宗
和泉式部と一遍
そして謡曲
時空を超えて生きる和泉式部
4.兼好が語る「こかわ」と一条室町
89段 「奥山に猫またというもの」
小川のほとり
小川と革堂
魔女のウワサ
5.故書が伝える小川の姿
「小河」の水上レストラン
~ 鴨川・納涼床のはしり?
小川一町
~ 小川うつぼや町(靫屋町)
Ⅶ 秀吉が開いた近世京都 豪奢絢爛たる時代
1.信長から始まる次なる京への道
信長と京都
信長と一松町界隈
1559年
上洛
- 寄宿先 室町通上京うら辻
1570年
上洛(義昭を奉じて)「上京・ろ庵」に投宿
「元ろあん町」と武者小路での築城プラン
「上京ろ庵」
~「半井馬廬庵」名高い医師
上京中学の北側
一松町の南端辺り
|
信長 自分の城を計画
- 武者小路通辺りに
2.幻の信長の居城 そして京都御苑
一松町には一条殿と日野殿の公家屋敷
3.稀代(きたい)のイリュージョナリスト秀吉
秀吉への悪口は徳川家へのコンプレックスの裏返し
徳川・松平
~ もともと新田・足利近辺時宗の破れ坊主の流れ者
三河の土豪程度の未亡人の入り婿が始まり
|
※ 「下民からの成り上がり」という秀吉への悪口はうさんくささ
をごまかすため
- 秀吉は時代の魔術師
パタパタと扇を仰ぐように日本をとりまとめた
~ 急ごしらえ
4.秀吉の京都大改造と聚楽第の出現
秀吉 京都大改造
伏見城 聚楽第 お土居
大航海時代というナンセンスな考え
小さな船
巨大な外城・外郭・団郭をもつ
5.聚楽第とお土居
日本史上唯一の王城を囲む壁
1591年 全長23㎞羅城-京廻ノ堤
高さ3.6~5.4m 厚さ18~20m
幻の聚楽第
上京中学・新町小学校から金箔瓦
6.京極竜子の光と影
京極家のお姫様
信長・光秀・そして秀吉
7.秀吉が憧れた京極竜子
おねと京極竜子
京極竜子と誓願寺
洛中の寺院を寺町通に移させた
☆「魂にうったえる授業」伊藤功一 NHKBOOKS 1992年 ②【再掲載 2011.7】

◇私の授業
□校長と授業
校長自らが授業実践を通して,その困難さや教材研究の労苦を,担任教
師たちと共感できる能力を指していて,そのことが校長として必要
[授業] 家族 浅間山噴火-遺跡に神社階段前逃げ遅れた二人
[授業] 屋根
林竹二
「子供は学びたがっている。教師はパンを欲しがっている子供に石を
与えている」
◎ 大切なのは「教師の内に伝えたいものがある」
∥
※ 集中とは?
◇開放的な研修を
授業を問い直すことの重要さ
= 教えるためにまず教師が学ばなければならない
↓
◎ 学問的根拠の必要性に目覚め,自信の授業を問い直すことによって
授業の再創造に取り組む
「授業の再創造」
□開放的な研修を
校外から優れた実践者や識見の持ち主を招いて共同による研修へと変
えていく
∥
学校外の優れた人との共同による解放的研修
□現職教育の現状
① 研修機会の不足
回数・人員に制限
旅費不足 → 自費参加研修
② 研修参加
授業補欠が思うように行かない
補欠 - 教務・教頭・校長
↑
◎ 人に迷惑をかけるとおっくうに
= 機会はあるが参加条件整備は不十分
↓
◎ 校内研修重視
□校内研修の問題点
① 義務として行われている
あまりにも義務的
毎年同じことの繰り返し,飽くことなく続ける
パターン化された研修主題と手順
→ 消極的な姿勢
↑
研修が自分自身のためのものでなく,いつも,子供のためにと
か教育公務員としての義務だからという発想
② 研修主題の設定にあたって教師自身を問うことが殆どない
研究の過程で最小の努力で最大の効果を上げるための方法が形
式的にやってみる程度のものにすり替わってしまう
↓
効率化の名の下に,最小限の努力しか払わずに,子供たちには
最大の変容を期待することになる
◎ 教師はいつでも他人をどうするかということばかりに目を向けて,
自分自身の資質をどのように向上させていくか,自分をどのように
変容させるかについてはほとんど無視され続けてきた。
↓
◎ 変革を
◎ 小学校と教員養成大学が共同して研究を!
授業に一般的な法則などない
究極は「取り返しのつかない出会いの場」
↓
◎自らを常に問題にする教師の誠実さ
NHK特集「若き教師たちへ」1991.4.29放送
「教え方ガイドブック」志水廣 明治図書 2006年 ⑩ /「考える日々Ⅱ」池田晶子 毎日新聞社 1999年【再掲載 2012.1】 [読書記録 教育]
今回は、10月23日に続いて、志水廣さんの
「算数力がつく教え方ガイドブック」10回目の紹介です。
○付け法に取り組むことにより、
声を掛ける機会が増え、子どもとの距離が近くなりました。
指導者におすすめです。
出版社の案内には、
「子どもの内なる知を引き出す算数授業ガイドブック決定版。
志水流算数・数学の授業論はつとに知れ渡っているが、この指導法の柱、
○つけ法も、復唱法も、自ら学ぶ問題解決型授業に迫るためのもの。こ
れら、子どもの内なる知を引き出し構成する授業のノウハウを、基礎基
本から高度なテクまで、実例をいれていただきながら示す。」
とあります。
今回紹介分で強く印象に残った言葉は…
・「机間巡視で子どもの様子を見守る。机間指導で子どもを個別に指導す
る。机間支援でヒントや助言で個別に支援する」
・「子ども全体の進行の様子を把握する。進まない場合は止めて一斉指導
する。そこで確認・見直しをする。」
・「志水式『○付け法』とは、大雑把にいえば机間指導の出前方式で赤ペ
ンで○付けすること。3分間で教室を一周するスピードで一人一人に
声を掛けながら行う指導法。」
・「○付け法のポイントは『スピード』(5秒で眺め声掛け→誤答の場合は
部分肯定+15秒アドバイス)と『正確さ』と『声掛け』」
もう一つ、再掲載になりますが、池田晶子さんの
「考える日々Ⅱ」を載せます。
若くして亡くなられましたが、
今でも多くのことをわたしに気付かせてくれることをありがたく思います。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「教え方ガイドブック」志水廣 明治図書 2006年 ⑩
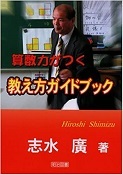
45「できる」までの練習
1 習熟の3段階
3ポイント
① 計算の手順が分かっていること(声に出して言わせる)
② 計算を少しずつ変化させて定着するまで繰り返す
フラッシュカード,計算カード
③ 直感的に答えが出るように
時間限定,枚数を決める
46 志水式音読計算練習法
1 計算カードの音読練習
カードを持って
47 机間指導のねらい
1 机間指導のねらいと3つの言葉
机間巡視 (子どもの様子を見守る)
机間指導 (子どもを個別に指導する)
机間支援 (ヒントや助言で個別に支援する)
3分後に…
2 具体的なねらい
① 子ども全体の進行の様子を把握する
進まない場合は止めて一斉指導
→ 確認・見直しを
② 子ども一人一人の実態を把握(評価)して支援指導する
評価と支援・指導は即時に行う
志水式「○付け法」
③ 子どもの考え方をつかむ
大まかに正答と誤答の割合,正答でも多様な考え方の種類の割合
をつかむ
④ その後の授業展開を修正することを教師が考える
3 机間指導の留意点
① 回るスピードを速くする
② 一人には多くて30秒以内
→ それ以上だと退屈して授業が崩れる
③ 目的を持って回る
思考のどの部分?
誰を見たい?
④ 回るコースを決めておく
⑤ メモを取らない
→ 支援・指導がおろそかになる
※ 机間指導を入力・出力
48 ○付け法で机間指導する
1 志水式「○付け法」とは何か
机間指導の出前方式で赤ペン○
3分間で一周
→ 一人一人へ声掛け
2 ○付けの基本方針
① 全員に○を付ける
② 分かる・できる喜びを与える
③ 肯定部分から始める
プロセス主義
④ ○付け法で気を付けるべきところは
①スピード ②正確さ ③声掛け ④実態把握
⑤次への指示 ⑥判断
⑤ 9割の子どもが見通しを持った時点で回るようにする
とりあえず①導入復習 ②最後の適用問題
◎ スピード,正確さ,声掛けから
49 ○付け法のよさ
1 教師にとっての○付け法のよさ
2 子どもにとっての○付け法
◎ 部分肯定の○付け
50 ○付け法の実際的方法
1 ○付け法のポイント
2 スピード
正答 - 5秒で眺め声掛け
誤答 - 部分肯定 +15秒アドバイス
※ 大きな声
3 正確さ
4 声掛け
○ 「はい,いいね」「調子いいね」「はい正解」
→大きく明るい声
× 「~は合ってるよ ~はちがうよ 考えてごらん」
「なるほどね ~は借りてきてから…」
→ 小さな声で励まし 先に肯定してから
☆「考える日々Ⅱ」池田晶子 毎日新聞社 1999年【再掲載 2012.1】
[出版社の案内]
人生が存在するのはなぜなのか。それは考えているからだ。世は謎を巡る。
千年紀の終わり、通り過ぎた日々へ、今いちど。哲学=考えることの光を。
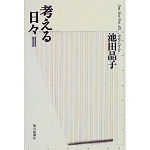
◇池田晶子さん
1960年東京生
文筆家 慶大哲学科卒
専門用語によらない哲学実践の表現開拓
◇幸福は欲するのではなく
欲すると言うことが不幸
= 幸福は欲するものではなく気が付くものだ
◎ 自分が誰だか分からないと気が付くことこそ幸福である。そのとき,自
分が宇宙そのものだと知るから…。
◇団結したのは資本であった
21世紀は壮大なる大失敗
IT化
→ 便利になった時間は愚劣なレジャーに使うぐらいしかない
= 人間の痴呆化
◎ 夢のインターネットの時代は知能の暗黒時代である。
人間の条件は
「生きて死ぬこと」
◇廃棄大処分の悦び
不要なものを捨てること
不要な人は廃棄する
→ 人から廃棄されないように努める
↑
◎ 各自にそういう覚悟が
◇「世代論」の腹立たしさ
団塊の世代
- 全共闘世代
「われわれは」か? 「私は」か?
◇お金を巡る「普通」の心証
金がほしい
→ 働く ○
→ 殺人する ×
◇生きることに「理由」があるか
なぜ生きているのか
→ 生まれたからだ
◇金
マネーでなくお金
= ものと遊離すべきではない
◇教育
◎ 教育が変わらなければ社会は変わり得ない。しかし,社会が変わらなけ
れば教育も変わらない。
教育 = 社会
◇「見える死」を見せてみろ
<脳死は死> と <脳死は人の死>
↓
◎ 見えないもの
◎ 死は言葉である
◇少子化とは誰の問題か
「産み損」
- 計算
◎ 出産が損得になってしまった
↓
◎ 生まれた子も損得に生きる
死ぬときは一人で死ねばいいではないか
= だからこそ生きることが自由
「算数力がつく教え方ガイドブック」10回目の紹介です。
○付け法に取り組むことにより、
声を掛ける機会が増え、子どもとの距離が近くなりました。
指導者におすすめです。
出版社の案内には、
「子どもの内なる知を引き出す算数授業ガイドブック決定版。
志水流算数・数学の授業論はつとに知れ渡っているが、この指導法の柱、
○つけ法も、復唱法も、自ら学ぶ問題解決型授業に迫るためのもの。こ
れら、子どもの内なる知を引き出し構成する授業のノウハウを、基礎基
本から高度なテクまで、実例をいれていただきながら示す。」
とあります。
今回紹介分で強く印象に残った言葉は…
・「机間巡視で子どもの様子を見守る。机間指導で子どもを個別に指導す
る。机間支援でヒントや助言で個別に支援する」
・「子ども全体の進行の様子を把握する。進まない場合は止めて一斉指導
する。そこで確認・見直しをする。」
・「志水式『○付け法』とは、大雑把にいえば机間指導の出前方式で赤ペ
ンで○付けすること。3分間で教室を一周するスピードで一人一人に
声を掛けながら行う指導法。」
・「○付け法のポイントは『スピード』(5秒で眺め声掛け→誤答の場合は
部分肯定+15秒アドバイス)と『正確さ』と『声掛け』」
もう一つ、再掲載になりますが、池田晶子さんの
「考える日々Ⅱ」を載せます。
若くして亡くなられましたが、
今でも多くのことをわたしに気付かせてくれることをありがたく思います。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「教え方ガイドブック」志水廣 明治図書 2006年 ⑩
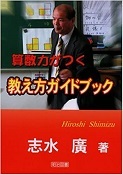
45「できる」までの練習
1 習熟の3段階
3ポイント
① 計算の手順が分かっていること(声に出して言わせる)
② 計算を少しずつ変化させて定着するまで繰り返す
フラッシュカード,計算カード
③ 直感的に答えが出るように
時間限定,枚数を決める
46 志水式音読計算練習法
1 計算カードの音読練習
カードを持って
47 机間指導のねらい
1 机間指導のねらいと3つの言葉
机間巡視 (子どもの様子を見守る)
机間指導 (子どもを個別に指導する)
机間支援 (ヒントや助言で個別に支援する)
3分後に…
2 具体的なねらい
① 子ども全体の進行の様子を把握する
進まない場合は止めて一斉指導
→ 確認・見直しを
② 子ども一人一人の実態を把握(評価)して支援指導する
評価と支援・指導は即時に行う
志水式「○付け法」
③ 子どもの考え方をつかむ
大まかに正答と誤答の割合,正答でも多様な考え方の種類の割合
をつかむ
④ その後の授業展開を修正することを教師が考える
3 机間指導の留意点
① 回るスピードを速くする
② 一人には多くて30秒以内
→ それ以上だと退屈して授業が崩れる
③ 目的を持って回る
思考のどの部分?
誰を見たい?
④ 回るコースを決めておく
⑤ メモを取らない
→ 支援・指導がおろそかになる
※ 机間指導を入力・出力
48 ○付け法で机間指導する
1 志水式「○付け法」とは何か
机間指導の出前方式で赤ペン○
3分間で一周
→ 一人一人へ声掛け
2 ○付けの基本方針
① 全員に○を付ける
② 分かる・できる喜びを与える
③ 肯定部分から始める
プロセス主義
④ ○付け法で気を付けるべきところは
①スピード ②正確さ ③声掛け ④実態把握
⑤次への指示 ⑥判断
⑤ 9割の子どもが見通しを持った時点で回るようにする
とりあえず①導入復習 ②最後の適用問題
◎ スピード,正確さ,声掛けから
49 ○付け法のよさ
1 教師にとっての○付け法のよさ
2 子どもにとっての○付け法
◎ 部分肯定の○付け
50 ○付け法の実際的方法
1 ○付け法のポイント
2 スピード
正答 - 5秒で眺め声掛け
誤答 - 部分肯定 +15秒アドバイス
※ 大きな声
3 正確さ
4 声掛け
○ 「はい,いいね」「調子いいね」「はい正解」
→大きく明るい声
× 「~は合ってるよ ~はちがうよ 考えてごらん」
「なるほどね ~は借りてきてから…」
→ 小さな声で励まし 先に肯定してから
☆「考える日々Ⅱ」池田晶子 毎日新聞社 1999年【再掲載 2012.1】
[出版社の案内]
人生が存在するのはなぜなのか。それは考えているからだ。世は謎を巡る。
千年紀の終わり、通り過ぎた日々へ、今いちど。哲学=考えることの光を。
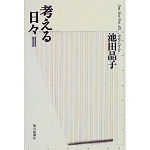
◇池田晶子さん
1960年東京生
文筆家 慶大哲学科卒
専門用語によらない哲学実践の表現開拓
◇幸福は欲するのではなく
欲すると言うことが不幸
= 幸福は欲するものではなく気が付くものだ
◎ 自分が誰だか分からないと気が付くことこそ幸福である。そのとき,自
分が宇宙そのものだと知るから…。
◇団結したのは資本であった
21世紀は壮大なる大失敗
IT化
→ 便利になった時間は愚劣なレジャーに使うぐらいしかない
= 人間の痴呆化
◎ 夢のインターネットの時代は知能の暗黒時代である。
人間の条件は
「生きて死ぬこと」
◇廃棄大処分の悦び
不要なものを捨てること
不要な人は廃棄する
→ 人から廃棄されないように努める
↑
◎ 各自にそういう覚悟が
◇「世代論」の腹立たしさ
団塊の世代
- 全共闘世代
「われわれは」か? 「私は」か?
◇お金を巡る「普通」の心証
金がほしい
→ 働く ○
→ 殺人する ×
◇生きることに「理由」があるか
なぜ生きているのか
→ 生まれたからだ
◇金
マネーでなくお金
= ものと遊離すべきではない
◇教育
◎ 教育が変わらなければ社会は変わり得ない。しかし,社会が変わらなけ
れば教育も変わらない。
教育 = 社会
◇「見える死」を見せてみろ
<脳死は死> と <脳死は人の死>
↓
◎ 見えないもの
◎ 死は言葉である
◇少子化とは誰の問題か
「産み損」
- 計算
◎ 出産が損得になってしまった
↓
◎ 生まれた子も損得に生きる
死ぬときは一人で死ねばいいではないか
= だからこそ生きることが自由



