「超定番 授業づくりの基礎基本」八木正一・上條晴夫 学事出版 2005年 ① /「やきもの紀行」神崎宣武 未来社 1984年【再掲載 2014.4】 [読書記録 教育]
今回は、八木正一さん、上條晴夫さんの
「超定番 授業づくりの基礎基本」の紹介 1回目です。
出版社の著者紹介には
「授業づくりの歴史や、授業設計の方法や授業づくりの基礎技術、研究授業の
方法、授業記録の方法における、授業づくりをする上で欠かせない基礎・基
本知識をまとめる。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「授業造りの歴史 3つの軸
① 教科専門の力量から教師の専門性へ
② 名人芸から教育技術へ
③ 効率よく教えるから自ら学ぶへ」
・「教授行為 - 教師の子どもに対する多様な働きかけ及びその組合せ」
・「授業の記述方法 スタイル
・重要指示、発問、説明 ・教師の教授行為・教材や板書事項」
・「水平的な授業への転換
① 正解のない内容の設定
② 子どもたちが身を乗り出すような『場』の設定」
もう一つ、再掲載になりますが、神崎宣武さんの
「やきもの紀行」を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「超定番 授業づくりの基礎基本」八木正一・上條晴夫 学事出版 2005年 ①
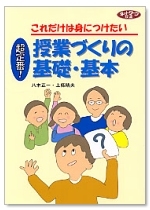
◇授業造りの歴史
1 3つの軸
① 教科専門の力量から教師の専門性へ
② 名人芸から教育技術へ
名人教師-齋藤喜博 → 教育技術
③ 効率よく教えるから自ら学ぶへ
授業パラダイム・授業システムの問題
2 基本としての教育内容・教材
(1) 教育内容の発見
科学的な概念や法則をこそ教育内容に
仮説実験授業 1963板倉聖宣
授業書 教科書+ノート+参考書=問題+討論+実験
|
質の高い教育内容研究
(2) 教材の発見 ~教材から楽しい授業へ~
「青い目の人形物語」森脇健夫 戦争授業
3 学習の仕掛けと授業行為の発見
(1) 学習の仕掛けの発見
「カードを使ってロンドを聴く」
(2) 教授行為の発見
授業 = 教師 + 教育内容 + 教材教具 + 子ども
+
ソフト
- 教授行為(教師の子どもに対する多様な働きかけ・組合せ)
(「教育技術の法則化運動」)
(3) 授業の記述の発見と教育技術
授業の記述方法の発見
スタイル
・重要指示、発問、説明などがフルセンテンスで書かれている
・教師の教授行為が具体的に書かれている
・教材や板書事項が具体的に書かれている
4 パラダイムの組み替えと授業づくり
~正解のない教育内容と場づくり~
Pフレイレ 近代教育=銀行型教育
↓
水平的な授業への転換
正解のない内容の設定
子どもたちが身を乗り出すような「場」の設定
(教師:アドバイザー、コーディネーターへ)
☆「やきもの紀行」神崎宣武 未来社 1984年【再掲載 2014.4】
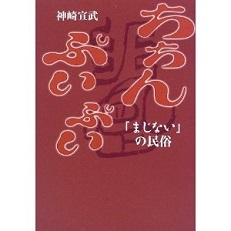
[出版社の案内]
土器・陶器・磁器の10窯をたずね、古老の話をきき、それぞれの窯のたどった
歴史、その生活圏や文化圏をこくめいに報告した“やきもの民俗学”の成果
◇山口県佐野(防府市) 昭和50年
炮烙(ほうらく)ありて
今は静かな土器の里
半農半工
焜炉 火消 炬燵
陶器 便壺と井戸側
すごいスピードで後ずさり
叩きの技術
ロクロ以前の2つの技法
叩き技法
1 くぼんだ型を回す
2 人が回る方法
土器の系譜
縄文弥生土器 それぞれの土地で簡単につくったもの
(専門職ではなし)
土師器 中世~近世へも
土器の始めに壺と堝
壺 … 種籾用
三足土堝の実用例
忘れられた素焼土器
◇岡山県備前 昭和44年
山陽道の窯場
無釉陶器
- 中世
須恵器
5世紀~12世紀
陶質土器
↓
陶器系 ・硬質で吸水性はほとんどない
・かたくなに中世陶器の伝統
∥
街道沿い
売るための切実姓がない 好立地
内なる歴史の語り部 金重逸翁
苦境の時代
◇兵庫県丹波立杭 昭和45年
山狭の窯場
火を吹く蛇窯
不利な立地を逆手にとって
◇愛知県常滑 昭和40年
煙が上空を染める町
土管
植木鉢
人間がロクロの甕づくり 土管
船あらばこそ
~ P105まで
「超定番 授業づくりの基礎基本」の紹介 1回目です。
出版社の著者紹介には
「授業づくりの歴史や、授業設計の方法や授業づくりの基礎技術、研究授業の
方法、授業記録の方法における、授業づくりをする上で欠かせない基礎・基
本知識をまとめる。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「授業造りの歴史 3つの軸
① 教科専門の力量から教師の専門性へ
② 名人芸から教育技術へ
③ 効率よく教えるから自ら学ぶへ」
・「教授行為 - 教師の子どもに対する多様な働きかけ及びその組合せ」
・「授業の記述方法 スタイル
・重要指示、発問、説明 ・教師の教授行為・教材や板書事項」
・「水平的な授業への転換
① 正解のない内容の設定
② 子どもたちが身を乗り出すような『場』の設定」
もう一つ、再掲載になりますが、神崎宣武さんの
「やきもの紀行」を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「超定番 授業づくりの基礎基本」八木正一・上條晴夫 学事出版 2005年 ①
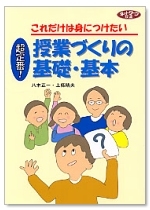
◇授業造りの歴史
1 3つの軸
① 教科専門の力量から教師の専門性へ
② 名人芸から教育技術へ
名人教師-齋藤喜博 → 教育技術
③ 効率よく教えるから自ら学ぶへ
授業パラダイム・授業システムの問題
2 基本としての教育内容・教材
(1) 教育内容の発見
科学的な概念や法則をこそ教育内容に
仮説実験授業 1963板倉聖宣
授業書 教科書+ノート+参考書=問題+討論+実験
|
質の高い教育内容研究
(2) 教材の発見 ~教材から楽しい授業へ~
「青い目の人形物語」森脇健夫 戦争授業
3 学習の仕掛けと授業行為の発見
(1) 学習の仕掛けの発見
「カードを使ってロンドを聴く」
(2) 教授行為の発見
授業 = 教師 + 教育内容 + 教材教具 + 子ども
+
ソフト
- 教授行為(教師の子どもに対する多様な働きかけ・組合せ)
(「教育技術の法則化運動」)
(3) 授業の記述の発見と教育技術
授業の記述方法の発見
スタイル
・重要指示、発問、説明などがフルセンテンスで書かれている
・教師の教授行為が具体的に書かれている
・教材や板書事項が具体的に書かれている
4 パラダイムの組み替えと授業づくり
~正解のない教育内容と場づくり~
Pフレイレ 近代教育=銀行型教育
↓
水平的な授業への転換
正解のない内容の設定
子どもたちが身を乗り出すような「場」の設定
(教師:アドバイザー、コーディネーターへ)
☆「やきもの紀行」神崎宣武 未来社 1984年【再掲載 2014.4】
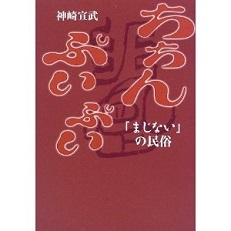
[出版社の案内]
土器・陶器・磁器の10窯をたずね、古老の話をきき、それぞれの窯のたどった
歴史、その生活圏や文化圏をこくめいに報告した“やきもの民俗学”の成果
◇山口県佐野(防府市) 昭和50年
炮烙(ほうらく)ありて
今は静かな土器の里
半農半工
焜炉 火消 炬燵
陶器 便壺と井戸側
すごいスピードで後ずさり
叩きの技術
ロクロ以前の2つの技法
叩き技法
1 くぼんだ型を回す
2 人が回る方法
土器の系譜
縄文弥生土器 それぞれの土地で簡単につくったもの
(専門職ではなし)
土師器 中世~近世へも
土器の始めに壺と堝
壺 … 種籾用
三足土堝の実用例
忘れられた素焼土器
◇岡山県備前 昭和44年
山陽道の窯場
無釉陶器
- 中世
須恵器
5世紀~12世紀
陶質土器
↓
陶器系 ・硬質で吸水性はほとんどない
・かたくなに中世陶器の伝統
∥
街道沿い
売るための切実姓がない 好立地
内なる歴史の語り部 金重逸翁
苦境の時代
◇兵庫県丹波立杭 昭和45年
山狭の窯場
火を吹く蛇窯
不利な立地を逆手にとって
◇愛知県常滑 昭和40年
煙が上空を染める町
土管
植木鉢
人間がロクロの甕づくり 土管
船あらばこそ
~ P105まで



