鷲田小彌太さんはこんなことを 35-「論争を快適にする30の方法」鷲田小彌太・廣瀬誠 PHP③ (最終) /「体育ぎらいの子」中森孜郎 岩波書店 1983年 ②【再掲載 2013.7】 [読書記録 一般]
今回は、3月25日に続いてわたしの読書ノートから、
「鷲田小彌太さんはこんなことを」35回目、
「論争を快適にする30の方法」の紹介3回目 最終です。
出版社の案内には
「夫婦の諍い、上司への反論、交通違反の言い逃れ、イデオロギーの対立…。
避けて通れない『言葉のケンカ』でいかに振る舞うか? 本書は、哲学教
授である著者がその技と心得を紹介する。 まず、論争に勝つ、勝つと血
眼になっている人は失格である。勝たない工夫が必要なのだ。その真意と
は何か。勝てば必ず疎まれるのが人間社会である。その原則をふまえ、あ
らゆる『論争の法則』を紹介している。『論争は体と頭に悪い』『バカを言
葉で納得させる方法はない』『無理が通れば道理が引っ込む』『論争はハン
グリーから生まれる』等々。では、論争の意義とは何なのか。『100人中99
人が賛成する時、あえて論争に挑め』『わが身に降りかかった火の粉を払
う』『教祖が強い理由』等、実践法も教えている。30の定義にはそれぞれ
日常生活の例題があけげられている。思わず目からウロコのエピソードが
満載。勝ばかりが能じゃない。大人のための快適論争術の指南書である。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「IT化 → 知ることより考えることが大切
『情報なんていくら手に入れても,それを考える頭がなければ何の意味も
ない』」
・「言葉の戦いは終生消えない
言葉はいつまでも残り、反復増幅する」
・「論争で勝つと思考が止まる - マルクス主義思想の腐敗と敗北から」
・「言葉の世界に身をさらす人は強い」
もう一つ、再掲載になりますが、中森孜郎さんの
「体育ぎらいの子」②を載せます。
体育は好きだけれど○○(器械運動 水泳)がという子がいます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆鷲田小彌太さんはこんなことを 35-「論争を快適にする30の方法」鷲田小彌太・廣瀬誠 PHP③(最終)
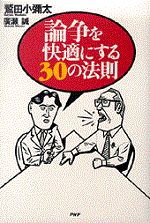
◇論争するからには論争に勝とう<定理7>
□定義19 論争に勝つのは天分である
「私怨」がなく,しかも,乾いた空気を与える「文体」(言葉)
の持ち主
~ まれ
IT化 知ることより考えることが大切
「情報なんていくら手に入れても,それを考える頭がな
ければ何の意味もない」
◎ 生きるとは何か?
◎ 考えるとは何か?
□定義20 負ける論争はしない
論争
= 不毛,不快
□定義21 論争する前に勝ちを制する
何にせよ驚かない 目が眩まない
= 何事にも対応できる柔軟さで自在な心が必要
◎ 周到な準備 + 自在な心
◇論争に勝つとろくな事がない<定理8>
□定義22 言葉の戦いは終生消えない
言葉はいつまでも残る
反復増幅する
□定義23 言葉で負けた者は言葉以外のもので勝とうとする
□定義24 論争で勝つと思考が止まる
マルクス主義
→ マルクス主義思想の腐敗と敗北
「土俵」を大きなものととらえてしまう
マルクス主義の自滅
◇ディベートをスポーツとして活用すれば<定理9>
□定義25 昼食時に「論争」を
□定義26 「朝まで生テレビ」は楽しい
この場限り
□定義27 異種格闘技は論争ではない
◇論争に資格はいらない<定理10>
□定義28 女子と小人は養いがたい
小人「どうもいいんじゃない」
女子 感情の動物
□定義29 猿にも分かるように論争する
□定義30 言葉の世界に身をさらす人は強い
☆「体育ぎらいの子」中森孜郎 岩波書店 1983年 ②【再掲載 2013.7】
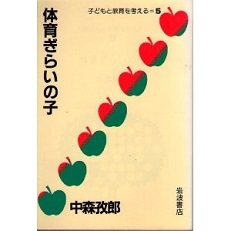
◇からだと対話するマット運動
□ムツミの場合
自分の体に意識を集中させる
→ 物事に立ち向かう力
困難を克服する力
□躓きの克服が体育好きの道
「生きていく証の汗」
「できる」
… 自分の体を自分の意志で思いのまま自由に動かすことができる。で
きていく過程を大切に!
□子供自身に問いかける
できていく実感を掴ませる
◎「最後まで見る」教師
~ 一人一人違う欠点
◇ここちよい「逆立ち」
□新しい観点の発見
野口三千三(元東京芸術大学教授)「野口体操」
動きの本質
= 中味の変化流動
逆立ち
◎「地球の中心に向かって液体を注ぎ込むイメージ」
↓
① 硬直されてきたからだを耕し直す
② リラクゼーションの重視
内部の変化を感じ取る内部感覚を養う
③ 流動的な動きのできるからだを育てる
④ 呼吸と動きを結び合わせる
□無理のない逆立ちを!
頭で立つ逆立ち
(1)立ち上がり方
正座
→ 上体を前に・両手と後頭部をマットに
→ 腰を浮かせる
→ 徐々に頭頂部に体重を委ねていく
→ 両膝をスッと腰に引きつけるように折り曲げる
- スッと自然に動かす
(2)伸び方について
2~3回呼吸
→ ゆっくりまっすぐ上方に足を伸ばす(水仙がゆっくり
伸びるように)
(3)立ち上がってから
リラックス ヨーガに近い
(4)おり方について
両足を締める
→ 一呼吸
→ 静かにおろす
(5)補助の仕方について
補助者 = 協力者
□「腕で立つ逆立ち」への発展
頭で立つ逆立ち
→ 無理のない前回り
「側転」ができるまで
教材の問い直しが授業を変える
「鷲田小彌太さんはこんなことを」35回目、
「論争を快適にする30の方法」の紹介3回目 最終です。
出版社の案内には
「夫婦の諍い、上司への反論、交通違反の言い逃れ、イデオロギーの対立…。
避けて通れない『言葉のケンカ』でいかに振る舞うか? 本書は、哲学教
授である著者がその技と心得を紹介する。 まず、論争に勝つ、勝つと血
眼になっている人は失格である。勝たない工夫が必要なのだ。その真意と
は何か。勝てば必ず疎まれるのが人間社会である。その原則をふまえ、あ
らゆる『論争の法則』を紹介している。『論争は体と頭に悪い』『バカを言
葉で納得させる方法はない』『無理が通れば道理が引っ込む』『論争はハン
グリーから生まれる』等々。では、論争の意義とは何なのか。『100人中99
人が賛成する時、あえて論争に挑め』『わが身に降りかかった火の粉を払
う』『教祖が強い理由』等、実践法も教えている。30の定義にはそれぞれ
日常生活の例題があけげられている。思わず目からウロコのエピソードが
満載。勝ばかりが能じゃない。大人のための快適論争術の指南書である。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「IT化 → 知ることより考えることが大切
『情報なんていくら手に入れても,それを考える頭がなければ何の意味も
ない』」
・「言葉の戦いは終生消えない
言葉はいつまでも残り、反復増幅する」
・「論争で勝つと思考が止まる - マルクス主義思想の腐敗と敗北から」
・「言葉の世界に身をさらす人は強い」
もう一つ、再掲載になりますが、中森孜郎さんの
「体育ぎらいの子」②を載せます。
体育は好きだけれど○○(器械運動 水泳)がという子がいます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆鷲田小彌太さんはこんなことを 35-「論争を快適にする30の方法」鷲田小彌太・廣瀬誠 PHP③(最終)
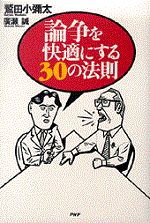
◇論争するからには論争に勝とう<定理7>
□定義19 論争に勝つのは天分である
「私怨」がなく,しかも,乾いた空気を与える「文体」(言葉)
の持ち主
~ まれ
IT化 知ることより考えることが大切
「情報なんていくら手に入れても,それを考える頭がな
ければ何の意味もない」
◎ 生きるとは何か?
◎ 考えるとは何か?
□定義20 負ける論争はしない
論争
= 不毛,不快
□定義21 論争する前に勝ちを制する
何にせよ驚かない 目が眩まない
= 何事にも対応できる柔軟さで自在な心が必要
◎ 周到な準備 + 自在な心
◇論争に勝つとろくな事がない<定理8>
□定義22 言葉の戦いは終生消えない
言葉はいつまでも残る
反復増幅する
□定義23 言葉で負けた者は言葉以外のもので勝とうとする
□定義24 論争で勝つと思考が止まる
マルクス主義
→ マルクス主義思想の腐敗と敗北
「土俵」を大きなものととらえてしまう
マルクス主義の自滅
◇ディベートをスポーツとして活用すれば<定理9>
□定義25 昼食時に「論争」を
□定義26 「朝まで生テレビ」は楽しい
この場限り
□定義27 異種格闘技は論争ではない
◇論争に資格はいらない<定理10>
□定義28 女子と小人は養いがたい
小人「どうもいいんじゃない」
女子 感情の動物
□定義29 猿にも分かるように論争する
□定義30 言葉の世界に身をさらす人は強い
☆「体育ぎらいの子」中森孜郎 岩波書店 1983年 ②【再掲載 2013.7】
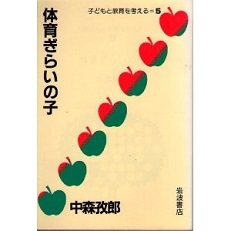
◇からだと対話するマット運動
□ムツミの場合
自分の体に意識を集中させる
→ 物事に立ち向かう力
困難を克服する力
□躓きの克服が体育好きの道
「生きていく証の汗」
「できる」
… 自分の体を自分の意志で思いのまま自由に動かすことができる。で
きていく過程を大切に!
□子供自身に問いかける
できていく実感を掴ませる
◎「最後まで見る」教師
~ 一人一人違う欠点
◇ここちよい「逆立ち」
□新しい観点の発見
野口三千三(元東京芸術大学教授)「野口体操」
動きの本質
= 中味の変化流動
逆立ち
◎「地球の中心に向かって液体を注ぎ込むイメージ」
↓
① 硬直されてきたからだを耕し直す
② リラクゼーションの重視
内部の変化を感じ取る内部感覚を養う
③ 流動的な動きのできるからだを育てる
④ 呼吸と動きを結び合わせる
□無理のない逆立ちを!
頭で立つ逆立ち
(1)立ち上がり方
正座
→ 上体を前に・両手と後頭部をマットに
→ 腰を浮かせる
→ 徐々に頭頂部に体重を委ねていく
→ 両膝をスッと腰に引きつけるように折り曲げる
- スッと自然に動かす
(2)伸び方について
2~3回呼吸
→ ゆっくりまっすぐ上方に足を伸ばす(水仙がゆっくり
伸びるように)
(3)立ち上がってから
リラックス ヨーガに近い
(4)おり方について
両足を締める
→ 一呼吸
→ 静かにおろす
(5)補助の仕方について
補助者 = 協力者
□「腕で立つ逆立ち」への発展
頭で立つ逆立ち
→ 無理のない前回り
「側転」ができるまで
教材の問い直しが授業を変える



