キーワード 読書について22-「読み聞かせで育つもの」高山智津子 神戸新聞総合出版センター 1992年 /「古代日本の発掘発見物語」玉利勲 国土社 1985年 ④【再掲載 2012.5】 [読書記録 教育]
今回は、4月1日に続いて、キーワード「読書について」の紹介22回目、
高山智津子さんの「読み聞かせで育つもの」を紹介します。
出版社の案内には、
「『読みきかせ』−読み手と聞き手が本の中の楽しい世界を共有することで生
まれる人と人との心のふれあい、ひびきあい。それがいくつも胸の奥深く
に蓄積されて感動する心になり、生きる力になり、困難に直面したときの
復元力になる、と本書の実践報告は示す」
とあります。
30年くらい前に出版された本ですので、
紹介されている本もかなり以前のものになります。
わたしが読むと今でもおもしろく感じます。
そのおもしろさを現在の子どもたちが感じてくれると‥
もう一つ、再掲載になりますが、玉利勲さんの
「古代日本の発掘発見物語」④を載せます。
子どもの時に読んでいたらよかったのにと思った本です。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆キーワード 読書について22-「読み聞かせで育つもの」高山智津子 神戸新聞総合出版センター 1992年
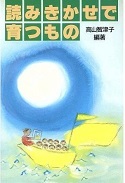
◇この本に夢中
「じごくのそうべえ」田島征彦 童心社
「ふれふれなんだこんなあめ」梅田俊作・佳子 岩崎書店
◇読み聞かせで育つもの
デフ・アンド・ブラインド
荒田幸子さん(視力障害)
米国留学 →「詩集 憩いのみぎわに」筑摩書房
お楽しみのもと 読み聞かせ
わんぱく文庫
大阪・視力障害者の読み聞かせ
子供が好きなもの
冒険もの・学園もの
◇心に残る読み聞かせ
心の触れ合いを育てる
読み聞かせで育つもの
① 言葉の発達を促す
言葉・イメージ
② イメージ豊かに育つ
創造力
③ 創造力も育つ
「言葉探しの旅」から「言葉探しの旅」藤本英二(高校出版)
物語はそのときの自分の心をカルタシス=浄化発散させる
優れた絵本の条件
① 繰り返し
② 質的変化
③ ドラマチックな展開
◇読み聞かせの勧め
楽しい本から
ちょっと工夫して
楽しい本は大人でも楽しみましょう
高学年の子どもも本の読み聞かせをどんなに喜ぶか
◇快いものとしての読み聞かせ
高学年にも読み聞かせ
本の中の楽しい世界を!
「高次は低次を制限する」
赤ちゃんからの読み聞かせ
遊びを促す絵本 一緒に遊びましょう
言葉が育つ
イメージを楽しみながらもう一つの世界をもう一つの人生を豊かに
親と子の響き合い
◇私の好きな作家
梅田俊作
岡田淳
ファンタジー
「2分間のぼうけん」
「学校ウサギをつかまえろ」
後藤竜二
「1ねん1くみ1ばんワル」
「のんびり転校生事件」
宮川ひろ
「先生のつうしんぼ」「春駒のうた」
森はな
「ハナ先生ものがたり」
さとうわきこ
「せんたくかあちゃん」
にしまきかやこ
アーノルド・ローベル
「どろんここぶた」
「がまくんかえるくん」
☆「古代日本の発掘発見物語」玉利勲 国土社 1985年 ④【再掲載 2012.5】

◇ヘドロの缶詰 -池の底にあった唐古遺跡
□森本六爾の死
弥生時代
稲作遺跡
- 昭和十年代 唐古遺跡
戦後 登呂遺跡
唐古遺跡 弥生時代
~ 後期 唐古池中心
森本六爾
明治36(1903)3月 現在桜井市(織田村)生
小学校に勤務しながら調査
大正13(1924)年
「大和における史前の遺跡」論文
↓
上京 「東京考古学会」結成 「考古学」
当時の考古学会への対抗心
昭和6(1931)4月
無理して旅費-ヨーロッパ留学
昭和7(1932)3月
帰国(病気)
昭和11(1936)1月
32歳で病死
◎松本清張『断碑』1954 モデル
□ヘドロを掘る
国道15号線
盛土用に唐古池の底の土を利用
末永雅雄博士が進言
東西109m×南北165m ヘドロ深さ1.5m
すべて人力
ツルハシメスコップ・モッコ・トロッコ
50人の作業員 弥生式土器が次々と
昭和12.1.8~
京都大学と共同調査
浜田耕作指導 末永調査主任
□木製農具の出現
作業終了 3月23日
調査終了3月28日
大小107基の竪穴と3基の井戸
ヘドロの缶詰
~ 木製品 農耕具、容器、装身具、武器、轆轤、
金属製刃物の使用も認められた
□広がる遺跡
土器 赤い彩色、シカや家の線彫りが目に付く
↓
五つの様式に分類(小林行雄)
↓
「大和唐古弥生式遺跡の研究」昭和18(1943)年3月
現在 用水池 → 養魚池に
今も池の底に弥生ムラの跡
昭和42(1967)年
唐古池付近で発掘調査
= 弥生ムラの範囲
田原本町
唐古地区~鍵地区
東西600m~南北600m 「唐古鍵遺跡」
◇掘り出された弥生時代のムラ - 登呂遺跡大発掘
□取り上げられたカメラ
杉原宗介(明治大)登呂遺跡初調査
遺跡写真を撮ると
→ 軍人に取り上げられてしまった
飛行機プロペラ工場現場
南水田3万㎡土取り昭和18.1
深さ2m ~ 大量土器・木の破片
↓
地元考古学者
安本博氏 許可を得て進行見守る
7月 丸木舟(前半分1m)
~ 東京考古学者に報告
|
毎日新聞
静岡支局 森豊記者も東京本社に記事
↓
静岡県による発掘調査
8~9月 17日間
□再開された発掘調査
昭和21年1月
明治大・後藤一守教授 杉浦氏中心
↓
昭和22年3月
「静岡市登呂遺跡遺跡調査会」
昭和22年7月13日 鍬入れ式 ~ 9月3日
延べ3000人が参加
2m×100mの小規模調査
昭和23年4月
「日本考古学協会」
□家と倉庫と水田
25年9月まで
~4年間
空腹との闘い
◇論争続く石の骨 -「明石原人」と直良信夫
□ついに人骨発見
昭和6年(1931)4月18日 直良信夫29歳
スコップを手に西八木海岸の崖の表面観察
百万年前の層から人骨
- 土を洗い流したのが失敗
□つきまとう不運
東京帝大理学部人類学教室の松村瞭博士に鑑定を依頼
松村 はじめ感激 → のち冷静に
石器についての論文 批判 鳥居龍蔵・大山柏ら
「日本に旧石器文化などあるはずがない」
↓
上京し基礎から勉強をやり直す
昭和20年4月 早大講師に
空襲で人骨燃える
→ 石器二個のみ残る
□解けない謎
長谷部言人教授
昭和22(1947)11月
写真と模型の保管知る
23(1948)7月
『人類学雑誌』に発表
ニポナントロプス・アカシエンス
芹沢長介(東北大)昭和45年6月
「二個の石器は旧石器時代のもの」
愛知医大 吉岡郁夫 昭和52(1979)~53(1978)発表
原人ではなくネアンデルタール人か新人のいずれか
- ネアンデルタール人級
東大 遠藤万里 獨協大 馬場悠男 昭和57年7月
「せいぜい一万年前」~現代
※ 完全には解決していない
高山智津子さんの「読み聞かせで育つもの」を紹介します。
出版社の案内には、
「『読みきかせ』−読み手と聞き手が本の中の楽しい世界を共有することで生
まれる人と人との心のふれあい、ひびきあい。それがいくつも胸の奥深く
に蓄積されて感動する心になり、生きる力になり、困難に直面したときの
復元力になる、と本書の実践報告は示す」
とあります。
30年くらい前に出版された本ですので、
紹介されている本もかなり以前のものになります。
わたしが読むと今でもおもしろく感じます。
そのおもしろさを現在の子どもたちが感じてくれると‥
もう一つ、再掲載になりますが、玉利勲さんの
「古代日本の発掘発見物語」④を載せます。
子どもの時に読んでいたらよかったのにと思った本です。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆キーワード 読書について22-「読み聞かせで育つもの」高山智津子 神戸新聞総合出版センター 1992年
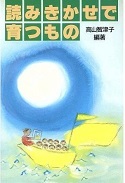
◇この本に夢中
「じごくのそうべえ」田島征彦 童心社
「ふれふれなんだこんなあめ」梅田俊作・佳子 岩崎書店
◇読み聞かせで育つもの
デフ・アンド・ブラインド
荒田幸子さん(視力障害)
米国留学 →「詩集 憩いのみぎわに」筑摩書房
お楽しみのもと 読み聞かせ
わんぱく文庫
大阪・視力障害者の読み聞かせ
子供が好きなもの
冒険もの・学園もの
◇心に残る読み聞かせ
心の触れ合いを育てる
読み聞かせで育つもの
① 言葉の発達を促す
言葉・イメージ
② イメージ豊かに育つ
創造力
③ 創造力も育つ
「言葉探しの旅」から「言葉探しの旅」藤本英二(高校出版)
物語はそのときの自分の心をカルタシス=浄化発散させる
優れた絵本の条件
① 繰り返し
② 質的変化
③ ドラマチックな展開
◇読み聞かせの勧め
楽しい本から
ちょっと工夫して
楽しい本は大人でも楽しみましょう
高学年の子どもも本の読み聞かせをどんなに喜ぶか
◇快いものとしての読み聞かせ
高学年にも読み聞かせ
本の中の楽しい世界を!
「高次は低次を制限する」
赤ちゃんからの読み聞かせ
遊びを促す絵本 一緒に遊びましょう
言葉が育つ
イメージを楽しみながらもう一つの世界をもう一つの人生を豊かに
親と子の響き合い
◇私の好きな作家
梅田俊作
岡田淳
ファンタジー
「2分間のぼうけん」
「学校ウサギをつかまえろ」
後藤竜二
「1ねん1くみ1ばんワル」
「のんびり転校生事件」
宮川ひろ
「先生のつうしんぼ」「春駒のうた」
森はな
「ハナ先生ものがたり」
さとうわきこ
「せんたくかあちゃん」
にしまきかやこ
アーノルド・ローベル
「どろんここぶた」
「がまくんかえるくん」
☆「古代日本の発掘発見物語」玉利勲 国土社 1985年 ④【再掲載 2012.5】

◇ヘドロの缶詰 -池の底にあった唐古遺跡
□森本六爾の死
弥生時代
稲作遺跡
- 昭和十年代 唐古遺跡
戦後 登呂遺跡
唐古遺跡 弥生時代
~ 後期 唐古池中心
森本六爾
明治36(1903)3月 現在桜井市(織田村)生
小学校に勤務しながら調査
大正13(1924)年
「大和における史前の遺跡」論文
↓
上京 「東京考古学会」結成 「考古学」
当時の考古学会への対抗心
昭和6(1931)4月
無理して旅費-ヨーロッパ留学
昭和7(1932)3月
帰国(病気)
昭和11(1936)1月
32歳で病死
◎松本清張『断碑』1954 モデル
□ヘドロを掘る
国道15号線
盛土用に唐古池の底の土を利用
末永雅雄博士が進言
東西109m×南北165m ヘドロ深さ1.5m
すべて人力
ツルハシメスコップ・モッコ・トロッコ
50人の作業員 弥生式土器が次々と
昭和12.1.8~
京都大学と共同調査
浜田耕作指導 末永調査主任
□木製農具の出現
作業終了 3月23日
調査終了3月28日
大小107基の竪穴と3基の井戸
ヘドロの缶詰
~ 木製品 農耕具、容器、装身具、武器、轆轤、
金属製刃物の使用も認められた
□広がる遺跡
土器 赤い彩色、シカや家の線彫りが目に付く
↓
五つの様式に分類(小林行雄)
↓
「大和唐古弥生式遺跡の研究」昭和18(1943)年3月
現在 用水池 → 養魚池に
今も池の底に弥生ムラの跡
昭和42(1967)年
唐古池付近で発掘調査
= 弥生ムラの範囲
田原本町
唐古地区~鍵地区
東西600m~南北600m 「唐古鍵遺跡」
◇掘り出された弥生時代のムラ - 登呂遺跡大発掘
□取り上げられたカメラ
杉原宗介(明治大)登呂遺跡初調査
遺跡写真を撮ると
→ 軍人に取り上げられてしまった
飛行機プロペラ工場現場
南水田3万㎡土取り昭和18.1
深さ2m ~ 大量土器・木の破片
↓
地元考古学者
安本博氏 許可を得て進行見守る
7月 丸木舟(前半分1m)
~ 東京考古学者に報告
|
毎日新聞
静岡支局 森豊記者も東京本社に記事
↓
静岡県による発掘調査
8~9月 17日間
□再開された発掘調査
昭和21年1月
明治大・後藤一守教授 杉浦氏中心
↓
昭和22年3月
「静岡市登呂遺跡遺跡調査会」
昭和22年7月13日 鍬入れ式 ~ 9月3日
延べ3000人が参加
2m×100mの小規模調査
昭和23年4月
「日本考古学協会」
□家と倉庫と水田
25年9月まで
~4年間
空腹との闘い
◇論争続く石の骨 -「明石原人」と直良信夫
□ついに人骨発見
昭和6年(1931)4月18日 直良信夫29歳
スコップを手に西八木海岸の崖の表面観察
百万年前の層から人骨
- 土を洗い流したのが失敗
□つきまとう不運
東京帝大理学部人類学教室の松村瞭博士に鑑定を依頼
松村 はじめ感激 → のち冷静に
石器についての論文 批判 鳥居龍蔵・大山柏ら
「日本に旧石器文化などあるはずがない」
↓
上京し基礎から勉強をやり直す
昭和20年4月 早大講師に
空襲で人骨燃える
→ 石器二個のみ残る
□解けない謎
長谷部言人教授
昭和22(1947)11月
写真と模型の保管知る
23(1948)7月
『人類学雑誌』に発表
ニポナントロプス・アカシエンス
芹沢長介(東北大)昭和45年6月
「二個の石器は旧石器時代のもの」
愛知医大 吉岡郁夫 昭和52(1979)~53(1978)発表
原人ではなくネアンデルタール人か新人のいずれか
- ネアンデルタール人級
東大 遠藤万里 獨協大 馬場悠男 昭和57年7月
「せいぜい一万年前」~現代
※ 完全には解決していない



