鷲田小彌太さんはこんなことを 36-「大学教授になる方法」PHP文庫 1995年(1) /「忘れられた日本人を読む」網野善彦 岩波セミナーブックス 2003年 ②【再掲載 2014.4】 [読書記録 一般]
今回は、4月5日に続いてわたしの読書ノートから、
「鷲田小彌太さんはこんなことを」36回目、
「大学教授になる方法」の紹介1回目です。
出版社の案内には
「医者や弁護士と違い、大学教授になるのに資格はいらない。しかも『知的』
な活動を行ない、その地位が特権的に保証されており、社会的評価も極めて
高い。そんな職業に誰もが就けるとしたら…。本書はそれを実現するための
最短のパスポート。偏差値50前後の人なら、方法さえ間違わなければ誰で
もなれることを様々な実例で紹介。いままで誰も書かなかった異色の就職・
転職ガイダンス。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「大学は学術の中心としてひろく知識を授けると共に深く専門の学芸を研究
し,知的,道徳的および応用能力を展開させることを目的とする
労基法 5章」
・「教授の仕事は名目上最高水準の知的教授でありその地位は教授会の自由裁
量(とりわけ人事権)によって二重三重にも保護されている」
・「大学教員の本分は研究活動。一切研究活動をしなくても降格源棒はない。
研究にどれだけ励んでも称賛されないと同時にではあるが」
もう一つ、再掲載になりますが、網野善彦さんの
「忘れられた日本人を読む」②を載せます。
網野さんが亡くなられて20年近く経ちました。
「百姓は単なる農業従事者ではない」という見方が広がったように思います。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆鷲田小彌太さんはこんなことを 36-「大学教授になる方法」PHP文庫 1995年(1)

◇職業としての大学教授
21世紀
高齢化社会,生涯教育・生涯学習の時代,モラトリアム時代
高度産業時代,高度知識社会,情報化社会,高度消費社会
非労働社会 等
階層としての大学教授
大学教員の数
国立 53188人
公立 6396人
私立 61583人
合計 121140人
短大 19830人
合計 140970人
∥
◎ 医者とほぼ同じ
大学教授の社会的地位
労基法 5章
「大学は学術の中心としてひろく知識を授けると共に深く専門の学芸
を研究し,知的,道徳的および応用能力を展開させることを目的と
する」
↑
目的達成のため
◎「学部」
人事権含む大幅な裁量権
◎「教授会」
重要事項審議
|
教授の仕事は名目上最高水準の知的教授でありその地位は教授会
の自由裁量(とりわけ人事権)によって二重三重にも保護されてい
る
◎ 終身雇用
東大 60歳定年制
地方国公立大 65歳定年制
私立60~70歳
= 社会的地位は高く安定している
大学教授の給与
20~30代安い
40代世間並み
50代頂上
60代高原
※ 20~30代は研究費に苦労
国立と私立に相違,大都市と地方に相違
しかし,本質的な違いはない
教授の仕事
(1)教育活動
勤務時間の規定がない
① 持ち分の授業のみ
平均3~6コマ
一年間に30回(実質25回)
② 隔週に教授会
③ 各種委員会
・授業 講義形式 一回原稿用紙40~50枚分
一年間に1000枚以上
◎ どのようにやろうと自由
- 手抜きもできる
(2)研究活動
大学教員の本分
一切研究活動をしなくても降格源棒はない
(研究にどれだけ励んでも称賛されないと同時に)
(3)学内行政
政治
~ 暇つぶしによい
(4)その他
仕事以外の活動
他校講師 届出,コマ数制限
→ 本務に差し支えなければ
その他自由
短期研修旅行と長研制度
☆「忘れられた日本人を読む」網野善彦 岩波セミナーブックス 2003年 ②【再掲載 2014.4】
[出版社の案内]
既存の日本像に鋭く切り込んでいる日本中世史家が、宮本常一の代表作『忘れ
られた日本人』を、用いられている民族語彙に注目しながら読みぬき、日本論
におけるその先駆性を明らかにする。歴史の中の老人・女性・子ども・遍歴民
の役割や東日本と西日本との間の大きな差異に早くから着目した点を浮き彫り
にし、宮本民俗学の真髄に迫る。
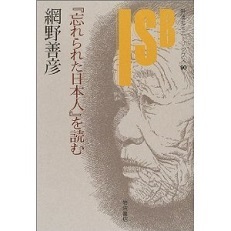
◇女の世間(1)
□老人・女性・子ども・遍歴民への着目
「忘れられた日本人」2つのテーマ
① 女性、老人、子ども、遍歴する人々
② 東日本と西日本の差異(社会、構造、質)
宮本常一
「男性中心の家父長制により女性が支配されているのは、東日本の実態
であり、西日本では実状が違う」
□現代に生きている歌垣(かがい)の世界
歌垣が昭和30年代前半頃まで各地に生きていた
対馬佐護
南河内郡磯城村(太子の一夜ほぼ)
|
古代
ある特定の場所が特定の時に歌垣の場になった
= 無縁の場
□中世の参籠は歌垣だった
「絵巻物による日本常民生活絵引」(全五巻)
解説は皆宮本常一
河村武春も出版に尽力
絵画資料研究の走り
昔話
子供が生まれないので七日間清水寺などの寺社に参籠したところ子ど
もを授かった
= 男女の交渉
|
◎ 市場や祭りのときは世俗の縁が切れ、男女の関係が究めて自由な
場となった
◎ 歌垣が昭和30年代まで生きていた
□女性だけの旅
善根宿での接待
- 女性だけの旅でも遍路の姿なら大事に扱われた
「ものぐさ太郎」
辻取り(道で女性をつかまえる)
□ルイス・フロイス「ヨーロッパ文化と日本文化」
・ 日本の女性は処女の純潔を少しも重んじない
・ 日本では意のままに幾人でも離別する
・ 日本ではしばしば妻が夫を離別する
・ 日本では娘がひとりで好きなところに行く
□夜這いという習俗
夜這いが普通の習俗だった
「名倉談義」等
明治以後、儀礼も夜這いもなくなった
現在でも夜這いが生きている世界がある(儀礼とルール)
□娘の家出
□財布のひもを握る女性
家内部経済に女性が強い発言権
織物と女性
養蚕 ~ 織物は女性の仕事だった
農夫 ←→ 蚕婦
男の鍬鋤 ←→ 女性の蚕桑
◎ 天皇が田植え、皇后が養蚕
◎ 公的な世界で税を出しているのが男性であるため注目されなかった
= 女性の名前は表に出ない
「鷲田小彌太さんはこんなことを」36回目、
「大学教授になる方法」の紹介1回目です。
出版社の案内には
「医者や弁護士と違い、大学教授になるのに資格はいらない。しかも『知的』
な活動を行ない、その地位が特権的に保証されており、社会的評価も極めて
高い。そんな職業に誰もが就けるとしたら…。本書はそれを実現するための
最短のパスポート。偏差値50前後の人なら、方法さえ間違わなければ誰で
もなれることを様々な実例で紹介。いままで誰も書かなかった異色の就職・
転職ガイダンス。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「大学は学術の中心としてひろく知識を授けると共に深く専門の学芸を研究
し,知的,道徳的および応用能力を展開させることを目的とする
労基法 5章」
・「教授の仕事は名目上最高水準の知的教授でありその地位は教授会の自由裁
量(とりわけ人事権)によって二重三重にも保護されている」
・「大学教員の本分は研究活動。一切研究活動をしなくても降格源棒はない。
研究にどれだけ励んでも称賛されないと同時にではあるが」
もう一つ、再掲載になりますが、網野善彦さんの
「忘れられた日本人を読む」②を載せます。
網野さんが亡くなられて20年近く経ちました。
「百姓は単なる農業従事者ではない」という見方が広がったように思います。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆鷲田小彌太さんはこんなことを 36-「大学教授になる方法」PHP文庫 1995年(1)

◇職業としての大学教授
21世紀
高齢化社会,生涯教育・生涯学習の時代,モラトリアム時代
高度産業時代,高度知識社会,情報化社会,高度消費社会
非労働社会 等
階層としての大学教授
大学教員の数
国立 53188人
公立 6396人
私立 61583人
合計 121140人
短大 19830人
合計 140970人
∥
◎ 医者とほぼ同じ
大学教授の社会的地位
労基法 5章
「大学は学術の中心としてひろく知識を授けると共に深く専門の学芸
を研究し,知的,道徳的および応用能力を展開させることを目的と
する」
↑
目的達成のため
◎「学部」
人事権含む大幅な裁量権
◎「教授会」
重要事項審議
|
教授の仕事は名目上最高水準の知的教授でありその地位は教授会
の自由裁量(とりわけ人事権)によって二重三重にも保護されてい
る
◎ 終身雇用
東大 60歳定年制
地方国公立大 65歳定年制
私立60~70歳
= 社会的地位は高く安定している
大学教授の給与
20~30代安い
40代世間並み
50代頂上
60代高原
※ 20~30代は研究費に苦労
国立と私立に相違,大都市と地方に相違
しかし,本質的な違いはない
教授の仕事
(1)教育活動
勤務時間の規定がない
① 持ち分の授業のみ
平均3~6コマ
一年間に30回(実質25回)
② 隔週に教授会
③ 各種委員会
・授業 講義形式 一回原稿用紙40~50枚分
一年間に1000枚以上
◎ どのようにやろうと自由
- 手抜きもできる
(2)研究活動
大学教員の本分
一切研究活動をしなくても降格源棒はない
(研究にどれだけ励んでも称賛されないと同時に)
(3)学内行政
政治
~ 暇つぶしによい
(4)その他
仕事以外の活動
他校講師 届出,コマ数制限
→ 本務に差し支えなければ
その他自由
短期研修旅行と長研制度
☆「忘れられた日本人を読む」網野善彦 岩波セミナーブックス 2003年 ②【再掲載 2014.4】
[出版社の案内]
既存の日本像に鋭く切り込んでいる日本中世史家が、宮本常一の代表作『忘れ
られた日本人』を、用いられている民族語彙に注目しながら読みぬき、日本論
におけるその先駆性を明らかにする。歴史の中の老人・女性・子ども・遍歴民
の役割や東日本と西日本との間の大きな差異に早くから着目した点を浮き彫り
にし、宮本民俗学の真髄に迫る。
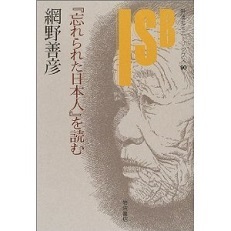
◇女の世間(1)
□老人・女性・子ども・遍歴民への着目
「忘れられた日本人」2つのテーマ
① 女性、老人、子ども、遍歴する人々
② 東日本と西日本の差異(社会、構造、質)
宮本常一
「男性中心の家父長制により女性が支配されているのは、東日本の実態
であり、西日本では実状が違う」
□現代に生きている歌垣(かがい)の世界
歌垣が昭和30年代前半頃まで各地に生きていた
対馬佐護
南河内郡磯城村(太子の一夜ほぼ)
|
古代
ある特定の場所が特定の時に歌垣の場になった
= 無縁の場
□中世の参籠は歌垣だった
「絵巻物による日本常民生活絵引」(全五巻)
解説は皆宮本常一
河村武春も出版に尽力
絵画資料研究の走り
昔話
子供が生まれないので七日間清水寺などの寺社に参籠したところ子ど
もを授かった
= 男女の交渉
|
◎ 市場や祭りのときは世俗の縁が切れ、男女の関係が究めて自由な
場となった
◎ 歌垣が昭和30年代まで生きていた
□女性だけの旅
善根宿での接待
- 女性だけの旅でも遍路の姿なら大事に扱われた
「ものぐさ太郎」
辻取り(道で女性をつかまえる)
□ルイス・フロイス「ヨーロッパ文化と日本文化」
・ 日本の女性は処女の純潔を少しも重んじない
・ 日本では意のままに幾人でも離別する
・ 日本ではしばしば妻が夫を離別する
・ 日本では娘がひとりで好きなところに行く
□夜這いという習俗
夜這いが普通の習俗だった
「名倉談義」等
明治以後、儀礼も夜這いもなくなった
現在でも夜這いが生きている世界がある(儀礼とルール)
□娘の家出
□財布のひもを握る女性
家内部経済に女性が強い発言権
織物と女性
養蚕 ~ 織物は女性の仕事だった
農夫 ←→ 蚕婦
男の鍬鋤 ←→ 女性の蚕桑
◎ 天皇が田植え、皇后が養蚕
◎ 公的な世界で税を出しているのが男性であるため注目されなかった
= 女性の名前は表に出ない



