「目からウロコの教育を考えるヒント」清水義範 講談社 2001年 ③ /「わたしが死について語るなら」山折哲雄 ポプラ社 2009年 ④(最終)【再掲載 2013.5】 [読書記録 教育]
今回は、4月12日に続いて、清水義範さんの
「目からウロコの教育を考えるヒント」3回目の紹介です。
出版社の紹介には
「こんな時代だからこそ、教育を根本から考えよう!『子供たちがあぶない』
『教育の危機』『日本はお先真っ暗』 それってホントですか?子供大好きの
シミズ博士がとことん考え尽くした、大納得の異色教育論。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「教育実習だけでいきなり担任を持つのは無茶というもの。先生にも修行期
間がほしい。」
・「教員の給料を2倍にして教員の待遇を良くし,いろいろな意味で憧れの職
業にしなければ。そうすれば人材が集まる」
・「学校選択制は違う種類の子とつき合える貴重な体験を奪う」
・「小学校に質の差を付け,幼い頃から人間を振り分けるような気がしてなら
ない。せめて小中学校では,世の中にはいろいろな人間がいるんだなあと
感じさせることが大切な教育だと思う。」
もう一つ、再掲載になりますが、山折哲雄さんの
「わたしが市について語るなら」④を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「目からウロコの教育を考えるヒント」清水義範 講談社 2001年 ③

◇生徒と先生のほどよいスタンス
「国語入試問題必勝法」
長短除外の法則
…「5つの中から一つ選べ」の問題では最短最長は外す!
対等の立場
◇先生にも修行期間を
「教育実習だけでいきなり担任を持つのは無茶というもの」
◇教育の質を上げる方法
「能力不足の者の切り捨ては教育とは相容れない方針だ」
教委区職員養成審議会
① 民間企業経験者の採用
② 初任者研修充実
「分限免職」
教育の質を上げる方策は能力不足の者を切り捨てるのがベストか?
∥
◎ 教育を忘れた文部省にあるまじき考え方
教員の給料を2倍にして教員の待遇を良くし,いろいろな意味で憧れの
職業にしなければ! → 人材が集まる
|
○ 教員の質を上げる方策はいろいろある
しかし,文部省はクビを切るだけ
∥
文部科学省もリストラをやりたがっている
◎ 質を向上させる方策
× 質の低い者を排除していく
◇時代の色に染まる公立学校
「学校選択制は違う種類の子とつき合える貴重な体験を奪う」
品川区
小学校の選択自由化(2000年~)
公立小に多様化が必要か
→ 公立は均質性こそ求められる
「小中学校だけ全種類の人間とつき合うことが出来た」
↑↓
◎ 学校選択制は学校の質の均一性をなくすことにつながる
教育レベルも上下二つの層に分化してゆきつつある
∥
◎ 違う層との関係がギクシャクしつつある
|
◎ 小学校に質の差を付け,幼い頃から人間を振り分けるような気がし
てならない。せめて小中学校では,世の中にはいろいろな人間がいる
んだなあと感じさせることが大切な教育だと思う。
☆「わたしが死について語るなら」山折哲雄 ポプラ社 2009年 ④(最終)【再掲載 2013.5】
[出版社の案内]
宗教学者・山折哲雄が、思春期を迎える未来のおとなたちに伝える「死」の話。
ストレートなテーマを、真摯に、実体験を交えて語りかけます。
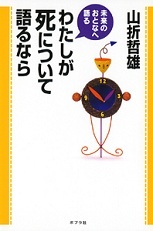
◇日本には「無常」の風が吹いていた
□古典のもつ強さ
「伸び伸び、明るく、元気よく」が存在しない時代になってしまった
シュタイナー学校
「古典は子どもにとって心の母乳になる」
古典
~ 声に出して文章のリズムを身体で感じる
身体で感じることが何よりも大切
□ 「万葉集」を読む
「『万葉集』『源氏物語』『平家物語』『謡曲』『浄瑠璃』これだけの古典に
親しんでいれば、それで日本人の価値観、宗教観、自然観のすべてが分
かる」 山折哲雄
「万葉集」
相聞歌(恋の歌)と挽歌(死者を悼む歌)
「源氏物語」を読む
「もののあはれ」 と 「もののけ」
「平家物語」を読む
無常の感覚
「謡曲」と「浄瑠璃」を読む
謡曲 シテの多くが亡霊や生き霊
= 語りのリズム
◎ 古典と語り
□「おまえは今死ねるか」
唐木順三「自殺について」アテネ文庫 弘文堂 1950年
「きけわだつみのこえ」
死の前に和歌
- 古典のリズムの強さ、すごさ
「目からウロコの教育を考えるヒント」3回目の紹介です。
出版社の紹介には
「こんな時代だからこそ、教育を根本から考えよう!『子供たちがあぶない』
『教育の危機』『日本はお先真っ暗』 それってホントですか?子供大好きの
シミズ博士がとことん考え尽くした、大納得の異色教育論。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「教育実習だけでいきなり担任を持つのは無茶というもの。先生にも修行期
間がほしい。」
・「教員の給料を2倍にして教員の待遇を良くし,いろいろな意味で憧れの職
業にしなければ。そうすれば人材が集まる」
・「学校選択制は違う種類の子とつき合える貴重な体験を奪う」
・「小学校に質の差を付け,幼い頃から人間を振り分けるような気がしてなら
ない。せめて小中学校では,世の中にはいろいろな人間がいるんだなあと
感じさせることが大切な教育だと思う。」
もう一つ、再掲載になりますが、山折哲雄さんの
「わたしが市について語るなら」④を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「目からウロコの教育を考えるヒント」清水義範 講談社 2001年 ③

◇生徒と先生のほどよいスタンス
「国語入試問題必勝法」
長短除外の法則
…「5つの中から一つ選べ」の問題では最短最長は外す!
対等の立場
◇先生にも修行期間を
「教育実習だけでいきなり担任を持つのは無茶というもの」
◇教育の質を上げる方法
「能力不足の者の切り捨ては教育とは相容れない方針だ」
教委区職員養成審議会
① 民間企業経験者の採用
② 初任者研修充実
「分限免職」
教育の質を上げる方策は能力不足の者を切り捨てるのがベストか?
∥
◎ 教育を忘れた文部省にあるまじき考え方
教員の給料を2倍にして教員の待遇を良くし,いろいろな意味で憧れの
職業にしなければ! → 人材が集まる
|
○ 教員の質を上げる方策はいろいろある
しかし,文部省はクビを切るだけ
∥
文部科学省もリストラをやりたがっている
◎ 質を向上させる方策
× 質の低い者を排除していく
◇時代の色に染まる公立学校
「学校選択制は違う種類の子とつき合える貴重な体験を奪う」
品川区
小学校の選択自由化(2000年~)
公立小に多様化が必要か
→ 公立は均質性こそ求められる
「小中学校だけ全種類の人間とつき合うことが出来た」
↑↓
◎ 学校選択制は学校の質の均一性をなくすことにつながる
教育レベルも上下二つの層に分化してゆきつつある
∥
◎ 違う層との関係がギクシャクしつつある
|
◎ 小学校に質の差を付け,幼い頃から人間を振り分けるような気がし
てならない。せめて小中学校では,世の中にはいろいろな人間がいる
んだなあと感じさせることが大切な教育だと思う。
☆「わたしが死について語るなら」山折哲雄 ポプラ社 2009年 ④(最終)【再掲載 2013.5】
[出版社の案内]
宗教学者・山折哲雄が、思春期を迎える未来のおとなたちに伝える「死」の話。
ストレートなテーマを、真摯に、実体験を交えて語りかけます。
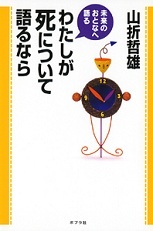
◇日本には「無常」の風が吹いていた
□古典のもつ強さ
「伸び伸び、明るく、元気よく」が存在しない時代になってしまった
シュタイナー学校
「古典は子どもにとって心の母乳になる」
古典
~ 声に出して文章のリズムを身体で感じる
身体で感じることが何よりも大切
□ 「万葉集」を読む
「『万葉集』『源氏物語』『平家物語』『謡曲』『浄瑠璃』これだけの古典に
親しんでいれば、それで日本人の価値観、宗教観、自然観のすべてが分
かる」 山折哲雄
「万葉集」
相聞歌(恋の歌)と挽歌(死者を悼む歌)
「源氏物語」を読む
「もののあはれ」 と 「もののけ」
「平家物語」を読む
無常の感覚
「謡曲」と「浄瑠璃」を読む
謡曲 シテの多くが亡霊や生き霊
= 語りのリズム
◎ 古典と語り
□「おまえは今死ねるか」
唐木順三「自殺について」アテネ文庫 弘文堂 1950年
「きけわだつみのこえ」
死の前に和歌
- 古典のリズムの強さ、すごさ



