「プロ親になる」親野智可等 宝島社 2005年 ⑤ /「旅の民俗学」宮本常一 河出書房新社 2006年 ③【再掲載 2012.7】 [読書記録 教育]
今回は、4月20日に続いて、親野智可等さんの
「プロ親になる」紹介の5回目です。
出版社の紹介には
「子供を伸ばす親の総合力を『親力』と呼んでいます。例えば、子供を愛し、
受け入れ、褒めて、伸ばしてやる力です。または、子供によい環境を作って
やったり、楽勉をプロデュースしたりする力です。この本では、皆さんの親
力をさらにパワーアップさせるための発想、アイディア、テクニックなどを
紹介しています。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「算数の教科書は復習のいい問題集になる」
・「なぞなぞは言語連想能力を高める知的な遊びである」
・「皆自分のペースで成長している」
「必要なのは叱ることではなく手助けすること」
・「人間が自分を愛せるかどうかということは、まず親に十分愛されたかどう
かで決まってくる。満たされている子どもは愛情を分け合う」
もう一つ、再掲載になりますが、宮本常一さんの
「旅の民俗学」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「プロ親になる」親野智可等 宝島社 2005年 ⑤

◇「楽勉」のすすめ(2)
□親力68
他の出版社の教科書を読ませることの効果
「おもしろい読み物」として教科書を読む
人気は理科
- 新鮮な驚きがおさらいにぴったり
□親力69
他の出版社の算数の教科書はいい問題集になる
よくできた問題集としての教科書
復習の問題集
前の学年の教科書で定着を深める
□親力70
あやとりには抜群の教育的効果がある
1 達成感
2 努力の大切さを知り集中力
3 手先が器用に
4 二人あやとりで人間関係
5 あやとり
6 必ず上達
□親力71
なぞなぞは言語連想能力を高める知的な遊びである
言語連想能力と場面連想能力
なぞなぞを楽しむことの効果
勉強にも役立つなぞなぞ
連想ゲーム しりとり遊び
◇子育てを楽しむために(1)
□親力72
熟した果実は自然に落ちる
自分なりのやり方で
そのときがくるのを待つ
◎ 皆自分のペースで成長している
自然な欲求が満たされなかった子ども
「抱き癖」と「サイレントベビー」
泣いたり笑ったりしてコミュニケーションを図ろうとする
熟した果実だけが自然に落ちる
□親力73
どの子もみんな、伸びたいと思っている
忘れ物の多い男の子
◎ 必要なのは叱ることではなく手助けすること
□親力74
しつけより愛情
満たされない思いのはけ口
愛情不足
□親力75
子どもは大人の公平さをいつも吟味している
無意識の「ひいき」
「公平な態度」では公平とは言えない
自分を愛せなくなる子ども
「人間が自分を愛せるかどうかということは、まず親に十分愛さ
れたかどうかで決まってくる」
|
◎ 自分が必要な存在で大切な存在だと感じさせてくれるのは親
以外にない
|
◎ 自己愛あってこその他者への愛
満たされている子どもは愛情を分け合う
☆「旅の民俗学」宮本常一 河出書房新社 2006年 ③【再掲載 2012.7】
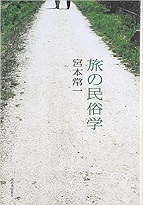
◇旅と伝説に魅せられて 松谷みよ子(1921~ 作家)
秋田の山村に行き続ける伝承
岩の上で稲植える姫君
◇松永伍一(1930~詩人)
史実と違う菅原道真像
祟り神として
~ 学問の神(江戸時代)
平家落人伝説の謎
「北里軍記」の御先祖捜し
◎ 伝説の中にどのくらい事実が潜んでいるか?
中世以降は事実に近い
作られたヒーロー 佐倉宗五郎
秀吉を矮小化する民衆の知恵
◇高野聖と平家部落 杉本苑子(1925~作家)
平家部落は幻集団
全国に100~300の平家部落
落人伝説の由来は?
真宗地帯に平家部落はなし
戦死者を弔い歩く僧
祟りを平家に託す
「源氏部落」のない理由
山奥に田を開く習俗
◇道の文化史 中西睦(1929~交通学者)
上りと下りの交通体系
南部牛が描く広域流通
荘園経済で問屋が誕生
損得のない民衆の社会
草戸千軒遺跡
◎「日本くらい民衆の中で平等が発達した国はなかった」
◇新志摩風土記
鳥羽の日和山
日和見山
青峰山の海難絵馬
はしりがねの島
◇漁村と港町
海と山
「山あて」-山岳信仰
泊
- 遠浅 港
~ 古い時代の日本の船は平底
津
- 水深の深い港
- 沖にとめた船
末子相続・家船・女の地位
一本釣りと末子相続
漁業と商業
漁民の生活感覚と行動力
泉佐野
- 機屋に失敗すると打瀬あみの漁師に
◎ 商業と漁業の関係は紙一重
漁民と土地
漁民の移動
西日本から東日本へ 大阪湾から西へ
◎ 鎖国がなければもう少し自由奔放だった
◇海と日本人 山崎朋子(1932~)
鎖国以前
鎖国の後遺症
以前は気軽に南の島々に
◎ 海は危険だなんて尻込みしている日本人はいなかった
赤いコメと海の道
コメ オリザ=サティバ=ジャポニカ
オリザ=サティバ=インディカ 赤くて長いコメ
海流の役割
島国根性とは何か
◇貴重な観光資源を保護する態度 荒垣秀雄(1902~1989)
憂うべき現状
新緑と紅葉の消失
花の名所・吉野の謎
地元の人の地元知らず
画一化
自然美を再創造せよ
◇宮本常一
1907年生 1981年没
天王寺師範学校卒業
小学校教諭
→ アチック・ミューゼアム
→ 武蔵野美術大学教授,日本常民文化研究所理事
日本観光文化研究所
「プロ親になる」紹介の5回目です。
出版社の紹介には
「子供を伸ばす親の総合力を『親力』と呼んでいます。例えば、子供を愛し、
受け入れ、褒めて、伸ばしてやる力です。または、子供によい環境を作って
やったり、楽勉をプロデュースしたりする力です。この本では、皆さんの親
力をさらにパワーアップさせるための発想、アイディア、テクニックなどを
紹介しています。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「算数の教科書は復習のいい問題集になる」
・「なぞなぞは言語連想能力を高める知的な遊びである」
・「皆自分のペースで成長している」
「必要なのは叱ることではなく手助けすること」
・「人間が自分を愛せるかどうかということは、まず親に十分愛されたかどう
かで決まってくる。満たされている子どもは愛情を分け合う」
もう一つ、再掲載になりますが、宮本常一さんの
「旅の民俗学」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「プロ親になる」親野智可等 宝島社 2005年 ⑤

◇「楽勉」のすすめ(2)
□親力68
他の出版社の教科書を読ませることの効果
「おもしろい読み物」として教科書を読む
人気は理科
- 新鮮な驚きがおさらいにぴったり
□親力69
他の出版社の算数の教科書はいい問題集になる
よくできた問題集としての教科書
復習の問題集
前の学年の教科書で定着を深める
□親力70
あやとりには抜群の教育的効果がある
1 達成感
2 努力の大切さを知り集中力
3 手先が器用に
4 二人あやとりで人間関係
5 あやとり
6 必ず上達
□親力71
なぞなぞは言語連想能力を高める知的な遊びである
言語連想能力と場面連想能力
なぞなぞを楽しむことの効果
勉強にも役立つなぞなぞ
連想ゲーム しりとり遊び
◇子育てを楽しむために(1)
□親力72
熟した果実は自然に落ちる
自分なりのやり方で
そのときがくるのを待つ
◎ 皆自分のペースで成長している
自然な欲求が満たされなかった子ども
「抱き癖」と「サイレントベビー」
泣いたり笑ったりしてコミュニケーションを図ろうとする
熟した果実だけが自然に落ちる
□親力73
どの子もみんな、伸びたいと思っている
忘れ物の多い男の子
◎ 必要なのは叱ることではなく手助けすること
□親力74
しつけより愛情
満たされない思いのはけ口
愛情不足
□親力75
子どもは大人の公平さをいつも吟味している
無意識の「ひいき」
「公平な態度」では公平とは言えない
自分を愛せなくなる子ども
「人間が自分を愛せるかどうかということは、まず親に十分愛さ
れたかどうかで決まってくる」
|
◎ 自分が必要な存在で大切な存在だと感じさせてくれるのは親
以外にない
|
◎ 自己愛あってこその他者への愛
満たされている子どもは愛情を分け合う
☆「旅の民俗学」宮本常一 河出書房新社 2006年 ③【再掲載 2012.7】
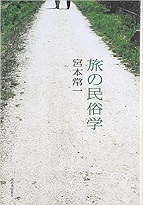
◇旅と伝説に魅せられて 松谷みよ子(1921~ 作家)
秋田の山村に行き続ける伝承
岩の上で稲植える姫君
◇松永伍一(1930~詩人)
史実と違う菅原道真像
祟り神として
~ 学問の神(江戸時代)
平家落人伝説の謎
「北里軍記」の御先祖捜し
◎ 伝説の中にどのくらい事実が潜んでいるか?
中世以降は事実に近い
作られたヒーロー 佐倉宗五郎
秀吉を矮小化する民衆の知恵
◇高野聖と平家部落 杉本苑子(1925~作家)
平家部落は幻集団
全国に100~300の平家部落
落人伝説の由来は?
真宗地帯に平家部落はなし
戦死者を弔い歩く僧
祟りを平家に託す
「源氏部落」のない理由
山奥に田を開く習俗
◇道の文化史 中西睦(1929~交通学者)
上りと下りの交通体系
南部牛が描く広域流通
荘園経済で問屋が誕生
損得のない民衆の社会
草戸千軒遺跡
◎「日本くらい民衆の中で平等が発達した国はなかった」
◇新志摩風土記
鳥羽の日和山
日和見山
青峰山の海難絵馬
はしりがねの島
◇漁村と港町
海と山
「山あて」-山岳信仰
泊
- 遠浅 港
~ 古い時代の日本の船は平底
津
- 水深の深い港
- 沖にとめた船
末子相続・家船・女の地位
一本釣りと末子相続
漁業と商業
漁民の生活感覚と行動力
泉佐野
- 機屋に失敗すると打瀬あみの漁師に
◎ 商業と漁業の関係は紙一重
漁民と土地
漁民の移動
西日本から東日本へ 大阪湾から西へ
◎ 鎖国がなければもう少し自由奔放だった
◇海と日本人 山崎朋子(1932~)
鎖国以前
鎖国の後遺症
以前は気軽に南の島々に
◎ 海は危険だなんて尻込みしている日本人はいなかった
赤いコメと海の道
コメ オリザ=サティバ=ジャポニカ
オリザ=サティバ=インディカ 赤くて長いコメ
海流の役割
島国根性とは何か
◇貴重な観光資源を保護する態度 荒垣秀雄(1902~1989)
憂うべき現状
新緑と紅葉の消失
花の名所・吉野の謎
地元の人の地元知らず
画一化
自然美を再創造せよ
◇宮本常一
1907年生 1981年没
天王寺師範学校卒業
小学校教諭
→ アチック・ミューゼアム
→ 武蔵野美術大学教授,日本常民文化研究所理事
日本観光文化研究所



