「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2008年 ③ /「最強最後の学習法」後藤武士 宝島社 2005年 ③(最終) 【再掲載 2016.8】 [読書記録 民俗]
今回は、3月9日に続いて、斎藤卓志さんの、
「世間師 宮本常一の仕事」の紹介 3回目です。
出版社の案内には、
「『忘れられた日本人』などで知られる民俗学者・宮本常一の生涯を
追った評伝。日本全国を旅した宮本の仕事を探索するとともに、学者
的でも民俗的でも高踏的でもない、宮本の人間に対するやさしさと温
かさを伝える。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「『日本残酷物語』全5巻 別巻2 平凡社は、宮本の体験と谷川の編集
力によるところが大きい」
・「宮本の体験を『日本文化の形成』などという文化論で終わらせては
ならない。神のような美しい庶民がいるんだよ。」 谷川健一
・「人生の火は愛情に他ならない」 石牟田道子
・「柳田の偉大さは分かるが信用しない。取材旅行をしていないから」
高田宏
もう一つ、再掲載になりますが、後藤武士さんの
「最強最後の学習法」③を載せます。
先輩から伝えられてわたしが取り組んでいることと同じような方法が
たくさん挙げられていることに驚きました。
☆「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2008年 ③
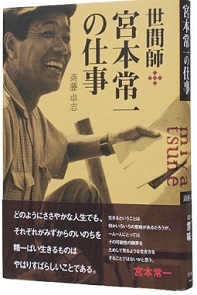
◇編集者と出会う
□谷川健一
平凡社編集者
→ 研究者
宮本と組んで
「綴り方風土記」全8巻 1953-54
「風土記日本」全6巻 1960
編集委員 大藤時彦,鎌田久子,宮本常一
「日本残酷物語」全5巻 別巻2 平凡社
宮本の体験と谷川の編集力
谷川 平成12年の取材時
「宮本の体験を『日本文化の形成』などという文化論で終わ
らせてはならない。神のような美しい庶民がいるんだよ。」
石牟田道子「ちくま日本文学全集 宮本常一」解説文
「人生の火は愛情に他ならない」
高田宏 「編集者放浪記」 (リクルート,1988) エッソ・エナジー
柳田の偉大さは分かるが信用しない
- 取材旅行をしていないから
□宮本常一と未来社
小箕俊介「舟山板」(さんぱん)昭和58年「宮本常一と未来社」
西谷能雄社長
佐渡二見出身 (弘文堂を退社して興した)
連絡係 松田政男(日本赤軍として仏より強制送還)南島出身
「忘れられた日本人」があまり売れなかったから著作集刊行に
山本安英「ぶどうの会」 久米明,坂本
「民話」宮本常一,西郷竹彦,竹内実,吉沢和夫
◇岡本・深沢・宮本の対談
□深沢一郎,岡本太郎,宮本常一
「民話」18号(昭和35年3月)に対談(鼎談)が収録
「土佐ゆず原乞食」の話
メクラの話は素晴らしい
◎ 目の見えなくなった人たちというのは,共通して自分の
中でいろいろな過去を消化していって,そして形にして一
つの物語に位置づけてしまう
「百鬼夜行」の芸術論
鬼面
~ 金太郎飴
◇一人芝居「土佐源氏」
□役者・坂本長利「土佐源氏」
昭和42(1967)年講演許可を得るため宮本を訪ねた
「やあ」「おうっ」
-「芝居はするが演技してはダメ」
宮本 「民話」
◎ どのようにささやかな人生でも,それぞれが自らの
人生を精いっぱい生きるのはやはり素晴らしいことで
ある。生きるということは何かいろいろな意味
昭和26(1951)年
「山本安英とぶどうの会」の研究生に
昭和42(1967)12.1~15日間 60回
「坂本長利 『土佐源氏』の世界」S55(1975)劇書房
毛利甚八
「PHP」№540 平成5年5月 宮本常一さんの微笑
独演劇「土佐源氏」
☆「最強最後の学習法」後藤武士 宝島社 2005年 ③(最終) 【再掲載 2016.8】
[出版社の案内]
中学受験、高校受験で難関校に受かる、基本は国語読解力だ!誰でも出
来てすぐ結果の出る6つの学習法で、必ず難関校に受かる。若くしてカ
リスマ講師になった著者が、自らの生徒にだけ教えてきた秘蔵の学習法
を開示。その基本は国語力。読書しなくても問題集の使い方次第で読解
力がアップ。そして暗記。5分間繰り返しとボールペンの活用で、必ず
記憶できる

<まとめ>
◇1時間目 最短時間で国語力をつける
① 読解力がなければ、国語だけでなく他の科目の教科書も理解で
きない。
テレビやゲームの説明書だって読んで理解できなければ、遊ぶ
こともできない。
② 読書でも読解力はつけられるが、時間がかかりすぎる。手っ取
り早く力をつけるには市販の問題集が一番いい。
③ 問題集は読解問題が多く、解答編が別冊になっていて、解説が
充実したものを選ぶこと。
解説文を読んで、とりあえず何を言っているのかわかれば、自
分のレベルに合っている。
④ 問題は必ず解くこと。そして、それ以上大切なのは「答え合わ
せ」と「解説を理解すること」。
解説が理解できなかったら得意な人に教えてもらおう。
⑤ どうしても問題が解けないときは答えをノートに書き写そう。
そしてなぜその答えになるのか、自分なりの解説を書く。それを
問題集の解説と比べるのだ。
⑥ 「天声人語」や「編集手帳」などの新聞のコラムにタイトルを
付けてみよう。うまく付けられれば、内容を理解できたというこ
と。
◇2時間目 ノート活用法
① ノートをうまく使えば貴重な学習記録になる。
自分がとこを間違ったのか、どこが弱点か、あとから見返すこ
とができる。
② ノートは科目ごとに1冊に固定すること。できれば、学校用と
自習用が欲しい。ルーズリーフは整理の苦手な子には向かない。
③ ノートは読み返すもの。きれいでなくても、わかりやすい字で
書こう。
④ 余白を十分にとれば見やすくなる。
⑤ あとから見直す学習記録だから、日付と見出しは忘れずに付け
ること。
⑥ アンダーラインに使う色は一色にすること。なおかつ、なるべ
く引かない。せいぜい1ページに1、2ヵ所。多いと見づらくな
る。
⑦ 間違ったところは、消すな。あとから見返すときに必要。
◇3時間目-間違い学習法をただす
① 子どもの勉強部屋はゲーム場になるだけ。勉強は食後のリビン
グで十分できる。
②「ながら勉強」も、しないより、するほうがまし。逆に音楽はい
いBGMになる。ただし、国語と英語の長文読解は「ながら勉強」
に向かない。
③ 10月と1月に始まるドラマはビデオに録画。試験期間が終わっ
たら見よう。
④ シミュレーショングームとRPGはやたら時間がかかるゲーム。
避けたほうが無難。どうしてもやりたいのなら、シューティング
ゲームか格闘技ゲーム。
◇4時間目-「5分間」暗記法
① 基本的なことは暗記が必要。九九を覚えなければ算数はできな
い。ルールを知らずして野球はできない。
② 子どもは暗記が苦手なんてウソ。好きなものは嫌でも覚える。
「モーニング娘」のメンバーや好きなスポーツのルールなどはす
ぐ覚えてしまう。
③ 暗記に時間をかける必要はない。電話番号のように何度も何度
も繰り返して接していれば覚えてしまう。要は回数だ。
④ 中学3年分の英語の動詞を覚えてみよう。単語リストを用意し
たら、まず25語を5分で覚える。
時間を計りながら、必ず、書いて声に出して覚えよう。
⑤ 5分たったらミニテスト。リストを見ずにどれだけ覚えている
か書き出そう。全部覚えてなくてもいい。さあ、覚えてなかった
ものを中心にまた5分で覚えよう。
そして4回も繰り返せばおぼえてしまうはず。
⑥ でも、翌日には忘れている。だから、翌日も繰り返す。昨日よ
りは早く覚えられるはず。これを1週間も繰り返せばバッチリだ。
◇5時間目-ボールペン学習法
① 間違いを消してはいけない。どこでどう間違えたかを、次に生
かすのだ。
② そのためにはノートにボールペン。消したくても消せない。
③ ボールペンの利点はそれだけではない。鉛筆と追って折れない。
滑らかに書ける。インクが減っていくので充実感が味わえる。
④ 3色ボールペンは避けよう。しかし、赤ボールペンは必要。間
違った問題は赤で答えを書き込む。「紅一点」で目立つから、あ
とからすぐにチェックできる。
◇6時間目-ぬりつぶし予定表
① 学習予定表は時間軸で作ってはいけない。
② やるべき課題を書き出して、それを予定表にする。
③ やった課題は消していこう。残ったものがやるべきことだ。
④ できれば、やるべき課題を何日でやるか決めよう。
⑤ 課題数を日数で割ればそれが1日の目安数。ノルマにすると大
変だけど目安はあったほうがいい。目安数にいかなくても明日や
ればいい。気楽に構えよう。
「世間師 宮本常一の仕事」の紹介 3回目です。
出版社の案内には、
「『忘れられた日本人』などで知られる民俗学者・宮本常一の生涯を
追った評伝。日本全国を旅した宮本の仕事を探索するとともに、学者
的でも民俗的でも高踏的でもない、宮本の人間に対するやさしさと温
かさを伝える。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「『日本残酷物語』全5巻 別巻2 平凡社は、宮本の体験と谷川の編集
力によるところが大きい」
・「宮本の体験を『日本文化の形成』などという文化論で終わらせては
ならない。神のような美しい庶民がいるんだよ。」 谷川健一
・「人生の火は愛情に他ならない」 石牟田道子
・「柳田の偉大さは分かるが信用しない。取材旅行をしていないから」
高田宏
もう一つ、再掲載になりますが、後藤武士さんの
「最強最後の学習法」③を載せます。
先輩から伝えられてわたしが取り組んでいることと同じような方法が
たくさん挙げられていることに驚きました。
☆「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2008年 ③
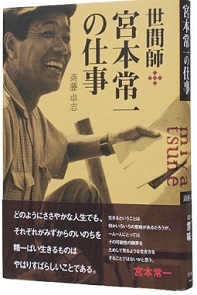
◇編集者と出会う
□谷川健一
平凡社編集者
→ 研究者
宮本と組んで
「綴り方風土記」全8巻 1953-54
「風土記日本」全6巻 1960
編集委員 大藤時彦,鎌田久子,宮本常一
「日本残酷物語」全5巻 別巻2 平凡社
宮本の体験と谷川の編集力
谷川 平成12年の取材時
「宮本の体験を『日本文化の形成』などという文化論で終わ
らせてはならない。神のような美しい庶民がいるんだよ。」
石牟田道子「ちくま日本文学全集 宮本常一」解説文
「人生の火は愛情に他ならない」
高田宏 「編集者放浪記」 (リクルート,1988) エッソ・エナジー
柳田の偉大さは分かるが信用しない
- 取材旅行をしていないから
□宮本常一と未来社
小箕俊介「舟山板」(さんぱん)昭和58年「宮本常一と未来社」
西谷能雄社長
佐渡二見出身 (弘文堂を退社して興した)
連絡係 松田政男(日本赤軍として仏より強制送還)南島出身
「忘れられた日本人」があまり売れなかったから著作集刊行に
山本安英「ぶどうの会」 久米明,坂本
「民話」宮本常一,西郷竹彦,竹内実,吉沢和夫
◇岡本・深沢・宮本の対談
□深沢一郎,岡本太郎,宮本常一
「民話」18号(昭和35年3月)に対談(鼎談)が収録
「土佐ゆず原乞食」の話
メクラの話は素晴らしい
◎ 目の見えなくなった人たちというのは,共通して自分の
中でいろいろな過去を消化していって,そして形にして一
つの物語に位置づけてしまう
「百鬼夜行」の芸術論
鬼面
~ 金太郎飴
◇一人芝居「土佐源氏」
□役者・坂本長利「土佐源氏」
昭和42(1967)年講演許可を得るため宮本を訪ねた
「やあ」「おうっ」
-「芝居はするが演技してはダメ」
宮本 「民話」
◎ どのようにささやかな人生でも,それぞれが自らの
人生を精いっぱい生きるのはやはり素晴らしいことで
ある。生きるということは何かいろいろな意味
昭和26(1951)年
「山本安英とぶどうの会」の研究生に
昭和42(1967)12.1~15日間 60回
「坂本長利 『土佐源氏』の世界」S55(1975)劇書房
毛利甚八
「PHP」№540 平成5年5月 宮本常一さんの微笑
独演劇「土佐源氏」
☆「最強最後の学習法」後藤武士 宝島社 2005年 ③(最終) 【再掲載 2016.8】
[出版社の案内]
中学受験、高校受験で難関校に受かる、基本は国語読解力だ!誰でも出
来てすぐ結果の出る6つの学習法で、必ず難関校に受かる。若くしてカ
リスマ講師になった著者が、自らの生徒にだけ教えてきた秘蔵の学習法
を開示。その基本は国語力。読書しなくても問題集の使い方次第で読解
力がアップ。そして暗記。5分間繰り返しとボールペンの活用で、必ず
記憶できる

<まとめ>
◇1時間目 最短時間で国語力をつける
① 読解力がなければ、国語だけでなく他の科目の教科書も理解で
きない。
テレビやゲームの説明書だって読んで理解できなければ、遊ぶ
こともできない。
② 読書でも読解力はつけられるが、時間がかかりすぎる。手っ取
り早く力をつけるには市販の問題集が一番いい。
③ 問題集は読解問題が多く、解答編が別冊になっていて、解説が
充実したものを選ぶこと。
解説文を読んで、とりあえず何を言っているのかわかれば、自
分のレベルに合っている。
④ 問題は必ず解くこと。そして、それ以上大切なのは「答え合わ
せ」と「解説を理解すること」。
解説が理解できなかったら得意な人に教えてもらおう。
⑤ どうしても問題が解けないときは答えをノートに書き写そう。
そしてなぜその答えになるのか、自分なりの解説を書く。それを
問題集の解説と比べるのだ。
⑥ 「天声人語」や「編集手帳」などの新聞のコラムにタイトルを
付けてみよう。うまく付けられれば、内容を理解できたというこ
と。
◇2時間目 ノート活用法
① ノートをうまく使えば貴重な学習記録になる。
自分がとこを間違ったのか、どこが弱点か、あとから見返すこ
とができる。
② ノートは科目ごとに1冊に固定すること。できれば、学校用と
自習用が欲しい。ルーズリーフは整理の苦手な子には向かない。
③ ノートは読み返すもの。きれいでなくても、わかりやすい字で
書こう。
④ 余白を十分にとれば見やすくなる。
⑤ あとから見直す学習記録だから、日付と見出しは忘れずに付け
ること。
⑥ アンダーラインに使う色は一色にすること。なおかつ、なるべ
く引かない。せいぜい1ページに1、2ヵ所。多いと見づらくな
る。
⑦ 間違ったところは、消すな。あとから見返すときに必要。
◇3時間目-間違い学習法をただす
① 子どもの勉強部屋はゲーム場になるだけ。勉強は食後のリビン
グで十分できる。
②「ながら勉強」も、しないより、するほうがまし。逆に音楽はい
いBGMになる。ただし、国語と英語の長文読解は「ながら勉強」
に向かない。
③ 10月と1月に始まるドラマはビデオに録画。試験期間が終わっ
たら見よう。
④ シミュレーショングームとRPGはやたら時間がかかるゲーム。
避けたほうが無難。どうしてもやりたいのなら、シューティング
ゲームか格闘技ゲーム。
◇4時間目-「5分間」暗記法
① 基本的なことは暗記が必要。九九を覚えなければ算数はできな
い。ルールを知らずして野球はできない。
② 子どもは暗記が苦手なんてウソ。好きなものは嫌でも覚える。
「モーニング娘」のメンバーや好きなスポーツのルールなどはす
ぐ覚えてしまう。
③ 暗記に時間をかける必要はない。電話番号のように何度も何度
も繰り返して接していれば覚えてしまう。要は回数だ。
④ 中学3年分の英語の動詞を覚えてみよう。単語リストを用意し
たら、まず25語を5分で覚える。
時間を計りながら、必ず、書いて声に出して覚えよう。
⑤ 5分たったらミニテスト。リストを見ずにどれだけ覚えている
か書き出そう。全部覚えてなくてもいい。さあ、覚えてなかった
ものを中心にまた5分で覚えよう。
そして4回も繰り返せばおぼえてしまうはず。
⑥ でも、翌日には忘れている。だから、翌日も繰り返す。昨日よ
りは早く覚えられるはず。これを1週間も繰り返せばバッチリだ。
◇5時間目-ボールペン学習法
① 間違いを消してはいけない。どこでどう間違えたかを、次に生
かすのだ。
② そのためにはノートにボールペン。消したくても消せない。
③ ボールペンの利点はそれだけではない。鉛筆と追って折れない。
滑らかに書ける。インクが減っていくので充実感が味わえる。
④ 3色ボールペンは避けよう。しかし、赤ボールペンは必要。間
違った問題は赤で答えを書き込む。「紅一点」で目立つから、あ
とからすぐにチェックできる。
◇6時間目-ぬりつぶし予定表
① 学習予定表は時間軸で作ってはいけない。
② やるべき課題を書き出して、それを予定表にする。
③ やった課題は消していこう。残ったものがやるべきことだ。
④ できれば、やるべき課題を何日でやるか決めよう。
⑤ 課題数を日数で割ればそれが1日の目安数。ノルマにすると大
変だけど目安はあったほうがいい。目安数にいかなくても明日や
ればいい。気楽に構えよう。
「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2008年 ② /「フィンランド・メソッド入門」北川達夫 経済界 2005年 ①(上)【再掲載 2016.1】 [読書記録 民俗]
今回は、3月6日に続いて、斎藤卓志さんの、
「世間師 宮本常一の仕事」の紹介 2回目です。
出版社の案内には、
「『忘れられた日本人』などで知られる民俗学者・宮本常一の生涯を
追った評伝。日本全国を旅した宮本の仕事を探索するとともに、学者
的でも民俗的でも高踏的でもない、宮本の人間に対するやさしさと温
かさを伝える。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「多くの人の力を有機的にまとめて,日本全体をよくするような考え
方を持つこと,それこそ政治なのではあるまいか。そうすれば,日
本人全体の生活が良くなる。わたしは文明がみんなに行き渡ったと
きは,どんなことをしても,それは贅沢とは言えないと思っている。
少数の人だけしか受けられないこと,それが贅沢なのである。すべ
ての人が贅沢したいと思っている。また,けして悪くないと考える。」
渋澤敬三
・「宮本の書いたものを読んでいくと,しゃべった人の人間性までが伝
わり,話している人間が浮き上がってくる…そうして聞き取った宮
本の姿はふっとんでいる」 高松圭吉
・「宮本にとっての民俗学は、現実の問題を解決するための手がかりで
あった」
もう一つ、再掲載になりますが、北川達夫さんの
「フィンランド・メソッド入門」①を載せます。
☆「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2008年 ②
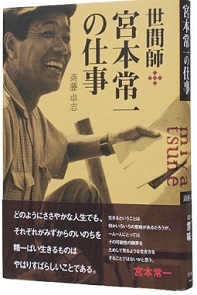
◇渋澤敬三の学問
□昭和10年4月14日 宮本,渋澤に会う
沢田四郎作 大坂・小児科専門開業医
昭和10年 アサ子(旧姓:玉田)との結婚
日本史学者・魚住惣五郎の紹介
「こんな我が儘な人は自分がもらってあげないと…」宮本の印象
◎ 柳田の「山の人生」と宮本の「忘れられた日本人」
渋澤
学問と実地
「学者になるな」
宮本は渋澤の判断を最優先
満州建国大学への誘い(恩師 森信三)を断念
東大講師への誘い(石田英一郎)も
□渋澤敬三
「多くの人の力を有機的にまとめて,日本全体をよくするような考
え方を持つこと,それこそ政治なのではあるまいか。そうすれば,
日本人全体の生活が良くなる。わたしは文明がみんなに行き渡っ
たときは,どんなことをしても,それは贅沢とは言えないと思っ
ている。少数の人だけしか受けられないこと,それが贅沢なので
ある。すべての人が贅沢したいと思っている。また,けして悪く
ないと考える。」
◇終戦前後
□高松圭吉(東京農業大学)
「柳田が縦なら渋澤は横,宮本はその間にいた」
「宮本の書いたものを読んでいくと,しゃべった人の人間性までが
伝わり,話している人間が浮き上がってくる…そうして聞き取っ
た宮本の姿はふっとんでいる」
◇対馬調査
□昭和25~26
対馬調査
→ 宮本のものの見方にとって一つの転換点
能登調査
早大・武田良三,外木典夫 東大院生・山階芳正
◇離島のために
□離島振興協議会
→ 大見重雄入所(安城市出身) 東農大・高松門下
浅野芳正(防大教授)旧姓・山階
宮本が事務局長
条件
①無報酬 ②誰にも悪いことを悪いと言える
神保教子
全国離島振興協議会書記 昭和29年2月12日
宮本の表の顔
「忘れられた日本人」昭和35年
内なる顔
「庶民の発見」昭和36年
→ ◎ 人間に対する揺るぎない信頼
宮本にとっての民俗学
= 現実の問題を解決するための手がかり
(財)日本離島センター
「しま」(№106 1981)宮本常一追悼号
高松圭吉「防波堤」
「何でもいいから問題提起しておけば,そこへ食いついてき
た人がもっと深めてくれる」
田村善次郎 S28(1953)1浪後 東京農業大学
↓ 河岡武春 峠下の村調査に参加
S29 林業金融調査会
◎立ち上げに宮本と高松が尽力
田村もメンバーに
→ 宮本に引き寄せられるように行動を共に
高松圭吉(現相模女子大学教授) 外木典夫(早稲田大学教授)
河岡武春(日本常民文化研究所常任理事)
→ 若い人たちも
神崎宣武,谷沢明,印南敏秀(武蔵野美術大学)
田村善次郎,香月洋一郎
→ 武蔵美生活文化研究所
日本観光文化研究所
大見
「宮本は人生の精神的支え」
大見重雄
1993年没「離島一路-回想 大見重雄と島の仲間たち」
全国離島振興協議会事務局長
(財)日本離島センター総務部長(H4.10~)
☆「フィンランド・メソッド入門」北川達夫 経済界 2005年 ①(上)【再掲載 2016.1】
[出版社の案内]
フィンランドの国語教科書で採用されている方法や、教育現場で用いら
れている手法を、世界ではじめて5つのメソッド、発想力・論理力・表
現力・批判的思考力・コミュニケーション力で分析。フィンランドでは
小学生から取り組んでいるカルタの考え方や書き方をはじめ、さまざま
なものの考え方・コミュニケーションの取り方などを総合的に学んでい
きます。今まで日本にはなかった教育メソッドですが、子どもから大人
までだれでも簡単に身につけることができます。
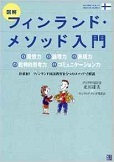
◇フィンランド共和国
森と湖の国
15~20万の湖
国土の7割が森林
北部ラップランド
福祉国家 ムーミン シベリウス
◇今なぜフィンランド・メソッドか
(北川氏)
外交官 → 国語教師
□グローバル・コミュニケーション力
基礎 ①発想力
②論理力
③表現力
応用 ④批判的思考力
⑤コミュニケーション力の育成
◇発想力
□徹底的にカルタを使う
カルタ
~ マインドマップ
中央にテーマ
~ 連想を放射状に
□中心のテーマから
テーマを中央に
← 先生が質問を投げ掛ける
□カルタを使って自己紹介
わたしは何?
□みんなで一つのカルタを書いてみる
発想力 → 分析力 → 創造力
◇論理力
「ミクシ(どうして?)」 攻撃の秘密
先生の「ミクシ」攻撃
「意見には理由」
大人にも養いたい論理力
□論理の回路を頭の中に
意見
- 理由の論理型
①意見
②なぜなら(理由1)
③それに(理由2)
④また(理由3)
□論理力を使って物語を読みましょう
原因と結果の法則
- 教える側の意識を変える
□先生の着眼点は「結果よりプロセス」
◇表現力
一番短い作文を書けるのは誰かな
「15個の単語をすべて使って作文を書こう。
一番短い作文を書くことができるのは誰かな?」
言葉を自由自在に使いこなす
フォーマットを使って作文を書こう
□初歩的なメソッドで物語を創作しましょう
① 基本的人物設定
趣味,仕事,名前,見た目,性格,職業名等
② 物語の登場人物の設定
味方,敵,何をしようとしているのか,武器等
□ショートストーリーを創作しましょう
カルタを使って発想力
作文の書き方
~ パラグラフ・ライティング
「中心文」 + 「支持文」
「世間師 宮本常一の仕事」の紹介 2回目です。
出版社の案内には、
「『忘れられた日本人』などで知られる民俗学者・宮本常一の生涯を
追った評伝。日本全国を旅した宮本の仕事を探索するとともに、学者
的でも民俗的でも高踏的でもない、宮本の人間に対するやさしさと温
かさを伝える。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「多くの人の力を有機的にまとめて,日本全体をよくするような考え
方を持つこと,それこそ政治なのではあるまいか。そうすれば,日
本人全体の生活が良くなる。わたしは文明がみんなに行き渡ったと
きは,どんなことをしても,それは贅沢とは言えないと思っている。
少数の人だけしか受けられないこと,それが贅沢なのである。すべ
ての人が贅沢したいと思っている。また,けして悪くないと考える。」
渋澤敬三
・「宮本の書いたものを読んでいくと,しゃべった人の人間性までが伝
わり,話している人間が浮き上がってくる…そうして聞き取った宮
本の姿はふっとんでいる」 高松圭吉
・「宮本にとっての民俗学は、現実の問題を解決するための手がかりで
あった」
もう一つ、再掲載になりますが、北川達夫さんの
「フィンランド・メソッド入門」①を載せます。
☆「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2008年 ②
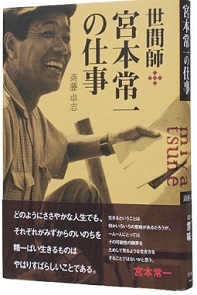
◇渋澤敬三の学問
□昭和10年4月14日 宮本,渋澤に会う
沢田四郎作 大坂・小児科専門開業医
昭和10年 アサ子(旧姓:玉田)との結婚
日本史学者・魚住惣五郎の紹介
「こんな我が儘な人は自分がもらってあげないと…」宮本の印象
◎ 柳田の「山の人生」と宮本の「忘れられた日本人」
渋澤
学問と実地
「学者になるな」
宮本は渋澤の判断を最優先
満州建国大学への誘い(恩師 森信三)を断念
東大講師への誘い(石田英一郎)も
□渋澤敬三
「多くの人の力を有機的にまとめて,日本全体をよくするような考
え方を持つこと,それこそ政治なのではあるまいか。そうすれば,
日本人全体の生活が良くなる。わたしは文明がみんなに行き渡っ
たときは,どんなことをしても,それは贅沢とは言えないと思っ
ている。少数の人だけしか受けられないこと,それが贅沢なので
ある。すべての人が贅沢したいと思っている。また,けして悪く
ないと考える。」
◇終戦前後
□高松圭吉(東京農業大学)
「柳田が縦なら渋澤は横,宮本はその間にいた」
「宮本の書いたものを読んでいくと,しゃべった人の人間性までが
伝わり,話している人間が浮き上がってくる…そうして聞き取っ
た宮本の姿はふっとんでいる」
◇対馬調査
□昭和25~26
対馬調査
→ 宮本のものの見方にとって一つの転換点
能登調査
早大・武田良三,外木典夫 東大院生・山階芳正
◇離島のために
□離島振興協議会
→ 大見重雄入所(安城市出身) 東農大・高松門下
浅野芳正(防大教授)旧姓・山階
宮本が事務局長
条件
①無報酬 ②誰にも悪いことを悪いと言える
神保教子
全国離島振興協議会書記 昭和29年2月12日
宮本の表の顔
「忘れられた日本人」昭和35年
内なる顔
「庶民の発見」昭和36年
→ ◎ 人間に対する揺るぎない信頼
宮本にとっての民俗学
= 現実の問題を解決するための手がかり
(財)日本離島センター
「しま」(№106 1981)宮本常一追悼号
高松圭吉「防波堤」
「何でもいいから問題提起しておけば,そこへ食いついてき
た人がもっと深めてくれる」
田村善次郎 S28(1953)1浪後 東京農業大学
↓ 河岡武春 峠下の村調査に参加
S29 林業金融調査会
◎立ち上げに宮本と高松が尽力
田村もメンバーに
→ 宮本に引き寄せられるように行動を共に
高松圭吉(現相模女子大学教授) 外木典夫(早稲田大学教授)
河岡武春(日本常民文化研究所常任理事)
→ 若い人たちも
神崎宣武,谷沢明,印南敏秀(武蔵野美術大学)
田村善次郎,香月洋一郎
→ 武蔵美生活文化研究所
日本観光文化研究所
大見
「宮本は人生の精神的支え」
大見重雄
1993年没「離島一路-回想 大見重雄と島の仲間たち」
全国離島振興協議会事務局長
(財)日本離島センター総務部長(H4.10~)
☆「フィンランド・メソッド入門」北川達夫 経済界 2005年 ①(上)【再掲載 2016.1】
[出版社の案内]
フィンランドの国語教科書で採用されている方法や、教育現場で用いら
れている手法を、世界ではじめて5つのメソッド、発想力・論理力・表
現力・批判的思考力・コミュニケーション力で分析。フィンランドでは
小学生から取り組んでいるカルタの考え方や書き方をはじめ、さまざま
なものの考え方・コミュニケーションの取り方などを総合的に学んでい
きます。今まで日本にはなかった教育メソッドですが、子どもから大人
までだれでも簡単に身につけることができます。
◇フィンランド共和国
森と湖の国
15~20万の湖
国土の7割が森林
北部ラップランド
福祉国家 ムーミン シベリウス
◇今なぜフィンランド・メソッドか
(北川氏)
外交官 → 国語教師
□グローバル・コミュニケーション力
基礎 ①発想力
②論理力
③表現力
応用 ④批判的思考力
⑤コミュニケーション力の育成
◇発想力
□徹底的にカルタを使う
カルタ
~ マインドマップ
中央にテーマ
~ 連想を放射状に
□中心のテーマから
テーマを中央に
← 先生が質問を投げ掛ける
□カルタを使って自己紹介
わたしは何?
□みんなで一つのカルタを書いてみる
発想力 → 分析力 → 創造力
◇論理力
「ミクシ(どうして?)」 攻撃の秘密
先生の「ミクシ」攻撃
「意見には理由」
大人にも養いたい論理力
□論理の回路を頭の中に
意見
- 理由の論理型
①意見
②なぜなら(理由1)
③それに(理由2)
④また(理由3)
□論理力を使って物語を読みましょう
原因と結果の法則
- 教える側の意識を変える
□先生の着眼点は「結果よりプロセス」
◇表現力
一番短い作文を書けるのは誰かな
「15個の単語をすべて使って作文を書こう。
一番短い作文を書くことができるのは誰かな?」
言葉を自由自在に使いこなす
フォーマットを使って作文を書こう
□初歩的なメソッドで物語を創作しましょう
① 基本的人物設定
趣味,仕事,名前,見た目,性格,職業名等
② 物語の登場人物の設定
味方,敵,何をしようとしているのか,武器等
□ショートストーリーを創作しましょう
カルタを使って発想力
作文の書き方
~ パラグラフ・ライティング
「中心文」 + 「支持文」



