樋口清之さんはこんなことを①-「日本人と人情」 大和書房 1994年 /「トイレ掃除」鍵山秀三郎(出典不明)① [読書記録 歴史]
今日は4月7日、日曜日です。
今回は、「樋口清之さんはこんなことを」1回目、
「日本人と人情」を紹介します。
うめぼし博士としてメディアによく登場されていましたね。
出版社の案内には、
「礼儀作法はなぜ必要なのか。儀式にはどんな意味があるのか。古来、
日本民族の心を表現し続けてきた伝統を再評価し、その効用をも明ら
かにする。日本人とは何かを明快に答えた、現代生活にも役立つ教養
書。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「マナー(約束事)とエチケット(マナー+道徳性・精神性)」
・「武士道の底流にあるのは女尊男卑。三行半を出すと男は百叩きか所
払いとなった」
・「人にものを勧めるときも下座から(その人から見て右側)ものを出
さないといけない」
・「おかわりするときに一口残すわけは、何もなくなると縁が切れてし
まうから」
わたしにはなるほどと思ってしまうことがたくさん書かれていました。
もう一つ、再掲載になりますが、鍵山秀三郎さんの
「トイレ掃除」①を載せます。
「自問」なのか「空気を読め」なのか、難しいところです。
新しい生活が始まってから一週間、
予定を立てて一日一日過ごしているのですが、思うようには…
☆樋口清之さんはこんなことを①-「日本人と人情」 大和書房 1994年
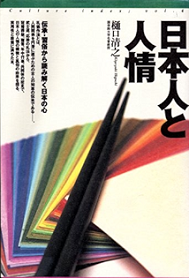
◇礼儀作法
相互の生活秩序を守る知恵
法律
… ドライで客観的に形式化されたもの
(血が通っていない)
道徳
… ウェットなもの
形として表れたものが礼儀作法
|
社会の繁栄とその中で自分自身が心身ともに豊かに生きてゆくた
めの秩序のスタイル
自発的なもの
マナー(約束事)とエチケット(マナー+道徳性・精神性)
◇礼の原点
イザナギ(男神)とイザナミ(女神)
いざなう
= 誘い合う
柱をまわる
= お祭り
◇武士道
わざ+ルール
→ 「術」 = レベルアップ
→ 法+道徳性
→ 道
底流にあるのは女尊男卑
三行半
… 男は百叩き か 所払い
日本はもとから女尊の社会
平安以後 形式的に男性が表面に
◇お辞儀
相手に敵意のないことを示す
- 昔(縄文から弥生)偉い人に会うと柏手を打つ
音によって神を招き寄せ魂をふり動かす
= 魂振り
◇敷居
敷居
① 危険
隙間から刀の刃が
② 保護のため
◇上座
左が上席
(=心臓の位置)
礼法の基準
人にものを勧めるときも下座から(その人から見て右側)ものを
出さないといけない
◇おかわり
おかわりするときに一口残すわけ
=「何もなくなると縁が切れる」
◇温石
お腹に石を当てて空腹感を紛らす(懐石)
◇服装
家紋
… 公家
牛車が誰の車か分からなくなるから
縁起のいい植物
→ 魔よけと家の繁栄
扇
… 送風 神を招く
武器 礼儀作法
日本 → 中国(ヤン) → ヨーロッパ(ファン)
左前
… 左側の襟が前に出るのではなく,右側の方が肌にくっつくこと
をいう
正
= 右側の襟を中に入れて右前に着物を着るのが正しい
右前
- 右手が利き手・すぐ懐に手を入れられる
登山下駄
… 一枚歯 高歯
草履
… 足の前半分だけ(足半)
踵をつけずに歩いた(速く音を出さずに歩いた)
◇結婚
江戸期
… 見合い(見合いは離婚率が低い)
平安期
… 自由恋愛
万葉期
… 野合
◇葬礼
お通夜
… 魂の再生を祈る行事
隠居
… 生きている家に戒名をつけ,世の中を捨て,俗人から離れて
坊さんになる格好で隠居する
三具足
… 香・花・燭
香典
… お香代
香典返しは消耗品(残らないもの お茶・のり・お菓子)
◇年中行事
年中行事
… 一年の節目節目に行われる祭り
= 365日の火の流れに潤いと変化を与え,労働を休んで喜び
を分かち明日の活力を養う日
- 年耕生産活動から
節句
… 五節句
人日(じんじつ1月1日)
上巳(じょうし3月3日)
端午(5月5日)
七夕(7月7日)
重陽(ちょうよう9月9日)
八朔(8月1日)冬至 彼岸 お盆など
節供(節句)
= 神へのお供えをする日
◇日の丸と君が代
薩英戦争(文久三年)
薩摩の船の標識に日の丸
「君が代」明治26年
薩摩琵琶のおめでたい唄
恋歌 君 = 恋人
古今集にも
◇村八分
誕生 成人 結婚 死亡 法事 火事 水害 病気 旅立ち 普請
- 疎外と救済のメカニズム
◇躾
母親は客観的になれない
物事の道理をわきまえさせ美醜善悪の区別を子どもに教えてい
くもの
= 知恵
☆「トイレ掃除」鍵山秀三郎(出典不明)①
◇「自問清掃」で掃除を励行
耳慣れない言葉ですが、「自問清掃」で成果を上げているのが、群馬
県富岡市教育委員会の取り組みです。
平成7年9月、富岡市内にある14の小・中学校の学校数育を任され
た岩井榮壽教育長が,教育方針の根幹に据えてはじめられたものです。
岩井教育長は、富岡市立富岡小学校の校長から教育長になられた方で
す。
現在では、この「自問清掃」が富岡市の学校教育の看板になっていま
す。
ここに、岩井教育長からご投稿いただいた「自問教育と掃除に関して」
の原稿があります。
この原稿は、「日本を美しくする会」発行の機関誌『清風掃々』第2
号に掲載されたものです。
ここに転載して、ご紹介します。
「いま、子供たちを取り巻く環境は、悪化の一途を辿り、校内暴力や登
校拒否は著しく増加して、青少年の非行はますます低年齢化と凶悪化
が進み、いまや子供たちの健全な成長発達が危機的な状況にあります。
その現象は子供たちの『心の荒み』の表れであり、大人たちへの無言
の警告なのかも知れません。
よりよい21世紀社会を創造し、繁栄させるには、子供たちに①我慢
の心、②思いやりの心、③気づきの心、④感謝の心、⑤正直な心を育
まねばなりません。
いま、富岡市内の小・中学校では、心の教育の充実を目指して、この
『五つの心』を育てるために『自問教育』(提唱者・竹内隆夫)を進め
ております。
自問教育は、人間教育の原点を見据えた教育であり、『清掃』(自問清
掃)という毎日の実践活動を通じて、子供たち一人ひとりに自身の動
機による成長発達を促すものであります。
自問清掃は、清掃のできない人や漬掃をしたくない人は、他人に迷
惑をかけないようにその場に座り、どうしたら清掃ができるようにな
るかを『自問』します。
教師は子供に信頼を置いて『信じて待つ』ことから出発し、清掃中は
教師の指示や命令や誘導は一切せず、子供の自発性の発揮を信じてひ
たすら待つという人間信頼を基調にして、教師も一緒になって無言で
掃除に取り組むものです。
富岡市教育委員会においては、学校の自問清掃の支援と職員自らの心
を磨くことを目的に『教育委員会掃除に学ぶ会』を平成8年12月に
発足させて、毎月第2・第4土曜日午前6時半から2時間、学校と教
育委員会のトイレ掃除を交互に実施し、今年2月の第1土曜日で26
回目を迎えました。いま、学校からの常時参加者もあって、実践活動
の成果の現れを期待しているところです」
今回は、「樋口清之さんはこんなことを」1回目、
「日本人と人情」を紹介します。
うめぼし博士としてメディアによく登場されていましたね。
出版社の案内には、
「礼儀作法はなぜ必要なのか。儀式にはどんな意味があるのか。古来、
日本民族の心を表現し続けてきた伝統を再評価し、その効用をも明ら
かにする。日本人とは何かを明快に答えた、現代生活にも役立つ教養
書。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「マナー(約束事)とエチケット(マナー+道徳性・精神性)」
・「武士道の底流にあるのは女尊男卑。三行半を出すと男は百叩きか所
払いとなった」
・「人にものを勧めるときも下座から(その人から見て右側)ものを出
さないといけない」
・「おかわりするときに一口残すわけは、何もなくなると縁が切れてし
まうから」
わたしにはなるほどと思ってしまうことがたくさん書かれていました。
もう一つ、再掲載になりますが、鍵山秀三郎さんの
「トイレ掃除」①を載せます。
「自問」なのか「空気を読め」なのか、難しいところです。
新しい生活が始まってから一週間、
予定を立てて一日一日過ごしているのですが、思うようには…
☆樋口清之さんはこんなことを①-「日本人と人情」 大和書房 1994年
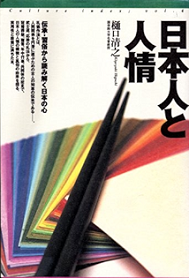
◇礼儀作法
相互の生活秩序を守る知恵
法律
… ドライで客観的に形式化されたもの
(血が通っていない)
道徳
… ウェットなもの
形として表れたものが礼儀作法
|
社会の繁栄とその中で自分自身が心身ともに豊かに生きてゆくた
めの秩序のスタイル
自発的なもの
マナー(約束事)とエチケット(マナー+道徳性・精神性)
◇礼の原点
イザナギ(男神)とイザナミ(女神)
いざなう
= 誘い合う
柱をまわる
= お祭り
◇武士道
わざ+ルール
→ 「術」 = レベルアップ
→ 法+道徳性
→ 道
底流にあるのは女尊男卑
三行半
… 男は百叩き か 所払い
日本はもとから女尊の社会
平安以後 形式的に男性が表面に
◇お辞儀
相手に敵意のないことを示す
- 昔(縄文から弥生)偉い人に会うと柏手を打つ
音によって神を招き寄せ魂をふり動かす
= 魂振り
◇敷居
敷居
① 危険
隙間から刀の刃が
② 保護のため
◇上座
左が上席
(=心臓の位置)
礼法の基準
人にものを勧めるときも下座から(その人から見て右側)ものを
出さないといけない
◇おかわり
おかわりするときに一口残すわけ
=「何もなくなると縁が切れる」
◇温石
お腹に石を当てて空腹感を紛らす(懐石)
◇服装
家紋
… 公家
牛車が誰の車か分からなくなるから
縁起のいい植物
→ 魔よけと家の繁栄
扇
… 送風 神を招く
武器 礼儀作法
日本 → 中国(ヤン) → ヨーロッパ(ファン)
左前
… 左側の襟が前に出るのではなく,右側の方が肌にくっつくこと
をいう
正
= 右側の襟を中に入れて右前に着物を着るのが正しい
右前
- 右手が利き手・すぐ懐に手を入れられる
登山下駄
… 一枚歯 高歯
草履
… 足の前半分だけ(足半)
踵をつけずに歩いた(速く音を出さずに歩いた)
◇結婚
江戸期
… 見合い(見合いは離婚率が低い)
平安期
… 自由恋愛
万葉期
… 野合
◇葬礼
お通夜
… 魂の再生を祈る行事
隠居
… 生きている家に戒名をつけ,世の中を捨て,俗人から離れて
坊さんになる格好で隠居する
三具足
… 香・花・燭
香典
… お香代
香典返しは消耗品(残らないもの お茶・のり・お菓子)
◇年中行事
年中行事
… 一年の節目節目に行われる祭り
= 365日の火の流れに潤いと変化を与え,労働を休んで喜び
を分かち明日の活力を養う日
- 年耕生産活動から
節句
… 五節句
人日(じんじつ1月1日)
上巳(じょうし3月3日)
端午(5月5日)
七夕(7月7日)
重陽(ちょうよう9月9日)
八朔(8月1日)冬至 彼岸 お盆など
節供(節句)
= 神へのお供えをする日
◇日の丸と君が代
薩英戦争(文久三年)
薩摩の船の標識に日の丸
「君が代」明治26年
薩摩琵琶のおめでたい唄
恋歌 君 = 恋人
古今集にも
◇村八分
誕生 成人 結婚 死亡 法事 火事 水害 病気 旅立ち 普請
- 疎外と救済のメカニズム
◇躾
母親は客観的になれない
物事の道理をわきまえさせ美醜善悪の区別を子どもに教えてい
くもの
= 知恵
☆「トイレ掃除」鍵山秀三郎(出典不明)①
◇「自問清掃」で掃除を励行
耳慣れない言葉ですが、「自問清掃」で成果を上げているのが、群馬
県富岡市教育委員会の取り組みです。
平成7年9月、富岡市内にある14の小・中学校の学校数育を任され
た岩井榮壽教育長が,教育方針の根幹に据えてはじめられたものです。
岩井教育長は、富岡市立富岡小学校の校長から教育長になられた方で
す。
現在では、この「自問清掃」が富岡市の学校教育の看板になっていま
す。
ここに、岩井教育長からご投稿いただいた「自問教育と掃除に関して」
の原稿があります。
この原稿は、「日本を美しくする会」発行の機関誌『清風掃々』第2
号に掲載されたものです。
ここに転載して、ご紹介します。
「いま、子供たちを取り巻く環境は、悪化の一途を辿り、校内暴力や登
校拒否は著しく増加して、青少年の非行はますます低年齢化と凶悪化
が進み、いまや子供たちの健全な成長発達が危機的な状況にあります。
その現象は子供たちの『心の荒み』の表れであり、大人たちへの無言
の警告なのかも知れません。
よりよい21世紀社会を創造し、繁栄させるには、子供たちに①我慢
の心、②思いやりの心、③気づきの心、④感謝の心、⑤正直な心を育
まねばなりません。
いま、富岡市内の小・中学校では、心の教育の充実を目指して、この
『五つの心』を育てるために『自問教育』(提唱者・竹内隆夫)を進め
ております。
自問教育は、人間教育の原点を見据えた教育であり、『清掃』(自問清
掃)という毎日の実践活動を通じて、子供たち一人ひとりに自身の動
機による成長発達を促すものであります。
自問清掃は、清掃のできない人や漬掃をしたくない人は、他人に迷
惑をかけないようにその場に座り、どうしたら清掃ができるようにな
るかを『自問』します。
教師は子供に信頼を置いて『信じて待つ』ことから出発し、清掃中は
教師の指示や命令や誘導は一切せず、子供の自発性の発揮を信じてひ
たすら待つという人間信頼を基調にして、教師も一緒になって無言で
掃除に取り組むものです。
富岡市教育委員会においては、学校の自問清掃の支援と職員自らの心
を磨くことを目的に『教育委員会掃除に学ぶ会』を平成8年12月に
発足させて、毎月第2・第4土曜日午前6時半から2時間、学校と教
育委員会のトイレ掃除を交互に実施し、今年2月の第1土曜日で26
回目を迎えました。いま、学校からの常時参加者もあって、実践活動
の成果の現れを期待しているところです」
「井沢式日本史入門 (1) 和とケガレ」井沢元彦 徳間書店 2009年 ②(後) /「異次元緩和の先にあるとてつもない日本」上念司 徳間書店 2013年【再掲載 2015.2】 [読書記録 歴史]
今回は、12月22日に続いて井沢元彦さんの
「井沢式日本史入門① 和とケガレ」の紹介 2回目(後)です。
出版社の紹介には
「『私は専門の歴史学者ではありません。であるけれども私は、なまじ
の学者より日本史のことがよっぽどよくわかっていると自負してい
ます』。教科書に載らない日本史の『ホントのトコロ』を井沢史観
でズバリ解説。隔月刊行シリーズ第一段は、日本固有の精神『和』
『ケガレ』をテーマに、唯一無二の新解釈で飛鳥時代から江戸時代
を再構築する。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「太子の『和』に基づく談合主義。記者クラブも稟議書も」
・「西洋は神との個人契約で個人主義,日本は和の集団主義」
・「出雲大社が象徴する『和の精神』。『雲太和二京三』の意味するもの
は、第一が和の精神、第二が仏教、大さんが天皇」
・「日本史の根底に流れる「話し合い教」を見逃すな」
・「武士の誕生もまた,『ケガレ仕事の外注』」
もう一つ、再掲載になりますが、
「異次元緩和の先にあるとてつもない日本」を載せます。
10年の時が、見立ての正誤をあきらかにしてくれているようです。
「とてつもない」日本、そうだなあとわたしは思います。
☆「井沢式日本史入門 (1) 和とケガレ」井沢元彦 徳間書店 2009年 ②(後)
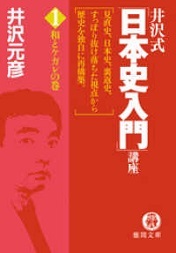
◇日本人が知らない日本固有の信仰 -それが「和」-
日本人が宗教音痴な理由
聖徳太子は仏教より「和」を重視している
太子 「世間虚仮」
この世は幻
- 彼岸主義
話し合いで決まったことは絶対にうまくいく?
「和に基づく談合主義」
記者クラブも
稟議書も
西洋は神との個人契約で個人主義,日本は和の集団主義
「和」という調整法は八百万の神々の国だからこそ
神話切り捨ては大間違い
日本書紀
- 天武天皇の命令
編集責任は息子の舎人親王
「国譲り神話」の根底にあるもの,それはやはり「和」
大国主
~ 日本に最初からいた先住民族の王様
話し合いで正当に譲られた
◇歴史から失われた真実
敗者大国主の「出雲神社」が一番大きかったという事実
口遊
「雲大和和二京三」出雲大社,東大寺大仏殿,大極殿
出雲大社は「日本の特異性」を体現している
太子の憲法十七条は「和の宗教」を高らかに歌い上げるもの
= 協調性の大切さ
日本史の根底に流れる「話し合い教」を見逃すな
出雲大社が象徴しているものは明らかに「和の精神」だ
「雲太和二京三」
→ 第一が和の精神,第二が仏教,大さんが天皇
日本の歴史教科書は前後のつながりが抜け落ちている
官僚が大臣の命令に従わない理由
徳川家に見る「話し合い文化」
ボトムアップ型システム(五人の老中の合議制)
あまりに日本的な「談合」と「天下り」
◇武士と差別の根源 日本人が最も忌み嫌う「ケガレ」とは何か
差別の原因は宗教にある
割り箸と湯飲み茶碗から日本人の特異性が透けて見える
ケガレ
- 数値では確立できない
「ケガレ」を流せるのは「ミソギ」だけ
死にかかわるものはすべて「ケガレ」になった
日本人の中にある差別意識
それは「死のケガレ」から来る
武士の誕生もまた,「ケガレ仕事の外注」
◇言霊の魔力
日本史は怨霊信仰を置き去りにした
日本史は言霊信仰を置き去りにした
☆「異次元緩和の先にあるとてつもない日本」上念司 徳間書店 2013年【再掲載 2015.2】

◇超金融緩和で激変し始めた日本の経済
1年間で実質金利は2.7%も下がっている
反アベノミクス論者たちのうろたえぶり
3本の矢
① インフレ率2%まで上昇
② 財政政策 国土強靱化
③ エネルギー 先端医療 女性活用
安定・成長・再分配
デフレとはお金に対する需要が増えること
「目標の独立性」をミスリードした○○
◇脱デフレで消える企業
ブラック企業
① 低賃金
② 長労働
③ 高離職率
安さを追求するビジネスモデルの終焉
人手不足という現実
公務員人気はあと数年で下火になる
デフレ
= 競争しなくてもいい世の中
イノベーション促進のために政府は何をすべきか
中小企業のアグレッシブな投資
◇被正規雇用の黄金時代がやってくる
これから労働市場は人手不足になる
ブラック企業は人手不足で行き詰まる
最初に恩恵を受けるのは被正規雇用・パート・アルバイト
◇バブル再来とその崩壊の行方
アメリカの尻ぬぐいをして起きた前回のバブル
◇日銀マネーが世界を変える
円安で韓国の衰退が始まった
韓国のイチャモンは懐具合
ほとんどの大手銀行が外資系となった韓国金融
韓国は通貨危機の可能性が高まっている
世界中が支那にそっぽを向き始めた
間もなく自滅
379兆円の不正資金流出
「井沢式日本史入門① 和とケガレ」の紹介 2回目(後)です。
出版社の紹介には
「『私は専門の歴史学者ではありません。であるけれども私は、なまじ
の学者より日本史のことがよっぽどよくわかっていると自負してい
ます』。教科書に載らない日本史の『ホントのトコロ』を井沢史観
でズバリ解説。隔月刊行シリーズ第一段は、日本固有の精神『和』
『ケガレ』をテーマに、唯一無二の新解釈で飛鳥時代から江戸時代
を再構築する。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「太子の『和』に基づく談合主義。記者クラブも稟議書も」
・「西洋は神との個人契約で個人主義,日本は和の集団主義」
・「出雲大社が象徴する『和の精神』。『雲太和二京三』の意味するもの
は、第一が和の精神、第二が仏教、大さんが天皇」
・「日本史の根底に流れる「話し合い教」を見逃すな」
・「武士の誕生もまた,『ケガレ仕事の外注』」
もう一つ、再掲載になりますが、
「異次元緩和の先にあるとてつもない日本」を載せます。
10年の時が、見立ての正誤をあきらかにしてくれているようです。
「とてつもない」日本、そうだなあとわたしは思います。
☆「井沢式日本史入門 (1) 和とケガレ」井沢元彦 徳間書店 2009年 ②(後)
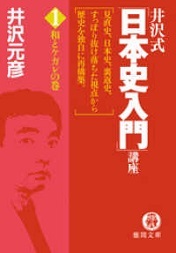
◇日本人が知らない日本固有の信仰 -それが「和」-
日本人が宗教音痴な理由
聖徳太子は仏教より「和」を重視している
太子 「世間虚仮」
この世は幻
- 彼岸主義
話し合いで決まったことは絶対にうまくいく?
「和に基づく談合主義」
記者クラブも
稟議書も
西洋は神との個人契約で個人主義,日本は和の集団主義
「和」という調整法は八百万の神々の国だからこそ
神話切り捨ては大間違い
日本書紀
- 天武天皇の命令
編集責任は息子の舎人親王
「国譲り神話」の根底にあるもの,それはやはり「和」
大国主
~ 日本に最初からいた先住民族の王様
話し合いで正当に譲られた
◇歴史から失われた真実
敗者大国主の「出雲神社」が一番大きかったという事実
口遊
「雲大和和二京三」出雲大社,東大寺大仏殿,大極殿
出雲大社は「日本の特異性」を体現している
太子の憲法十七条は「和の宗教」を高らかに歌い上げるもの
= 協調性の大切さ
日本史の根底に流れる「話し合い教」を見逃すな
出雲大社が象徴しているものは明らかに「和の精神」だ
「雲太和二京三」
→ 第一が和の精神,第二が仏教,大さんが天皇
日本の歴史教科書は前後のつながりが抜け落ちている
官僚が大臣の命令に従わない理由
徳川家に見る「話し合い文化」
ボトムアップ型システム(五人の老中の合議制)
あまりに日本的な「談合」と「天下り」
◇武士と差別の根源 日本人が最も忌み嫌う「ケガレ」とは何か
差別の原因は宗教にある
割り箸と湯飲み茶碗から日本人の特異性が透けて見える
ケガレ
- 数値では確立できない
「ケガレ」を流せるのは「ミソギ」だけ
死にかかわるものはすべて「ケガレ」になった
日本人の中にある差別意識
それは「死のケガレ」から来る
武士の誕生もまた,「ケガレ仕事の外注」
◇言霊の魔力
日本史は怨霊信仰を置き去りにした
日本史は言霊信仰を置き去りにした
☆「異次元緩和の先にあるとてつもない日本」上念司 徳間書店 2013年【再掲載 2015.2】

◇超金融緩和で激変し始めた日本の経済
1年間で実質金利は2.7%も下がっている
反アベノミクス論者たちのうろたえぶり
3本の矢
① インフレ率2%まで上昇
② 財政政策 国土強靱化
③ エネルギー 先端医療 女性活用
安定・成長・再分配
デフレとはお金に対する需要が増えること
「目標の独立性」をミスリードした○○
◇脱デフレで消える企業
ブラック企業
① 低賃金
② 長労働
③ 高離職率
安さを追求するビジネスモデルの終焉
人手不足という現実
公務員人気はあと数年で下火になる
デフレ
= 競争しなくてもいい世の中
イノベーション促進のために政府は何をすべきか
中小企業のアグレッシブな投資
◇被正規雇用の黄金時代がやってくる
これから労働市場は人手不足になる
ブラック企業は人手不足で行き詰まる
最初に恩恵を受けるのは被正規雇用・パート・アルバイト
◇バブル再来とその崩壊の行方
アメリカの尻ぬぐいをして起きた前回のバブル
◇日銀マネーが世界を変える
円安で韓国の衰退が始まった
韓国のイチャモンは懐具合
ほとんどの大手銀行が外資系となった韓国金融
韓国は通貨危機の可能性が高まっている
世界中が支那にそっぽを向き始めた
間もなく自滅
379兆円の不正資金流出



