「中世の東海道をゆく」榎原雅治 中央公論新社 2008年 / 読書ノート「遠藤周作さんはこんなことを」⑫-『安岡章太郎15の対話』安岡章太郎 新潮社 1997年より「井上洋治・遠藤周作との対話」【再掲載 2014.7】 [読書記録 歴史]
今回は、榎原雅治さんの
「中世の東海道をゆく」を紹介します。
出版社の紹介には
「弘安3年(1280)11月、ひとりの貴族が馬に乗り、わずかな随伴者
とともに東海道を京から鎌倉へと向かっていた-。中世の旅路は潮
の干潮など自然条件に大きく左右され、また、木曾三川の流路や遠
州平野に広がる湖沼など東海道沿道の景色も現在とかなり異なって
いた。本書は鎌倉時代の紀行文を題材に、再伸の発掘調査の成果な
どを取り入れ、中世の旅人の眼に映った景色やそこに住む人々の営
みを再現するものである。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「明応の大地震は明応7(1498)年8月25日辰の時(午前7~9時)に発
生した。御前崎で発生し本州中部が揺れた。大波で海辺2,30町の
民家がことごとく流された。M8.2~8.4。」
・「明応の地震で、竜川右岸の地は裂け3~5尺の波が来て、山は割れ、
崩れた。ほどなく大波が天をついて襲ってきた。幾万人か知らず流
された。」
・「浜名湖は淡水湖だったか?鎌倉時代にすでに汽水湖となっていた。
浜名湖淡水説の誕生、汽水化説は江戸時代中期より」
・「天竜川は天中川か天竜川か?『続日本紀』には、麁玉河、広瀬河、
天ちうといふ河、天中川」
もう一つ、再掲載になりますが、
「遠藤周作さんはこんなことを」⑫を載せます。
短いメモです。
☆「中世の東海道をゆく」榎原雅治 中央公論新社 2008年

◇湖畔にて-橋本
□浜名の風景
浜名へ
明応の大地震
明応7(1498)年8月25日辰の時(午前7~9時)
御前崎で発生 → 本州中部
大波で海辺2,30町の民家がことごとく流された
M8.2~8.4
天竜川右岸
地は裂け3~5尺の波,山は割れ崩れた
ほどなく大波が天をついて襲ってきた
幾万人か知らず流される
「円通松堂禅師語録」
大きな引き潮現象
- 伊勢大被害
浜名湖の変容
明応地震以後
「橋本宿」の名は消える
→ 近世「新居関」宿も
しかし,風光明媚の地、橋本宿は壊滅
今切 2説
① 地震直後の津波により出現
② 地震で浜名湖全体の沈降 → 海水流入
翌6月10日台風による高潮により今切出現
浜名湖変化
① 遠州灘と浜名湖はつながっていなかった
② 浜名川
以前は遠州灘に向かい西に流れていた
③ 地震により1m沈降
満潮時には海水が逆上する汽水湖に |
◎ 3㎞以上隔たったところに
古代・中世資料の描く浜名湖
地震以前
… 橋が架けられていた「浜名の橋」
長さ170m 広さ4m 高さ4.8m
9世紀前半にはすでに架けられていた
明治初期まで橋本村有り
現在も新居町浜名の内に
※ 入江があったかなかったか
橋本の形
P92 図3-2
浜名湖は沈降したか
浜名湖は淡水湖だったか
- 鎌倉時代にすでに汽水湖
浜名湖淡水説の誕生
汽水化説は江戸時代中期より
沈降説の誕生と進化
地震学者 都司嘉宣氏 1980年
◇平野の風景 遠州平野
遠州の内海
野津には津あり
「曳馬」は明治になって命名された新地名
中世の引間の位置はまだ特定されていない
内陸水面,今之浦
都市・見付 裸祭り
天竜川
天中川か天竜川か
『続日本紀』
麁玉河 715年
→ 広瀬河 853年
→ 天ちうといふ河 11世紀後半
天中川 1223年
◎ 鎌倉時代 「テンデューガワ」か?
☆読書ノート「遠藤周作さんはこんなことを」⑫-『安岡章太郎15の対話』安岡章太郎 新潮社 1997年より「井上洋治・遠藤周作との対話」【再掲載 2014.7】
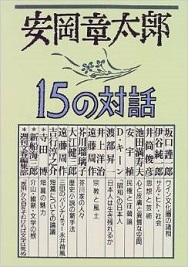
・口語訳聖書のなじみがたさ
・明治になってからも隠れキリシタンが捕まった
浦上村全村の人間を捕まえて日本各地へ
→ 津和野・金沢・高知
・日本のキリスト教徒 100万人
(60万人がプロテスタント 40万人がカトリック)
・隠れキリシタンと留学生
プロテスタント
- マリアを拝まない
カトリック
- マリアを拝む エファソの公会議
・隠れキリシタンは元々転び者
転ばなかったら死んでいる
・水と禊ぎ
水に対するイメージと宗教とは密接な関係
・プロセスの時代
「中世の東海道をゆく」を紹介します。
出版社の紹介には
「弘安3年(1280)11月、ひとりの貴族が馬に乗り、わずかな随伴者
とともに東海道を京から鎌倉へと向かっていた-。中世の旅路は潮
の干潮など自然条件に大きく左右され、また、木曾三川の流路や遠
州平野に広がる湖沼など東海道沿道の景色も現在とかなり異なって
いた。本書は鎌倉時代の紀行文を題材に、再伸の発掘調査の成果な
どを取り入れ、中世の旅人の眼に映った景色やそこに住む人々の営
みを再現するものである。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「明応の大地震は明応7(1498)年8月25日辰の時(午前7~9時)に発
生した。御前崎で発生し本州中部が揺れた。大波で海辺2,30町の
民家がことごとく流された。M8.2~8.4。」
・「明応の地震で、竜川右岸の地は裂け3~5尺の波が来て、山は割れ、
崩れた。ほどなく大波が天をついて襲ってきた。幾万人か知らず流
された。」
・「浜名湖は淡水湖だったか?鎌倉時代にすでに汽水湖となっていた。
浜名湖淡水説の誕生、汽水化説は江戸時代中期より」
・「天竜川は天中川か天竜川か?『続日本紀』には、麁玉河、広瀬河、
天ちうといふ河、天中川」
もう一つ、再掲載になりますが、
「遠藤周作さんはこんなことを」⑫を載せます。
短いメモです。
☆「中世の東海道をゆく」榎原雅治 中央公論新社 2008年

◇湖畔にて-橋本
□浜名の風景
浜名へ
明応の大地震
明応7(1498)年8月25日辰の時(午前7~9時)
御前崎で発生 → 本州中部
大波で海辺2,30町の民家がことごとく流された
M8.2~8.4
天竜川右岸
地は裂け3~5尺の波,山は割れ崩れた
ほどなく大波が天をついて襲ってきた
幾万人か知らず流される
「円通松堂禅師語録」
大きな引き潮現象
- 伊勢大被害
浜名湖の変容
明応地震以後
「橋本宿」の名は消える
→ 近世「新居関」宿も
しかし,風光明媚の地、橋本宿は壊滅
今切 2説
① 地震直後の津波により出現
② 地震で浜名湖全体の沈降 → 海水流入
翌6月10日台風による高潮により今切出現
浜名湖変化
① 遠州灘と浜名湖はつながっていなかった
② 浜名川
以前は遠州灘に向かい西に流れていた
③ 地震により1m沈降
満潮時には海水が逆上する汽水湖に |
◎ 3㎞以上隔たったところに
古代・中世資料の描く浜名湖
地震以前
… 橋が架けられていた「浜名の橋」
長さ170m 広さ4m 高さ4.8m
9世紀前半にはすでに架けられていた
明治初期まで橋本村有り
現在も新居町浜名の内に
※ 入江があったかなかったか
橋本の形
P92 図3-2
浜名湖は沈降したか
浜名湖は淡水湖だったか
- 鎌倉時代にすでに汽水湖
浜名湖淡水説の誕生
汽水化説は江戸時代中期より
沈降説の誕生と進化
地震学者 都司嘉宣氏 1980年
◇平野の風景 遠州平野
遠州の内海
野津には津あり
「曳馬」は明治になって命名された新地名
中世の引間の位置はまだ特定されていない
内陸水面,今之浦
都市・見付 裸祭り
天竜川
天中川か天竜川か
『続日本紀』
麁玉河 715年
→ 広瀬河 853年
→ 天ちうといふ河 11世紀後半
天中川 1223年
◎ 鎌倉時代 「テンデューガワ」か?
☆読書ノート「遠藤周作さんはこんなことを」⑫-『安岡章太郎15の対話』安岡章太郎 新潮社 1997年より「井上洋治・遠藤周作との対話」【再掲載 2014.7】
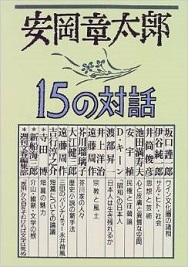
・口語訳聖書のなじみがたさ
・明治になってからも隠れキリシタンが捕まった
浦上村全村の人間を捕まえて日本各地へ
→ 津和野・金沢・高知
・日本のキリスト教徒 100万人
(60万人がプロテスタント 40万人がカトリック)
・隠れキリシタンと留学生
プロテスタント
- マリアを拝まない
カトリック
- マリアを拝む エファソの公会議
・隠れキリシタンは元々転び者
転ばなかったら死んでいる
・水と禊ぎ
水に対するイメージと宗教とは密接な関係
・プロセスの時代
「井沢式日本史入門(1)和とケガレ」井沢元彦 徳間書店 2009年 ①(前) /「大きな学力」寺内義和 労働旬報社 1997年 ③【再掲載 2015.8】 [読書記録 歴史]
今回は、井沢元彦さんの
「井沢式日本史入門(1)和とケガレ」の紹介 1回目(前)です。
出版社の紹介には
「『私は専門の歴史学者ではありません。であるけれども私は、なまじ
の学者より日本史のことがよっぽどよくわかっていると自負してい
ます』。教科書に載らない日本史の『ホントのトコロ』を井沢史観
でズバリ解説。隔月刊行シリーズ第一段は、日本固有の精神『和』
『ケガレ』をテーマに、唯一無二の新解釈で飛鳥時代から江戸時代
を再構築する。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「『憲法17条』が談合と護送船団方式の生みの親
物事は何でも話し合いで決めなさいから協調性の国へ」
・「信長は宗教戦争や宗教テロを起こす人間,起こすぞといった人間も
含めてみんな殺した。しかし本願寺が『もう戦争行為はしません』
と誓ったとき,一転して信仰の自由を決めている。信長・秀吉以
降,お寺はすべて非武装地帯となった」
・「『宗教は人間の基本的行動を決定する』という世界標準」
もう一つ、再掲載になりますが、寺内義和さんの
「大きな学力」③を載せます。
本当の学力とは何か、読んだ当時考えさせられたことを思い出します。
☆「井沢式日本史入門(1)和とケガレ」井沢元彦 徳間書店 2009年 ①(前)
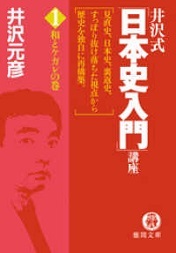
◇既存の歴史学が本末転倒であると断じる理由
「憲法17条」が談合と護送船団方式の生みの親
物事は何でも話し合いで決めなさい
→ 協調性の国
信長が宗教テロを根絶してくれた?
日本における宗教テロの代表「天文法華の乱」
日蓮宗
- 教徒の寺すべて焼き討ち
日本でも「敵対する宗派は皆殺し」が当たり前の戦国時代
日蓮宗は本願寺を焼き討ち
→ 山科本願寺
石山本願寺(現在の大阪城の場所)
二度と焼き討ちにあわないように
日本人は今でも信長が残した歴史的恩恵の中にいる
信長は宗教戦争や宗教テロを起こす人間,起こすぞといった人
間も含めてみんな殺した。しかし本願寺が「もう戦争行為はしま
せん」と誓ったとき,一転して信仰の自由を決めている。
→ 信長・秀吉以降,お寺はすべて非武装地帯
◇世界史との比較では日本史の「特異性」が見えてこない
名前があるかないかで「考古学」と「歴史学」が分かれる
名前が分からない物や人
→ 考古学
「文字」が生まれて初めて「文明」が生まれる
猿 - 火や道具 → 猿人 -体ごつく脳小
→ 原人 → 現世人類(クロマニョン人)
5千年前
① エジプト
② インダス
③ メソポタミア
④ 黄河
文字がない
記録メディアの進化
中国文明 - 紙の発明
エジプトのパピロス
メソポタミアの粘土板
インドの石文
口伝から記録へ
四大文明がすべて大河のほとりにある理由
- 精神文化を代表するのは宗教
技術的文化 と 精神文化
◇文明の個性が宗教に集約される
最初宗教はすべて多神教だった
「一神教誕生」こうしてユダヤ人は世界を変えた
創造主 - 排他的 - 独善的
ユダヤ ~ エホバ
モーセ 「エクソダス」エジプトからの大脱出→
プロンストランド(イスラエル)
十戒
待望のメシア「イエス」を殺したユダヤ人
イスラエル王国のソロモン王 DC10世紀 ローマの植民地に
→ 独立への期待
英傑の出現を期待 = メシア
↑
ユダヤ人の怒り
死刑にしろ ピラト助命を蹴ろうとす
映画「ザ・パッション」
ユダヤ人迫害の原点に立ち返る
イエス死後
古代イスラエル王国は過酷な運命 - ちりぢりに
ユダヤ人
キリストを磔にした責めを負うべき
↑
いい飯,いい服 迫害 ユダヤ人居住区「ゲットー」
ナチスドイツ 「ホロコースト」
ホロコーストとユダヤ人の国「イスラエル」再建
「シオンの丘」の名を取り「シオニズム」建国運動
19世紀後半
キリスト教が一神教である根拠
「三位一体の神学とは何か」
エホバ = カトリック・精霊の三位一体説「トリンティ」
神父-カトリック 牧師-プロテスタント
法王 たくさんの宗派
ユダヤ教は不十分,キリスト教はニセモノ
- そして仏教が誕生した
マホメット
「わたしは本当の神の言葉を聞いた」 アッラー
ユダヤVSキリストVSイスラム
嘘つきはどれだ
妥協点がない
キリスト教徒イスラム教の対立の裏には「石油」がある
かつては棲み分け
イスラム-砂浜 キリスト-森林
日本にもあった 一神教と同じ構想の図式
「宗教は人間の基本的行動を決定する」という世界標準
☆「大きな学力」寺内義和 労働旬報社 1997年 ③【再掲載 2015.8】
[出版社の案内]
70年代に私学運動に登場して以来、戦略家、組織者として恐れられ、
全国に影響を与え続けた著者が、波風体験がうみだす人間力を豊富な
事例で解き明かす。偏差値教育をのりこえる21世紀への羅針盤。
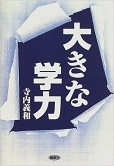
◇「大きな学力」の基本的な力
1 目標をつくり,それを追求する力
- 目標はどこから生まれるか
① 目標とは要求を自覚し組織すること
② 鋭い危機感,ハングリー精神が目標を高める
謙虚さとむさぼるような吸引力
軽蔑
… 何でも知ったかぶりをして自己満足,自己完結して
いる人間を見ると,うんざりし,いらだつことがある
③ 達成体験,感動体験が確信を与える
次なる挑戦に向かわせる
④ 触発が行動を喚起し参加を広げる
「要求」「現状認識(鋭い危機感)
「達成・感動体験」「触発」
2 生きて働く知識,技術,体力,感性
- 要求,関心,生活体験に裏付けられたもの
・ 生きて働く知識(身に付く)
・ 「もっと学びたい」と探求心を起こさせる知識
・ 活用される知識
|
◎結局は,自分の要求や興味・関心・生活体験と切り結んだ知識
3 関係を広げ,深める力
- 共感力,総評価,聞く力,表現力,行動力
① 要求の一致が土台
② 説得は「魂」と「関係」でするもの
「働きかける」能力
③ 聞く力について
「説き,教え,感化する教師」
→ 「認め,寄り添い,引き出す教師」
④ 究極は共鳴能力と総評価の人間観
⑤ 「対立者」が「共鳴者」に変わるとき
◇「大きな学力」はどこからつくか
1 波風の立つ体験
絶望・感動・達成感・発見・出会い
2 主体的体験
参画と挑戦
絶望・辛さ・苦しさ
→ 転化 → 感動・喜び・達成感
◇波風の立つ体験
1 「お年寄りを大切にせよ」
2 「絶望体験がつくる人間力」
生きる目標の喪失・挫折
「生きがい」
関係の断絶
「関係」
キューブラー・ロス
「波風のたくさん立つ,満たされた瞬間の多い人生を送り
ますように」
※ 人間の幸・不幸は置かれた状態で決まるわけではない。その中
で,自分の個性や力を精一杯発揮し,さらに,自分の中にある新
しい力を発見していく。そこに感動が生まれる。それが幸せの大
きな要素である。
3 「感動体験がつくる人間力」
今学校は子供たちにどれだけ感動体験を与えているか
「私たちが目指すのは,一人一人が求められる学校,若さと魅力
を十分発揮できる学校,かけがえのない仲間ができる学校,そ
して夢と感動のある学校」
4 「出会い」がつくる人間力
◇絶望から希望へ
「罪と罰」 ドストエフスキー
「個人的体験」 大江健三郎 - 異質との共生
「イエスの生涯・キリストの誕生」 遠藤周作
◎ 民衆から普遍的な信仰を集めた人は皆深い人間愛を持ち,人の
弱さを糾弾するのではなく,むしろ,人の不可解さに共感してい
るのではないか。
「井沢式日本史入門(1)和とケガレ」の紹介 1回目(前)です。
出版社の紹介には
「『私は専門の歴史学者ではありません。であるけれども私は、なまじ
の学者より日本史のことがよっぽどよくわかっていると自負してい
ます』。教科書に載らない日本史の『ホントのトコロ』を井沢史観
でズバリ解説。隔月刊行シリーズ第一段は、日本固有の精神『和』
『ケガレ』をテーマに、唯一無二の新解釈で飛鳥時代から江戸時代
を再構築する。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「『憲法17条』が談合と護送船団方式の生みの親
物事は何でも話し合いで決めなさいから協調性の国へ」
・「信長は宗教戦争や宗教テロを起こす人間,起こすぞといった人間も
含めてみんな殺した。しかし本願寺が『もう戦争行為はしません』
と誓ったとき,一転して信仰の自由を決めている。信長・秀吉以
降,お寺はすべて非武装地帯となった」
・「『宗教は人間の基本的行動を決定する』という世界標準」
もう一つ、再掲載になりますが、寺内義和さんの
「大きな学力」③を載せます。
本当の学力とは何か、読んだ当時考えさせられたことを思い出します。
☆「井沢式日本史入門(1)和とケガレ」井沢元彦 徳間書店 2009年 ①(前)
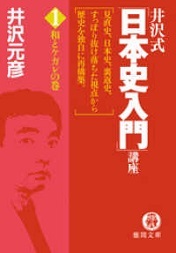
◇既存の歴史学が本末転倒であると断じる理由
「憲法17条」が談合と護送船団方式の生みの親
物事は何でも話し合いで決めなさい
→ 協調性の国
信長が宗教テロを根絶してくれた?
日本における宗教テロの代表「天文法華の乱」
日蓮宗
- 教徒の寺すべて焼き討ち
日本でも「敵対する宗派は皆殺し」が当たり前の戦国時代
日蓮宗は本願寺を焼き討ち
→ 山科本願寺
石山本願寺(現在の大阪城の場所)
二度と焼き討ちにあわないように
日本人は今でも信長が残した歴史的恩恵の中にいる
信長は宗教戦争や宗教テロを起こす人間,起こすぞといった人
間も含めてみんな殺した。しかし本願寺が「もう戦争行為はしま
せん」と誓ったとき,一転して信仰の自由を決めている。
→ 信長・秀吉以降,お寺はすべて非武装地帯
◇世界史との比較では日本史の「特異性」が見えてこない
名前があるかないかで「考古学」と「歴史学」が分かれる
名前が分からない物や人
→ 考古学
「文字」が生まれて初めて「文明」が生まれる
猿 - 火や道具 → 猿人 -体ごつく脳小
→ 原人 → 現世人類(クロマニョン人)
5千年前
① エジプト
② インダス
③ メソポタミア
④ 黄河
文字がない
記録メディアの進化
中国文明 - 紙の発明
エジプトのパピロス
メソポタミアの粘土板
インドの石文
口伝から記録へ
四大文明がすべて大河のほとりにある理由
- 精神文化を代表するのは宗教
技術的文化 と 精神文化
◇文明の個性が宗教に集約される
最初宗教はすべて多神教だった
「一神教誕生」こうしてユダヤ人は世界を変えた
創造主 - 排他的 - 独善的
ユダヤ ~ エホバ
モーセ 「エクソダス」エジプトからの大脱出→
プロンストランド(イスラエル)
十戒
待望のメシア「イエス」を殺したユダヤ人
イスラエル王国のソロモン王 DC10世紀 ローマの植民地に
→ 独立への期待
英傑の出現を期待 = メシア
↑
ユダヤ人の怒り
死刑にしろ ピラト助命を蹴ろうとす
映画「ザ・パッション」
ユダヤ人迫害の原点に立ち返る
イエス死後
古代イスラエル王国は過酷な運命 - ちりぢりに
ユダヤ人
キリストを磔にした責めを負うべき
↑
いい飯,いい服 迫害 ユダヤ人居住区「ゲットー」
ナチスドイツ 「ホロコースト」
ホロコーストとユダヤ人の国「イスラエル」再建
「シオンの丘」の名を取り「シオニズム」建国運動
19世紀後半
キリスト教が一神教である根拠
「三位一体の神学とは何か」
エホバ = カトリック・精霊の三位一体説「トリンティ」
神父-カトリック 牧師-プロテスタント
法王 たくさんの宗派
ユダヤ教は不十分,キリスト教はニセモノ
- そして仏教が誕生した
マホメット
「わたしは本当の神の言葉を聞いた」 アッラー
ユダヤVSキリストVSイスラム
嘘つきはどれだ
妥協点がない
キリスト教徒イスラム教の対立の裏には「石油」がある
かつては棲み分け
イスラム-砂浜 キリスト-森林
日本にもあった 一神教と同じ構想の図式
「宗教は人間の基本的行動を決定する」という世界標準
☆「大きな学力」寺内義和 労働旬報社 1997年 ③【再掲載 2015.8】
[出版社の案内]
70年代に私学運動に登場して以来、戦略家、組織者として恐れられ、
全国に影響を与え続けた著者が、波風体験がうみだす人間力を豊富な
事例で解き明かす。偏差値教育をのりこえる21世紀への羅針盤。
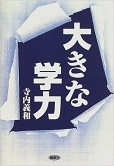
◇「大きな学力」の基本的な力
1 目標をつくり,それを追求する力
- 目標はどこから生まれるか
① 目標とは要求を自覚し組織すること
② 鋭い危機感,ハングリー精神が目標を高める
謙虚さとむさぼるような吸引力
軽蔑
… 何でも知ったかぶりをして自己満足,自己完結して
いる人間を見ると,うんざりし,いらだつことがある
③ 達成体験,感動体験が確信を与える
次なる挑戦に向かわせる
④ 触発が行動を喚起し参加を広げる
「要求」「現状認識(鋭い危機感)
「達成・感動体験」「触発」
2 生きて働く知識,技術,体力,感性
- 要求,関心,生活体験に裏付けられたもの
・ 生きて働く知識(身に付く)
・ 「もっと学びたい」と探求心を起こさせる知識
・ 活用される知識
|
◎結局は,自分の要求や興味・関心・生活体験と切り結んだ知識
3 関係を広げ,深める力
- 共感力,総評価,聞く力,表現力,行動力
① 要求の一致が土台
② 説得は「魂」と「関係」でするもの
「働きかける」能力
③ 聞く力について
「説き,教え,感化する教師」
→ 「認め,寄り添い,引き出す教師」
④ 究極は共鳴能力と総評価の人間観
⑤ 「対立者」が「共鳴者」に変わるとき
◇「大きな学力」はどこからつくか
1 波風の立つ体験
絶望・感動・達成感・発見・出会い
2 主体的体験
参画と挑戦
絶望・辛さ・苦しさ
→ 転化 → 感動・喜び・達成感
◇波風の立つ体験
1 「お年寄りを大切にせよ」
2 「絶望体験がつくる人間力」
生きる目標の喪失・挫折
「生きがい」
関係の断絶
「関係」
キューブラー・ロス
「波風のたくさん立つ,満たされた瞬間の多い人生を送り
ますように」
※ 人間の幸・不幸は置かれた状態で決まるわけではない。その中
で,自分の個性や力を精一杯発揮し,さらに,自分の中にある新
しい力を発見していく。そこに感動が生まれる。それが幸せの大
きな要素である。
3 「感動体験がつくる人間力」
今学校は子供たちにどれだけ感動体験を与えているか
「私たちが目指すのは,一人一人が求められる学校,若さと魅力
を十分発揮できる学校,かけがえのない仲間ができる学校,そ
して夢と感動のある学校」
4 「出会い」がつくる人間力
◇絶望から希望へ
「罪と罰」 ドストエフスキー
「個人的体験」 大江健三郎 - 異質との共生
「イエスの生涯・キリストの誕生」 遠藤周作
◎ 民衆から普遍的な信仰を集めた人は皆深い人間愛を持ち,人の
弱さを糾弾するのではなく,むしろ,人の不可解さに共感してい
るのではないか。



