樋口清之さんはこんなことを④-「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」樋口清之監修 豊島健吾著 大和書房 1988年 /「文系学部廃止の衝撃」吉見俊哉 集英社新書 2016年 ①【再掲載 2017.2】 [読書記録 歴史]
今日は4月17日、水曜日です。
今回は、4月14日に続いて「樋口清之さんはこんなことを」4回目、
「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」を紹介します。
30年以上前に出された本ですが、
書かれている内容は古くはなっていません。
見られなくなったり、忘れられつつあるものが多いのですが。
「言い伝え」られることが失われつつあることをさびしく感じます。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「自然の石は神の拠り所」
・「肩車は土を踏まないことにより神聖を保つことから」
・「門付け(家の門口を訪ね、簡単な藝や祝詞を述べて金や米の報酬を得
る)」
- 子供の頃、毎年来ていた「獅子舞」。こわかったなあ。
・「地神(チジン ジシン ジノカミ ジヌシサマ)は屋敷神として屋敷の西
北北隅や小区画につくられたほこら。その人が死んでから33年ある
いは50年経つと地神になると伝えられる」
- 遠州地方では、まだまだ残っています。
・「綱引きは歳占いの神事。二つの集落で勝負し、勝った方が豊作とさ
れる。綱は神の使いの蛇とされる」
もう一つ、再掲載になりますが、吉見俊哉さんの
「文系学部廃止の衝撃」①を載せます。
- 日本学術会議が2001年に「21世紀における人文・社会科学の役割と
その重要性」声明
2020年の「日本学術会議問題」を思い出しました。
☆樋口清之さんはこんなことを④-「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」樋口清之監修 豊島健吾編著 大和書房 1988年

◇挨拶
前にあるものを押しのけて進むこと
禅宗「一挨一拶」
禅僧が押し問答をして悟りの度合いを確かめること
→ 問答 返答 応答
以前は「モノイ」
物言い
朝 おはよう
昼 飲みましたか お茶あがり おせんどさん
夕方 おしまいな
暗い おばんでござります
◇雨乞い
呪法
① おこもり
② 雨乞い踊り
③ 貰い水
④ 神を怒らす
⑤ 女相撲
⑥ 百升洗い
⑦ 千歯焚き
◇石上
いしがみ シャクジ
自然の石
= 神の拠り所
◇狼
ヤマイヌ
山住神社 - 狼を大口真神
◇肩車
土を踏まないことにより神聖を保つ
神祭り参加
… 馬 肩車
◇河童
水神少童
◇門付け
家の門口を訪ね、簡単な藝や祝詞を述べて金や米の報酬を得る
正月・小正月
万歳、春駒、鳥追い
◇外道
元仏教用語
仏の教えを受けない者 = 邪教
外道
モグラより大きくネズミより小さい動物
◇庚申信仰
60年 60日以外の庚申の日に行われる信仰行事
= 中国・道教の説
人間体内に三尸(さんし)の虫がいて庚申の日の夜睡眠中の体
内から抜け出して天に昇り天帝にその人の罪過を告げるから、早
死にする
◎長生きするには身を慎んで徹夜せよ
徹夜 = 守庚申
奈良時代から酒食の宴
江戸期 - 全国各地に庚申講
◇五月節供
田植えの月
= 一年中もっとも重要な月
五月五日
女の家 女の宿 女の夜
◇座頭
僧形盲人
- 語り物・謡・浄瑠璃・お祓い・按摩・針灸
盲人団体
-「当道」 検校・別当・匂当・座頭 の四段階
◇地神
チジン ジシン ジノカミ 死神ジヌシサマ
屋敷神
- 屋敷西北北隅や小区画にほこら
その人が死んでから33年あるいは50年経つと地神になる
= 土地の神 屋敷の守護神
◇憑き物
狐 犬神 ゲドウ トウビョウ 蛇 猫 狸 ゴンボタネ
◎特定の家,人につく
狐持ち 犬神筋 ← 世間から迫害
◇綱引き
歳占い=神事
東日本 - 小正月
西日本 - 盆綱引きとして七月
九州 - 中秋の名月を機会に
◎二つの集落で勝負
- 勝った方が豊作
綱
= 神の使いの蛇
◇手拭い
本来の目的は手を拭うものではなかった
古くはユテ、テサジ、ナガタナ
= 頭にかぶるもの
手拭いをかぶって挨拶した
= 手拭いが霊妙な力
◇冬至
一年の家で最も日照時間が短い月
太陽の光が弱まる時期
= 農耕生活の一種の危機
= 神々を村に迎えて盛大に祝う行事が冬至前後に
冬至の夜
神聖な旅人(弘法大師とする例が多い)が村を訪れて奇蹟をしめ
した
カボチャ・蒟蒻・ユズ湯
◇直会(なおらい)
神に供したものをおろし,祭祀斜や氏子たちがいただくこと
- 現在では神事終了後の宴会を指す
☆「文系学部廃止の衝撃」吉見俊哉 集英社新書 2016年 ①【再掲載 2017.2】

1 瞬く間に広がった「文系学部廃止」報道
□きっかけ
2015.6.8
文科省通知 各法人学長宛
「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」
6月後半
- 報道がエスカレート
□文科省批判の集中砲火
文科省バッシング
7月末~9月
□海外メディア
産業界からも相次ぐ批判
□文科省通知には何が書かれていたのか
「特に教員養成系学部・大学院 人文社会科学部系学部・大学院」
国立大は法人化されてから、まるでかつての社会主義国のように6
年ごとに立てる中期目標・中期計画に縛られている
- 中期計画の達成度で評価され、叱られたり褒められたり
▲ 膨大な時間を割く 2003年~
2「通知」批判背後にある暗黙の前提
□通知内容は一年前に公表されていた
2015.5.27
国立大学法人評価委員会に素案
前年8月に「ミッションの再定義」
□「文系学部廃止」批判の背景
突然の問題視
1 2015年夏の政治状況
安保 - 安倍政権
2 新国立競技場建設問題
3 文科省
2014年と2015年の政治状況変化を読み込まなかった
◎「儲かる理系」対「儲からない文系」という構図
3 分離の不均衡はいつから構造化?
□国立大における文系と理系
□戦争の時代に築かれた理系重視
戦争がない時代は法科系エリート
1910年以降
- ◎即戦力としての軍事力強化の時代
理化学研究所(1917)
土木学会(1914)
日本鉄鋼協会(1915)
ロビー活動
法科系の支配権を理工系が奪還
1940年「科学動員実施計画綱領」に結実
選択と集中 = 総力戦に!
□現在に引き継がれる戦時の研究予算体制
◎ロジック
「戦争に勝つには産業経済力の増強しかなく、それには大学の研
究力を強化しなければならない」
- そもそも、勝てるのかという目的自体を客観的に批判する視
点は生まれてこない
◎高度経済成長によってさらに強まる理系優先
岸信介内閣の松田竹千代文部大臣
「国立大の法文系を全廃してそれらはすべて私立に任せ国公立は
理工系中心に構成していくべきだ」
国立大
理系は定員増
文系は定員数抑制
□ポスト高度成長期にも継続する理系中心の体制
1970 80年代以降
◎ 理系は政策的に保護され、
手厚い予算から文系は保護から外され続けた
□理系偏重の科学技術政策に対する問題提起
日本学術会議 2001年
「21世紀における人文・社会科学の役割とその重要性」声明
今回は、4月14日に続いて「樋口清之さんはこんなことを」4回目、
「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」を紹介します。
30年以上前に出された本ですが、
書かれている内容は古くはなっていません。
見られなくなったり、忘れられつつあるものが多いのですが。
「言い伝え」られることが失われつつあることをさびしく感じます。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「自然の石は神の拠り所」
・「肩車は土を踏まないことにより神聖を保つことから」
・「門付け(家の門口を訪ね、簡単な藝や祝詞を述べて金や米の報酬を得
る)」
- 子供の頃、毎年来ていた「獅子舞」。こわかったなあ。
・「地神(チジン ジシン ジノカミ ジヌシサマ)は屋敷神として屋敷の西
北北隅や小区画につくられたほこら。その人が死んでから33年ある
いは50年経つと地神になると伝えられる」
- 遠州地方では、まだまだ残っています。
・「綱引きは歳占いの神事。二つの集落で勝負し、勝った方が豊作とさ
れる。綱は神の使いの蛇とされる」
もう一つ、再掲載になりますが、吉見俊哉さんの
「文系学部廃止の衝撃」①を載せます。
- 日本学術会議が2001年に「21世紀における人文・社会科学の役割と
その重要性」声明
2020年の「日本学術会議問題」を思い出しました。
☆樋口清之さんはこんなことを④-「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」樋口清之監修 豊島健吾編著 大和書房 1988年

◇挨拶
前にあるものを押しのけて進むこと
禅宗「一挨一拶」
禅僧が押し問答をして悟りの度合いを確かめること
→ 問答 返答 応答
以前は「モノイ」
物言い
朝 おはよう
昼 飲みましたか お茶あがり おせんどさん
夕方 おしまいな
暗い おばんでござります
◇雨乞い
呪法
① おこもり
② 雨乞い踊り
③ 貰い水
④ 神を怒らす
⑤ 女相撲
⑥ 百升洗い
⑦ 千歯焚き
◇石上
いしがみ シャクジ
自然の石
= 神の拠り所
◇狼
ヤマイヌ
山住神社 - 狼を大口真神
◇肩車
土を踏まないことにより神聖を保つ
神祭り参加
… 馬 肩車
◇河童
水神少童
◇門付け
家の門口を訪ね、簡単な藝や祝詞を述べて金や米の報酬を得る
正月・小正月
万歳、春駒、鳥追い
◇外道
元仏教用語
仏の教えを受けない者 = 邪教
外道
モグラより大きくネズミより小さい動物
◇庚申信仰
60年 60日以外の庚申の日に行われる信仰行事
= 中国・道教の説
人間体内に三尸(さんし)の虫がいて庚申の日の夜睡眠中の体
内から抜け出して天に昇り天帝にその人の罪過を告げるから、早
死にする
◎長生きするには身を慎んで徹夜せよ
徹夜 = 守庚申
奈良時代から酒食の宴
江戸期 - 全国各地に庚申講
◇五月節供
田植えの月
= 一年中もっとも重要な月
五月五日
女の家 女の宿 女の夜
◇座頭
僧形盲人
- 語り物・謡・浄瑠璃・お祓い・按摩・針灸
盲人団体
-「当道」 検校・別当・匂当・座頭 の四段階
◇地神
チジン ジシン ジノカミ 死神ジヌシサマ
屋敷神
- 屋敷西北北隅や小区画にほこら
その人が死んでから33年あるいは50年経つと地神になる
= 土地の神 屋敷の守護神
◇憑き物
狐 犬神 ゲドウ トウビョウ 蛇 猫 狸 ゴンボタネ
◎特定の家,人につく
狐持ち 犬神筋 ← 世間から迫害
◇綱引き
歳占い=神事
東日本 - 小正月
西日本 - 盆綱引きとして七月
九州 - 中秋の名月を機会に
◎二つの集落で勝負
- 勝った方が豊作
綱
= 神の使いの蛇
◇手拭い
本来の目的は手を拭うものではなかった
古くはユテ、テサジ、ナガタナ
= 頭にかぶるもの
手拭いをかぶって挨拶した
= 手拭いが霊妙な力
◇冬至
一年の家で最も日照時間が短い月
太陽の光が弱まる時期
= 農耕生活の一種の危機
= 神々を村に迎えて盛大に祝う行事が冬至前後に
冬至の夜
神聖な旅人(弘法大師とする例が多い)が村を訪れて奇蹟をしめ
した
カボチャ・蒟蒻・ユズ湯
◇直会(なおらい)
神に供したものをおろし,祭祀斜や氏子たちがいただくこと
- 現在では神事終了後の宴会を指す
☆「文系学部廃止の衝撃」吉見俊哉 集英社新書 2016年 ①【再掲載 2017.2】
1 瞬く間に広がった「文系学部廃止」報道
□きっかけ
2015.6.8
文科省通知 各法人学長宛
「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」
6月後半
- 報道がエスカレート
□文科省批判の集中砲火
文科省バッシング
7月末~9月
□海外メディア
産業界からも相次ぐ批判
□文科省通知には何が書かれていたのか
「特に教員養成系学部・大学院 人文社会科学部系学部・大学院」
国立大は法人化されてから、まるでかつての社会主義国のように6
年ごとに立てる中期目標・中期計画に縛られている
- 中期計画の達成度で評価され、叱られたり褒められたり
▲ 膨大な時間を割く 2003年~
2「通知」批判背後にある暗黙の前提
□通知内容は一年前に公表されていた
2015.5.27
国立大学法人評価委員会に素案
前年8月に「ミッションの再定義」
□「文系学部廃止」批判の背景
突然の問題視
1 2015年夏の政治状況
安保 - 安倍政権
2 新国立競技場建設問題
3 文科省
2014年と2015年の政治状況変化を読み込まなかった
◎「儲かる理系」対「儲からない文系」という構図
3 分離の不均衡はいつから構造化?
□国立大における文系と理系
□戦争の時代に築かれた理系重視
戦争がない時代は法科系エリート
1910年以降
- ◎即戦力としての軍事力強化の時代
理化学研究所(1917)
土木学会(1914)
日本鉄鋼協会(1915)
ロビー活動
法科系の支配権を理工系が奪還
1940年「科学動員実施計画綱領」に結実
選択と集中 = 総力戦に!
□現在に引き継がれる戦時の研究予算体制
◎ロジック
「戦争に勝つには産業経済力の増強しかなく、それには大学の研
究力を強化しなければならない」
- そもそも、勝てるのかという目的自体を客観的に批判する視
点は生まれてこない
◎高度経済成長によってさらに強まる理系優先
岸信介内閣の松田竹千代文部大臣
「国立大の法文系を全廃してそれらはすべて私立に任せ国公立は
理工系中心に構成していくべきだ」
国立大
理系は定員増
文系は定員数抑制
□ポスト高度成長期にも継続する理系中心の体制
1970 80年代以降
◎ 理系は政策的に保護され、
手厚い予算から文系は保護から外され続けた
□理系偏重の科学技術政策に対する問題提起
日本学術会議 2001年
「21世紀における人文・社会科学の役割とその重要性」声明
「小さな人生論」藤尾秀昭 致知出版社 2005年 ③ /「土のいろ」集成 第十一巻 101~106号(前半)【再掲載 2017.1】 [読書記録 一般]
今日は4月16日、火曜日です。
今回は、4月13日に続いて、藤尾秀昭さんの
「小さな人生論 2」の紹介 3回目です。
出版社の案内には、
「『致知』創刊25周年の刊行以来、好評のうちに増刷を重ねて
いる『小さな人生論』。本書は川島廣守氏(日本プロ野球組織
コミッショナー)からヤンキースの松井秀喜選手に贈られた
書としても話題を呼んだ作品の続篇だ。
『自分を高める』『人生に残すもの』『何のために生きるのか』
『命を伝承する』『人生の法則』『先哲の英知をくむ』の各章
テーマのもと、著者の折々の思いが記している。
『人は皆、一個の天真を宿してこの世に生まれてくる、という。
その1個の天真を深く掘り下げ、高め、仕上げていくことこ
そ、各人が果たすべき人生のテーマといえる……』
人生と向き合うための座右の書として、活用いただきたい一冊。」
とあります。
もう一つ、再掲載になりますが、かつての郷土誌、
「土のいろ集成」第11巻を載せます。
☆「小さな人生論」藤尾秀昭 致知出版社 2005年 ③
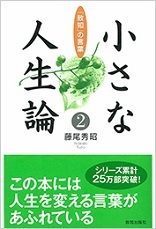
◇母の力
大正から昭和にかけ、熱烈な説教講演で多くの信奉者を集め
た真宗大谷派の憎・暁烏敏の短歌がある。
十億の人に十億の母あらむも
わが母にまさる母ありなむや
十億の人に十億の母がいる。
中には立派な母、優れた母もたくさんいるだろう。
だが、自分にとっては自分の母こそが最高の母だ、というの
である。
この素朴な母への讃美には、共感を覚える人が多いに違いな
い。
生後小児麻痺を患い、不自由な身体になった詩画家の はら
みちをさんは、母に背負われて小学校を卒業した。
そのはらさんの作品の一つに、「どしゃぶりの中を」と題す
る詩がある。
どしゃぶりの中を
母は僕を背負って走った
母の乳房がゆれ
僕は背中でバウンドした
どしゃぶりの中を
母は僕を背負って走った
母の白いうなじに雨と
僕の泪が流れた
どしゃぶりの中を
母は僕を背負って走った
いくら走っても遠いのに
僕はぬれたって平気なのに
どしゃぶりの中を
母は僕を背負って走った
火を吐く山の機関車のように
母の力がばくはつした
もう一つ、詩を掲げる。
サトウハチローの「母の日記をよみました」である。
母の日記をよみました
-悲しきことのみ多かりき
されど よろこびの日もありき-
そのよろこびの日もありきという文字が
太く強くしるされているのが
かえってボクには
かなしくて かなしくて……
多言は要すまい。
子を思う母の力強い愛。
その愛を感じ、母の喜怒衰楽に触れて人は人生を確立してい
く。
母に愛された記憶こそ、一人ひとりの生きる力の根源である。
その母の力こそ、ひいては日本という国を支えた根本である。
そう思わないわけにはいかない。
近年、母の力の衰えが感じられてならない。
虐待、養育放棄、果ては子殺し。
頻出する事件はその突出した表れのようである。
かつて児童福祉施設は親を失い、寄る辺ない子どものための
施設だった。
だがいまでは、虐待する親から子どもを引き離し、守るため
の施設と化しているという現実が、母の力の衰えを端的に示し
ている。
規範を失い、混乱する現代の世相の根本にあるものは、母の
力の衰弱と無関係ではない。
母の力の覚醒が求められてならない。
13歳の愛娘めぐみさんを北朝鮮に拉致されて28年、その奪
還に奔走する横田早紀江さんに、特集にご登場いただいた。
「めぐみは必ず取り戻します。そして、日本を凛とした国にし
ます。私はそれに命を懸けているのです」
毅然とした声が耳元に響いている。
母の力は死んではいない。
☆「土のいろ」集成 第十一巻 101~106号(前半)【再掲載 2017.1】
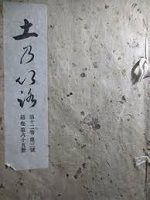
◇復刊第18号 通刊101号 昭和37年11月
□遠州大念仏後編
◇復刊第19号 通刊102号 昭和38年1月
□法多山思玄上人(上) 山口直蔵
□浜松特産「足袋のあれこれ」 須部弥一郎
徳川中期より
特産地 = 浜松と松本
足袋と旅
紺染めと厚地木綿
- 紺屋
□竜禅寺の不動堂 市川象三郎
□浜松の「リズム社」について 渥美 実
大正末
浜松の音楽結社「リズム社」
~ 「赤い鳥」運動
小学校教師同人として発足
県善三郎,松井多聞,関川美作雄,水谷正義,仲野静
30号まで
- 大正11年5月~大正13年11月
◇復刊第20号 通刊103号 昭和38年5月
□西浦田楽はね能の詞章について 鈴木進
□法多山思玄上人(下) 山口直蔵
□新居の民俗覚え書き 山口幸洋
大倉戸のこと
大倉戸
- 古代の屯倉に由来
「お倉が崎」
- 三宅性が多い
戸 = 河や海の入り口の意味
湊は水の戸 大和は山の戸
節分
- ヤイカガシとナタもち(炒り豆を臼でつぶし,つきたての餅)
五月一日
虫除け
= イチジクの葉を一枚敷いて線香
すわま
三月節句
→ 米の粉に黒砂糖と溜まりを加えて練って蒸す
はんぺんの形,波形
□持統天皇と引馬野 川見駒太郎
697年 8月1日
702年秋 参河御幸「続日本紀」
□嫁たたきの大の子について 渥美静一
◇復刊第21号 通刊104号 昭和38年9月
□浜松通信事業の90年 鈴木犀十郎
浜松宿
「遠州浜松広いようで狭い 横に車が二丁立たぬ」
□湖東地方の風俗と言語 鈴木敏
◇復刊第22号 通刊105号 昭和39年1月
□浜松・金原氏の起こり 小山正
蒲の庄
藤原静並が越後から国司役人として3番目
大像(だいしょう)開拓
→ 伊勢神宮をお祀り
→ 神宮領に捧げた
= 蒲の御厨(みくり)
24郷
→ 43か村(寛政期)
金原将監晴時 金原法橋(寺の住職)が領主に
鎌倉期
・ 朝廷からの役人(国司)の治めている国に守護
・ 私有地の庄園には地頭
↓
蒲庄に遠藤氏来る
遠(江)の藤(原) = 遠藤 1185~1300年頃
鎌倉武士 本拠屋敷は鎌倉
任地には第二の屋敷
遠藤氏の次に金原晴時 1300~1580年頃
金原法橋 「妙恩寺略縁起」
大野の政清の子供
下総国金原大宮の別当職
→ 鎌倉期に抜擢され遠州に
知行1万8千石
28か村領す 左近将監
家康入城の翌年
台場に新居
→ 帰農して庄屋や神官
□蜆塚発掘調査の総まとめ 鈴木謹一
□大手前から成子坂まで 須部弥一郎
大手前
- 元城小前 伊勢屋文具店,川瀬文明堂,松柏堂文具店
榎木町
- 大木屋,山本屋呉服店,木綿屋洋服店,道惣金物店
連尺
- 谷島屋書店,文泉堂,鴻池屋
大手前
- 山口屋菓子店,伝馬町巌邑堂
□子供の遊戯抄 小池誠二
「てんつば」「おたたき」「あなどち」「ギッコンバッタン」
今回は、4月13日に続いて、藤尾秀昭さんの
「小さな人生論 2」の紹介 3回目です。
出版社の案内には、
「『致知』創刊25周年の刊行以来、好評のうちに増刷を重ねて
いる『小さな人生論』。本書は川島廣守氏(日本プロ野球組織
コミッショナー)からヤンキースの松井秀喜選手に贈られた
書としても話題を呼んだ作品の続篇だ。
『自分を高める』『人生に残すもの』『何のために生きるのか』
『命を伝承する』『人生の法則』『先哲の英知をくむ』の各章
テーマのもと、著者の折々の思いが記している。
『人は皆、一個の天真を宿してこの世に生まれてくる、という。
その1個の天真を深く掘り下げ、高め、仕上げていくことこ
そ、各人が果たすべき人生のテーマといえる……』
人生と向き合うための座右の書として、活用いただきたい一冊。」
とあります。
もう一つ、再掲載になりますが、かつての郷土誌、
「土のいろ集成」第11巻を載せます。
☆「小さな人生論」藤尾秀昭 致知出版社 2005年 ③
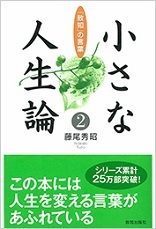
◇母の力
大正から昭和にかけ、熱烈な説教講演で多くの信奉者を集め
た真宗大谷派の憎・暁烏敏の短歌がある。
十億の人に十億の母あらむも
わが母にまさる母ありなむや
十億の人に十億の母がいる。
中には立派な母、優れた母もたくさんいるだろう。
だが、自分にとっては自分の母こそが最高の母だ、というの
である。
この素朴な母への讃美には、共感を覚える人が多いに違いな
い。
生後小児麻痺を患い、不自由な身体になった詩画家の はら
みちをさんは、母に背負われて小学校を卒業した。
そのはらさんの作品の一つに、「どしゃぶりの中を」と題す
る詩がある。
どしゃぶりの中を
母は僕を背負って走った
母の乳房がゆれ
僕は背中でバウンドした
どしゃぶりの中を
母は僕を背負って走った
母の白いうなじに雨と
僕の泪が流れた
どしゃぶりの中を
母は僕を背負って走った
いくら走っても遠いのに
僕はぬれたって平気なのに
どしゃぶりの中を
母は僕を背負って走った
火を吐く山の機関車のように
母の力がばくはつした
もう一つ、詩を掲げる。
サトウハチローの「母の日記をよみました」である。
母の日記をよみました
-悲しきことのみ多かりき
されど よろこびの日もありき-
そのよろこびの日もありきという文字が
太く強くしるされているのが
かえってボクには
かなしくて かなしくて……
多言は要すまい。
子を思う母の力強い愛。
その愛を感じ、母の喜怒衰楽に触れて人は人生を確立してい
く。
母に愛された記憶こそ、一人ひとりの生きる力の根源である。
その母の力こそ、ひいては日本という国を支えた根本である。
そう思わないわけにはいかない。
近年、母の力の衰えが感じられてならない。
虐待、養育放棄、果ては子殺し。
頻出する事件はその突出した表れのようである。
かつて児童福祉施設は親を失い、寄る辺ない子どものための
施設だった。
だがいまでは、虐待する親から子どもを引き離し、守るため
の施設と化しているという現実が、母の力の衰えを端的に示し
ている。
規範を失い、混乱する現代の世相の根本にあるものは、母の
力の衰弱と無関係ではない。
母の力の覚醒が求められてならない。
13歳の愛娘めぐみさんを北朝鮮に拉致されて28年、その奪
還に奔走する横田早紀江さんに、特集にご登場いただいた。
「めぐみは必ず取り戻します。そして、日本を凛とした国にし
ます。私はそれに命を懸けているのです」
毅然とした声が耳元に響いている。
母の力は死んではいない。
☆「土のいろ」集成 第十一巻 101~106号(前半)【再掲載 2017.1】
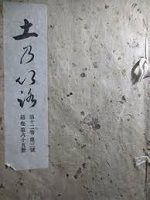
◇復刊第18号 通刊101号 昭和37年11月
□遠州大念仏後編
◇復刊第19号 通刊102号 昭和38年1月
□法多山思玄上人(上) 山口直蔵
□浜松特産「足袋のあれこれ」 須部弥一郎
徳川中期より
特産地 = 浜松と松本
足袋と旅
紺染めと厚地木綿
- 紺屋
□竜禅寺の不動堂 市川象三郎
□浜松の「リズム社」について 渥美 実
大正末
浜松の音楽結社「リズム社」
~ 「赤い鳥」運動
小学校教師同人として発足
県善三郎,松井多聞,関川美作雄,水谷正義,仲野静
30号まで
- 大正11年5月~大正13年11月
◇復刊第20号 通刊103号 昭和38年5月
□西浦田楽はね能の詞章について 鈴木進
□法多山思玄上人(下) 山口直蔵
□新居の民俗覚え書き 山口幸洋
大倉戸のこと
大倉戸
- 古代の屯倉に由来
「お倉が崎」
- 三宅性が多い
戸 = 河や海の入り口の意味
湊は水の戸 大和は山の戸
節分
- ヤイカガシとナタもち(炒り豆を臼でつぶし,つきたての餅)
五月一日
虫除け
= イチジクの葉を一枚敷いて線香
すわま
三月節句
→ 米の粉に黒砂糖と溜まりを加えて練って蒸す
はんぺんの形,波形
□持統天皇と引馬野 川見駒太郎
697年 8月1日
702年秋 参河御幸「続日本紀」
□嫁たたきの大の子について 渥美静一
◇復刊第21号 通刊104号 昭和38年9月
□浜松通信事業の90年 鈴木犀十郎
浜松宿
「遠州浜松広いようで狭い 横に車が二丁立たぬ」
□湖東地方の風俗と言語 鈴木敏
◇復刊第22号 通刊105号 昭和39年1月
□浜松・金原氏の起こり 小山正
蒲の庄
藤原静並が越後から国司役人として3番目
大像(だいしょう)開拓
→ 伊勢神宮をお祀り
→ 神宮領に捧げた
= 蒲の御厨(みくり)
24郷
→ 43か村(寛政期)
金原将監晴時 金原法橋(寺の住職)が領主に
鎌倉期
・ 朝廷からの役人(国司)の治めている国に守護
・ 私有地の庄園には地頭
↓
蒲庄に遠藤氏来る
遠(江)の藤(原) = 遠藤 1185~1300年頃
鎌倉武士 本拠屋敷は鎌倉
任地には第二の屋敷
遠藤氏の次に金原晴時 1300~1580年頃
金原法橋 「妙恩寺略縁起」
大野の政清の子供
下総国金原大宮の別当職
→ 鎌倉期に抜擢され遠州に
知行1万8千石
28か村領す 左近将監
家康入城の翌年
台場に新居
→ 帰農して庄屋や神官
□蜆塚発掘調査の総まとめ 鈴木謹一
□大手前から成子坂まで 須部弥一郎
大手前
- 元城小前 伊勢屋文具店,川瀬文明堂,松柏堂文具店
榎木町
- 大木屋,山本屋呉服店,木綿屋洋服店,道惣金物店
連尺
- 谷島屋書店,文泉堂,鴻池屋
大手前
- 山口屋菓子店,伝馬町巌邑堂
□子供の遊戯抄 小池誠二
「てんつば」「おたたき」「あなどち」「ギッコンバッタン」



