「教育改革のゆくえ」藤田英典 岩波ブックレット 2006年 ①(前) /「妖怪と怨霊の日本史」田中聡 集英社新書 2002年 ⑤【再掲載 2015.9】 [読書記録 教育]
今回は、藤田英典さんの、
「教育改革のゆくえ」の紹介 1回目です。
出版社の案内には、
「学校選択制の導入、就学援助家庭の増加、『特色ある学校づくり』の
名のもとに広がる地域格差、学力格差。近年、社会のライフラインで
ある公教育が危機にさらされている.海外の事例を参照しつつ,日本
の教育の特性と、それらに変化をもたらした1980年代以降のさまざ
まな改革の問題点を明るみに出し、異なる未来への転換を訴える。」
とあります。
免許更新制を続けたらどうなるかを想定もできないのに、
どうして「教育改革」「教育改革」と突き進むのでしょうか。
教育改革の成果を問うこともなく次々と…。
現場が混乱し、疲弊するだけなのに。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「格差教育・格差社会におけるラディカルな改革は危険」
・「『改革のための改革』は、日本の教育の優れた側面とその基盤を解体
し、日本の教育をますます歪め、ダメにしていく可能性が大きい」
・「日本の地域社会や学校にはコミュニティというものが担保されてい
る。その点が重要な背景・秘訣の一つであろう。それにより日本の
学校の『コミュニティ性』・ケア機能が働いてきた。しかし,コミュ
ニティ性・ケア機能の基盤を突き崩すような改革(改悪)が進められ
てきた」
・「東京都では26%の生徒が私立中学に通う一方、25%の生徒が就学援
助を必要としている」
もう一つ、再掲載になりますが、田中聡さんの
「妖怪と怨霊の日本史」⑤を載せます。
「光る君へ」の世界ですね。
☆「教育改革のゆくえ」藤田英典 岩波ブックレット 2006年 ①(前)
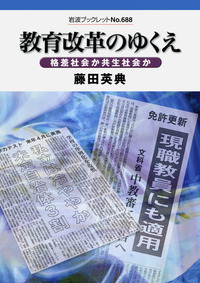
◇はじめに 危険な改革幻想 - 教育改革国民会議の経験
Ⅰ 危険な「改革のための改革」
□危険な改革幻想 - 教育改革国民会議の経験
格差教育・格差社会
~ ラディカルな改革は危険
□教育改革の時代 - 四半世紀に渡る改革
1980 学校指導要領 ゆとりと充実
1983~87 臨教審
「個性の重視」「教育の個性化」
= 多様化,弾力化
→ 中高一貫・学校選択制
→ 新自由主義・市場原理主義
1992 月一回の学校五日制
1995 月二回の学校五日制
2002 完全学校五日制
藤田
→ 教育改革国民会議で様々な提言
□「反対のための反対」より遙かに危険な「改革のための改革」
藤田の批判
① 五日制の安易な導入・拡大とセットになった「ゆとり教
育」改革、及びそれへの反動としての「テスト学力重視」
政策
② 義務教育段階からの教育機会の不当な差別化格差化をも
たらす「強者の論理」による教育の改変
③ 成果主義的・統制主義的・査察主義的な改革・政策:学
校と教師、とりわけ公立学校の教師を理不尽に非難し、そ
の自信と誇り、夢と情熱を低下させる可能性やその誠実な
実践と学校改善,自己研鑽の努力を妨げる可能性の大きい
改革
④ 義務教育費国庫負担金問題と教育基本法「改正」問題
→ ◎ 日本の教育の優れた側面とその基盤を解体し、日本の教育を
ますます歪め、ダメにしていく可能性が大きい
※ 反対のための反対は制度やシステムを変えないからまだマシ
Ⅱ 教育改革が招く<教育的危機>
□これまでの改革は成功したのか?
改革の理由・目的
①「教育原理」:校内暴力、いじめ、不登校、学級崩壊、少年犯
罪、高校中退、落ちこぼれ 等
②「変わる社会」への対応:IT化、グローバル化、知識社会、国
際間競争の激化
③「日本の教育は時代遅れになっている」: 知識詰め込み教育、
受験偏重教育、画一教育、行きすぎた平等主義、中央集権的体
制
□「教育病理」現象は解決・改善したか?
改善されていない
誤り
① 教育病理としてのとらえ方
→ 実際は社会病理
② 教育実践より教育の制度・システムを変えれば解決・改
善すると考えた
□世界が注目する「日本の少年犯罪水準の低さ」
「日本の地域社会や学校にはコミュニティというものが担保されて
いる。その点が重要な背景・秘訣の一つであろう」
= 日本の学校の「コミュニティ性」・ケア機能
生活指導・生徒指導・特別活動
↑↓
× しかし,コミュニティ性・ケア機能の基盤を突き崩すよう
な改革が進められてきた
= 改悪
□「グローバル化する知識社会」と「ゆとり教育」との矛盾
具体的には、エリート的な中高一貫校・教育特区校や学校選択制、
習熟度別学習や発展的学習の導入・拡大を進め、小・中の段階から、
できる子供や恵まれて、家庭の子供のための特別ルートを造るとい
う改革
□時間も掛けず,努力もせずに力がつくことはない
ゆとり教育
~ 「時間も掛けず努力もせず力がつく」考えの具体化
↑↓
◎ 問題解決能力も創造性も知識・能力を基盤にしてこそ,より
よく形式され発揮される
□就学援助率の急上昇と教育格差の拡大
「格差社会・格差教育」
先進諸国の中で日本は米国に次ぐ不平等社会
□学校選択制の拡大と「リッチ・フライト」
ホワイト・フライト
→ 白人 上中層が郊外へ
◎東京都 ~ 26%が私立中学,25%が就学援助
☆「妖怪と怨霊の日本史」田中聡 集英社新書 2002年 ⑤【再掲載 2015.9】
[出版社の案内]
元始、日本は妖怪の国であった。彼らはこの国のあらゆる場所に暮らし、
人間と共存してきた。しかし、時代とともに妖怪はその姿を歴史の表舞
台から消した。
本書は、その跡を膨大な資料でたどり、本来の歴史の中に位置づけた、
まったく新しい『日本史』への試みである。そこから浮かび上がるのは、
まさに『天皇家』を中心とした権力闘争の壮大なドラマであった。
怨みを飲んで抹殺されていった者どもの魂が、怨霊となって人間の歴史
に介入する。ここに、知られざる歴史の真髄が語られる。
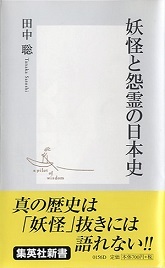
◇怨霊の心
愛欲の天狗
貞観5(863)年の怨霊会から3年後
藤原良房が初めて摂政に
北家栄華の礎
娘の明子を文徳天皇の女御
→ 9歳の孫を清和天皇
明子 = 染殿后
~ 狐憑き(祓おうとした聖人が后を好きに)
聖人は山へ帰され断食
→ 鬼になる
鬼と親しくなった后 ← しかし、良房も天皇も無力
天狗と鬼の違い
= 怨霊化する前に法術を学んでいたかどうか
情念の権化
- 僧侶を無用心に女に近づけることの警告
天狗の正体
染殿后 物の怪に悩まされた
憑いたのは 僧正真済
反骨の僧 相応和尚が加持
しかし、馬鹿にされ,以後,宮廷との関係を拒絶
天狐
アマギツネ = 天狗
紺青鬼と天狗
染殿后に憑いたのは
「紺青鬼?」
后に惚れたのは
「金峯山の沙門」
鬼
= 心に地獄を作り出した者たちの姿
真済
→ 狐独 「紺青鬼」
群衆は「太郎坊」
幽霊の誕生
『日本霊異記』
前世-現世-来世
~ 因果応報
平安の怨霊
- 生前の怨みをストレートに遺恨在る相手に
= 幽霊の誕生
紺青鬼は幽霊の先駆け
9世紀末 宇多天皇の下
上層貴族の宮都居住義務化
→ 怨霊も次々と生み出されていく
「もののけ」
当初「物の気」邪気 「物のさとし」
「教育改革のゆくえ」の紹介 1回目です。
出版社の案内には、
「学校選択制の導入、就学援助家庭の増加、『特色ある学校づくり』の
名のもとに広がる地域格差、学力格差。近年、社会のライフラインで
ある公教育が危機にさらされている.海外の事例を参照しつつ,日本
の教育の特性と、それらに変化をもたらした1980年代以降のさまざ
まな改革の問題点を明るみに出し、異なる未来への転換を訴える。」
とあります。
免許更新制を続けたらどうなるかを想定もできないのに、
どうして「教育改革」「教育改革」と突き進むのでしょうか。
教育改革の成果を問うこともなく次々と…。
現場が混乱し、疲弊するだけなのに。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「格差教育・格差社会におけるラディカルな改革は危険」
・「『改革のための改革』は、日本の教育の優れた側面とその基盤を解体
し、日本の教育をますます歪め、ダメにしていく可能性が大きい」
・「日本の地域社会や学校にはコミュニティというものが担保されてい
る。その点が重要な背景・秘訣の一つであろう。それにより日本の
学校の『コミュニティ性』・ケア機能が働いてきた。しかし,コミュ
ニティ性・ケア機能の基盤を突き崩すような改革(改悪)が進められ
てきた」
・「東京都では26%の生徒が私立中学に通う一方、25%の生徒が就学援
助を必要としている」
もう一つ、再掲載になりますが、田中聡さんの
「妖怪と怨霊の日本史」⑤を載せます。
「光る君へ」の世界ですね。
☆「教育改革のゆくえ」藤田英典 岩波ブックレット 2006年 ①(前)
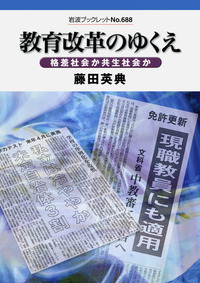
◇はじめに 危険な改革幻想 - 教育改革国民会議の経験
Ⅰ 危険な「改革のための改革」
□危険な改革幻想 - 教育改革国民会議の経験
格差教育・格差社会
~ ラディカルな改革は危険
□教育改革の時代 - 四半世紀に渡る改革
1980 学校指導要領 ゆとりと充実
1983~87 臨教審
「個性の重視」「教育の個性化」
= 多様化,弾力化
→ 中高一貫・学校選択制
→ 新自由主義・市場原理主義
1992 月一回の学校五日制
1995 月二回の学校五日制
2002 完全学校五日制
藤田
→ 教育改革国民会議で様々な提言
□「反対のための反対」より遙かに危険な「改革のための改革」
藤田の批判
① 五日制の安易な導入・拡大とセットになった「ゆとり教
育」改革、及びそれへの反動としての「テスト学力重視」
政策
② 義務教育段階からの教育機会の不当な差別化格差化をも
たらす「強者の論理」による教育の改変
③ 成果主義的・統制主義的・査察主義的な改革・政策:学
校と教師、とりわけ公立学校の教師を理不尽に非難し、そ
の自信と誇り、夢と情熱を低下させる可能性やその誠実な
実践と学校改善,自己研鑽の努力を妨げる可能性の大きい
改革
④ 義務教育費国庫負担金問題と教育基本法「改正」問題
→ ◎ 日本の教育の優れた側面とその基盤を解体し、日本の教育を
ますます歪め、ダメにしていく可能性が大きい
※ 反対のための反対は制度やシステムを変えないからまだマシ
Ⅱ 教育改革が招く<教育的危機>
□これまでの改革は成功したのか?
改革の理由・目的
①「教育原理」:校内暴力、いじめ、不登校、学級崩壊、少年犯
罪、高校中退、落ちこぼれ 等
②「変わる社会」への対応:IT化、グローバル化、知識社会、国
際間競争の激化
③「日本の教育は時代遅れになっている」: 知識詰め込み教育、
受験偏重教育、画一教育、行きすぎた平等主義、中央集権的体
制
□「教育病理」現象は解決・改善したか?
改善されていない
誤り
① 教育病理としてのとらえ方
→ 実際は社会病理
② 教育実践より教育の制度・システムを変えれば解決・改
善すると考えた
□世界が注目する「日本の少年犯罪水準の低さ」
「日本の地域社会や学校にはコミュニティというものが担保されて
いる。その点が重要な背景・秘訣の一つであろう」
= 日本の学校の「コミュニティ性」・ケア機能
生活指導・生徒指導・特別活動
↑↓
× しかし,コミュニティ性・ケア機能の基盤を突き崩すよう
な改革が進められてきた
= 改悪
□「グローバル化する知識社会」と「ゆとり教育」との矛盾
具体的には、エリート的な中高一貫校・教育特区校や学校選択制、
習熟度別学習や発展的学習の導入・拡大を進め、小・中の段階から、
できる子供や恵まれて、家庭の子供のための特別ルートを造るとい
う改革
□時間も掛けず,努力もせずに力がつくことはない
ゆとり教育
~ 「時間も掛けず努力もせず力がつく」考えの具体化
↑↓
◎ 問題解決能力も創造性も知識・能力を基盤にしてこそ,より
よく形式され発揮される
□就学援助率の急上昇と教育格差の拡大
「格差社会・格差教育」
先進諸国の中で日本は米国に次ぐ不平等社会
□学校選択制の拡大と「リッチ・フライト」
ホワイト・フライト
→ 白人 上中層が郊外へ
◎東京都 ~ 26%が私立中学,25%が就学援助
☆「妖怪と怨霊の日本史」田中聡 集英社新書 2002年 ⑤【再掲載 2015.9】
[出版社の案内]
元始、日本は妖怪の国であった。彼らはこの国のあらゆる場所に暮らし、
人間と共存してきた。しかし、時代とともに妖怪はその姿を歴史の表舞
台から消した。
本書は、その跡を膨大な資料でたどり、本来の歴史の中に位置づけた、
まったく新しい『日本史』への試みである。そこから浮かび上がるのは、
まさに『天皇家』を中心とした権力闘争の壮大なドラマであった。
怨みを飲んで抹殺されていった者どもの魂が、怨霊となって人間の歴史
に介入する。ここに、知られざる歴史の真髄が語られる。
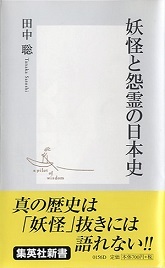
◇怨霊の心
愛欲の天狗
貞観5(863)年の怨霊会から3年後
藤原良房が初めて摂政に
北家栄華の礎
娘の明子を文徳天皇の女御
→ 9歳の孫を清和天皇
明子 = 染殿后
~ 狐憑き(祓おうとした聖人が后を好きに)
聖人は山へ帰され断食
→ 鬼になる
鬼と親しくなった后 ← しかし、良房も天皇も無力
天狗と鬼の違い
= 怨霊化する前に法術を学んでいたかどうか
情念の権化
- 僧侶を無用心に女に近づけることの警告
天狗の正体
染殿后 物の怪に悩まされた
憑いたのは 僧正真済
反骨の僧 相応和尚が加持
しかし、馬鹿にされ,以後,宮廷との関係を拒絶
天狐
アマギツネ = 天狗
紺青鬼と天狗
染殿后に憑いたのは
「紺青鬼?」
后に惚れたのは
「金峯山の沙門」
鬼
= 心に地獄を作り出した者たちの姿
真済
→ 狐独 「紺青鬼」
群衆は「太郎坊」
幽霊の誕生
『日本霊異記』
前世-現世-来世
~ 因果応報
平安の怨霊
- 生前の怨みをストレートに遺恨在る相手に
= 幽霊の誕生
紺青鬼は幽霊の先駆け
9世紀末 宇多天皇の下
上層貴族の宮都居住義務化
→ 怨霊も次々と生み出されていく
「もののけ」
当初「物の気」邪気 「物のさとし」
「村の若者たち」宮本常一 家の光協会 2004年 ①(前) / 「職員室の経営学」 飯田稔 ぎょうせい 1998年 ②【再掲載 2015.3】 [読書記録 民俗]
今回は宮本常一さんの、
「村の若者たち」の紹介 1回目です。
出版社の案内には、
「農村から都会へと、大量に人口が流出した昭和30年代の高度経済成
長期、村に残った若者たちの苦悩とその未来を描いた本書は、現在も
全く色褪せず、我々の人生に光を灯してくれる。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「村の宿命
田畑に限りがあることから誰かが富むと誰かが没落する
家の外で自分を戒め控えめにすることから鬱屈した気持ちが家の中
へ」
・「日本の村は小さい地域社会といえるが、不況の時は社会保障の役割を
果たしてもいた」
・「兵隊、最初は農家の次男三男だった」
・「能登の次男三男が都会に出て風呂屋の経営者となることが多かった」
もう一つ、再掲載になりますが、飯田稔さんの
「職員室の経営学」②を載せます。
☆「村の若者たち」宮本常一 家の光協会 2004年 ①(前)
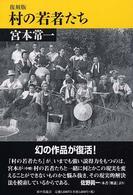
◇村に残る若者の苦悶
村に残る若者の悲しみ
働いても褒められぬ生活
孤独
村の宿命
限りがある田畑
~ 誰かが富むと誰かが没落する
家の外で自分を戒め控えめに
→ 鬱屈した気持ちが家の中へ
農に従う若者
くたびれる生活
支出に現金
伸びようと努力しても
勉学の機会が与えられない
さびれゆく村
青年団の指名が少なくなってきた
◇せまい世界の余り者
せまい世界
自給自足の村
= 他の村の世話にならない
山田野理夫『南部牛追唄』
義務と責任ばかり多い
- 堕胎間引き
「生きていくことの難しさ」
日本の村
= 小さい地域社会
~ 不況の時は社会保障の役割
妻子の意味
村内人口制限
大坂
「大和婿」
- 律儀でよく働く
次男三男は養子に行くより他にはけ場がなかった
余り者
オジ・オジボーズ 名子、被官
分家
次男三男の3割程度
- 後はオジロクで終わる
オバ暮らし
白川村(女の子 外に出さない)
→ 大家族 ~ 労働者
◎ 村の中で一番手を焼いたのが余った人間の処分
◇次男三男の新しい世界
富める者と貧しき者
次男三男を村の外で生活のたつようにすること
女子
- 東北 ~ 身売り 子どもを売る村
兵隊
最初は農家の次男三男
都会への道
愛知県佐久島
- 子どもをやる風習
ハシケ業
村に残る次男三男
能登
- 風呂屋
☆「職員室の経営学」 飯田稔 ぎょうせい 1998年 ②【再掲載 2015.3】
[出版社の案内]
今から10余年前、多くの人は“学校の活性化”を口にした。そして今、
大きな教育改革の時を迎えた。しかし、教育内容、方法などだけでな
く、最も変わらなければならないのは、教師その人ではないか。
学制130年、いつか強固にできてしまった教師の体質。職員室を中心に
つくられた、教師の人間関係や行動様式。これがまた、“学校の常識は
世間の非常識”と批判の対象になっている。本書は、教職の抱える問題
点、教師に気づいてほしいことなど、率直に書いた連載に、当面する教
育問題を書き加えるとともに、各章とも手直しして一冊にまとめたもの
である。

◇一言多い人足りない人
思いこみに思い上がりが重なると
二言三言気を付けて笑顔で諭す
やはり大事な表現力
言いたいことを一言多いと相手に感じさせずに巧みに言い切る
表現力
一言足りない人も
言いにくくても注意しなければならないことがある
→ ◎ 言う人の判断力と聞く人の素直さ
◇どうしてこんな事言うの
自ら解決しないで
~ 責任はだれがとる
「教頭が」「教頭が」と…
→ 大切なのは「わたしの不行き届き」
◇ちょっといい風景・ちょっといい話
いい風景
子どもが教師を取り囲む風景
~ 心理的支持基盤
学校の御都合主義ばかりが…
学校の自己責任・自助努力
ちょっといい話
学校の苦労などジャーナリズムは知らない
居丈高にならないで
教職の世界に被害者意識
どれほど努めようと叩かれるのは自分たち
→ 防衛本能が先に立つ
新しい教育実践を生み出す気持ちも鈍りがち
でも教育改革の今、教師の気勢があがらないでどうする
スクールリーダー
◎ 風に向かって毅然として立ち校内を励ます人でありたい
三つのいい話
◎「自信は謙虚さを生み,自信のなさは虚勢を張らせる」
「村の若者たち」の紹介 1回目です。
出版社の案内には、
「農村から都会へと、大量に人口が流出した昭和30年代の高度経済成
長期、村に残った若者たちの苦悩とその未来を描いた本書は、現在も
全く色褪せず、我々の人生に光を灯してくれる。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「村の宿命
田畑に限りがあることから誰かが富むと誰かが没落する
家の外で自分を戒め控えめにすることから鬱屈した気持ちが家の中
へ」
・「日本の村は小さい地域社会といえるが、不況の時は社会保障の役割を
果たしてもいた」
・「兵隊、最初は農家の次男三男だった」
・「能登の次男三男が都会に出て風呂屋の経営者となることが多かった」
もう一つ、再掲載になりますが、飯田稔さんの
「職員室の経営学」②を載せます。
☆「村の若者たち」宮本常一 家の光協会 2004年 ①(前)
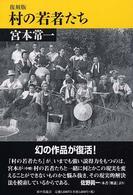
◇村に残る若者の苦悶
村に残る若者の悲しみ
働いても褒められぬ生活
孤独
村の宿命
限りがある田畑
~ 誰かが富むと誰かが没落する
家の外で自分を戒め控えめに
→ 鬱屈した気持ちが家の中へ
農に従う若者
くたびれる生活
支出に現金
伸びようと努力しても
勉学の機会が与えられない
さびれゆく村
青年団の指名が少なくなってきた
◇せまい世界の余り者
せまい世界
自給自足の村
= 他の村の世話にならない
山田野理夫『南部牛追唄』
義務と責任ばかり多い
- 堕胎間引き
「生きていくことの難しさ」
日本の村
= 小さい地域社会
~ 不況の時は社会保障の役割
妻子の意味
村内人口制限
大坂
「大和婿」
- 律儀でよく働く
次男三男は養子に行くより他にはけ場がなかった
余り者
オジ・オジボーズ 名子、被官
分家
次男三男の3割程度
- 後はオジロクで終わる
オバ暮らし
白川村(女の子 外に出さない)
→ 大家族 ~ 労働者
◎ 村の中で一番手を焼いたのが余った人間の処分
◇次男三男の新しい世界
富める者と貧しき者
次男三男を村の外で生活のたつようにすること
女子
- 東北 ~ 身売り 子どもを売る村
兵隊
最初は農家の次男三男
都会への道
愛知県佐久島
- 子どもをやる風習
ハシケ業
村に残る次男三男
能登
- 風呂屋
☆「職員室の経営学」 飯田稔 ぎょうせい 1998年 ②【再掲載 2015.3】
[出版社の案内]
今から10余年前、多くの人は“学校の活性化”を口にした。そして今、
大きな教育改革の時を迎えた。しかし、教育内容、方法などだけでな
く、最も変わらなければならないのは、教師その人ではないか。
学制130年、いつか強固にできてしまった教師の体質。職員室を中心に
つくられた、教師の人間関係や行動様式。これがまた、“学校の常識は
世間の非常識”と批判の対象になっている。本書は、教職の抱える問題
点、教師に気づいてほしいことなど、率直に書いた連載に、当面する教
育問題を書き加えるとともに、各章とも手直しして一冊にまとめたもの
である。

◇一言多い人足りない人
思いこみに思い上がりが重なると
二言三言気を付けて笑顔で諭す
やはり大事な表現力
言いたいことを一言多いと相手に感じさせずに巧みに言い切る
表現力
一言足りない人も
言いにくくても注意しなければならないことがある
→ ◎ 言う人の判断力と聞く人の素直さ
◇どうしてこんな事言うの
自ら解決しないで
~ 責任はだれがとる
「教頭が」「教頭が」と…
→ 大切なのは「わたしの不行き届き」
◇ちょっといい風景・ちょっといい話
いい風景
子どもが教師を取り囲む風景
~ 心理的支持基盤
学校の御都合主義ばかりが…
学校の自己責任・自助努力
ちょっといい話
学校の苦労などジャーナリズムは知らない
居丈高にならないで
教職の世界に被害者意識
どれほど努めようと叩かれるのは自分たち
→ 防衛本能が先に立つ
新しい教育実践を生み出す気持ちも鈍りがち
でも教育改革の今、教師の気勢があがらないでどうする
スクールリーダー
◎ 風に向かって毅然として立ち校内を励ます人でありたい
三つのいい話
◎「自信は謙虚さを生み,自信のなさは虚勢を張らせる」



