「この国の教育のあり方」山口隆博 アルク 2007年 /「国家を考えてみよう」橋本治 ちくまプリマー新書 2016年 ①【再掲載 2017.10】 [読書記録 教育]
今日は4月26日、金曜日です。
今回は、山口隆博さんの
「この国の教育のあり方」を紹介します。
出版社の案内には、
「月刊『子ども英語』誌上において、ぜひ会って話を聞いてみたいという
方々に会い、インタビュー記事を連載。そのなかから、とくに『教育』
というテーマにしぼり、読者からの反響が高かった15人に再登場いた
だき、出版。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「ナナメの関係」
・「光るものを見つけ出すのが教師の責任」
・「子どもの主体性を奪うことが悲劇を生む
周囲の元気が子どもを変えていく」
・「学力とは『自分の意見を言える力』」
・「ほんとうの学力は人間のポテンシャル」
もう一つ、再掲載になりますが、橋本治さんの
「国家を考えてみよう」①を載せます。
☆「この国の教育のあり方」山口隆博 アルク 2007年
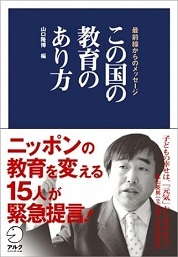
◇陰山英男
立命館小学校副校長
悪い事例に目くじら立てずよい事例に目を向けて挑戦を
改革を進める過程でトラブルはつきもの
大切なのは子どもが元気になること
◇藤原和博
かつての学校はまぶしい存在だった
ひとつの「正解」ではなく「納得解」をさがす力が必要
ナナメの関係
◇金森俊朗
子どもの学びたいものが無視されている
先生はキャッチャー
◇親野智可等
杉山桂一 1958年生
「親力」と「楽勉」
◇宮城まり子
「光るものを見つけ出したい」
- それが教師の責任
◇岡田尊司
1960年香川県生 精神科医 京都医療少年院
子どもの主体性を奪うことが悲劇を生む
周囲の元気が子どもを変えていく
◇魚住絹代
元女子少年院法務教官
親の無条件の愛
自分の「居場所」と「存在価値」を求め続けて
◇平井雷太
1949年生 すぺーすらくだ
一方的な押しつけでは子どもは決して育たない
なぜどの子どもにも同じ宿題が出されるのか
時間を計ることで子ども自身が自分の先生になれる
自分が学ばない人は教えない方がいい
◇有元秀文
国立教育政策研究所教育課程研究センター
「読解力」
学力とは「自分の意見を言える力」
◇鈴木敏志
未来教育デザイナー
競うのではなく「意志ある学び」で能力を高める
◇堀田力
1934年京都府生
逆戻りさせてはならない人を育てるゆとり教育
◇北城挌太郎
1944年生 日本IBM
イノベーションの担い手を育てる教育
◇寺脇研
1952年生
臨教審から国家の目標が変わった
◇村井実
慶応大学名誉教授
「個のための教育」を
ほんとうの学力は人間のポテンシャル
☆「国家を考えてみよう」橋本治 ちくまプリマー新書 2016年 ①【再掲載 2017.10】

◇国家を考えない
□2つの国家
① 国家=国民
nation 人 = 国民を中心にして考える
② 国家=領土
state 土地= 領土を前提にして考える
□昔の中国の「国」と「国民」の考え方
國 クニ 境界
邑 クニ 人のいる国
□国家は誰のもの?
「国家は支配者のもの」
→ 「国家は国民のもの」(近代国家)
□国はなかなか国民のものにならない
「国」と「国家」はどうちがう?
国家
- 家長のもの(天皇)
□長い間「国家」と無縁だった日本
明治時代から「国家」という言葉が定着
天下と国家
□日本で国家が始まる
□日本に「国家」がやってきた
□日本人である前に町人、百姓だった(階層)
□武士のみ「我々日本人」
明治維新は一部の限られた日本人(支配階級)のやったものであった
□王政復古と大政奉還
□明治の「国家」は天皇のものだった
明治の「国家」
= 天皇
「政府」
= 国家を支える組織
□天皇がなんでもできる憲法
帝国憲法
~ 日本は天皇のもので天皇は何でもできる
□天皇も国民のように騙せられる
しかし、天皇は何でもできるわけではない
= 「天皇は何でもできる建前になっている」
- 最終的に決定する権利を持っているだけ
とかく「国家」という言葉を使わなかった人
□福沢諭吉が語る政府
<元来人民と政府との間柄はもと同一対にてその職分を区別し、政府
は人民の名分となりなりて法を施し、人民は必ずこの法を守るべし
と、固く約束したるものなり>
- 社会契約説に基づいて
「政府と人民は約束してなんかいないんだから、政府の言うことにな
んて従う必要なんかないよ」
と暗に言っている
「政府に従わなくていい」という罠
= 政府への脅し
◎福澤は「学問のすすめ」の中で「国家」という言葉を使わなかった
「政府も天皇のもの」にしてしまった人たち
福澤
大日本帝国憲法が発布される前年『帝室論』
「天皇はいくら尊敬されてもいいが政治に関係すべきではない」
政府
~ 国家を運営する組織
◎ 後に「政府」を構成するような人たちが、まだ若い明治天皇を担
ぎ出して始まったのが明治維新
政治の中心は「政府」
文句の言いようのないシンボリックな人を担ぎ出したのはOK
◎「天皇は何でもできる」という前提を作っておけば「天皇がご了承
になった」のひとことで明治政府はなんでもすることが可能になっ
てしまう
「国家」や「天皇」から逃げる福沢諭吉
「国家」に逆らうと国家的な不良になる
昔のまともな人間は「親に背く不良」になることが怖くてで
きない
~ 国家を批判することは、家長である「お父さん=天皇」の
悪口を言うことになるのでできなかった
今回は、山口隆博さんの
「この国の教育のあり方」を紹介します。
出版社の案内には、
「月刊『子ども英語』誌上において、ぜひ会って話を聞いてみたいという
方々に会い、インタビュー記事を連載。そのなかから、とくに『教育』
というテーマにしぼり、読者からの反響が高かった15人に再登場いた
だき、出版。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「ナナメの関係」
・「光るものを見つけ出すのが教師の責任」
・「子どもの主体性を奪うことが悲劇を生む
周囲の元気が子どもを変えていく」
・「学力とは『自分の意見を言える力』」
・「ほんとうの学力は人間のポテンシャル」
もう一つ、再掲載になりますが、橋本治さんの
「国家を考えてみよう」①を載せます。
☆「この国の教育のあり方」山口隆博 アルク 2007年
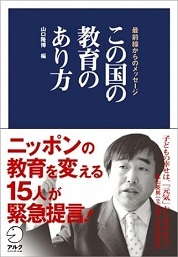
◇陰山英男
立命館小学校副校長
悪い事例に目くじら立てずよい事例に目を向けて挑戦を
改革を進める過程でトラブルはつきもの
大切なのは子どもが元気になること
◇藤原和博
かつての学校はまぶしい存在だった
ひとつの「正解」ではなく「納得解」をさがす力が必要
ナナメの関係
◇金森俊朗
子どもの学びたいものが無視されている
先生はキャッチャー
◇親野智可等
杉山桂一 1958年生
「親力」と「楽勉」
◇宮城まり子
「光るものを見つけ出したい」
- それが教師の責任
◇岡田尊司
1960年香川県生 精神科医 京都医療少年院
子どもの主体性を奪うことが悲劇を生む
周囲の元気が子どもを変えていく
◇魚住絹代
元女子少年院法務教官
親の無条件の愛
自分の「居場所」と「存在価値」を求め続けて
◇平井雷太
1949年生 すぺーすらくだ
一方的な押しつけでは子どもは決して育たない
なぜどの子どもにも同じ宿題が出されるのか
時間を計ることで子ども自身が自分の先生になれる
自分が学ばない人は教えない方がいい
◇有元秀文
国立教育政策研究所教育課程研究センター
「読解力」
学力とは「自分の意見を言える力」
◇鈴木敏志
未来教育デザイナー
競うのではなく「意志ある学び」で能力を高める
◇堀田力
1934年京都府生
逆戻りさせてはならない人を育てるゆとり教育
◇北城挌太郎
1944年生 日本IBM
イノベーションの担い手を育てる教育
◇寺脇研
1952年生
臨教審から国家の目標が変わった
◇村井実
慶応大学名誉教授
「個のための教育」を
ほんとうの学力は人間のポテンシャル
☆「国家を考えてみよう」橋本治 ちくまプリマー新書 2016年 ①【再掲載 2017.10】

◇国家を考えない
□2つの国家
① 国家=国民
nation 人 = 国民を中心にして考える
② 国家=領土
state 土地= 領土を前提にして考える
□昔の中国の「国」と「国民」の考え方
國 クニ 境界
邑 クニ 人のいる国
□国家は誰のもの?
「国家は支配者のもの」
→ 「国家は国民のもの」(近代国家)
□国はなかなか国民のものにならない
「国」と「国家」はどうちがう?
国家
- 家長のもの(天皇)
□長い間「国家」と無縁だった日本
明治時代から「国家」という言葉が定着
天下と国家
□日本で国家が始まる
□日本に「国家」がやってきた
□日本人である前に町人、百姓だった(階層)
□武士のみ「我々日本人」
明治維新は一部の限られた日本人(支配階級)のやったものであった
□王政復古と大政奉還
□明治の「国家」は天皇のものだった
明治の「国家」
= 天皇
「政府」
= 国家を支える組織
□天皇がなんでもできる憲法
帝国憲法
~ 日本は天皇のもので天皇は何でもできる
□天皇も国民のように騙せられる
しかし、天皇は何でもできるわけではない
= 「天皇は何でもできる建前になっている」
- 最終的に決定する権利を持っているだけ
とかく「国家」という言葉を使わなかった人
□福沢諭吉が語る政府
<元来人民と政府との間柄はもと同一対にてその職分を区別し、政府
は人民の名分となりなりて法を施し、人民は必ずこの法を守るべし
と、固く約束したるものなり>
- 社会契約説に基づいて
「政府と人民は約束してなんかいないんだから、政府の言うことにな
んて従う必要なんかないよ」
と暗に言っている
「政府に従わなくていい」という罠
= 政府への脅し
◎福澤は「学問のすすめ」の中で「国家」という言葉を使わなかった
「政府も天皇のもの」にしてしまった人たち
福澤
大日本帝国憲法が発布される前年『帝室論』
「天皇はいくら尊敬されてもいいが政治に関係すべきではない」
政府
~ 国家を運営する組織
◎ 後に「政府」を構成するような人たちが、まだ若い明治天皇を担
ぎ出して始まったのが明治維新
政治の中心は「政府」
文句の言いようのないシンボリックな人を担ぎ出したのはOK
◎「天皇は何でもできる」という前提を作っておけば「天皇がご了承
になった」のひとことで明治政府はなんでもすることが可能になっ
てしまう
「国家」や「天皇」から逃げる福沢諭吉
「国家」に逆らうと国家的な不良になる
昔のまともな人間は「親に背く不良」になることが怖くてで
きない
~ 国家を批判することは、家長である「お父さん=天皇」の
悪口を言うことになるのでできなかった
「わたしの校長奮闘記」山内宣治 一茎書房 2000年 ⑤ /「加藤秀俊著作集3」中央公論社 1981年 ④【再掲載 2017.3】 [読書記録 教育]
今日は4月25日、木曜日です。
今回は、4月22日に続いて、山内宣治さんの
「大わたしの校長奮闘記」の紹介 5回目です。
出版社の案内には、
「学校が学校となる。喜博を追い求めた著者が、涙あり笑いありのエピ
ソードを交えてかきつづった学校づくりの物語。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「どんな小さなものでも良い.自分の実践で自分の事実を創り出さない
限り、楽しい仕事ができないばかりか、人間としても枯渇してしまう」
・「教師の仕事は、授業や学校行事の中で、子どもを変え、子どもに力を
つけることである」
・「質の高い授業や学校行事でなければ、清潔で顔つきのはっきりとし
た、強靭な子どもは育たない」
・「『質』を問題にし、具体的に行うことを『事実に即して考える』『形式
を排除する』『はだかになって学ぶ』と3つにまとめて示した」
先年度、6年社会科を受け持ちました。12時までの勤務であり、3年、
4年、5年の授業も持っていたので、ノートを見る時間がありません。
6年社会科は、1時間でこれだけのことを身に付けなければならないの
かと思うほど内容が詰まっています。好きな児童はよいのですが、皆が内
容を理解するのは難しいと感じ、毎時間プリントを活用することにしまし
た(他学年も同様)。
教材研究に時間をかけ、プリントづくりに励みました。繰り返す内に、
まとめ方が上達し、内容が定着していくことを感じました。自分の知識も
深まりました。
子どもに力をつけるためにどのような取り組みをするかが大切だと感じ
ました。
もう一つ、再掲載になりますが、
「加藤秀俊著作集3」④を載せます。
- 明治新政府「閥の思想」は郷党閥により創られた閥である
派閥は内部利益の画策に努める
内部利益のみ…
☆「わたしの校長奮闘記」山内宣治 一茎書房 2000年 ⑤

<「学校経営について」山内宣治さんの本より>
◇津久志小学校経営方針①
校長になつたいきさつはどうであろうと、自分が校長なのだから校長と
しての仕事をしなければ、と腹をくくったのはこの時である。
そうして出したのが次の経営方針である。
6月29日のことであった。
津久志小学校に来て
1.私は教育という仕事は創造的なものだと考えてきた。だから、教育と
いう仕事は楽しいのだと思っている。どんな小さなものでも良い.自分
の実践で自分の事実を創り出さない限り、楽しい仕事ができないばかり
か、人間としても枯渇してしまうのだと思う。
2.教師の仕事は、授業や学校行事の中で、子どもを変え、子どもに力を
つけることである。
3.子どもを変え、子どもにカをつけるためには、あくまでも質の高い授
業や学校行事を追究し、創造しなければならない。質の高いものでなけ
れば、清潔で顔つきのはっきりとした、強靭な子どもは育たない。
4.それには、教師には子どもが見え、教材が見えなければならない。
① あくまでも事実に即して考えること。
目の前に子どもができないという事実があったら、それは教師
のやり方が悪いのだと考えなければならないのだと思う。どんな
にまずいと思えるやり方であっても、子どもが良くなれば、その
中には優れた原理原則が含まれていると思うので、自分の目で見
て、自分に取り入れることができるものをさがすように心がける。
② できるだけ形式を排除すること。
形が人間をつくるということもあるし、自分たちの創り出した
ことが形となることだってある。しかし、形式に寄りかかると、
形式ばかりが目について子どもが見えなくなる。そこで、今ある
形式が子どもにとって意味のないものであったり、子どもをだめ
にするものになっていないかどうか、今一度学校の中を見直して
みてほしい。
③ はだかになって学ぶこと。
教師の仕事は職人の世界と同じで頭では分かったつもりになっ
ていても、やってみるとできないことがたくさんある。また、人
のすばらしさというのは、苦労し努力したものでなければ、その
すばらしさは本当には分からないのだとも思う。生みの苦しみは
あるけれど、自分の身をもってやった分だけが本物で、自分を創
るためには大いに恥をかかなければならない。
5.教育というのは総合的な営みである。だから、たとえ技術はなくても、
教師の持つ人間性が子どもをつくることもある。したがって自分がより
人間的な人間になるために、良いものを見たり、良い体験をしたり、そ
してそれを職場に広げる関係をつくりたい。
要するに、自分の精神を肥やすことを大切にしたい。
6.具体的にやりたいこと。
① 雑談を充実させる。
② 子どもを鍛え、子どもをつくる仕事。
(書き込み、問題づくり、長距離走、柔軟運動、合唱、行進)
学校づくりの要素にはいろいろあると思うが、私は単純に「教師づ
くり」だと考えて、それに徹しようと思った。うちの学校はこんな研
究をしているのですよ、というようなアドバルーンを上げたり、珍し
いイベントを組んで学校の特徴を売り込むというようなことで「学校
づくり」をしたと考えることだけはしたくなかった。私は、津久志小
学校の先生方が、「教師」である前に、まず「人間」として生きても
らいたいと願った。教育という仕事を通じて生きる喜びを知り、教師
である自分に誇りを持ち、前向きに、しかも謙虚に生きてもらいたい
と願った。そして、「子どもを育てる」というところから目をそらしさ
えしなければ、技術や方法は必要があれば自然に身につき、おのずか
ら生まれるものだとも考えた。
私はここで「質」を問題にし、具体的に行うことを「事実に即して考え
る」「形式を排除する」「はだかになって学ぶ」と3つにまとめて示した
が、それは半月の間、私の目で学校を見て、井口さんと話し合った結論と
言ってもよかった。
だから、これは、今の先生方にはこれが欠けていますよ、というに等し
いものだけれど、しかし、欠点を欠点としてあげるのではなく、このよう
な形で津久志小でなくてもどこにでも通用する一般的なものとして方向を
示すにとどめておけば、先生方には、実践を積むにつれて自分に欠けてい
たものが見えてくるだろうと言う私の計算であった。
これを、まず井口さんに見てもらった。
黙って一字一句を確かめるように読んでいた井口さんは、
「私は、基本的にはこれで納得。この方針でやって下さい。」
とうなずいてくれた。
そして、自分自身に向けたように「山内さんは、大きいのう」と口の中
でつぶやくのを聞いて、尊敬に値する校長として認めてくれたかと思うと、
ほんとうに嬉しかった。
そんなわけで私は、翌日の職務会に、自信を持って、意気揚々とこれを
提示した。
ところが、先生方の表情はまったく動かず、私のことばがむなしく頭の
上を通り過ぎていくだけであった。
もちろん質問も出ない。
「こんな良いことが香いてあるのに、分からんのかなあ」と思いながら話
すのでよけいにくどくなり、かなり長い話だったらしい。
今でもその時の話になると田中悦子さんは、
「あの時校長先生は、何やら難しい話を、長々とようしゃべっちゃった。」
(以下略)
☆「加藤秀俊著作集3」中央公論社 1981年 ④【再掲載 2017.3】

(2)不幸の問題
□資本 = 税金
日本の工業化は,大衆のエネルギーを徹底的に絞り上げ,吸い上げ
ることによってのみ可能であった
= 不満
→ 西南戦争
□支配パターンが受け継がれる
① 政府権力の絶対化
② アウトサイダー,不遇な人々に対する冷淡さ
新政府
閥の思想 = 郷党閥により創られた閥
→ 派閥
閥 → 内部利益の画策
□急速な工業化 = 見事な成果
しかし大きな犠牲もあった
不幸な人々,閥の思想
救いは新聞
◇強国日本
(1)軍隊
□軍事力が強くなれば西洋との競争に勝つことができない
□封建時代
① 領主のためのサムライ集団だった
② 実戦経験がない 剣術→剣道に
□明治5年
徴兵令 国民皆兵
□日本の工業化は「軍事工業化」
長州の陸軍 VS 薩摩の海軍
ドイツ イギリス
閉鎖性
□統帥権問題
政治からの独立・世論からの独立
□軍は統帥権を掲げて自由な行動を取り得た
(日本の軍国主義を育てた協力発育剤=統帥権)
□担げたのは最高権力者として天皇をいだいていたから
統帥権の背景に天皇
(2)国家の成立
□絶対権力で強引に西洋とのスピード競争にかけた
= 明治政府はレーサー
□日本国憲法
伊藤博文
ハーバード・スペンサーと会った
スペンサー
「日本における天皇を西洋のキリスト教の神のかわりとして考え
たらどうか?」
= 一神教 信仰を統一原理に
→ 天皇制の確立
□教育勅語
→ 国家観念(国が大きな家=家長)
国が大きな家 = 家長にたとえられた
= 国も大きな家であり家族は家長に従うものだ
国民は天皇に従順
忠孝一致「お互い日本人ではないか」
□天皇の神格化
学校教育を通じて
ご真影・教育勅語
= 「聖物」
◎ 日本の議会はその国家の枠の中での相対的自由をしかもらえな
かった
今回は、4月22日に続いて、山内宣治さんの
「大わたしの校長奮闘記」の紹介 5回目です。
出版社の案内には、
「学校が学校となる。喜博を追い求めた著者が、涙あり笑いありのエピ
ソードを交えてかきつづった学校づくりの物語。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「どんな小さなものでも良い.自分の実践で自分の事実を創り出さない
限り、楽しい仕事ができないばかりか、人間としても枯渇してしまう」
・「教師の仕事は、授業や学校行事の中で、子どもを変え、子どもに力を
つけることである」
・「質の高い授業や学校行事でなければ、清潔で顔つきのはっきりとし
た、強靭な子どもは育たない」
・「『質』を問題にし、具体的に行うことを『事実に即して考える』『形式
を排除する』『はだかになって学ぶ』と3つにまとめて示した」
先年度、6年社会科を受け持ちました。12時までの勤務であり、3年、
4年、5年の授業も持っていたので、ノートを見る時間がありません。
6年社会科は、1時間でこれだけのことを身に付けなければならないの
かと思うほど内容が詰まっています。好きな児童はよいのですが、皆が内
容を理解するのは難しいと感じ、毎時間プリントを活用することにしまし
た(他学年も同様)。
教材研究に時間をかけ、プリントづくりに励みました。繰り返す内に、
まとめ方が上達し、内容が定着していくことを感じました。自分の知識も
深まりました。
子どもに力をつけるためにどのような取り組みをするかが大切だと感じ
ました。
もう一つ、再掲載になりますが、
「加藤秀俊著作集3」④を載せます。
- 明治新政府「閥の思想」は郷党閥により創られた閥である
派閥は内部利益の画策に努める
内部利益のみ…
☆「わたしの校長奮闘記」山内宣治 一茎書房 2000年 ⑤

<「学校経営について」山内宣治さんの本より>
◇津久志小学校経営方針①
校長になつたいきさつはどうであろうと、自分が校長なのだから校長と
しての仕事をしなければ、と腹をくくったのはこの時である。
そうして出したのが次の経営方針である。
6月29日のことであった。
津久志小学校に来て
1.私は教育という仕事は創造的なものだと考えてきた。だから、教育と
いう仕事は楽しいのだと思っている。どんな小さなものでも良い.自分
の実践で自分の事実を創り出さない限り、楽しい仕事ができないばかり
か、人間としても枯渇してしまうのだと思う。
2.教師の仕事は、授業や学校行事の中で、子どもを変え、子どもに力を
つけることである。
3.子どもを変え、子どもにカをつけるためには、あくまでも質の高い授
業や学校行事を追究し、創造しなければならない。質の高いものでなけ
れば、清潔で顔つきのはっきりとした、強靭な子どもは育たない。
4.それには、教師には子どもが見え、教材が見えなければならない。
① あくまでも事実に即して考えること。
目の前に子どもができないという事実があったら、それは教師
のやり方が悪いのだと考えなければならないのだと思う。どんな
にまずいと思えるやり方であっても、子どもが良くなれば、その
中には優れた原理原則が含まれていると思うので、自分の目で見
て、自分に取り入れることができるものをさがすように心がける。
② できるだけ形式を排除すること。
形が人間をつくるということもあるし、自分たちの創り出した
ことが形となることだってある。しかし、形式に寄りかかると、
形式ばかりが目について子どもが見えなくなる。そこで、今ある
形式が子どもにとって意味のないものであったり、子どもをだめ
にするものになっていないかどうか、今一度学校の中を見直して
みてほしい。
③ はだかになって学ぶこと。
教師の仕事は職人の世界と同じで頭では分かったつもりになっ
ていても、やってみるとできないことがたくさんある。また、人
のすばらしさというのは、苦労し努力したものでなければ、その
すばらしさは本当には分からないのだとも思う。生みの苦しみは
あるけれど、自分の身をもってやった分だけが本物で、自分を創
るためには大いに恥をかかなければならない。
5.教育というのは総合的な営みである。だから、たとえ技術はなくても、
教師の持つ人間性が子どもをつくることもある。したがって自分がより
人間的な人間になるために、良いものを見たり、良い体験をしたり、そ
してそれを職場に広げる関係をつくりたい。
要するに、自分の精神を肥やすことを大切にしたい。
6.具体的にやりたいこと。
① 雑談を充実させる。
② 子どもを鍛え、子どもをつくる仕事。
(書き込み、問題づくり、長距離走、柔軟運動、合唱、行進)
学校づくりの要素にはいろいろあると思うが、私は単純に「教師づ
くり」だと考えて、それに徹しようと思った。うちの学校はこんな研
究をしているのですよ、というようなアドバルーンを上げたり、珍し
いイベントを組んで学校の特徴を売り込むというようなことで「学校
づくり」をしたと考えることだけはしたくなかった。私は、津久志小
学校の先生方が、「教師」である前に、まず「人間」として生きても
らいたいと願った。教育という仕事を通じて生きる喜びを知り、教師
である自分に誇りを持ち、前向きに、しかも謙虚に生きてもらいたい
と願った。そして、「子どもを育てる」というところから目をそらしさ
えしなければ、技術や方法は必要があれば自然に身につき、おのずか
ら生まれるものだとも考えた。
私はここで「質」を問題にし、具体的に行うことを「事実に即して考え
る」「形式を排除する」「はだかになって学ぶ」と3つにまとめて示した
が、それは半月の間、私の目で学校を見て、井口さんと話し合った結論と
言ってもよかった。
だから、これは、今の先生方にはこれが欠けていますよ、というに等し
いものだけれど、しかし、欠点を欠点としてあげるのではなく、このよう
な形で津久志小でなくてもどこにでも通用する一般的なものとして方向を
示すにとどめておけば、先生方には、実践を積むにつれて自分に欠けてい
たものが見えてくるだろうと言う私の計算であった。
これを、まず井口さんに見てもらった。
黙って一字一句を確かめるように読んでいた井口さんは、
「私は、基本的にはこれで納得。この方針でやって下さい。」
とうなずいてくれた。
そして、自分自身に向けたように「山内さんは、大きいのう」と口の中
でつぶやくのを聞いて、尊敬に値する校長として認めてくれたかと思うと、
ほんとうに嬉しかった。
そんなわけで私は、翌日の職務会に、自信を持って、意気揚々とこれを
提示した。
ところが、先生方の表情はまったく動かず、私のことばがむなしく頭の
上を通り過ぎていくだけであった。
もちろん質問も出ない。
「こんな良いことが香いてあるのに、分からんのかなあ」と思いながら話
すのでよけいにくどくなり、かなり長い話だったらしい。
今でもその時の話になると田中悦子さんは、
「あの時校長先生は、何やら難しい話を、長々とようしゃべっちゃった。」
(以下略)
☆「加藤秀俊著作集3」中央公論社 1981年 ④【再掲載 2017.3】
(2)不幸の問題
□資本 = 税金
日本の工業化は,大衆のエネルギーを徹底的に絞り上げ,吸い上げ
ることによってのみ可能であった
= 不満
→ 西南戦争
□支配パターンが受け継がれる
① 政府権力の絶対化
② アウトサイダー,不遇な人々に対する冷淡さ
新政府
閥の思想 = 郷党閥により創られた閥
→ 派閥
閥 → 内部利益の画策
□急速な工業化 = 見事な成果
しかし大きな犠牲もあった
不幸な人々,閥の思想
救いは新聞
◇強国日本
(1)軍隊
□軍事力が強くなれば西洋との競争に勝つことができない
□封建時代
① 領主のためのサムライ集団だった
② 実戦経験がない 剣術→剣道に
□明治5年
徴兵令 国民皆兵
□日本の工業化は「軍事工業化」
長州の陸軍 VS 薩摩の海軍
ドイツ イギリス
閉鎖性
□統帥権問題
政治からの独立・世論からの独立
□軍は統帥権を掲げて自由な行動を取り得た
(日本の軍国主義を育てた協力発育剤=統帥権)
□担げたのは最高権力者として天皇をいだいていたから
統帥権の背景に天皇
(2)国家の成立
□絶対権力で強引に西洋とのスピード競争にかけた
= 明治政府はレーサー
□日本国憲法
伊藤博文
ハーバード・スペンサーと会った
スペンサー
「日本における天皇を西洋のキリスト教の神のかわりとして考え
たらどうか?」
= 一神教 信仰を統一原理に
→ 天皇制の確立
□教育勅語
→ 国家観念(国が大きな家=家長)
国が大きな家 = 家長にたとえられた
= 国も大きな家であり家族は家長に従うものだ
国民は天皇に従順
忠孝一致「お互い日本人ではないか」
□天皇の神格化
学校教育を通じて
ご真影・教育勅語
= 「聖物」
◎ 日本の議会はその国家の枠の中での相対的自由をしかもらえな
かった



