「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ⑭(最終) /「知っとくナットク社会科クイズ101」森茂岳雄 日本標準 2005年【再掲載 2014.3】 [読書記録 宗教]
今回は、10月25日に続いて山折哲雄さん、ひろさちやさんの
「死を見つめて生きる」の紹介14回目 最終です。
出版社の紹介には
「よりよい人生をおくるためにいま「生・老・病・死」を見直す。現代を生き
る人たちの死生観のあり方、残された時間を大切に過ごす生き方への提言。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「お釈迦様『死後の世界については考えるな』
死後の世界を考えるより今この人生をどう生きるかの方が大切」
・「氷が溶けて水になるように、生がとけて死になる。お浄土が少しずつつくら
れていく。脳死などという考え方はバカげている」
・「お経を読むだけで本物の弔いを教えない僧侶。葬式とは違う告別式も止めさ
せるべき。告別式は本来無宗教のはず。お別れ会だから宗教なんて必要な
い。お坊さんが葬儀屋の手先だと思われてしまっている」
・「もっと老病死と仲良くしましょう」
もう一つ、再掲載になりますが、森茂岳雄さんの
「知っとくナットク社会科クイズ101」を載せます。
☆「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ⑭(最終)
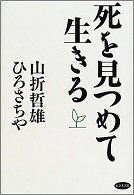
◇死への時間をいかに生きるか(2)
□死後の世界と日本人の死生観
死後の世界を宗教はどうとらえているのか - ひろさちや
□「毒矢の喩え」に見る仏教の死生観 - ひろさちや
お釈迦様「死後の世界については考えるな」
◎ 死後の世界を考えるより今この人生をどう生きるかの方が大切
□執着を断ち切れない人間にこそ浄土がある - ひろさちや
死者は生前の業によって全校をすれば天国に行くし、悪行をすれば地
獄に落ちると教えられたお釈迦様
|
◎執着を断ち切ることのできない人間にとってお浄土は存在している
□日一日お浄土が自分の中にできていく-ひろさちや
氷が溶けて水になるように、生がとけて死になる
「生100% + 死0%」
↓
「生 75% + 死25%」
↓
「生 0% + 死100%」
◎ お浄土が少しずつつくられていく
脳死などという考え方はバカげている
□「最期の美しさ」をどう求めるか-山折哲雄
良寛(1758-1831)辞世の句
「裏を見せ 表を見せて 散るもみじ」
人間の明暗、光と影、欲望と老熟、様々な人間の姿
良寛の芸術と仏教の二筋道
~ 背後に無常観
□葬式もお墓もやがて不要になるときが来る
戒名は今すぐ止めてしまいなさい - ひろさちや
俗人のまま死んで仏さまのところに行くから出家する必要はない
お経を読むだけで本物の弔いを教えない僧侶 - ひろさちや
告別式も止めさせるべき - 葬式とは違う
告別式は本来無宗教のはず
お別れ会だから宗教なんて必要ない
→ お坊さんが葬儀屋の手先だと思われてしまっている
|
お坊さんはお経を読むだけ
生前に仏教を教えてないので死んだ人に一生懸命教え
ているだけ
|
<死とはどういうものなのか遺族としんみり語り合うことがお坊さ
んの役目のはず>
|
◎ わたしたちは即得往生で、死んだその瞬間にお浄土に行く
仏さまが迎えてきてくださり、死んだ瞬間に仏さまの国
へ行く
「一握り散骨」で遺骨を地球全体に還元したい - 山折哲雄
妻との約束
= 葬式はしない、お墓はつくらない、遺骨は残さない
|
◎ 戒名は死後の勲章
死んでから自分の慕いに執着する愚かさ - ひろさちや
◇あとがき ひろさちや
カルカッタ
街頭に死体「老病死」
↑↓
現代日本
老も病も死も見えなくなっている
= 影の部分に覆いを掛けている
老 … 老人ホーム 病院
病 … 病院
死 … 病院
↓
◎ もっと老病死と仲良くしましょう
◇山折哲雄
1931.5.11 サンフランシスコ生
1959 東北大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学
東北大学インド哲学科でインド仏教と古代叙情詩を学ぶ
↓
東北大学助教授
国立歴史博物館教授
国際日本文化研究センター教授
現在(出版当時=ハマコウ註)国際日本文化センター所長
◇ひろさちや
1936.7.27 大阪生
宗教評論家
東京大学文学部印度哲学科卒
同大学院人文科学研究科印度哲学博士課程修了
大正大学客員教授
2002.12.30 読了
☆「知っとくナットク社会科クイズ101」森茂岳雄 日本標準 2005年【再掲載 2014.3】
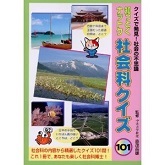
◇日本一低い山
天保山 4.5m 江戸の浮世絵にも
170年前天保年間
大阪湾や淀川整備の土砂を積み上げた山(人工)
当時は20m
→ 幕末
[砲台設置で削られた + 地盤沈下]
1995年国土地理院の地形図から消える
→ 復活
基準は東京湾の海面高
徳島県徳島市の弁天山 6.1m(天然)
◇最南端
東京の沖ノ鳥島(台湾より南-ハワイと同じくらい)
満潮時 二つの岩が数十㎝
→ 1987~89 囲い込み工事・補強
沖ノ鳥島
[周囲40万平方キロメートルの海底資源 + 漁業権]
◇島の大きさは
1番 択捉島 31831平方キロメートル
2番 国後島 1500平方キロメートル
◎ 周囲100m以上が島
◇急流
富山県の常願寺川
56㎞で3000mの高低
水田に巨石 6.5m 400t
氾濫
日本一の暴れ川
流域に四十数個の巨石
ヨハネス・デレーケ
◇海から一番遠い
長野県臼田町
1985年「星の町」宣言
国土測量は国土地理院
◇100年間で100㎞短くなった石狩川
曲がりくねっていた川
→ 改修
◇中国地方の名は
京都から
「近国 - 中国 - 遠国」
◇一番短い国道
神戸市の国道174号 187m
◇境界線が引かれていない県境
全国で20箇所
長野県境と新潟県境 長野県小谷村
富士山山頂付近
飛び地
- 和歌山県北山村は村全体が飛び地
◇降雨大
屋久島 月に35日といわれるくらい
尾鷲市
「死を見つめて生きる」の紹介14回目 最終です。
出版社の紹介には
「よりよい人生をおくるためにいま「生・老・病・死」を見直す。現代を生き
る人たちの死生観のあり方、残された時間を大切に過ごす生き方への提言。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「お釈迦様『死後の世界については考えるな』
死後の世界を考えるより今この人生をどう生きるかの方が大切」
・「氷が溶けて水になるように、生がとけて死になる。お浄土が少しずつつくら
れていく。脳死などという考え方はバカげている」
・「お経を読むだけで本物の弔いを教えない僧侶。葬式とは違う告別式も止めさ
せるべき。告別式は本来無宗教のはず。お別れ会だから宗教なんて必要な
い。お坊さんが葬儀屋の手先だと思われてしまっている」
・「もっと老病死と仲良くしましょう」
もう一つ、再掲載になりますが、森茂岳雄さんの
「知っとくナットク社会科クイズ101」を載せます。
☆「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ⑭(最終)
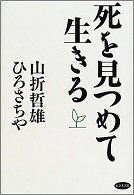
◇死への時間をいかに生きるか(2)
□死後の世界と日本人の死生観
死後の世界を宗教はどうとらえているのか - ひろさちや
□「毒矢の喩え」に見る仏教の死生観 - ひろさちや
お釈迦様「死後の世界については考えるな」
◎ 死後の世界を考えるより今この人生をどう生きるかの方が大切
□執着を断ち切れない人間にこそ浄土がある - ひろさちや
死者は生前の業によって全校をすれば天国に行くし、悪行をすれば地
獄に落ちると教えられたお釈迦様
|
◎執着を断ち切ることのできない人間にとってお浄土は存在している
□日一日お浄土が自分の中にできていく-ひろさちや
氷が溶けて水になるように、生がとけて死になる
「生100% + 死0%」
↓
「生 75% + 死25%」
↓
「生 0% + 死100%」
◎ お浄土が少しずつつくられていく
脳死などという考え方はバカげている
□「最期の美しさ」をどう求めるか-山折哲雄
良寛(1758-1831)辞世の句
「裏を見せ 表を見せて 散るもみじ」
人間の明暗、光と影、欲望と老熟、様々な人間の姿
良寛の芸術と仏教の二筋道
~ 背後に無常観
□葬式もお墓もやがて不要になるときが来る
戒名は今すぐ止めてしまいなさい - ひろさちや
俗人のまま死んで仏さまのところに行くから出家する必要はない
お経を読むだけで本物の弔いを教えない僧侶 - ひろさちや
告別式も止めさせるべき - 葬式とは違う
告別式は本来無宗教のはず
お別れ会だから宗教なんて必要ない
→ お坊さんが葬儀屋の手先だと思われてしまっている
|
お坊さんはお経を読むだけ
生前に仏教を教えてないので死んだ人に一生懸命教え
ているだけ
|
<死とはどういうものなのか遺族としんみり語り合うことがお坊さ
んの役目のはず>
|
◎ わたしたちは即得往生で、死んだその瞬間にお浄土に行く
仏さまが迎えてきてくださり、死んだ瞬間に仏さまの国
へ行く
「一握り散骨」で遺骨を地球全体に還元したい - 山折哲雄
妻との約束
= 葬式はしない、お墓はつくらない、遺骨は残さない
|
◎ 戒名は死後の勲章
死んでから自分の慕いに執着する愚かさ - ひろさちや
◇あとがき ひろさちや
カルカッタ
街頭に死体「老病死」
↑↓
現代日本
老も病も死も見えなくなっている
= 影の部分に覆いを掛けている
老 … 老人ホーム 病院
病 … 病院
死 … 病院
↓
◎ もっと老病死と仲良くしましょう
◇山折哲雄
1931.5.11 サンフランシスコ生
1959 東北大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学
東北大学インド哲学科でインド仏教と古代叙情詩を学ぶ
↓
東北大学助教授
国立歴史博物館教授
国際日本文化研究センター教授
現在(出版当時=ハマコウ註)国際日本文化センター所長
◇ひろさちや
1936.7.27 大阪生
宗教評論家
東京大学文学部印度哲学科卒
同大学院人文科学研究科印度哲学博士課程修了
大正大学客員教授
2002.12.30 読了
☆「知っとくナットク社会科クイズ101」森茂岳雄 日本標準 2005年【再掲載 2014.3】
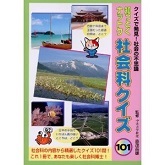
◇日本一低い山
天保山 4.5m 江戸の浮世絵にも
170年前天保年間
大阪湾や淀川整備の土砂を積み上げた山(人工)
当時は20m
→ 幕末
[砲台設置で削られた + 地盤沈下]
1995年国土地理院の地形図から消える
→ 復活
基準は東京湾の海面高
徳島県徳島市の弁天山 6.1m(天然)
◇最南端
東京の沖ノ鳥島(台湾より南-ハワイと同じくらい)
満潮時 二つの岩が数十㎝
→ 1987~89 囲い込み工事・補強
沖ノ鳥島
[周囲40万平方キロメートルの海底資源 + 漁業権]
◇島の大きさは
1番 択捉島 31831平方キロメートル
2番 国後島 1500平方キロメートル
◎ 周囲100m以上が島
◇急流
富山県の常願寺川
56㎞で3000mの高低
水田に巨石 6.5m 400t
氾濫
日本一の暴れ川
流域に四十数個の巨石
ヨハネス・デレーケ
◇海から一番遠い
長野県臼田町
1985年「星の町」宣言
国土測量は国土地理院
◇100年間で100㎞短くなった石狩川
曲がりくねっていた川
→ 改修
◇中国地方の名は
京都から
「近国 - 中国 - 遠国」
◇一番短い国道
神戸市の国道174号 187m
◇境界線が引かれていない県境
全国で20箇所
長野県境と新潟県境 長野県小谷村
富士山山頂付近
飛び地
- 和歌山県北山村は村全体が飛び地
◇降雨大
屋久島 月に35日といわれるくらい
尾鷲市
「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ⑫ /「心が壊れる子どもたち」 宮川俊彦 講談社 1987年 ③(最終)【再掲載 2014.5】 [読書記録 宗教]
今回は、10月5日に続いて山折哲雄さん、ひろさちやさんの
「死を見つめて生きる」の紹介 12回目です。
出版社の紹介には
「よりよい人生をおくるためにいま「生・老・病・死」を見直す。現代を生き
る人たちの死生観のあり方、残された時間を大切に過ごす生き方への提言。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「真実は辛く痛みを伴う。しかし真実の上に立たない限り本当の問題解決は
ない」
・「日本人は簡単に人を信じ、平気で嘘をつく」
・「組織を裏切ることが悪という独特の組織論は、日本人が千年以上かけて築
き上げてきた人間観といえる」
・「醜い姿を子どもに見せなければ本当の父親、母親とは言えない」
もう一つ、再掲載になりますが、宮川俊彦さんの
「心が壊れる子どもたち」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ⑫
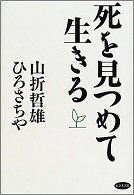
◇日本人の人間観を変えてしまったもの(1)
□どうしてこんなに嘘が多いのか
嘘の上に成り立っている日本の家庭 - ひろさちや
◎ 真実は辛く痛みを伴う。しかし真実の上に立たない限り本当の問
題解決はない
「不妄語戒」と「嘘も方便」が並立する矛盾 - 山折哲雄
仏教五戒
-「不妄五戒」
= 嘘をつくな
-「嘘も方便」
= 許容範囲
心とは本来ただならぬもの - 山折哲雄
最近の学生
~ 多元的な自己をもっている
一つのアイデンティティを主張できない時代
∥
◎ 若者たちを教育しにくい時代
「嘘も方便」は日本人にしか通用しない - ひろさちや
西洋人の感覚 - 相手に嘘をついたというのは敵宣言
|
◎ 日本人は簡単に人を信じ、平気で嘘をつく
疑うもの同士を結びつけているものは何か - 山折哲雄
近代ヨーロッパ
人間観の基礎 = 「他人とは疑うべき存在である」
トーマス・ホッブス(1588-1679)
「人間は人間にとって狼だ」
西欧社会
(1) ① 超越神信仰
近代は「神殺し」
② 第一原理
理性 愛 フェアプレイ精神 正義
(2) 契約という観念
疑うもの同士を契約で結びつける方法
□日本的価値観が浸食され始めた
日本人には理解できないイスラムの観念 - ひろさちや
日本人の考え方
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」
西洋的価値観に浸食される日本人の人間観 - 山折哲雄
西洋 普遍的原理・価値観が超越的に存在
↑↓
日本 神仏信仰と多元的な価値観
= 契約社会ではない
人間はお互いに信じ合わなければならない倫理
-モラル
組織を裏切ることが悪
- 独特の組織論
∥
◎ 日本人が千年以上かけて築き上げてきた人間観
↑↓
◎ 最近内部告発者増加
→ 日本の社会 自滅のおそれ
◎ 今の世の中
親は「他人を疑え」と教えている
→ 本当は「他人を信じなさい」と教えるべき
「滅私奉公」を自らの手で壊し始めた日本企業 - ひろさちや
万葉の情緒を育んだ「集団」と「独り」の関係 - 山折哲雄
日本社会は「集団主義」を媒介にして、様々なプラスの装置を作っ
てきた
|
◎ 集団から抜け出すこともできた(以下の方法で)
旅に出る 忍者になる 山で修行する
∥
独りになる
◎ 集団と独り
個は集団内部が前提
「独り」の伝統を風化させたことが混乱の要因 - 山折哲雄
尾崎放哉(1885-1926) 種田山頭火(1882-1940)
「独り」として独立
「独り」をたくさん抱えた集団は強くなる
|
集団としてつながった独り
□親がかっこよくある必要などない
理想の父親を求める母子家庭の子どもたち - 山折哲雄
母子家庭に育った子どもは他に父親を探そうとする
上司 先輩 友達(必ずしもすばらしい人とは限らない)
∥
◎ 慕われる人のほとんどは平均以下の人
人間は本来見苦しく醜いもの - ひろさちや
本来、人間の父親や母親は見苦しく醜いもの
親は子に醜い姿をさらせ - ひろさちや
日本の家庭にはもう本物の父親というものが存在していない
|
◎ 醜い姿を子どもに見せなければ本当の父親、母親とは言えない
☆「心が壊れる子どもたち」 宮川俊彦 講談社 1987年 ③(最終)【再掲載 2014.5】
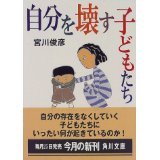
◇沈殿してゆく子どもたち
おとなしく静かに沈殿してゆく子どもたち
- 自己の風景化 意見の喪失から思考の喪失へ
無感覚・無思考の半人間
◇さらに過激になる子どもたち
極悪化した行為
善悪の基準すら自己の感情に委ねてゆく
行為の歯止めがなく感覚に振り回される
復讐・反乱
→ 犯罪的行為に 狭量さ 行動の純粋性と計画性
低年齢化 オカルトへ-宗教
麻薬や幻覚剤の広まり
= 自分の異化
◇危険信号にどう答えるか
・ 色や味を問う
・ 理由わけを尋ねる
・ 何でも言える場を作る
・ 創ることを習慣づける
・ 面と向かうこと(面と向かいすぎないこと)
・ 子どもをかわさない
・ 表面で見ない
・ 話を聞く姿勢を持ち続ける
・ 親の失敗や欠点を語る
・ 本音を語る
・ 生きてきた軌跡を語る
・ ホッとさせる
・ 出会いを求めさせる
・ 違っていることを良しとする
・ 自分の知り方を教える
・ 「なぜ」と考えさせる
・ 「もしも」と考えさせる
・ 「どうすれば」と考えさせる
・ 即断しない
・ 理想を語りすぎない
・ 目標を持たせる
・ 楽しさを見つけさせる
・ 体験させる
・ 人に興味を持たせる
・ 付き合いを教える
・ 人間関係の苦悩を示す
・ 生きる場を見せる
・ 現実を語る
・ 変わってゆくことを教える
・ したたかさを示す
・ 事件に目を向けさせる
・ 通学路を変えさせる
・ 学校だけに目を向けない
・ 抜ける目を持つ
・ 厳しくする
・ 良い悪いのけじめを付ける
・ 夫婦げんかをする
・ 共感する
「死を見つめて生きる」の紹介 12回目です。
出版社の紹介には
「よりよい人生をおくるためにいま「生・老・病・死」を見直す。現代を生き
る人たちの死生観のあり方、残された時間を大切に過ごす生き方への提言。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「真実は辛く痛みを伴う。しかし真実の上に立たない限り本当の問題解決は
ない」
・「日本人は簡単に人を信じ、平気で嘘をつく」
・「組織を裏切ることが悪という独特の組織論は、日本人が千年以上かけて築
き上げてきた人間観といえる」
・「醜い姿を子どもに見せなければ本当の父親、母親とは言えない」
もう一つ、再掲載になりますが、宮川俊彦さんの
「心が壊れる子どもたち」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ⑫
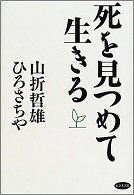
◇日本人の人間観を変えてしまったもの(1)
□どうしてこんなに嘘が多いのか
嘘の上に成り立っている日本の家庭 - ひろさちや
◎ 真実は辛く痛みを伴う。しかし真実の上に立たない限り本当の問
題解決はない
「不妄語戒」と「嘘も方便」が並立する矛盾 - 山折哲雄
仏教五戒
-「不妄五戒」
= 嘘をつくな
-「嘘も方便」
= 許容範囲
心とは本来ただならぬもの - 山折哲雄
最近の学生
~ 多元的な自己をもっている
一つのアイデンティティを主張できない時代
∥
◎ 若者たちを教育しにくい時代
「嘘も方便」は日本人にしか通用しない - ひろさちや
西洋人の感覚 - 相手に嘘をついたというのは敵宣言
|
◎ 日本人は簡単に人を信じ、平気で嘘をつく
疑うもの同士を結びつけているものは何か - 山折哲雄
近代ヨーロッパ
人間観の基礎 = 「他人とは疑うべき存在である」
トーマス・ホッブス(1588-1679)
「人間は人間にとって狼だ」
西欧社会
(1) ① 超越神信仰
近代は「神殺し」
② 第一原理
理性 愛 フェアプレイ精神 正義
(2) 契約という観念
疑うもの同士を契約で結びつける方法
□日本的価値観が浸食され始めた
日本人には理解できないイスラムの観念 - ひろさちや
日本人の考え方
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」
西洋的価値観に浸食される日本人の人間観 - 山折哲雄
西洋 普遍的原理・価値観が超越的に存在
↑↓
日本 神仏信仰と多元的な価値観
= 契約社会ではない
人間はお互いに信じ合わなければならない倫理
-モラル
組織を裏切ることが悪
- 独特の組織論
∥
◎ 日本人が千年以上かけて築き上げてきた人間観
↑↓
◎ 最近内部告発者増加
→ 日本の社会 自滅のおそれ
◎ 今の世の中
親は「他人を疑え」と教えている
→ 本当は「他人を信じなさい」と教えるべき
「滅私奉公」を自らの手で壊し始めた日本企業 - ひろさちや
万葉の情緒を育んだ「集団」と「独り」の関係 - 山折哲雄
日本社会は「集団主義」を媒介にして、様々なプラスの装置を作っ
てきた
|
◎ 集団から抜け出すこともできた(以下の方法で)
旅に出る 忍者になる 山で修行する
∥
独りになる
◎ 集団と独り
個は集団内部が前提
「独り」の伝統を風化させたことが混乱の要因 - 山折哲雄
尾崎放哉(1885-1926) 種田山頭火(1882-1940)
「独り」として独立
「独り」をたくさん抱えた集団は強くなる
|
集団としてつながった独り
□親がかっこよくある必要などない
理想の父親を求める母子家庭の子どもたち - 山折哲雄
母子家庭に育った子どもは他に父親を探そうとする
上司 先輩 友達(必ずしもすばらしい人とは限らない)
∥
◎ 慕われる人のほとんどは平均以下の人
人間は本来見苦しく醜いもの - ひろさちや
本来、人間の父親や母親は見苦しく醜いもの
親は子に醜い姿をさらせ - ひろさちや
日本の家庭にはもう本物の父親というものが存在していない
|
◎ 醜い姿を子どもに見せなければ本当の父親、母親とは言えない
☆「心が壊れる子どもたち」 宮川俊彦 講談社 1987年 ③(最終)【再掲載 2014.5】
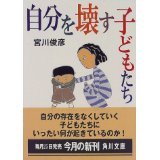
◇沈殿してゆく子どもたち
おとなしく静かに沈殿してゆく子どもたち
- 自己の風景化 意見の喪失から思考の喪失へ
無感覚・無思考の半人間
◇さらに過激になる子どもたち
極悪化した行為
善悪の基準すら自己の感情に委ねてゆく
行為の歯止めがなく感覚に振り回される
復讐・反乱
→ 犯罪的行為に 狭量さ 行動の純粋性と計画性
低年齢化 オカルトへ-宗教
麻薬や幻覚剤の広まり
= 自分の異化
◇危険信号にどう答えるか
・ 色や味を問う
・ 理由わけを尋ねる
・ 何でも言える場を作る
・ 創ることを習慣づける
・ 面と向かうこと(面と向かいすぎないこと)
・ 子どもをかわさない
・ 表面で見ない
・ 話を聞く姿勢を持ち続ける
・ 親の失敗や欠点を語る
・ 本音を語る
・ 生きてきた軌跡を語る
・ ホッとさせる
・ 出会いを求めさせる
・ 違っていることを良しとする
・ 自分の知り方を教える
・ 「なぜ」と考えさせる
・ 「もしも」と考えさせる
・ 「どうすれば」と考えさせる
・ 即断しない
・ 理想を語りすぎない
・ 目標を持たせる
・ 楽しさを見つけさせる
・ 体験させる
・ 人に興味を持たせる
・ 付き合いを教える
・ 人間関係の苦悩を示す
・ 生きる場を見せる
・ 現実を語る
・ 変わってゆくことを教える
・ したたかさを示す
・ 事件に目を向けさせる
・ 通学路を変えさせる
・ 学校だけに目を向けない
・ 抜ける目を持つ
・ 厳しくする
・ 良い悪いのけじめを付ける
・ 夫婦げんかをする
・ 共感する



