「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ④ /『あの人に会いたい』「NHKあの人に会いたい」刊行委員会 新潮文庫 2008年 ④【再掲載 2017.8】 [読書記録 一般]
今回は、7月22日に続いて山折哲雄さんの
「死を見つめて生きる」の紹介 4回目です。
出版社の紹介には
「よりよい人生をおくるためにいま「生・老・病・死」を見直す。現代を生き
る人たちの死生観のあり方、残された時間を大切に過ごす生き方への提言。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「『あなたは本来家庭に求めるべきものを他人に求めています。しかし、そ
れは家庭に寄ってしか与えられないものです。あなたが真に求められる
のは親子、夫婦、兄弟だけなのです。』とはっきり言うべき」
・「宗教の愛は世俗的な愛を超えたもの。それを与えられるのは家庭しかない」
・「あらゆる存在が皆最高の価値をもっている。誰もがそのままで百点満点」
・「人をあるがままに愛することができるのは家庭だけ」
もう一つ、再掲載になりますが、NHKあの人に会いたい刊行委員会の
「あの人に会いたい」④を載せます。
言葉が映像と一緒に語られるとより印象に強く残ることが分かります。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ④
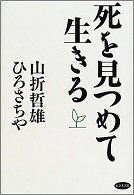
◇支えを失って漂流する日本人の魂(1)
□人間の幸せの本質は何なのか(1)
本当の幸せが分からなくなった日本人-ひろさちや
インドはこのままの方がいい
家族と一緒にいられない日本
家庭に求めるものを他人に求める人たち-ひろさちや
「あなたは本来家庭に求めるべきものを他人に求めています。しかし、
それは家庭に寄ってしか与えられないものです。あなたが真に求めら
れるのは親子、夫婦、兄弟だけなのです。」とはっきり言うべき
※◎日本の仏教は明治以降「小乗仏教」なるものに毒されました。特に戦
後、文献学者が小乗仏教こそ本物だと言ったことが仏教に悪影響
◎本来、在家仏教で家族皆で仏教の場をもち実践していくことが大切
◎日本人は宗教をもったときに家族を復活させることができる。
◎親と子が「わたしたちは阿弥陀仏を一緒に信じている人だよ」と言え
たときに本当の家族が生まれる
∥
同じ信仰を持ったとき初めて心の意味での家族になれる
↑↓
今の日本はまさに無宗教だから家庭をつくることができていない
宗教をもったとき、はじめて本当に癒やされる-ひろさちや
両足を失った青年米兵の自殺の話
~ 仏教の慈悲心
あるがままを愛することができるか-ひろさちや
青年米兵を救えたのは神さま仏さまの愛のみ
∥
宗教の愛は世俗的な愛を超えたもの
それを与えられるのは家庭しかない
法華経
「諸法実相」
あらゆる存在が皆最高の価値をもっている
= 誰もがそのままで百点満点
ところが世の中のものさしでは寿命は長い方がよく短い方が悪い
そのため、人の心臓を奪ってまで、わが子に長生きさせようとする。
それは間違った行為。
子どものあるがままを愛することができる、それが本当の愛情であ
り宗教の愛情 - 安部譲治の母親
↑↓
対極は学校
勉強のできる子、スポーツのできる子を愛する
1番から100番まで成績の順位をつけて全児童生徒との半数
しか存在価値を認めない
→ そんな教育に救いのあるはずがない
◎ 人をあるがままに愛することができるのは家庭だけ
☆『あの人に会いたい』「NHKあの人に会いたい」刊行委員会 新潮文庫 2008年 ④【再掲載 2017.8】
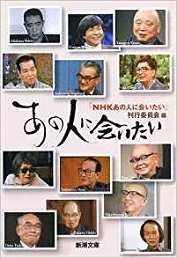
◇星野道夫 1952-1996
緊張感がなくなると考えることもなくなったしまう
アラスカに住みたくなって写真家になった
こんなところに人の生活があるのかな
住んでみればどこも同じ
生き物が生きていることの不思議さ
クマは人を襲いたいなんて思っていない
◎「アラスカの中でもしクマがいなかったらキャンプしていて安全だけれど
もえらくつまらないものになる」
◇淀川長治 1909-1998
サヨナラ サヨナラ サヨナラ
映画こそが国と国との垣を取る
人生の師匠チャップリン
1951(S26)「映画の友」編集長 チャップリン訪問
◎大切なのは はじめて出会うこと
見た 楽しんだ 泣いた やがてサヨナラ
◇高田好胤 1924-1998
かたよらないこだわらないとらわれない心
恐ろしいほどの厳しさが本当のやさしさ
1949~ 20年間修学旅行生相手に案内
厳しさのない優しさ
= 甘い
訓練によってのみ個性の輝きは磨かれる
悪い個性を選別剪定してやるのが親の先生の務め
◎訓練なき個性は野生
偏らないこだわらないとらわれない心
◇佐田稲子 1902-1998
ものも言えない
言わないでいる 働く人たちの言いたいことを言いたい
働いている人が自分のことを書く時代
「キャラメル工場から」
小林多喜二の死
慰問に行けば近所に対して言い訳が立つ
ものが言えなかった時代を知っている人間にはその貴重さが分かります
◇白洲正子 1910-1998
旅は道草が楽しい
いつでもが道中
◎「時代から取り残されたようなところに日本の美しさがある」
少しあばれたもののほうがいい
免許皆伝なのにできないことがある
自分を発見するために書く
旧白州邸 武相荘 町田市熊ケ谷町
「死を見つめて生きる」の紹介 4回目です。
出版社の紹介には
「よりよい人生をおくるためにいま「生・老・病・死」を見直す。現代を生き
る人たちの死生観のあり方、残された時間を大切に過ごす生き方への提言。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「『あなたは本来家庭に求めるべきものを他人に求めています。しかし、そ
れは家庭に寄ってしか与えられないものです。あなたが真に求められる
のは親子、夫婦、兄弟だけなのです。』とはっきり言うべき」
・「宗教の愛は世俗的な愛を超えたもの。それを与えられるのは家庭しかない」
・「あらゆる存在が皆最高の価値をもっている。誰もがそのままで百点満点」
・「人をあるがままに愛することができるのは家庭だけ」
もう一つ、再掲載になりますが、NHKあの人に会いたい刊行委員会の
「あの人に会いたい」④を載せます。
言葉が映像と一緒に語られるとより印象に強く残ることが分かります。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「死を見つめて生きる」山折哲雄・ひろさちや ビジネス社 2002年 ④
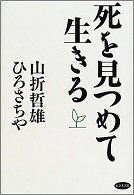
◇支えを失って漂流する日本人の魂(1)
□人間の幸せの本質は何なのか(1)
本当の幸せが分からなくなった日本人-ひろさちや
インドはこのままの方がいい
家族と一緒にいられない日本
家庭に求めるものを他人に求める人たち-ひろさちや
「あなたは本来家庭に求めるべきものを他人に求めています。しかし、
それは家庭に寄ってしか与えられないものです。あなたが真に求めら
れるのは親子、夫婦、兄弟だけなのです。」とはっきり言うべき
※◎日本の仏教は明治以降「小乗仏教」なるものに毒されました。特に戦
後、文献学者が小乗仏教こそ本物だと言ったことが仏教に悪影響
◎本来、在家仏教で家族皆で仏教の場をもち実践していくことが大切
◎日本人は宗教をもったときに家族を復活させることができる。
◎親と子が「わたしたちは阿弥陀仏を一緒に信じている人だよ」と言え
たときに本当の家族が生まれる
∥
同じ信仰を持ったとき初めて心の意味での家族になれる
↑↓
今の日本はまさに無宗教だから家庭をつくることができていない
宗教をもったとき、はじめて本当に癒やされる-ひろさちや
両足を失った青年米兵の自殺の話
~ 仏教の慈悲心
あるがままを愛することができるか-ひろさちや
青年米兵を救えたのは神さま仏さまの愛のみ
∥
宗教の愛は世俗的な愛を超えたもの
それを与えられるのは家庭しかない
法華経
「諸法実相」
あらゆる存在が皆最高の価値をもっている
= 誰もがそのままで百点満点
ところが世の中のものさしでは寿命は長い方がよく短い方が悪い
そのため、人の心臓を奪ってまで、わが子に長生きさせようとする。
それは間違った行為。
子どものあるがままを愛することができる、それが本当の愛情であ
り宗教の愛情 - 安部譲治の母親
↑↓
対極は学校
勉強のできる子、スポーツのできる子を愛する
1番から100番まで成績の順位をつけて全児童生徒との半数
しか存在価値を認めない
→ そんな教育に救いのあるはずがない
◎ 人をあるがままに愛することができるのは家庭だけ
☆『あの人に会いたい』「NHKあの人に会いたい」刊行委員会 新潮文庫 2008年 ④【再掲載 2017.8】
◇星野道夫 1952-1996
緊張感がなくなると考えることもなくなったしまう
アラスカに住みたくなって写真家になった
こんなところに人の生活があるのかな
住んでみればどこも同じ
生き物が生きていることの不思議さ
クマは人を襲いたいなんて思っていない
◎「アラスカの中でもしクマがいなかったらキャンプしていて安全だけれど
もえらくつまらないものになる」
◇淀川長治 1909-1998
サヨナラ サヨナラ サヨナラ
映画こそが国と国との垣を取る
人生の師匠チャップリン
1951(S26)「映画の友」編集長 チャップリン訪問
◎大切なのは はじめて出会うこと
見た 楽しんだ 泣いた やがてサヨナラ
◇高田好胤 1924-1998
かたよらないこだわらないとらわれない心
恐ろしいほどの厳しさが本当のやさしさ
1949~ 20年間修学旅行生相手に案内
厳しさのない優しさ
= 甘い
訓練によってのみ個性の輝きは磨かれる
悪い個性を選別剪定してやるのが親の先生の務め
◎訓練なき個性は野生
偏らないこだわらないとらわれない心
◇佐田稲子 1902-1998
ものも言えない
言わないでいる 働く人たちの言いたいことを言いたい
働いている人が自分のことを書く時代
「キャラメル工場から」
小林多喜二の死
慰問に行けば近所に対して言い訳が立つ
ものが言えなかった時代を知っている人間にはその貴重さが分かります
◇白洲正子 1910-1998
旅は道草が楽しい
いつでもが道中
◎「時代から取り残されたようなところに日本の美しさがある」
少しあばれたもののほうがいい
免許皆伝なのにできないことがある
自分を発見するために書く
旧白州邸 武相荘 町田市熊ケ谷町
「就活のやり方 いつ・何を・どう?ぜんぶ!」実務教育出版 2013年 /「学力低下の実態」苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦美・諸田裕子 岩波ブックレット№578 2002年 ②【再掲載 2014.2】 [読書記録 一般]
今回は、実務教育出版の
「終活のやり方 いつ・何を・どう?ぜんぶ!」を紹介します。
出版社の案内には、
「どの時期に何をすべきか…? 就活に必要なすべてがわかる、就活総合本
の『新定番』書!先輩には聞きづらい就活の常識が満載!」
「どの時期に何をすべきか教えます。先輩には聞きづらいシューカツのキホ
ンがわかる。」
とあります。
もう一つ、再掲載になりますが、岩波ブックレットの
「学力低下の実態」②を載せます。
経済的格差、家庭格差の影響の大きさを感じます。
それではどうすればよいのか、話し合われる必要も感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「就活のやり方 いつ・何を・どう?ぜんぶ!」実務教育出版 2013年
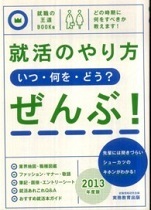
◇情報
サイト
リクナビ、マイナビ、キャリタス就活
キャリアセンター
会社四季報
中小企業
・グッドカンパニー大賞 ・ソーシャルビジネス55選
・おもてなし経営企業選 ・元気なモノ作り中小企業330社
・中小企業IT経営力大賞 ・ものづくり日本大賞
会社説明会
WEBサイト
・ハローワークインターネットサービス
・大卒等就職情報WEB提供サービス
・ジョブウェイ(中小企業)
◇業界
銀行 証券 生保・損保 建設・不動産 鉄鋼 製菓
食品・飲料 運輸・交通 自動車 電機 マスコミ
流通・小売 ゲーム・映画 通信 アパレル コンサルティング
公務員 お客様は?
BtoB(企業間取引)
BtoC(企業と一般消費者)
◇職種
企業 営業・ジム・総務・人事・経理・広報宣伝・企画・店舗管理・
バイヤー(調達・購買)・販売・セールスエンジニア
情報システム・生産管理・MR(医薬情報担当)・研究開発
専門的 編集者・WEBデザイナー・映像製作・ツアーコンダクター・
フライドアテンダント・ホテルスタッフ
インテリアコーディネーター・コンサルタント
ファンドマネージャー・プログラマー・システムエンジニア
ゲームクリエーター
◇筆記試験
適性検査
一般常識試験
WEBテスト
SPI(リクルートキャリア)
SPI3
テストセンター
CAB・GAB(コンピュータ職・総合適性検査)
◇面接、自己分析
参考
◎おすすめ本
「面接の達人」中谷彰宏
「面接の10分前、1日前、10日前にやるべきこと」
☆「学力低下の実態」苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦美・諸田裕子 岩波ブックレット№578 2002年 ②【再掲載 2014.2】
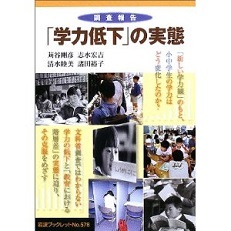
◇第一部 小学生の基礎学力はどう変わったか(2)
2.今回の調査について
□2001.11 関西都市圏での調査
1989年の大阪大学グループ実施「学力生活総合調査」をもとにして
① 学力テスト
② 生活と学習についてのアンケート
小5 2100名 中2 3700名
↓
これを元に調査 小16校 中11校(前回の7割)
小5 921名 中2 1281名
1989年 → 2001年
国私立進学率は 3%から7%へ
(東京は25%)
前回70~80%正答という基本的な内容
3.基礎学力は下がっているのか
(1) 正答率の変化
平均点 小国 小算 中国 中算
1989 78.9 80.6 71.4 69.6
↓
2001 70.9 68.3 67.0 63.9
-8.0 -12.3 -4.4 -5.7
(2) 学力差は拡大したか
算数の点数の下方シフト
中学算数のフタコブラクダ
80点代 17.9% 30点代 7.9%
「フタコブ化」
=できる子とできない子の格差が拡大して,フタコブ化が進む
(3) 通塾状況と学力の関係~塾の影響から見た公立学校の教育力
通塾率 1989年 2001年
小 29.2% 29.4%
中 54.4% 50.7%
通塾者と被通塾者の差
1989年 2001年 1989と2001の差
通 非通 差 通 非通 差 通塾 非通塾
小国 80.9 78.0 -2.9 75.9 69.6 -4.5 -5.0 -8.4
小算 84.6 78.9 -5.7 73.0 67.5 -5.5 -11.6 -11.4
中国 74.5 68.3 -6.2 71.9 63.2 -8.7 -2.6 -5.1
中算 75.8 62.5 -13.3 74.5 54.5 -20.0 -1.3 -8.0
∥
中算 公立学校の教科面での学習指導力の低下
∥
◎ 塾に行く者と行かない者,行けない者との格差の拡大
小算 通塾グループ
◎かつての塾に通わなかった子より平均点で6点低い
◎◎<分析>◎◎
① 塾に行けば万全とは言えない
② 学校の授業を工夫改善すれば塾に頼らなくても子供の基礎学力がアッ
プする可能性はある
③ 学校に於ける教科の指導力がさらに低下すれば塾に行ったとしても学
力の保障が難しくなる
「終活のやり方 いつ・何を・どう?ぜんぶ!」を紹介します。
出版社の案内には、
「どの時期に何をすべきか…? 就活に必要なすべてがわかる、就活総合本
の『新定番』書!先輩には聞きづらい就活の常識が満載!」
「どの時期に何をすべきか教えます。先輩には聞きづらいシューカツのキホ
ンがわかる。」
とあります。
もう一つ、再掲載になりますが、岩波ブックレットの
「学力低下の実態」②を載せます。
経済的格差、家庭格差の影響の大きさを感じます。
それではどうすればよいのか、話し合われる必要も感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「就活のやり方 いつ・何を・どう?ぜんぶ!」実務教育出版 2013年
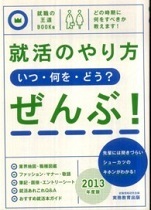
◇情報
サイト
リクナビ、マイナビ、キャリタス就活
キャリアセンター
会社四季報
中小企業
・グッドカンパニー大賞 ・ソーシャルビジネス55選
・おもてなし経営企業選 ・元気なモノ作り中小企業330社
・中小企業IT経営力大賞 ・ものづくり日本大賞
会社説明会
WEBサイト
・ハローワークインターネットサービス
・大卒等就職情報WEB提供サービス
・ジョブウェイ(中小企業)
◇業界
銀行 証券 生保・損保 建設・不動産 鉄鋼 製菓
食品・飲料 運輸・交通 自動車 電機 マスコミ
流通・小売 ゲーム・映画 通信 アパレル コンサルティング
公務員 お客様は?
BtoB(企業間取引)
BtoC(企業と一般消費者)
◇職種
企業 営業・ジム・総務・人事・経理・広報宣伝・企画・店舗管理・
バイヤー(調達・購買)・販売・セールスエンジニア
情報システム・生産管理・MR(医薬情報担当)・研究開発
専門的 編集者・WEBデザイナー・映像製作・ツアーコンダクター・
フライドアテンダント・ホテルスタッフ
インテリアコーディネーター・コンサルタント
ファンドマネージャー・プログラマー・システムエンジニア
ゲームクリエーター
◇筆記試験
適性検査
一般常識試験
WEBテスト
SPI(リクルートキャリア)
SPI3
テストセンター
CAB・GAB(コンピュータ職・総合適性検査)
◇面接、自己分析
参考
◎おすすめ本
「面接の達人」中谷彰宏
「面接の10分前、1日前、10日前にやるべきこと」
☆「学力低下の実態」苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦美・諸田裕子 岩波ブックレット№578 2002年 ②【再掲載 2014.2】
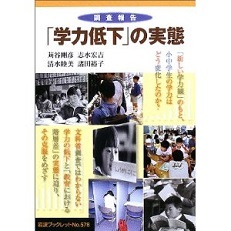
◇第一部 小学生の基礎学力はどう変わったか(2)
2.今回の調査について
□2001.11 関西都市圏での調査
1989年の大阪大学グループ実施「学力生活総合調査」をもとにして
① 学力テスト
② 生活と学習についてのアンケート
小5 2100名 中2 3700名
↓
これを元に調査 小16校 中11校(前回の7割)
小5 921名 中2 1281名
1989年 → 2001年
国私立進学率は 3%から7%へ
(東京は25%)
前回70~80%正答という基本的な内容
3.基礎学力は下がっているのか
(1) 正答率の変化
平均点 小国 小算 中国 中算
1989 78.9 80.6 71.4 69.6
↓
2001 70.9 68.3 67.0 63.9
-8.0 -12.3 -4.4 -5.7
(2) 学力差は拡大したか
算数の点数の下方シフト
中学算数のフタコブラクダ
80点代 17.9% 30点代 7.9%
「フタコブ化」
=できる子とできない子の格差が拡大して,フタコブ化が進む
(3) 通塾状況と学力の関係~塾の影響から見た公立学校の教育力
通塾率 1989年 2001年
小 29.2% 29.4%
中 54.4% 50.7%
通塾者と被通塾者の差
1989年 2001年 1989と2001の差
通 非通 差 通 非通 差 通塾 非通塾
小国 80.9 78.0 -2.9 75.9 69.6 -4.5 -5.0 -8.4
小算 84.6 78.9 -5.7 73.0 67.5 -5.5 -11.6 -11.4
中国 74.5 68.3 -6.2 71.9 63.2 -8.7 -2.6 -5.1
中算 75.8 62.5 -13.3 74.5 54.5 -20.0 -1.3 -8.0
∥
中算 公立学校の教科面での学習指導力の低下
∥
◎ 塾に行く者と行かない者,行けない者との格差の拡大
小算 通塾グループ
◎かつての塾に通わなかった子より平均点で6点低い
◎◎<分析>◎◎
① 塾に行けば万全とは言えない
② 学校の授業を工夫改善すれば塾に頼らなくても子供の基礎学力がアッ
プする可能性はある
③ 学校に於ける教科の指導力がさらに低下すれば塾に行ったとしても学
力の保障が難しくなる



