五木寛之「第28話 コロナ禍に思うこと~その4」(連載『五木寛之のラジオ千夜一夜』-月刊「ラジオ深夜便」誌より)① /「なぜ学校に行かせるの」寺脇研 日本経済新聞社 1997年 ①【再掲載 2014.4】 [読書記録 一般]
今回は、月刊『ラジオ深夜便』誌より、五木寛之さんの
「第28話 コロナ禍に思うこと~その4」の紹介1回目です。
月刊「ラジオ深夜便」誌を購読しています。
放送のエッセンスが載せられていて、わたしは広い知恵を学んでいます。
もう一つ、再掲載になりますが、寺脇研さんの
「なぜ学校に行かせるの」①を載せます。
「ミスターゆとり教育」、ゆとり教育の旗振り役を務めていた寺脇さんの本。
読み直してこの25年間の学校教育振り返りました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆五木寛之「第28話 コロナ禍に思うこと~その4」(連載『五木寛之のラジオ千夜一夜』-月刊「ラジオ深夜便」誌より))①
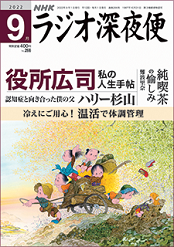
□五木寛之
1932(昭和7)年、福岡県生まれ。作家。2005(平成17)年スタートの「わが人生の
歌語り」以来、<ラジオ深夜便>にレギュラ-出演する。『親鸞』『回想のすすめ』
等、著書多数。88歳になった今も、小説やエッセーをはじめ幅広い活躍を続ける
五木宽之さんが、自らの来し方を振り返りながら、毎回さまざまなテーマで語りま
す。
前回は、新型コロナウイルスの流行という困難な状況を念頭に、800年以上前
の日本で生まれた「他力」という思想について、私なりの解釈をお話ししました。
「他力」とは、本来、宗教用語ですが、人生で起こるありとあらゆることが自分
一人の力によるものではないといぅ考え方だと私は考えています。
私たちは皆、この世の森羅万象、地球上のすべての人々によって生かされている
存在なのではないでしょぅか。
◇「他力」の考え方で絶望に苦しむこともなく、自分らしく生きられるのではない だろうか
人生には、どんなに頑張ってもやることなすことうまくいかないことがあるもの
です。
そんなとき、「あんなに頑張ったのに、なぜ」と悲憤慷慨してしまうと、よけい
につらい思いをするだけかもしれません。
私は物事がうまく運ばないとき、「たまたま他力の風が吹かなかっただけだ」と考
えてみるようにしています。
すると、気持ちがす-っと楽になるのです。逆に、物事が想像以上にうまく運ん
だときは、「自分の力ではない。他力のおかげだ」と考えることで、天狗にならず
に済んでいるように思います。
自分の力ですべてをコントロールしていると考えてしまうと、挫折したときは絶
望しやすく、うまくいったらいったで有頂天になり自分を見失いやすいのではない
か。
「他力」という考え方に思いをはせると、立ち直れないほどの絶 望に苦しむこと
もなく、自分らしく生きられるような気がするのです。
☆「なぜ学校に行かせるの」寺脇研 日本経済新聞社 1997年 ①【再掲載 2014.4】
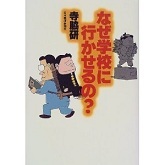
◇何でもあり
前提
- 情報伝達手段の発展・国の豊かさ
「何でもあり」 ←→ 「こうでなければいけない」
学習 教育
◇熱血先生
熱血先生は押しつけ先生
- 先生の独りよがり = 押しつけ
これからの先生
「本当にやるべき責任だけを果たしてもらって,それ以上のことは押し
つけがましくやらない」
∥
◎ 本当にやるべく事を厚く
◇権利と責任
家庭教育
「していいことといけないことのけじめを教える」
権利と義務は表裏一体
= 家庭教育の役割
先生の守備範囲
本分 = 指導要領の中味をきちんと身に付けさせること
家庭・地域・自主性に任せる部分を
|
◎ 一生懸命にやってもだめだったら,それを自分の責任で引き受け
ていくことも大切
◇骨は強いが関節が弱い
小中のつなぎ 中高のつなぎ
小中一貫 中高一貫
◇寺脇研
1952(昭和27)年 福岡生まれ
1975(昭和50)年 東京大学法学部卒業 ミスター偏差値
以後 広島県教育長 文部省医学教育課長
現在 文部省生涯学習局生涯学習振興課長(当時=ハマコウ註)
◇勉強
理由目的
「夢を実現したいから」 → 苦しいことには耐えられる
|
◎ 自発的に勉強する子を育てる
進路指導
= 子供が夢を見つけていく時間 生活科・社会科
◇生きる力
人生80年
生きる力 = 百年を生き抜いていく力
◇小中学校教育
市町村の裁量で
- 負担も市町村民が
30人学級も可能
~ 予算上積・自己負担
先生は親や子供によく説明すべき = 説明責任
官僚制
~ 人への責任転嫁・自分のみ大過なく
日教組 対 文部省
◇学校が変われば生徒も変わる
悪いと思われている学校ほど中を見せるべき
∥
今以上に評判が悪くなることはない
= 積極的に学んでいる姿を外に
◇公立と私立
私立 … 特定の目的
公立 … 特定の意識を持たない ~ いろいろな人間
◇校区の弾力化
留意 … 学校を選ぶのはあくまでも子供 - 定数制が問題
◇就職協定廃止
企業
「学歴・卒業歴ではなく,学校で何を学んできたか,どんな人間かを
じっくり見て採用する」事が大切
↓
◎ 良い学校に入ったらいい企業に入る世の中の崩壊
∥
◎ 企業が変わっている(終身雇用制の崩壊)
「第28話 コロナ禍に思うこと~その4」の紹介1回目です。
月刊「ラジオ深夜便」誌を購読しています。
放送のエッセンスが載せられていて、わたしは広い知恵を学んでいます。
もう一つ、再掲載になりますが、寺脇研さんの
「なぜ学校に行かせるの」①を載せます。
「ミスターゆとり教育」、ゆとり教育の旗振り役を務めていた寺脇さんの本。
読み直してこの25年間の学校教育振り返りました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆五木寛之「第28話 コロナ禍に思うこと~その4」(連載『五木寛之のラジオ千夜一夜』-月刊「ラジオ深夜便」誌より))①
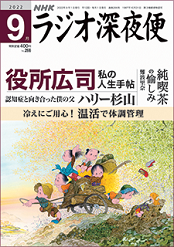
□五木寛之
1932(昭和7)年、福岡県生まれ。作家。2005(平成17)年スタートの「わが人生の
歌語り」以来、<ラジオ深夜便>にレギュラ-出演する。『親鸞』『回想のすすめ』
等、著書多数。88歳になった今も、小説やエッセーをはじめ幅広い活躍を続ける
五木宽之さんが、自らの来し方を振り返りながら、毎回さまざまなテーマで語りま
す。
前回は、新型コロナウイルスの流行という困難な状況を念頭に、800年以上前
の日本で生まれた「他力」という思想について、私なりの解釈をお話ししました。
「他力」とは、本来、宗教用語ですが、人生で起こるありとあらゆることが自分
一人の力によるものではないといぅ考え方だと私は考えています。
私たちは皆、この世の森羅万象、地球上のすべての人々によって生かされている
存在なのではないでしょぅか。
◇「他力」の考え方で絶望に苦しむこともなく、自分らしく生きられるのではない だろうか
人生には、どんなに頑張ってもやることなすことうまくいかないことがあるもの
です。
そんなとき、「あんなに頑張ったのに、なぜ」と悲憤慷慨してしまうと、よけい
につらい思いをするだけかもしれません。
私は物事がうまく運ばないとき、「たまたま他力の風が吹かなかっただけだ」と考
えてみるようにしています。
すると、気持ちがす-っと楽になるのです。逆に、物事が想像以上にうまく運ん
だときは、「自分の力ではない。他力のおかげだ」と考えることで、天狗にならず
に済んでいるように思います。
自分の力ですべてをコントロールしていると考えてしまうと、挫折したときは絶
望しやすく、うまくいったらいったで有頂天になり自分を見失いやすいのではない
か。
「他力」という考え方に思いをはせると、立ち直れないほどの絶 望に苦しむこと
もなく、自分らしく生きられるような気がするのです。
☆「なぜ学校に行かせるの」寺脇研 日本経済新聞社 1997年 ①【再掲載 2014.4】
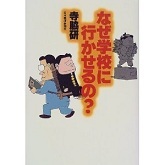
◇何でもあり
前提
- 情報伝達手段の発展・国の豊かさ
「何でもあり」 ←→ 「こうでなければいけない」
学習 教育
◇熱血先生
熱血先生は押しつけ先生
- 先生の独りよがり = 押しつけ
これからの先生
「本当にやるべき責任だけを果たしてもらって,それ以上のことは押し
つけがましくやらない」
∥
◎ 本当にやるべく事を厚く
◇権利と責任
家庭教育
「していいことといけないことのけじめを教える」
権利と義務は表裏一体
= 家庭教育の役割
先生の守備範囲
本分 = 指導要領の中味をきちんと身に付けさせること
家庭・地域・自主性に任せる部分を
|
◎ 一生懸命にやってもだめだったら,それを自分の責任で引き受け
ていくことも大切
◇骨は強いが関節が弱い
小中のつなぎ 中高のつなぎ
小中一貫 中高一貫
◇寺脇研
1952(昭和27)年 福岡生まれ
1975(昭和50)年 東京大学法学部卒業 ミスター偏差値
以後 広島県教育長 文部省医学教育課長
現在 文部省生涯学習局生涯学習振興課長(当時=ハマコウ註)
◇勉強
理由目的
「夢を実現したいから」 → 苦しいことには耐えられる
|
◎ 自発的に勉強する子を育てる
進路指導
= 子供が夢を見つけていく時間 生活科・社会科
◇生きる力
人生80年
生きる力 = 百年を生き抜いていく力
◇小中学校教育
市町村の裁量で
- 負担も市町村民が
30人学級も可能
~ 予算上積・自己負担
先生は親や子供によく説明すべき = 説明責任
官僚制
~ 人への責任転嫁・自分のみ大過なく
日教組 対 文部省
◇学校が変われば生徒も変わる
悪いと思われている学校ほど中を見せるべき
∥
今以上に評判が悪くなることはない
= 積極的に学んでいる姿を外に
◇公立と私立
私立 … 特定の目的
公立 … 特定の意識を持たない ~ いろいろな人間
◇校区の弾力化
留意 … 学校を選ぶのはあくまでも子供 - 定数制が問題
◇就職協定廃止
企業
「学歴・卒業歴ではなく,学校で何を学んできたか,どんな人間かを
じっくり見て採用する」事が大切
↓
◎ 良い学校に入ったらいい企業に入る世の中の崩壊
∥
◎ 企業が変わっている(終身雇用制の崩壊)
「教え方ガイドブック」志水廣 明治図書 2006年 ⑤ /「日本の名句名言」増原良彦 講談社現代新書 1988年 ③【再掲載 2014.4】 [読書記録 教育]
今回は、9月26日に続いて、志水廣さんの
「算数力がつく教え方ガイドブック」5回目の紹介です。
出版社の案内には、
「子どもの内なる知を引き出す算数授業ガイドブック決定版。
志水流算数・数学の授業論はつとに知れ渡っているが、この指導法の柱、
○つけ法も、復唱法も、自ら学ぶ問題解決型授業に迫るためのもの。こ
れら、子どもの内なる知を引き出し構成する授業のノウハウを、基礎基
本から高度なテクまで、実例をいれていただきながら示す。」
とあります。
今回紹介分で強く印象に残った言葉は…
・「教えるべきことは簡潔に手際よく教えていく」
・「広げていくためには適用問題をやること。でも,その前に一斉学習でやる
べきこと」
・「教科書通りの授業ができたらかなりの腕前」
・「算数教科書は幕の内弁当的な構成
問題文 情景図 式 考え方 まとめ 練習」
もう一つ、再掲載になりますが、増原良彦(ひろさちやさんの本名)さんの
「日本の名句名言」③を載せます。
次の文を見るたびに、なるほどなあと思います。
「日本の考え方
会社役員 会社員より派閥の利害
政治家 国民に対する政治責任よりも党利党略
大学教授 学生教育より自分の後輩」
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「教え方ガイドブック」志水廣 明治図書 2006年 ⑤
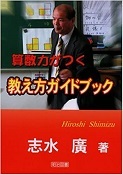
11 問題解決型授業のモデル
1 問題解決型授業の流れ
広島県竹原市立忠海西小学校
2 具体的取り組み P34~37
12 教えることと考えさせること
1 教えることと考えさせることの区別
「教えるべきこと」 数学での定義に当たること
「考えさせるべきこと」 数学での性質(定理)に当たること
また,定義の適用も
◎ 定義と性質の区別
「定義」の教科書での表現
○「~といいます」「~は~です」「~と書き,~と読みます」
教えるべきことは簡潔に手際よく教えていく
13 1を聞いて10を生み出す力
1 算数の授業はピンポイント学習だ
概念理解のために
① 定義を言葉で言える
② 具体例を挙げることができる
③ 方法を言える
④ 図や絵に表すことができる
⑤ 理由を言える
⑥ 適用問題を解くことができる
具体例 1~2が多いが広げて類推できるようにする
2 広げていく指導のあり方
広げていくためには適用問題をやること
∥
でも,その前に一斉学習でやるべきこと
Ⅱ 教科書の扱い方
14 算数の教科書の特質
1 教科書通りに教えることができたら一人前
教科書通りの授業ができたらかなりの腕前
2 安心感の根拠
支持される理由
① 算数の基礎基本の内容が載っている
② 指導要領により作られ検定を受けている
③ 時間とエネルギーが掛けられている
④ 親切で丁寧である
3 親切で丁寧であること
算数教科書
問題文 情景図 式 考え方 まとめ 練習 = (幕の内弁当)
4 実際の教科書で
書き込みのスペース
15 教科書の役割は
1 子どもと教師にとっての役割 P44
2 教科書に書き込む
事前
・学習問題,学習課題を明確にする … マーカー
・ヒントはどこか? 教師が工夫したヒントを書き込む
・ねらいは何か? 知識・技能と考え方
・子どもが使用する空きスペースは式,答えなどを書く
・定義と性質を区別する
・必要な準備物を書き込む
本番
・子どもが難しかった問題があれば,その場でメモする 10秒で
事後の反省
・授業後5分間で処理する
・子どもの反応(よい考え,つまずき)で気が付いたことをメモする
・問題に対する正答率もメモするとよい
・今終わったところを線で区切る
16 教科書の使い方のパターン
1 教科書の使い方はほぼ5つである
① 実際→教科書→実際型
② 教科書→実際型
③ 実際→教科書型
④ 教科書型 教科書のみ
⑤ 実際→型 教科書を離れて
☆「日本の名句名言」増原良彦 講談社現代新書 1988年 ③【再掲載 2014.4】
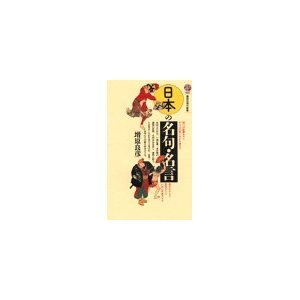
◇「御神酒あがらぬ神はない」
吉田兼好
「下戸ならぬこそ、をのこはよけれ」
井原西鶴
「世の中に下戸の建てたる蔵もなし」
若山牧水
「白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒は静かに飲むべかりけり」
井伏鱒二
「コノサカヅキヲ受ケテクレ ドウゾナミナミツイデオクレ
ハナニアラシノタトヘモアルゾ 『サヨナラ』ダケガ人生ダ」
|
◎日本人はヨーロッパ人の半分しかアルデヒド脱水素酵素を持っていない
◇「人間五十年。化天の内をくらぶれば夢幻のごとくなり」幸若
幸若舞曲『敦盛』
「人間五十年。下天の内をくらぶれば夢幻のごとくなり」
◎ 我々の一生は短い、かりに一生が50年だとすればそれは下天の一昼
夜でしかない
◇「花は桜木人は武士」『仮名手本忠臣蔵』
花
「花」といえば平安後期までは「梅」
平安後期からは 桜
江戸時代の武士の美意識
独善的な支配者
◇「武士道と云は、死ぬ事と見つけたり」 山本常朝『葉隠』
□ノブレス・オブリージュ(仏語)
高貴なる者にはそれだけの大きな義務がある
= 高貴なる者の責任は大
◎戦争になるとイギリスではまず王家の者が銃を持って戦場に出掛ける。
◎戦場での死亡率もエリート層の方が高い。
フォークランド戦争ではアンドリュー王子が率先して戦場に!
|
法の下での平等はそのままにエリート層の道義的義務を高くしよ
うという考え方
イスラム
鞭打ちの刑 - 自由人は奴隷の二倍
↑↓
日本のエリート層
被害者意識ばかりが強くて「高貴なる者の義務」無自覚
「武士は食わねど高楊枝」 = 外面だけ取り繕う
∥
武士に支配者としての自覚がなかった
関心は「主君に気に入られること」
∥
◎ 主君の飼い犬であって被支配者階級における支配者としての責任は
これっぽっちも持っていなかった
□日本の考え方
会社役員
会社員より派閥の利害
政治家
国民に対する政治責任よりも党利党略
大学教授
学生教育より自分の後輩
「算数力がつく教え方ガイドブック」5回目の紹介です。
出版社の案内には、
「子どもの内なる知を引き出す算数授業ガイドブック決定版。
志水流算数・数学の授業論はつとに知れ渡っているが、この指導法の柱、
○つけ法も、復唱法も、自ら学ぶ問題解決型授業に迫るためのもの。こ
れら、子どもの内なる知を引き出し構成する授業のノウハウを、基礎基
本から高度なテクまで、実例をいれていただきながら示す。」
とあります。
今回紹介分で強く印象に残った言葉は…
・「教えるべきことは簡潔に手際よく教えていく」
・「広げていくためには適用問題をやること。でも,その前に一斉学習でやる
べきこと」
・「教科書通りの授業ができたらかなりの腕前」
・「算数教科書は幕の内弁当的な構成
問題文 情景図 式 考え方 まとめ 練習」
もう一つ、再掲載になりますが、増原良彦(ひろさちやさんの本名)さんの
「日本の名句名言」③を載せます。
次の文を見るたびに、なるほどなあと思います。
「日本の考え方
会社役員 会社員より派閥の利害
政治家 国民に対する政治責任よりも党利党略
大学教授 学生教育より自分の後輩」
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「教え方ガイドブック」志水廣 明治図書 2006年 ⑤
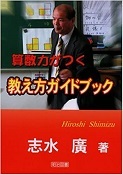
11 問題解決型授業のモデル
1 問題解決型授業の流れ
広島県竹原市立忠海西小学校
2 具体的取り組み P34~37
12 教えることと考えさせること
1 教えることと考えさせることの区別
「教えるべきこと」 数学での定義に当たること
「考えさせるべきこと」 数学での性質(定理)に当たること
また,定義の適用も
◎ 定義と性質の区別
「定義」の教科書での表現
○「~といいます」「~は~です」「~と書き,~と読みます」
教えるべきことは簡潔に手際よく教えていく
13 1を聞いて10を生み出す力
1 算数の授業はピンポイント学習だ
概念理解のために
① 定義を言葉で言える
② 具体例を挙げることができる
③ 方法を言える
④ 図や絵に表すことができる
⑤ 理由を言える
⑥ 適用問題を解くことができる
具体例 1~2が多いが広げて類推できるようにする
2 広げていく指導のあり方
広げていくためには適用問題をやること
∥
でも,その前に一斉学習でやるべきこと
Ⅱ 教科書の扱い方
14 算数の教科書の特質
1 教科書通りに教えることができたら一人前
教科書通りの授業ができたらかなりの腕前
2 安心感の根拠
支持される理由
① 算数の基礎基本の内容が載っている
② 指導要領により作られ検定を受けている
③ 時間とエネルギーが掛けられている
④ 親切で丁寧である
3 親切で丁寧であること
算数教科書
問題文 情景図 式 考え方 まとめ 練習 = (幕の内弁当)
4 実際の教科書で
書き込みのスペース
15 教科書の役割は
1 子どもと教師にとっての役割 P44
2 教科書に書き込む
事前
・学習問題,学習課題を明確にする … マーカー
・ヒントはどこか? 教師が工夫したヒントを書き込む
・ねらいは何か? 知識・技能と考え方
・子どもが使用する空きスペースは式,答えなどを書く
・定義と性質を区別する
・必要な準備物を書き込む
本番
・子どもが難しかった問題があれば,その場でメモする 10秒で
事後の反省
・授業後5分間で処理する
・子どもの反応(よい考え,つまずき)で気が付いたことをメモする
・問題に対する正答率もメモするとよい
・今終わったところを線で区切る
16 教科書の使い方のパターン
1 教科書の使い方はほぼ5つである
① 実際→教科書→実際型
② 教科書→実際型
③ 実際→教科書型
④ 教科書型 教科書のみ
⑤ 実際→型 教科書を離れて
☆「日本の名句名言」増原良彦 講談社現代新書 1988年 ③【再掲載 2014.4】
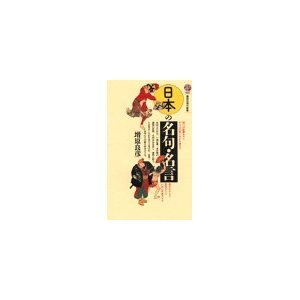
◇「御神酒あがらぬ神はない」
吉田兼好
「下戸ならぬこそ、をのこはよけれ」
井原西鶴
「世の中に下戸の建てたる蔵もなし」
若山牧水
「白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒は静かに飲むべかりけり」
井伏鱒二
「コノサカヅキヲ受ケテクレ ドウゾナミナミツイデオクレ
ハナニアラシノタトヘモアルゾ 『サヨナラ』ダケガ人生ダ」
|
◎日本人はヨーロッパ人の半分しかアルデヒド脱水素酵素を持っていない
◇「人間五十年。化天の内をくらぶれば夢幻のごとくなり」幸若
幸若舞曲『敦盛』
「人間五十年。下天の内をくらぶれば夢幻のごとくなり」
◎ 我々の一生は短い、かりに一生が50年だとすればそれは下天の一昼
夜でしかない
◇「花は桜木人は武士」『仮名手本忠臣蔵』
花
「花」といえば平安後期までは「梅」
平安後期からは 桜
江戸時代の武士の美意識
独善的な支配者
◇「武士道と云は、死ぬ事と見つけたり」 山本常朝『葉隠』
□ノブレス・オブリージュ(仏語)
高貴なる者にはそれだけの大きな義務がある
= 高貴なる者の責任は大
◎戦争になるとイギリスではまず王家の者が銃を持って戦場に出掛ける。
◎戦場での死亡率もエリート層の方が高い。
フォークランド戦争ではアンドリュー王子が率先して戦場に!
|
法の下での平等はそのままにエリート層の道義的義務を高くしよ
うという考え方
イスラム
鞭打ちの刑 - 自由人は奴隷の二倍
↑↓
日本のエリート層
被害者意識ばかりが強くて「高貴なる者の義務」無自覚
「武士は食わねど高楊枝」 = 外面だけ取り繕う
∥
武士に支配者としての自覚がなかった
関心は「主君に気に入られること」
∥
◎ 主君の飼い犬であって被支配者階級における支配者としての責任は
これっぽっちも持っていなかった
□日本の考え方
会社役員
会社員より派閥の利害
政治家
国民に対する政治責任よりも党利党略
大学教授
学生教育より自分の後輩



