明日24日(日)まで第11回ハイスクール国際ジオラマグランプリ2024 「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 ⑤(最終) /『子どもから大人になれない日本人』深谷昌志 リヨン社 2005年 ①(前半)【再掲載 2016.8】 [読書記録 民俗]
今回は、3月20日に続いて、斎藤卓志さんの、
「世間師 宮本常一の仕事」の紹介5回目 最終です。
出版社の案内には、
「『忘れられた日本人』などで知られる民俗学者・宮本常一の生涯を
追った評伝。日本全国を旅した宮本の仕事を探索するとともに、学者
的でも民俗的でも高踏的でもない、宮本の人間に対するやさしさと温
かさを伝える。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「『宮本は神(宗教)の問題をやらなかった』 『宮本にとっての神は庶民
だ』- 谷川健一」
・「お猿さんの芸で笑うんだけど人が笑っている笑顔も目に入る。全然知らない人
たちが一緒にお猿産の芸を見て童心に帰っていい笑顔になる。猿まわしは輪の
芸能だ。- 宮本常一」
・「『電波の流れる先に行って,野良でも炉端でも聞いて帰って話をする。
スタジオで考えるな,現場で考えろ。』 - 宮本常一が永六輔に」
・「人が人を信頼し得るということが,しあわせというもので,しあわ
せというものは人が人を信じる以外にないのです。人を信じない
世界にしあわせというものはないのです。 - 宮本常一」
もう一つ、再掲載になりますが、深谷昌志さんの
「子どもから大人になれない日本人」①を載せます。
- 「ギフテッド」と「スローラナー」二対する教育
この考え方は大切だとわたしは思うのですが、
日本に導入されたらどうなるだろうと考えてしまいました。
第11回ハイスクール国際ジオラマグランプリ2024 HiD2024
いよいよ明日24日(日)までジオラマの甲子園が開催中。
観覧無料、直接投票もできます。
会場はザザシティ浜松 西館1階特設会場です。
時間があればぜひ。
※ 浜松ジオラマファクトリー Fasebook

☆「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 ⑤(最終)
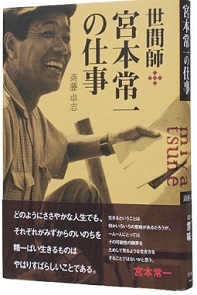
◇周防大島に帰る
□兄・村崎義正と弟・村崎修二
村崎修二 S52(1977)4.8宮本常一と会う
「修ちゃん」と呼ばれた
猿回しの芸の復活を頼んだ
「文化を守ることは命を守る行為」
宮本は村崎を京大の今西錦司に紹介している
生きた文化
「体験」「想像」「記憶」「関心」
□最晩年
『東和町誌』全一巻
『民衆の生活と文化』未来社 昭和53年
後書き
米山俊直,田村善次郎,宮田登
寄稿者
伊藤幹治,網野善彦,竹田亘,村武精一,宮田登,
米山俊直、祖父江孝男,坪井洋文,田村善次郎,石毛直道,
稲垣尚友、加藤俊秀,神崎宣武,潮田鉄雄,高松圭吉
谷川健一
「宮本は神(宗教)の問題をやらなかった」
「宮本にとっての神は庶民だ」
猿回しは「輪の芸能」(宮本)
お猿さんの芸で笑うんだけど人が笑っている笑顔も目に入る。全然知
らない人たちが一緒にお猿産の芸を見て童心に帰っていい笑顔になる。
暖かいムード
◇旅駆けた常一
□民俗学者宮本常一の孤独
終始アカデミックの外に
武蔵野美大,観光文化研究所
~ 友には恵まれたが朋のいる場所ではなかった
◎ 聞いた内容が,それを誇ってくれた人への信頼によって裏
打ちされている
- 自分が見てきたことへのこだわり
研究者の領域からはみ出た
永六輔「時代の証言者」(朝日新聞 平成18年2月2日)
宮本が永に…
「電波の流れる先に行って,野良でも炉端でも聞いて帰って
話をする。スタジオで考えるな,現場で考えろ。」
→ フットワークの良さ
生き物としての芸能再生のために
鬼太鼓座
木下忠(愛知大学)
「宮本さんにはカリスマがある」
東の菅江真澄 西の宮本常一
立ち位置は常に「いま」
多くの年寄りから話を聞いた
□絵巻の仕事
絵と解説
□宮本最晩年の講演から
「人が人を信頼し得るということが,しあわせというもので,しあ
わせというものは人が人を信じる以外にないのです。人を信じな
い世界にしあわせというものはないのです」
◇あとがき
□稲武の夏焼温泉へ
設楽町名倉の後藤治夫さんに呼ばれて
後藤さん 93歳
『シベリア抑留記』春風社 2005年
序文は澤地久枝
□谷川先生より教えられた「宮本のテーマは人だ」
= 宮本の人間に対する優しさ温かさ
□宮本アサ子さん
「常一伝は書き手によってさまざまな形になりましょう」
☆『子どもから大人になれない日本人』深谷昌志 リヨン社 2005年 ①(前半)【再掲載 2016.8】

◇親離れ子離れした人間関係に
① 子どもの意見や考えに耳を傾けよう = 子どもも中学生になると、
自分の世界を持つ。
親が自分の意見や考えをいう前に、子どもの考えを話させよう。親
が思っている以上に成長している子どもの姿が浮かんでくる。
② 自立のプログラムを作ろう = こづかいでどこまでまかなうか。門
限を何時までにするか。ケイタイの費用限度をどう考えるかなど、領
域を分けて、子どもの自立を具体的 に考えよう。
そして、子どもの年齢に応じた形で自立のプログラムを考えよう。
③ 弱みを見せよう
= 子どもは親をビッグな存在と思っている。そして、親をいつま
でたっても超えられないと感じている。それだけに、子どもが中
学生くらいになったら、親は子どもに弱みを見せよう。
弱みを突破口として、子どもは自立の道をたどれるようになる。
④ 時には、本音でぶつかる
= 親としての弱みを見せ、子どもの意見を聞くのがすべてではな
い。時には、本音でぶつかろう。とくに絶対に譲れないと思うよ
うなことは、安易に妥協しないで、親としての権威を示そう。
強い親とぶつかって、自立するから、しっかりとした子どもが
育つのである。
⑤ 親をやめる
= 母親が細かく世話をしていると、子どもはそれを当たり前と思
い、そうした環境に安住しやすい。
そこで、子どもが中学生くらいになったら、世話をするという
意味での親をやめる時があってよいのではないか。
⑥ 親も自分の世界を持つ
= 親、とくに専業主婦の母親は、子育てに専念するので、自分の
世界を持ちにくい。そのため、子どもが親離れの時期になった時、
子どもにしがみつきがちになる。
子どもが小学校高学年になったら、子離れの準備として、母親
は自分の世界を持つための努力を重ねるべきであろう。
◇個人差への対応
海外へ行く時、小学校を訪問するようにしている。
高校や大学はどこの社会でもそれほど変わりはない。
しかし、義務教育の学校は津々浦々まで設置されるので、その社会
の問題がストレートな形で学校の姿に現れてくる。
アメリカ・サンフランシスコの学校を訪ねた時、小学4年生のクラ
ス23名の内、メキシコ、中国、韓国、エジプトなど、14の母国語を
話す子どもがいた。5年生は23名で、13言語だった。
もっともそうした他民族社会の姿は、ヨーロッパの学級にも見られ
る。
ドイツのフランクフルトを訪ねた時、ドイツ系と思えない子どもが
多かった。担当官に聞いてみると、市内の学校に在籍する生徒の内、
ドイツ人は4割で、半数以上が他国籍だった。
さらに、ニュージーランドのオークランドでもサモアやフイージー
など、少数民族との共存問題が学級内にも影を投げかけていた。
マニラでタガログ語と英語、マレーシアでは、マレー語、中国語、
英語など、教室内で使う言語が問題になるくらいに、多民族の状態は
教育を難しくしている。
使用している言葉が異なるから、着る物から勉強への構えまで、す
べての面で子ども一人一人が異なる。
そうした多様さへの対応が学校として困難な課題となる。
日本では考えられない事態だが、サンフランシスコの給食を例にと
ると、食事は、
① 全部を家から持ってくる子、
② 主食を持参し、飲み物だけ買う子、
③ ランチを食べる子
とにわかれ、③のランチも、アジア、アメリカ、メキシコの選択があ
り、その上、アレルギーなどの対策もとられていた。
韓国育ちの子どもはキムチが好きだし、中国生まれは饅頭が好物だ。
宗教上の理由から肉を食べない人もいるし、信条的なベジタリアン
もいる。したがって、日本のように一つのメニューで学校給食を展開
することはできないらしい。
子どもの個体差への対応が浸透しているので、欧米の学校では、普
通のことのように、学力別の編成がおこなわれている。
数人の子どもがいれば、一人一人の顔かたちが違うように、学習に
対する構えが異なる。
だから、個人差に対応する形で、授業が展開される。
しかし、学校で尋ねてみると、かなり慎重に個人差への対応を実践
しているのがわかる。
どこの親も、可能なら「ギフテッド」(知的に恵まれた)クラスの子
どもを入れたい。そして、「スローラーナー」クラスは避けたい。「ギ
フテッド」の子どもが自信を持ち、スローラーナーはひけ目を感じが
ちだ。
そこで、多くの学校では、スローラーナーのクラスは
① 少人数で、
② 校内のよい場所に教室があり、
③ 力量の優れた教師が担当する。
それと同時に、ギフテッドのクラスでは、
① 授業の進度を速めるのではなく、
② ボランティア活動を重視する、
③ アメフトのようなチーム・スポーツを大事にする、
④ デイベイト(討議)を多用する、
⑤ 読書を薦める
などを配慮している場合が多い。
校長に話を聞いてみると、ギフテッドの子どもは知的に恵まれてい
るのだから、勉強を教えれば小学生でも高校レベルの教材をマスター
できる。
しかし、そんなに先回りして教えても意味があると思えない。ただ、
ギフテッドの子どもは、いずれ一流の大学へ進学して社会のリーダー
になる人材だ。
それなのに、スローラーナーを蔑視したりしがちだ。
だから
◎ 福祉施設などで社会的な弱者への共感性を育てると同時に、
◎ 団体スポーツをして、集団内での行動の仕方を習得させる。
◎ 読書で自分なりの見方を作るだけでなく、
◎ 話し合いの技術を磨くことが大事だ。
ギフテッドの子どもは、傲慢な若者に育ちやすい問題児だと思って
対応すべきだという。
こうした指摘を、特定の校長だけではなく、多くの学校で聞くこと
ができた。
「世間師 宮本常一の仕事」の紹介5回目 最終です。
出版社の案内には、
「『忘れられた日本人』などで知られる民俗学者・宮本常一の生涯を
追った評伝。日本全国を旅した宮本の仕事を探索するとともに、学者
的でも民俗的でも高踏的でもない、宮本の人間に対するやさしさと温
かさを伝える。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「『宮本は神(宗教)の問題をやらなかった』 『宮本にとっての神は庶民
だ』- 谷川健一」
・「お猿さんの芸で笑うんだけど人が笑っている笑顔も目に入る。全然知らない人
たちが一緒にお猿産の芸を見て童心に帰っていい笑顔になる。猿まわしは輪の
芸能だ。- 宮本常一」
・「『電波の流れる先に行って,野良でも炉端でも聞いて帰って話をする。
スタジオで考えるな,現場で考えろ。』 - 宮本常一が永六輔に」
・「人が人を信頼し得るということが,しあわせというもので,しあわ
せというものは人が人を信じる以外にないのです。人を信じない
世界にしあわせというものはないのです。 - 宮本常一」
もう一つ、再掲載になりますが、深谷昌志さんの
「子どもから大人になれない日本人」①を載せます。
- 「ギフテッド」と「スローラナー」二対する教育
この考え方は大切だとわたしは思うのですが、
日本に導入されたらどうなるだろうと考えてしまいました。
第11回ハイスクール国際ジオラマグランプリ2024 HiD2024
いよいよ明日24日(日)までジオラマの甲子園が開催中。
観覧無料、直接投票もできます。
会場はザザシティ浜松 西館1階特設会場です。
時間があればぜひ。
※ 浜松ジオラマファクトリー Fasebook

☆「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 ⑤(最終)
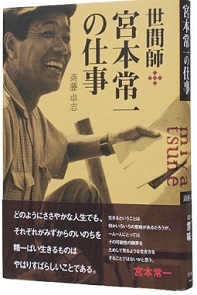
◇周防大島に帰る
□兄・村崎義正と弟・村崎修二
村崎修二 S52(1977)4.8宮本常一と会う
「修ちゃん」と呼ばれた
猿回しの芸の復活を頼んだ
「文化を守ることは命を守る行為」
宮本は村崎を京大の今西錦司に紹介している
生きた文化
「体験」「想像」「記憶」「関心」
□最晩年
『東和町誌』全一巻
『民衆の生活と文化』未来社 昭和53年
後書き
米山俊直,田村善次郎,宮田登
寄稿者
伊藤幹治,網野善彦,竹田亘,村武精一,宮田登,
米山俊直、祖父江孝男,坪井洋文,田村善次郎,石毛直道,
稲垣尚友、加藤俊秀,神崎宣武,潮田鉄雄,高松圭吉
谷川健一
「宮本は神(宗教)の問題をやらなかった」
「宮本にとっての神は庶民だ」
猿回しは「輪の芸能」(宮本)
お猿さんの芸で笑うんだけど人が笑っている笑顔も目に入る。全然知
らない人たちが一緒にお猿産の芸を見て童心に帰っていい笑顔になる。
暖かいムード
◇旅駆けた常一
□民俗学者宮本常一の孤独
終始アカデミックの外に
武蔵野美大,観光文化研究所
~ 友には恵まれたが朋のいる場所ではなかった
◎ 聞いた内容が,それを誇ってくれた人への信頼によって裏
打ちされている
- 自分が見てきたことへのこだわり
研究者の領域からはみ出た
永六輔「時代の証言者」(朝日新聞 平成18年2月2日)
宮本が永に…
「電波の流れる先に行って,野良でも炉端でも聞いて帰って
話をする。スタジオで考えるな,現場で考えろ。」
→ フットワークの良さ
生き物としての芸能再生のために
鬼太鼓座
木下忠(愛知大学)
「宮本さんにはカリスマがある」
東の菅江真澄 西の宮本常一
立ち位置は常に「いま」
多くの年寄りから話を聞いた
□絵巻の仕事
絵と解説
□宮本最晩年の講演から
「人が人を信頼し得るということが,しあわせというもので,しあ
わせというものは人が人を信じる以外にないのです。人を信じな
い世界にしあわせというものはないのです」
◇あとがき
□稲武の夏焼温泉へ
設楽町名倉の後藤治夫さんに呼ばれて
後藤さん 93歳
『シベリア抑留記』春風社 2005年
序文は澤地久枝
□谷川先生より教えられた「宮本のテーマは人だ」
= 宮本の人間に対する優しさ温かさ
□宮本アサ子さん
「常一伝は書き手によってさまざまな形になりましょう」
☆『子どもから大人になれない日本人』深谷昌志 リヨン社 2005年 ①(前半)【再掲載 2016.8】
◇親離れ子離れした人間関係に
① 子どもの意見や考えに耳を傾けよう = 子どもも中学生になると、
自分の世界を持つ。
親が自分の意見や考えをいう前に、子どもの考えを話させよう。親
が思っている以上に成長している子どもの姿が浮かんでくる。
② 自立のプログラムを作ろう = こづかいでどこまでまかなうか。門
限を何時までにするか。ケイタイの費用限度をどう考えるかなど、領
域を分けて、子どもの自立を具体的 に考えよう。
そして、子どもの年齢に応じた形で自立のプログラムを考えよう。
③ 弱みを見せよう
= 子どもは親をビッグな存在と思っている。そして、親をいつま
でたっても超えられないと感じている。それだけに、子どもが中
学生くらいになったら、親は子どもに弱みを見せよう。
弱みを突破口として、子どもは自立の道をたどれるようになる。
④ 時には、本音でぶつかる
= 親としての弱みを見せ、子どもの意見を聞くのがすべてではな
い。時には、本音でぶつかろう。とくに絶対に譲れないと思うよ
うなことは、安易に妥協しないで、親としての権威を示そう。
強い親とぶつかって、自立するから、しっかりとした子どもが
育つのである。
⑤ 親をやめる
= 母親が細かく世話をしていると、子どもはそれを当たり前と思
い、そうした環境に安住しやすい。
そこで、子どもが中学生くらいになったら、世話をするという
意味での親をやめる時があってよいのではないか。
⑥ 親も自分の世界を持つ
= 親、とくに専業主婦の母親は、子育てに専念するので、自分の
世界を持ちにくい。そのため、子どもが親離れの時期になった時、
子どもにしがみつきがちになる。
子どもが小学校高学年になったら、子離れの準備として、母親
は自分の世界を持つための努力を重ねるべきであろう。
◇個人差への対応
海外へ行く時、小学校を訪問するようにしている。
高校や大学はどこの社会でもそれほど変わりはない。
しかし、義務教育の学校は津々浦々まで設置されるので、その社会
の問題がストレートな形で学校の姿に現れてくる。
アメリカ・サンフランシスコの学校を訪ねた時、小学4年生のクラ
ス23名の内、メキシコ、中国、韓国、エジプトなど、14の母国語を
話す子どもがいた。5年生は23名で、13言語だった。
もっともそうした他民族社会の姿は、ヨーロッパの学級にも見られ
る。
ドイツのフランクフルトを訪ねた時、ドイツ系と思えない子どもが
多かった。担当官に聞いてみると、市内の学校に在籍する生徒の内、
ドイツ人は4割で、半数以上が他国籍だった。
さらに、ニュージーランドのオークランドでもサモアやフイージー
など、少数民族との共存問題が学級内にも影を投げかけていた。
マニラでタガログ語と英語、マレーシアでは、マレー語、中国語、
英語など、教室内で使う言語が問題になるくらいに、多民族の状態は
教育を難しくしている。
使用している言葉が異なるから、着る物から勉強への構えまで、す
べての面で子ども一人一人が異なる。
そうした多様さへの対応が学校として困難な課題となる。
日本では考えられない事態だが、サンフランシスコの給食を例にと
ると、食事は、
① 全部を家から持ってくる子、
② 主食を持参し、飲み物だけ買う子、
③ ランチを食べる子
とにわかれ、③のランチも、アジア、アメリカ、メキシコの選択があ
り、その上、アレルギーなどの対策もとられていた。
韓国育ちの子どもはキムチが好きだし、中国生まれは饅頭が好物だ。
宗教上の理由から肉を食べない人もいるし、信条的なベジタリアン
もいる。したがって、日本のように一つのメニューで学校給食を展開
することはできないらしい。
子どもの個体差への対応が浸透しているので、欧米の学校では、普
通のことのように、学力別の編成がおこなわれている。
数人の子どもがいれば、一人一人の顔かたちが違うように、学習に
対する構えが異なる。
だから、個人差に対応する形で、授業が展開される。
しかし、学校で尋ねてみると、かなり慎重に個人差への対応を実践
しているのがわかる。
どこの親も、可能なら「ギフテッド」(知的に恵まれた)クラスの子
どもを入れたい。そして、「スローラーナー」クラスは避けたい。「ギ
フテッド」の子どもが自信を持ち、スローラーナーはひけ目を感じが
ちだ。
そこで、多くの学校では、スローラーナーのクラスは
① 少人数で、
② 校内のよい場所に教室があり、
③ 力量の優れた教師が担当する。
それと同時に、ギフテッドのクラスでは、
① 授業の進度を速めるのではなく、
② ボランティア活動を重視する、
③ アメフトのようなチーム・スポーツを大事にする、
④ デイベイト(討議)を多用する、
⑤ 読書を薦める
などを配慮している場合が多い。
校長に話を聞いてみると、ギフテッドの子どもは知的に恵まれてい
るのだから、勉強を教えれば小学生でも高校レベルの教材をマスター
できる。
しかし、そんなに先回りして教えても意味があると思えない。ただ、
ギフテッドの子どもは、いずれ一流の大学へ進学して社会のリーダー
になる人材だ。
それなのに、スローラーナーを蔑視したりしがちだ。
だから
◎ 福祉施設などで社会的な弱者への共感性を育てると同時に、
◎ 団体スポーツをして、集団内での行動の仕方を習得させる。
◎ 読書で自分なりの見方を作るだけでなく、
◎ 話し合いの技術を磨くことが大事だ。
ギフテッドの子どもは、傲慢な若者に育ちやすい問題児だと思って
対応すべきだという。
こうした指摘を、特定の校長だけではなく、多くの学校で聞くこと
ができた。
第11回ハイスクール国際ジオラマグランプリ2024 22日より 「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2008年 ④ /「学校教育うらおもて事典」佐藤秀夫 小学館 2000年 ①【再掲載 2016.9】 [読書記録 民俗]
第11回ハイスクール国際ジオラマグランプリ2024 HiD2024
今年もジオラマの甲子園が今週末に浜松で開かれ、
一般公開展示が行われます。
観覧は無料、作品をご覧になり直接投票ができます。
会場はザザシティ浜松 西館1階特設会場です。
ぜひ、足をお運びください。

今回は、3月12日に続いて、斎藤卓志さんの、
「世間師 宮本常一の仕事」の紹介 4回目です。
出版社の案内には、
「『忘れられた日本人』などで知られる民俗学者・宮本常一の生涯を
追った評伝。日本全国を旅した宮本の仕事を探索するとともに、学者
的でも民俗的でも高踏的でもない、宮本の人間に対するやさしさと温
かさを伝える。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「『今日歴史学者は多いが歴史家は極めて少ない』 桑原武夫」
・「宮本のキーワードは『実践者』」
・「あるくみるきくが理念 →『わたしの日本地図』シリーズ」
・「だれにも分かるように書け」
「学者に向かって書くな」
「行かなければ話にならない」
・「『自然は美しい しかし 人の手が加わるとあたたかくなる
そのあたたかなものを求めて 歩いてみよう」宮本常一」
もう一つ、再掲載になりますが、佐藤秀夫さんの
「学校教育うらおもて事典」①を載せます。
本書を読み、初めて知ったことがかなりありました。
☆「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2,008年 ④
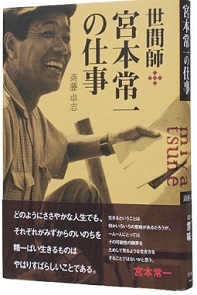
◇豊かな国の民俗学
□文化財保護委員会
昭和37~
3カ年計画 緊急調査 30箇所
自分で直接聞いた体験から言葉を紡いでいる
□池沢夏樹『忘れられた日本人』の感想
◎ この人の学問の特徴はまず持って明るいことではないだろうか。
風通しが良くて,開放的で,明るい
= 論文は書かないがメッセージは伝える
□桑原武夫
『日本の名著』中公新書 1962
「今日歴史学者は多いが歴史家は極めて少ない」
□宮本の文章は私的なもの
宮本のキーワード 「実践者」
「民俗をやってきたのは人間が生きる尊さ,生きる意味は何かの
追求でしかないんですよね」
本来の伝説とは
-「ものを産みだし変えていく力」
□猿回しの復活
村崎義正,村崎修二兄弟
人は繋がりの中で生きている,人とつながることが人として生
きることだ。
□司馬遼太郎
「宮本常一 - 同時代の証言」日本観光文化研究所
『21世紀に生きる君たちへ』平成8年
◇滞在地 「東京・府中」
□谷沢明(愛知淑徳大学)
「宮本は褒めて育てる人」
「どうじゃ,おもしろいじゃろか」
「あるくみるきく」
→ 「あるくみるきく」が理念
『わたしの日本地図』シリーズ
□昭和36年
府中市に家 54歳
大西伍一(旧友)が図書館長 慶友社
□昭和40(1965)年
武蔵野美術大学教授
□須藤功
民俗学写真家
『お祭りさん』昭和38年
浜松自衛隊で広報 「まつり同好会」
「だれにも分かるように書け」
「学者に向かって書くな」
『昭和のくらし』全十巻
『西浦のまつり』 未来社 1970
「行かなければ話にならない」
◇タネを播く
□「その気にさせる」
テレビ番組『日本の詩情』
自然は美しい
しかし
人の手が加わるとあたたかくなる
そのあたたかなものを求めて
歩いてみよう 宮本常一
☆「学校教育うらおもて事典」佐藤秀夫 小学館 2000年 ①【再掲載 2016.9】
[出版社の案内]
21世紀・学校の大改革を目前に、学校の慣行『モノ・コト』の成り立
ちをうらからおもてから掘り起こす事典。○×△、内申書、総合的な
学習、日の丸、君が代等39項目について徹底解明。
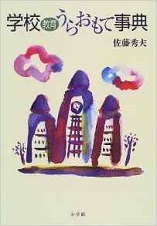
◇一条校
□正規の学校
= 学校教育法・第一条規定
文部省所轄
小学校・中学校・高等学校・大学・聾学校・盲学校
養護学校・高等専門学校・中高一貫校(中等教育学校)
□「正規の学校」観
専修学校と各種学校は含まれない
各種学校への道を選ぶ
自由学園(羽仁もと子)文化学院(西村伊作) 明治学院
在日外国人学校には極めて冷たい 国権主義的教育観
◇中学校
三等区分
大中小
~ 明治日本の開発
中学入学
他の社会的特権性は認められなかった
◇大学校
大学校
= 文部省以外の官公庁所管の学校の名称
「大学」の登場
1886年 森有礼の「諸学校令」
最頂点
- 帝国大学に
「校」をつけない
文部省の縄張りから外れたもの
- 警察大学校,防衛大学校,防衛医科大学校,海上保安大学校
~ 無視できない
◇予備校
進学の予備
= 自校の専門教育課程への予備課程に他ならなかった
受験の予備
公正な選抜
→ 入学時の選抜試験の厳密化に収斂
ヨーロッパのような「二つの国民」の形成回避
→ 受験予備 激烈化
予備校の成立
- 私立大学によるものが多かった
◇父母会(保護者会)
父兄,保護者そして父母
「父兄」の系譜
1872年「学制布告書」最初で最後
「父母後見人等」から「学級児童保護者」へ
1879「教育令」
- 父母及後見人等
1890「第二次小学校令」
- 学齢児童ヲ保護スベキ者
1891「文部省令」
保護の内容
・ 就学させる義務主体
・ 授業料納入
父母
→ 父母及戸主
→ 後見人
→ 後見人及戸主
1900「第三次小学校令」
- 学齢児童保護者
「父兄会」と「母姉会」
父兄の存在?
親と学校との関係
= 特殊日本的事情
親の協力のありよう
制度管理・教育内容
=「オカミの学校」
維持・運営面
=「地域の学校」
教員給与
◎ 1940年まで地域負担
= 親の金銭的・労働的な協力が不可欠
- 家族財産に権限を持つ「父兄」集団の協力
よって戸主会・父兄会が深く関わった
①ハード担当
「父兄会」年一回
②ソフト担当
「母姉会」しばしば
◎ 父兄会の母姉会化
1920年~
◎ 名目上は「母姉会」の解消,「父兄会」への吸収だったが,
実体的には「父兄会」の解体,母姉会への単一化という矛盾
に満ちた過程であった。
母姉のみの父兄会は戦前から
◎西日本では「育友会」と呼ばれる
今年もジオラマの甲子園が今週末に浜松で開かれ、
一般公開展示が行われます。
観覧は無料、作品をご覧になり直接投票ができます。
会場はザザシティ浜松 西館1階特設会場です。
ぜひ、足をお運びください。

今回は、3月12日に続いて、斎藤卓志さんの、
「世間師 宮本常一の仕事」の紹介 4回目です。
出版社の案内には、
「『忘れられた日本人』などで知られる民俗学者・宮本常一の生涯を
追った評伝。日本全国を旅した宮本の仕事を探索するとともに、学者
的でも民俗的でも高踏的でもない、宮本の人間に対するやさしさと温
かさを伝える。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「『今日歴史学者は多いが歴史家は極めて少ない』 桑原武夫」
・「宮本のキーワードは『実践者』」
・「あるくみるきくが理念 →『わたしの日本地図』シリーズ」
・「だれにも分かるように書け」
「学者に向かって書くな」
「行かなければ話にならない」
・「『自然は美しい しかし 人の手が加わるとあたたかくなる
そのあたたかなものを求めて 歩いてみよう」宮本常一」
もう一つ、再掲載になりますが、佐藤秀夫さんの
「学校教育うらおもて事典」①を載せます。
本書を読み、初めて知ったことがかなりありました。
☆「世間師 宮本常一の仕事」斎藤卓志 春風社 2,008年 ④
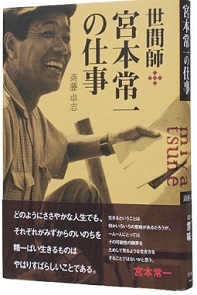
◇豊かな国の民俗学
□文化財保護委員会
昭和37~
3カ年計画 緊急調査 30箇所
自分で直接聞いた体験から言葉を紡いでいる
□池沢夏樹『忘れられた日本人』の感想
◎ この人の学問の特徴はまず持って明るいことではないだろうか。
風通しが良くて,開放的で,明るい
= 論文は書かないがメッセージは伝える
□桑原武夫
『日本の名著』中公新書 1962
「今日歴史学者は多いが歴史家は極めて少ない」
□宮本の文章は私的なもの
宮本のキーワード 「実践者」
「民俗をやってきたのは人間が生きる尊さ,生きる意味は何かの
追求でしかないんですよね」
本来の伝説とは
-「ものを産みだし変えていく力」
□猿回しの復活
村崎義正,村崎修二兄弟
人は繋がりの中で生きている,人とつながることが人として生
きることだ。
□司馬遼太郎
「宮本常一 - 同時代の証言」日本観光文化研究所
『21世紀に生きる君たちへ』平成8年
◇滞在地 「東京・府中」
□谷沢明(愛知淑徳大学)
「宮本は褒めて育てる人」
「どうじゃ,おもしろいじゃろか」
「あるくみるきく」
→ 「あるくみるきく」が理念
『わたしの日本地図』シリーズ
□昭和36年
府中市に家 54歳
大西伍一(旧友)が図書館長 慶友社
□昭和40(1965)年
武蔵野美術大学教授
□須藤功
民俗学写真家
『お祭りさん』昭和38年
浜松自衛隊で広報 「まつり同好会」
「だれにも分かるように書け」
「学者に向かって書くな」
『昭和のくらし』全十巻
『西浦のまつり』 未来社 1970
「行かなければ話にならない」
◇タネを播く
□「その気にさせる」
テレビ番組『日本の詩情』
自然は美しい
しかし
人の手が加わるとあたたかくなる
そのあたたかなものを求めて
歩いてみよう 宮本常一
☆「学校教育うらおもて事典」佐藤秀夫 小学館 2000年 ①【再掲載 2016.9】
[出版社の案内]
21世紀・学校の大改革を目前に、学校の慣行『モノ・コト』の成り立
ちをうらからおもてから掘り起こす事典。○×△、内申書、総合的な
学習、日の丸、君が代等39項目について徹底解明。
◇一条校
□正規の学校
= 学校教育法・第一条規定
文部省所轄
小学校・中学校・高等学校・大学・聾学校・盲学校
養護学校・高等専門学校・中高一貫校(中等教育学校)
□「正規の学校」観
専修学校と各種学校は含まれない
各種学校への道を選ぶ
自由学園(羽仁もと子)文化学院(西村伊作) 明治学院
在日外国人学校には極めて冷たい 国権主義的教育観
◇中学校
三等区分
大中小
~ 明治日本の開発
中学入学
他の社会的特権性は認められなかった
◇大学校
大学校
= 文部省以外の官公庁所管の学校の名称
「大学」の登場
1886年 森有礼の「諸学校令」
最頂点
- 帝国大学に
「校」をつけない
文部省の縄張りから外れたもの
- 警察大学校,防衛大学校,防衛医科大学校,海上保安大学校
~ 無視できない
◇予備校
進学の予備
= 自校の専門教育課程への予備課程に他ならなかった
受験の予備
公正な選抜
→ 入学時の選抜試験の厳密化に収斂
ヨーロッパのような「二つの国民」の形成回避
→ 受験予備 激烈化
予備校の成立
- 私立大学によるものが多かった
◇父母会(保護者会)
父兄,保護者そして父母
「父兄」の系譜
1872年「学制布告書」最初で最後
「父母後見人等」から「学級児童保護者」へ
1879「教育令」
- 父母及後見人等
1890「第二次小学校令」
- 学齢児童ヲ保護スベキ者
1891「文部省令」
保護の内容
・ 就学させる義務主体
・ 授業料納入
父母
→ 父母及戸主
→ 後見人
→ 後見人及戸主
1900「第三次小学校令」
- 学齢児童保護者
「父兄会」と「母姉会」
父兄の存在?
親と学校との関係
= 特殊日本的事情
親の協力のありよう
制度管理・教育内容
=「オカミの学校」
維持・運営面
=「地域の学校」
教員給与
◎ 1940年まで地域負担
= 親の金銭的・労働的な協力が不可欠
- 家族財産に権限を持つ「父兄」集団の協力
よって戸主会・父兄会が深く関わった
①ハード担当
「父兄会」年一回
②ソフト担当
「母姉会」しばしば
◎ 父兄会の母姉会化
1920年~
◎ 名目上は「母姉会」の解消,「父兄会」への吸収だったが,
実体的には「父兄会」の解体,母姉会への単一化という矛盾
に満ちた過程であった。
母姉のみの父兄会は戦前から
◎西日本では「育友会」と呼ばれる



