樋口清之さんはこんなことを⑤-「日本人はなぜ水に流したがるのか」 MG出版 1988年(1) / 池田潔「自由と規律」 岩波新書 1949年 ①【再掲載 2017.2】 [読書記録 歴史]
今日は4月20日、土曜日です。
今回は、4月17日に続いて「樋口清之さんはこんなことを」5回目、
「日本人はなぜ水に流したがるのか」の紹介 1回目です。
梅干し博士の語り口を思い出します。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「日本人の行動様式は過去にこだわらずあげつらわず責めず忘れ受容し
許す。人間関係を維持する知恵であり寛容な人間性の美点である。
しかし、国際社会では、無神経、無定見、無責任ととられる」
・「ごみを捨てても川から海へ流れて消えていくことから、自然の浄化作
用に頼ってものを捨てる習慣がついてしまった」
・「八百万の神は自然への感謝とともに自然の力を恐れて力を鎮めるため」
もう一つ、再掲載になりますが、池田潔さんの
「自由と規律」①を載せます。
75年間出版され続けている、わたしが大好きな本です。
☆樋口清之さんはこんなことを⑤-「日本人はなぜ水に流したがるのか」 MG出版 1988年(1)

◇序
<水に流す>
□現実的な知恵
(他人の過去や失策を許容しこれからのことに行動)
× 責任所在うやむや「なあなあ体質」
日本人の行動様式
= 過去にこだわらずあげつらわず責めず忘れ受容し許す
人間関係を維持する知恵
寛容な人間性の美点
↓↑
国際社会では 無神経 無定見 無責任
豊かな水資源
→ 「清浄志向」
「禊ぎ」穢れや罪も洗い流す
稲作の要は水
→ 水を神に見,水の流れを生活信条,生きる哲学にまで高めた精
神文化
◎ 水に流す日本人の心情,行動様式
◇清浄機能
□川は巨大なごみ捨て場だった
オランダ人デレーケ
石川県常願寺川に対して「これは川ではない滝だ」
流れの速い川
・年間降水量多い
・地形 急傾斜
= 流れが速く清浄さをすぐ取り戻す
ごみを捨てても川から海へ流れて消えていく
京都ではかつて死体を鴨川へ = 水葬
◎ 自然の浄化作用に頼ってものを捨てる習慣
□川はありがたや水洗便所
平安時代貴族
桶箱に用便し朝、加茂川に捨てた
→ 川の浄化作用
モンスーン 用便が不潔なため
乾燥地帯では土に還る
便所 書院造り
便所 = 雪隠 暗闇 武士に不用心
農村では糞尿が肥料として重要に
→ 外便所くみ出しやすい
◎ 生活の清浄さ
□千差万別する日本の自然
川の氾濫は未だに止められない
- 日本は自然の恵みが豊かであるが自然から受ける脅威も大きい
四つの形の災害
火山 津波 日照り 水害
八百万の神
=「自然への感謝」 + 「自然の力を恐れて力を鎮めるため」
□災害が日本人を強くした
自然が大暴れするからといってなかなか土地を離れられない
= 土地への執着心(土地には祖先の霊が宿っていると信じた)
祖霊は土地と家にくっつく
→ 自然の変化に対しては順応
変化に対して素直についていく性質
◎ 諦めの良さと立ち直り身替わりの素早さ
□日本人は二重人格的である
大きな寒暖差
→ じっと耐える我慢強い性格
□「済まない」は流れを濁らせたこと
住む 済む
= 澄む
川が澄んでいない
澄まない
= 済まない
「私のために流れが悪くなり済みません」
- 人間関係を滑らかにする呪文
◎濁らすのは「異端者・病気・災害」
気心の知れた仲間意識があるから,正面から対立するより,否
を認めた方が相手も許してくれる
◎「済みません」は一種の防御態勢
◇日本の禊ぎ思考
□水の聖水としての役割
禊ぎ
=「水さそそぎ」「身をそそぐ」
水に物心両面にわたる汚れを洗い流す浄化作業(霊威)がある
と信じられている
◎四大宗教
水の聖水としての役割
□禊ぎの始まり
イザナギ
□喪に服するも禊ぎである
神社
- 死穢を忌む風習
伊勢神宮は僧侶の参宮を許さなかった
- 死者の葬送
禊ぎに塩=海水の象徴(清めの塩)
喪に服す
最小単位七日間 初七日
14,21,28,49日
◎必ず水辺で禊ぎ 精進落とし
□禊ぎは悪霊退散のおまじない
盛り塩 豆まき 流し雛
☆池田潔「自由と規律」 岩波新書 1949年 ①【再掲載 2017.2】
[出版社の案内]
ケンブリッジ,オックスフォードの両大学は,英国型紳士修業と結びつい
て世界的に有名だが,あまり知られていないその前過程のパブリック・ス
クールこそ,イギリス人の性格形成に基本的な重要性をもっている.若き
日をそこに学んだ著者は,自由の精神が厳格な規律の中で見事に育まれて
ゆく教育システムを,体験を通して興味深く描く
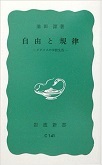
◇パブリックスクールの本質と起源
□イギリス人文史
= 個人の自由獲得の歴史
□イギリス産業史
= 自由企業確立を目的とした不断の闘争
富の原動力は鉄と石炭
□パブリックスクール
スパルタ式教育
精神と肉体の訓練
→ 卒業後 ケンブリッジ,オックスフォード大へ
□イートン校
「ウォータールーの戦勝はイートン校の校庭において獲得された」
□イギリスの学校制度
①公立 エレメンタリースクール → グラマースクール
②私立 プレップスクール → パブリックスクール
(寄宿制) (寄宿制)
□高等教育卒業生は政界,学界,教職,僧職,軍,官界上層へ
実業世界へはまれ
□パブリックスクールの起源
1387年 ウィンチェスター校 オックスフォード・ニューカレージのため
1446年 イートン校
ケンブリッジ・キングスカレージのため
創立当初は予備校
→ 現在は入試必要
16世紀僧院没落
→ 施設基金を教育目的に利用
- 中世パブリックスクール
中世パブリックスクール
ラグビー校,イートン校,ハロー校,ストニーハースト校等
近世パブリックスクール
ウェリントン校,リース校等
◇パブリックスクールの制度
□1902年 教育法令
官公立
エレメンタリースクール(初等)グラマースクール(中等)
庶民学校
基本知識 + 職業教育
→ 社会に出るか師範学校・専門学校へ
極めて優秀な者のみ諸大学へ
実社会
プロフェッションを除いては,高等教育必要なし
- 学校は高度の学問を修める者のための施設観しっかり
かつて商工階級
物質主義的人生観
- 文化教養を蔑視
教育とは「必要でさえない害毒」
1870年 一大改革
1876年 義務教育制度
1899年 教育局
1902年 教育法令 ランカスター・ベルの尽力
↑↓
私立
全校寄宿制度 寄付と高額な授業料・寄宿料
プレパトリースクール(初等)パブリックスクール(中等)
家庭の躾
→ 家庭教師
→ プレップスクール
地方・様々な規模 学校の色・寄宿生活
在学年限規定なし
試験によりパブリックスクールへ
→パブリックスクール
14~19世紀私財を以て経営され,全員寄宿制度によって
指導階級の子弟に中等教育を施す私立のグラマースクール
イングランドに31 スコットランドに4
修了後 オックスフォード・ケンブリッジ大学
(大学は古代二大学に限られる=伝統尊重)
陸軍士官学校・海軍士官学校へ
今回は、4月17日に続いて「樋口清之さんはこんなことを」5回目、
「日本人はなぜ水に流したがるのか」の紹介 1回目です。
梅干し博士の語り口を思い出します。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「日本人の行動様式は過去にこだわらずあげつらわず責めず忘れ受容し
許す。人間関係を維持する知恵であり寛容な人間性の美点である。
しかし、国際社会では、無神経、無定見、無責任ととられる」
・「ごみを捨てても川から海へ流れて消えていくことから、自然の浄化作
用に頼ってものを捨てる習慣がついてしまった」
・「八百万の神は自然への感謝とともに自然の力を恐れて力を鎮めるため」
もう一つ、再掲載になりますが、池田潔さんの
「自由と規律」①を載せます。
75年間出版され続けている、わたしが大好きな本です。
☆樋口清之さんはこんなことを⑤-「日本人はなぜ水に流したがるのか」 MG出版 1988年(1)

◇序
<水に流す>
□現実的な知恵
(他人の過去や失策を許容しこれからのことに行動)
× 責任所在うやむや「なあなあ体質」
日本人の行動様式
= 過去にこだわらずあげつらわず責めず忘れ受容し許す
人間関係を維持する知恵
寛容な人間性の美点
↓↑
国際社会では 無神経 無定見 無責任
豊かな水資源
→ 「清浄志向」
「禊ぎ」穢れや罪も洗い流す
稲作の要は水
→ 水を神に見,水の流れを生活信条,生きる哲学にまで高めた精
神文化
◎ 水に流す日本人の心情,行動様式
◇清浄機能
□川は巨大なごみ捨て場だった
オランダ人デレーケ
石川県常願寺川に対して「これは川ではない滝だ」
流れの速い川
・年間降水量多い
・地形 急傾斜
= 流れが速く清浄さをすぐ取り戻す
ごみを捨てても川から海へ流れて消えていく
京都ではかつて死体を鴨川へ = 水葬
◎ 自然の浄化作用に頼ってものを捨てる習慣
□川はありがたや水洗便所
平安時代貴族
桶箱に用便し朝、加茂川に捨てた
→ 川の浄化作用
モンスーン 用便が不潔なため
乾燥地帯では土に還る
便所 書院造り
便所 = 雪隠 暗闇 武士に不用心
農村では糞尿が肥料として重要に
→ 外便所くみ出しやすい
◎ 生活の清浄さ
□千差万別する日本の自然
川の氾濫は未だに止められない
- 日本は自然の恵みが豊かであるが自然から受ける脅威も大きい
四つの形の災害
火山 津波 日照り 水害
八百万の神
=「自然への感謝」 + 「自然の力を恐れて力を鎮めるため」
□災害が日本人を強くした
自然が大暴れするからといってなかなか土地を離れられない
= 土地への執着心(土地には祖先の霊が宿っていると信じた)
祖霊は土地と家にくっつく
→ 自然の変化に対しては順応
変化に対して素直についていく性質
◎ 諦めの良さと立ち直り身替わりの素早さ
□日本人は二重人格的である
大きな寒暖差
→ じっと耐える我慢強い性格
□「済まない」は流れを濁らせたこと
住む 済む
= 澄む
川が澄んでいない
澄まない
= 済まない
「私のために流れが悪くなり済みません」
- 人間関係を滑らかにする呪文
◎濁らすのは「異端者・病気・災害」
気心の知れた仲間意識があるから,正面から対立するより,否
を認めた方が相手も許してくれる
◎「済みません」は一種の防御態勢
◇日本の禊ぎ思考
□水の聖水としての役割
禊ぎ
=「水さそそぎ」「身をそそぐ」
水に物心両面にわたる汚れを洗い流す浄化作業(霊威)がある
と信じられている
◎四大宗教
水の聖水としての役割
□禊ぎの始まり
イザナギ
□喪に服するも禊ぎである
神社
- 死穢を忌む風習
伊勢神宮は僧侶の参宮を許さなかった
- 死者の葬送
禊ぎに塩=海水の象徴(清めの塩)
喪に服す
最小単位七日間 初七日
14,21,28,49日
◎必ず水辺で禊ぎ 精進落とし
□禊ぎは悪霊退散のおまじない
盛り塩 豆まき 流し雛
☆池田潔「自由と規律」 岩波新書 1949年 ①【再掲載 2017.2】
[出版社の案内]
ケンブリッジ,オックスフォードの両大学は,英国型紳士修業と結びつい
て世界的に有名だが,あまり知られていないその前過程のパブリック・ス
クールこそ,イギリス人の性格形成に基本的な重要性をもっている.若き
日をそこに学んだ著者は,自由の精神が厳格な規律の中で見事に育まれて
ゆく教育システムを,体験を通して興味深く描く
◇パブリックスクールの本質と起源
□イギリス人文史
= 個人の自由獲得の歴史
□イギリス産業史
= 自由企業確立を目的とした不断の闘争
富の原動力は鉄と石炭
□パブリックスクール
スパルタ式教育
精神と肉体の訓練
→ 卒業後 ケンブリッジ,オックスフォード大へ
□イートン校
「ウォータールーの戦勝はイートン校の校庭において獲得された」
□イギリスの学校制度
①公立 エレメンタリースクール → グラマースクール
②私立 プレップスクール → パブリックスクール
(寄宿制) (寄宿制)
□高等教育卒業生は政界,学界,教職,僧職,軍,官界上層へ
実業世界へはまれ
□パブリックスクールの起源
1387年 ウィンチェスター校 オックスフォード・ニューカレージのため
1446年 イートン校
ケンブリッジ・キングスカレージのため
創立当初は予備校
→ 現在は入試必要
16世紀僧院没落
→ 施設基金を教育目的に利用
- 中世パブリックスクール
中世パブリックスクール
ラグビー校,イートン校,ハロー校,ストニーハースト校等
近世パブリックスクール
ウェリントン校,リース校等
◇パブリックスクールの制度
□1902年 教育法令
官公立
エレメンタリースクール(初等)グラマースクール(中等)
庶民学校
基本知識 + 職業教育
→ 社会に出るか師範学校・専門学校へ
極めて優秀な者のみ諸大学へ
実社会
プロフェッションを除いては,高等教育必要なし
- 学校は高度の学問を修める者のための施設観しっかり
かつて商工階級
物質主義的人生観
- 文化教養を蔑視
教育とは「必要でさえない害毒」
1870年 一大改革
1876年 義務教育制度
1899年 教育局
1902年 教育法令 ランカスター・ベルの尽力
↑↓
私立
全校寄宿制度 寄付と高額な授業料・寄宿料
プレパトリースクール(初等)パブリックスクール(中等)
家庭の躾
→ 家庭教師
→ プレップスクール
地方・様々な規模 学校の色・寄宿生活
在学年限規定なし
試験によりパブリックスクールへ
→パブリックスクール
14~19世紀私財を以て経営され,全員寄宿制度によって
指導階級の子弟に中等教育を施す私立のグラマースクール
イングランドに31 スコットランドに4
修了後 オックスフォード・ケンブリッジ大学
(大学は古代二大学に限られる=伝統尊重)
陸軍士官学校・海軍士官学校へ
樋口清之さんはこんなことを④-「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」樋口清之監修 豊島健吾著 大和書房 1988年 /「文系学部廃止の衝撃」吉見俊哉 集英社新書 2016年 ①【再掲載 2017.2】 [読書記録 歴史]
今日は4月17日、水曜日です。
今回は、4月14日に続いて「樋口清之さんはこんなことを」4回目、
「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」を紹介します。
30年以上前に出された本ですが、
書かれている内容は古くはなっていません。
見られなくなったり、忘れられつつあるものが多いのですが。
「言い伝え」られることが失われつつあることをさびしく感じます。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「自然の石は神の拠り所」
・「肩車は土を踏まないことにより神聖を保つことから」
・「門付け(家の門口を訪ね、簡単な藝や祝詞を述べて金や米の報酬を得
る)」
- 子供の頃、毎年来ていた「獅子舞」。こわかったなあ。
・「地神(チジン ジシン ジノカミ ジヌシサマ)は屋敷神として屋敷の西
北北隅や小区画につくられたほこら。その人が死んでから33年ある
いは50年経つと地神になると伝えられる」
- 遠州地方では、まだまだ残っています。
・「綱引きは歳占いの神事。二つの集落で勝負し、勝った方が豊作とさ
れる。綱は神の使いの蛇とされる」
もう一つ、再掲載になりますが、吉見俊哉さんの
「文系学部廃止の衝撃」①を載せます。
- 日本学術会議が2001年に「21世紀における人文・社会科学の役割と
その重要性」声明
2020年の「日本学術会議問題」を思い出しました。
☆樋口清之さんはこんなことを④-「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」樋口清之監修 豊島健吾編著 大和書房 1988年

◇挨拶
前にあるものを押しのけて進むこと
禅宗「一挨一拶」
禅僧が押し問答をして悟りの度合いを確かめること
→ 問答 返答 応答
以前は「モノイ」
物言い
朝 おはよう
昼 飲みましたか お茶あがり おせんどさん
夕方 おしまいな
暗い おばんでござります
◇雨乞い
呪法
① おこもり
② 雨乞い踊り
③ 貰い水
④ 神を怒らす
⑤ 女相撲
⑥ 百升洗い
⑦ 千歯焚き
◇石上
いしがみ シャクジ
自然の石
= 神の拠り所
◇狼
ヤマイヌ
山住神社 - 狼を大口真神
◇肩車
土を踏まないことにより神聖を保つ
神祭り参加
… 馬 肩車
◇河童
水神少童
◇門付け
家の門口を訪ね、簡単な藝や祝詞を述べて金や米の報酬を得る
正月・小正月
万歳、春駒、鳥追い
◇外道
元仏教用語
仏の教えを受けない者 = 邪教
外道
モグラより大きくネズミより小さい動物
◇庚申信仰
60年 60日以外の庚申の日に行われる信仰行事
= 中国・道教の説
人間体内に三尸(さんし)の虫がいて庚申の日の夜睡眠中の体
内から抜け出して天に昇り天帝にその人の罪過を告げるから、早
死にする
◎長生きするには身を慎んで徹夜せよ
徹夜 = 守庚申
奈良時代から酒食の宴
江戸期 - 全国各地に庚申講
◇五月節供
田植えの月
= 一年中もっとも重要な月
五月五日
女の家 女の宿 女の夜
◇座頭
僧形盲人
- 語り物・謡・浄瑠璃・お祓い・按摩・針灸
盲人団体
-「当道」 検校・別当・匂当・座頭 の四段階
◇地神
チジン ジシン ジノカミ 死神ジヌシサマ
屋敷神
- 屋敷西北北隅や小区画にほこら
その人が死んでから33年あるいは50年経つと地神になる
= 土地の神 屋敷の守護神
◇憑き物
狐 犬神 ゲドウ トウビョウ 蛇 猫 狸 ゴンボタネ
◎特定の家,人につく
狐持ち 犬神筋 ← 世間から迫害
◇綱引き
歳占い=神事
東日本 - 小正月
西日本 - 盆綱引きとして七月
九州 - 中秋の名月を機会に
◎二つの集落で勝負
- 勝った方が豊作
綱
= 神の使いの蛇
◇手拭い
本来の目的は手を拭うものではなかった
古くはユテ、テサジ、ナガタナ
= 頭にかぶるもの
手拭いをかぶって挨拶した
= 手拭いが霊妙な力
◇冬至
一年の家で最も日照時間が短い月
太陽の光が弱まる時期
= 農耕生活の一種の危機
= 神々を村に迎えて盛大に祝う行事が冬至前後に
冬至の夜
神聖な旅人(弘法大師とする例が多い)が村を訪れて奇蹟をしめ
した
カボチャ・蒟蒻・ユズ湯
◇直会(なおらい)
神に供したものをおろし,祭祀斜や氏子たちがいただくこと
- 現在では神事終了後の宴会を指す
☆「文系学部廃止の衝撃」吉見俊哉 集英社新書 2016年 ①【再掲載 2017.2】

1 瞬く間に広がった「文系学部廃止」報道
□きっかけ
2015.6.8
文科省通知 各法人学長宛
「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」
6月後半
- 報道がエスカレート
□文科省批判の集中砲火
文科省バッシング
7月末~9月
□海外メディア
産業界からも相次ぐ批判
□文科省通知には何が書かれていたのか
「特に教員養成系学部・大学院 人文社会科学部系学部・大学院」
国立大は法人化されてから、まるでかつての社会主義国のように6
年ごとに立てる中期目標・中期計画に縛られている
- 中期計画の達成度で評価され、叱られたり褒められたり
▲ 膨大な時間を割く 2003年~
2「通知」批判背後にある暗黙の前提
□通知内容は一年前に公表されていた
2015.5.27
国立大学法人評価委員会に素案
前年8月に「ミッションの再定義」
□「文系学部廃止」批判の背景
突然の問題視
1 2015年夏の政治状況
安保 - 安倍政権
2 新国立競技場建設問題
3 文科省
2014年と2015年の政治状況変化を読み込まなかった
◎「儲かる理系」対「儲からない文系」という構図
3 分離の不均衡はいつから構造化?
□国立大における文系と理系
□戦争の時代に築かれた理系重視
戦争がない時代は法科系エリート
1910年以降
- ◎即戦力としての軍事力強化の時代
理化学研究所(1917)
土木学会(1914)
日本鉄鋼協会(1915)
ロビー活動
法科系の支配権を理工系が奪還
1940年「科学動員実施計画綱領」に結実
選択と集中 = 総力戦に!
□現在に引き継がれる戦時の研究予算体制
◎ロジック
「戦争に勝つには産業経済力の増強しかなく、それには大学の研
究力を強化しなければならない」
- そもそも、勝てるのかという目的自体を客観的に批判する視
点は生まれてこない
◎高度経済成長によってさらに強まる理系優先
岸信介内閣の松田竹千代文部大臣
「国立大の法文系を全廃してそれらはすべて私立に任せ国公立は
理工系中心に構成していくべきだ」
国立大
理系は定員増
文系は定員数抑制
□ポスト高度成長期にも継続する理系中心の体制
1970 80年代以降
◎ 理系は政策的に保護され、
手厚い予算から文系は保護から外され続けた
□理系偏重の科学技術政策に対する問題提起
日本学術会議 2001年
「21世紀における人文・社会科学の役割とその重要性」声明
今回は、4月14日に続いて「樋口清之さんはこんなことを」4回目、
「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」を紹介します。
30年以上前に出された本ですが、
書かれている内容は古くはなっていません。
見られなくなったり、忘れられつつあるものが多いのですが。
「言い伝え」られることが失われつつあることをさびしく感じます。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「自然の石は神の拠り所」
・「肩車は土を踏まないことにより神聖を保つことから」
・「門付け(家の門口を訪ね、簡単な藝や祝詞を述べて金や米の報酬を得
る)」
- 子供の頃、毎年来ていた「獅子舞」。こわかったなあ。
・「地神(チジン ジシン ジノカミ ジヌシサマ)は屋敷神として屋敷の西
北北隅や小区画につくられたほこら。その人が死んでから33年ある
いは50年経つと地神になると伝えられる」
- 遠州地方では、まだまだ残っています。
・「綱引きは歳占いの神事。二つの集落で勝負し、勝った方が豊作とさ
れる。綱は神の使いの蛇とされる」
もう一つ、再掲載になりますが、吉見俊哉さんの
「文系学部廃止の衝撃」①を載せます。
- 日本学術会議が2001年に「21世紀における人文・社会科学の役割と
その重要性」声明
2020年の「日本学術会議問題」を思い出しました。
☆樋口清之さんはこんなことを④-「日本人の『言い伝え』もの知り辞典」樋口清之監修 豊島健吾編著 大和書房 1988年

◇挨拶
前にあるものを押しのけて進むこと
禅宗「一挨一拶」
禅僧が押し問答をして悟りの度合いを確かめること
→ 問答 返答 応答
以前は「モノイ」
物言い
朝 おはよう
昼 飲みましたか お茶あがり おせんどさん
夕方 おしまいな
暗い おばんでござります
◇雨乞い
呪法
① おこもり
② 雨乞い踊り
③ 貰い水
④ 神を怒らす
⑤ 女相撲
⑥ 百升洗い
⑦ 千歯焚き
◇石上
いしがみ シャクジ
自然の石
= 神の拠り所
◇狼
ヤマイヌ
山住神社 - 狼を大口真神
◇肩車
土を踏まないことにより神聖を保つ
神祭り参加
… 馬 肩車
◇河童
水神少童
◇門付け
家の門口を訪ね、簡単な藝や祝詞を述べて金や米の報酬を得る
正月・小正月
万歳、春駒、鳥追い
◇外道
元仏教用語
仏の教えを受けない者 = 邪教
外道
モグラより大きくネズミより小さい動物
◇庚申信仰
60年 60日以外の庚申の日に行われる信仰行事
= 中国・道教の説
人間体内に三尸(さんし)の虫がいて庚申の日の夜睡眠中の体
内から抜け出して天に昇り天帝にその人の罪過を告げるから、早
死にする
◎長生きするには身を慎んで徹夜せよ
徹夜 = 守庚申
奈良時代から酒食の宴
江戸期 - 全国各地に庚申講
◇五月節供
田植えの月
= 一年中もっとも重要な月
五月五日
女の家 女の宿 女の夜
◇座頭
僧形盲人
- 語り物・謡・浄瑠璃・お祓い・按摩・針灸
盲人団体
-「当道」 検校・別当・匂当・座頭 の四段階
◇地神
チジン ジシン ジノカミ 死神ジヌシサマ
屋敷神
- 屋敷西北北隅や小区画にほこら
その人が死んでから33年あるいは50年経つと地神になる
= 土地の神 屋敷の守護神
◇憑き物
狐 犬神 ゲドウ トウビョウ 蛇 猫 狸 ゴンボタネ
◎特定の家,人につく
狐持ち 犬神筋 ← 世間から迫害
◇綱引き
歳占い=神事
東日本 - 小正月
西日本 - 盆綱引きとして七月
九州 - 中秋の名月を機会に
◎二つの集落で勝負
- 勝った方が豊作
綱
= 神の使いの蛇
◇手拭い
本来の目的は手を拭うものではなかった
古くはユテ、テサジ、ナガタナ
= 頭にかぶるもの
手拭いをかぶって挨拶した
= 手拭いが霊妙な力
◇冬至
一年の家で最も日照時間が短い月
太陽の光が弱まる時期
= 農耕生活の一種の危機
= 神々を村に迎えて盛大に祝う行事が冬至前後に
冬至の夜
神聖な旅人(弘法大師とする例が多い)が村を訪れて奇蹟をしめ
した
カボチャ・蒟蒻・ユズ湯
◇直会(なおらい)
神に供したものをおろし,祭祀斜や氏子たちがいただくこと
- 現在では神事終了後の宴会を指す
☆「文系学部廃止の衝撃」吉見俊哉 集英社新書 2016年 ①【再掲載 2017.2】
1 瞬く間に広がった「文系学部廃止」報道
□きっかけ
2015.6.8
文科省通知 各法人学長宛
「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」
6月後半
- 報道がエスカレート
□文科省批判の集中砲火
文科省バッシング
7月末~9月
□海外メディア
産業界からも相次ぐ批判
□文科省通知には何が書かれていたのか
「特に教員養成系学部・大学院 人文社会科学部系学部・大学院」
国立大は法人化されてから、まるでかつての社会主義国のように6
年ごとに立てる中期目標・中期計画に縛られている
- 中期計画の達成度で評価され、叱られたり褒められたり
▲ 膨大な時間を割く 2003年~
2「通知」批判背後にある暗黙の前提
□通知内容は一年前に公表されていた
2015.5.27
国立大学法人評価委員会に素案
前年8月に「ミッションの再定義」
□「文系学部廃止」批判の背景
突然の問題視
1 2015年夏の政治状況
安保 - 安倍政権
2 新国立競技場建設問題
3 文科省
2014年と2015年の政治状況変化を読み込まなかった
◎「儲かる理系」対「儲からない文系」という構図
3 分離の不均衡はいつから構造化?
□国立大における文系と理系
□戦争の時代に築かれた理系重視
戦争がない時代は法科系エリート
1910年以降
- ◎即戦力としての軍事力強化の時代
理化学研究所(1917)
土木学会(1914)
日本鉄鋼協会(1915)
ロビー活動
法科系の支配権を理工系が奪還
1940年「科学動員実施計画綱領」に結実
選択と集中 = 総力戦に!
□現在に引き継がれる戦時の研究予算体制
◎ロジック
「戦争に勝つには産業経済力の増強しかなく、それには大学の研
究力を強化しなければならない」
- そもそも、勝てるのかという目的自体を客観的に批判する視
点は生まれてこない
◎高度経済成長によってさらに強まる理系優先
岸信介内閣の松田竹千代文部大臣
「国立大の法文系を全廃してそれらはすべて私立に任せ国公立は
理工系中心に構成していくべきだ」
国立大
理系は定員増
文系は定員数抑制
□ポスト高度成長期にも継続する理系中心の体制
1970 80年代以降
◎ 理系は政策的に保護され、
手厚い予算から文系は保護から外され続けた
□理系偏重の科学技術政策に対する問題提起
日本学術会議 2001年
「21世紀における人文・社会科学の役割とその重要性」声明



