「梅原猛の授業 道徳」梅原猛 朝日新聞社 2003年 ③(最終) /「学校の役割は終わったのか」NHK出版 2001年 ⑤【再掲載 2012.7】 [読書記録 教育]
今回は、11月27日に続いて、梅原猛さんの
「梅原猛の授業 道徳」3回目の紹介 最終です。
出版社の著者紹介には
「大ベストセラー『梅原猛の授業 仏教』につづくシリーズ第二作で、哲学者
は、道徳をテーマに選びました。前巻と同じく、京都の洛南中学での授業
をもとにまとめた、難しいことをわかりやすく解説する絶好の入門書。
中学生、高校生はもちろん、その親たちまで、だれが読んでも大丈夫。現
代の日本人にとって、何が大切なのか、何を中心に生きていくべきなのか。
生半可な知識をもとにした凡百の生き方書とは異なる、深い学識と洞察に
もとづく必読書。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「仏教-不妄語戒 神道-清明心 儒教-巧言令色、鮮し仁」
・「偽善という嘘 - 政治家 教育者 宗教者」
・「逆境の時どう気持ちに答えるかで人生の価値が決まる」
・「忍辱(にんにく)の徳 立派な人は不遇なときに昂然とし、得意なとき
になにか自分の成功はまちがいないではないかと反省しているもの」
・「近代は人間の欲望を神とした。近代文明には畏敬の心が欠如」
もう一つ、再掲載になりますが、
「学校の役割は終わったのか」⑤を載せます。
出版から20年以上となりますが、課題は残ったままだと感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「梅原猛の授業 道徳」梅原猛 朝日新聞社 2003年 ③(最終)
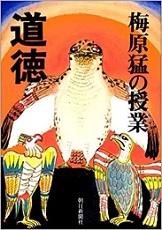
◇第七時限 第二の戒律 嘘をついてはいけない
□第二の戒律 「嘘をついてはいけない」
仏教 不妄語戒
神道 清明心~ ~命名「清」「誠」
儒教 巧言令色、鮮し仁
□人の世を明るくする嘘は許される?
芸術は嘘?
宗教も嘘?
許せない嘘
- 人を騙す嘘
□嘘が当たり前になった社会
偽善という嘘
- 政治家 教育者 宗教者
追従 おべっか
「必ずしも真実を言う必要はありません」
□生一本で嘘をつけない坊ちゃん
漱石 - 文学は4つ
= 真、善、美、荘厳
□日本の将来を予言した漱石
明治という新時代への批判
◇第八限 「よだかの星」と「坊ちゃん」
□よだかの人生には悔いが残る
生きとし生けるものの悲しい気持ち
□正義感は強いが短気な坊ちゃん
□坊ちゃんはエゴイストで無鉄砲
□真正直な人間こそが必要とされる
「清」に対する愛情
◇第九時限 第三の戒律 「盗みをしてはいけない」
□第三の戒律
「盗みをしてはいけない」
□選ばれた人間であるという傲慢
「オディプス王」「平家物語」
□反面教師としての太宰治の生き方
「やけになってはいけない」
逆境の時どう気持ちに答えるかで人生の価値が決まる
□企業の詐欺が資本主義を危うくする
エンロン、ワールドカケ
◇第十時 人生をよりよく生きるために 1 努力と創造
□天才とは努力する才能である
二宮尊徳と楠木正成 尊徳「勤勉」
◇第11時限 人生をよりよく生きるために 2 愛と信
□倫理学
… 道徳を研究する学問
□恋愛は高貴な魂を持つ人間の行い
恋は燃え上がる
□信の関係があって義務がある
家庭
~ 愛
職場
~ 信 儒教 = 信のためには仁が必要
□×「教育勅語に帰れ」
忍辱(にんにく)の徳
= 辱めを忍べ
立派な人は不遇なときに昂然とし、得意なときになにか自分の
成功はまちがいないではないかと反省しているもの
□家庭の愛と職場の信を両立させる
カント 義務が中心
|
独身 妻や子どもを愛せないような人間はどこかまずい
◇第十二時限 人生をよりよく生きるために 3 感謝と哀れみ
□この世とあの世を旅している
人間は死んでもまたいつか帰ってくる
→ 6世紀仏教 浄土教 この世とあの世の無限従順
□大切なのは永遠や絶対という考え方
キリスト教
あの世とこの世の往復は一回 裁判
近代人の信仰
自我信仰、人間信仰、と進歩信仰
□近代は人間の欲望を神とした
□近代文明には畏敬の心が欠如
□自利利他 のこころを表した四弘 際限
☆「学校の役割は終わったのか」NHK出版 2001年 ⑤【再掲載 2012.7】

◇学習指導要領・教科書検定とは何か(2)
□教科書検定は何のためにあるのか
文部科学省
「一種類の国定教科書しか認めなかった画一主義を排し、民間のつくる
多様な教科書を使っていくために内容のチェックを行う」
チェック項目
・ 学習指導要領を過不足無く取り上げているか
・ 発達段階に沿っているか
・ 政治宗教の扱いが公正か
・ 一面的見解を十分な配慮無く取り上げていないか
・ 図書の内容は厳選されているか
・ 誤り、不正確なところ、相互矛盾の場所はないか
∥
基本は学習指導要領への準拠制のチェック
□検定システムのあらまし
4年サイクル
① 申請
② 調査 教科調査官約50名
③ 審査 教科用図書検定調査審議会 120名 10部会
※ 97~98%が「合否の判定保留」
→ 検定意見の通知
※ 修正表
「最初の記述」→「検定意見」→「修正後の記述」3段階
↓
◎ 修正内容の審査
□教科書検定の法的根拠と論争
法的根拠
1947年の学校教育法
論争
東京教育大学 家永三郎「家永裁判」
教育権論争
最高裁「検定制度は合憲」しかし行きすぎがあってはならない
「杉本判決」
1982年 「侵略進出」問題
1986年「新編日本史」問題
2001年 「つくる会」問題
□教科書は誰が選んでいるのか
市町村教委
地教行法 23条6項
教科書発行法7条1項
4年に一度選択がえ
都道府県教委により採択地区が決められている
「広域採択」- 採択地区協議会 - 選定委員会(調査員)
↓
各都道府県教委に報告 → 文部大臣に報告
小中高で151000000冊
小中無償 441億円 発行社 63社
□「教師外し」か「採択手続きの適正化」か
「絞り込み」ある程度絞り込む
「学校票」 ◎廃止の動き = 教師外し
文部省 1990.3.26 通知
2000.9 学校票廃止の指導
|
重要なのは「公正さ」
任免制下の教育委員会による採択が民意に基づくと言えるのか?
□教科書問題は「教育権論争」
大人たちが「教育権」を主張しあう内に当の子供たちは教育自体にそっぽ
を向き始めている
= 「子供の置き去り」
◇悩める教師たちの現状
春政春
1949生 大阪大大学院教授(教育社会学)
黒沼克史
1955生 ノンフィクションライター 筑波大卒
□多忙によるストレス 72%の教師がストレス感
① 多忙
② 研究授業
③ 自分の力
④ 行事準備
⑤ 校務分掌
◎ 新たな指導が座布団のように積み重なる状態
□子供を取り巻く環境の変化
どこまでやってもきりがない。基準が無くゴールが見えにくい
∥
◎ 達成感を得にくい職業
コミュニケーションをとりにくい
「なめられている」感覚
□疲れ果てる教師
◎ 多様化する子供たちの問題行動を前に教師たちは疲れ果て追い詰められ
ている
「向いていない。やめたい…」
教育行政の不備
教育行政として新しいものを導入するならば当然条件整備をしなけれ
ばならない
= 制度改革とセットで
□「5時までが勝負」
課題解決のキーワードは?
①「学級王国」から「地域」へ
②「5時までが勝負」
- 優先順位を!
「梅原猛の授業 道徳」3回目の紹介 最終です。
出版社の著者紹介には
「大ベストセラー『梅原猛の授業 仏教』につづくシリーズ第二作で、哲学者
は、道徳をテーマに選びました。前巻と同じく、京都の洛南中学での授業
をもとにまとめた、難しいことをわかりやすく解説する絶好の入門書。
中学生、高校生はもちろん、その親たちまで、だれが読んでも大丈夫。現
代の日本人にとって、何が大切なのか、何を中心に生きていくべきなのか。
生半可な知識をもとにした凡百の生き方書とは異なる、深い学識と洞察に
もとづく必読書。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「仏教-不妄語戒 神道-清明心 儒教-巧言令色、鮮し仁」
・「偽善という嘘 - 政治家 教育者 宗教者」
・「逆境の時どう気持ちに答えるかで人生の価値が決まる」
・「忍辱(にんにく)の徳 立派な人は不遇なときに昂然とし、得意なとき
になにか自分の成功はまちがいないではないかと反省しているもの」
・「近代は人間の欲望を神とした。近代文明には畏敬の心が欠如」
もう一つ、再掲載になりますが、
「学校の役割は終わったのか」⑤を載せます。
出版から20年以上となりますが、課題は残ったままだと感じます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「梅原猛の授業 道徳」梅原猛 朝日新聞社 2003年 ③(最終)
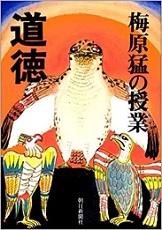
◇第七時限 第二の戒律 嘘をついてはいけない
□第二の戒律 「嘘をついてはいけない」
仏教 不妄語戒
神道 清明心~ ~命名「清」「誠」
儒教 巧言令色、鮮し仁
□人の世を明るくする嘘は許される?
芸術は嘘?
宗教も嘘?
許せない嘘
- 人を騙す嘘
□嘘が当たり前になった社会
偽善という嘘
- 政治家 教育者 宗教者
追従 おべっか
「必ずしも真実を言う必要はありません」
□生一本で嘘をつけない坊ちゃん
漱石 - 文学は4つ
= 真、善、美、荘厳
□日本の将来を予言した漱石
明治という新時代への批判
◇第八限 「よだかの星」と「坊ちゃん」
□よだかの人生には悔いが残る
生きとし生けるものの悲しい気持ち
□正義感は強いが短気な坊ちゃん
□坊ちゃんはエゴイストで無鉄砲
□真正直な人間こそが必要とされる
「清」に対する愛情
◇第九時限 第三の戒律 「盗みをしてはいけない」
□第三の戒律
「盗みをしてはいけない」
□選ばれた人間であるという傲慢
「オディプス王」「平家物語」
□反面教師としての太宰治の生き方
「やけになってはいけない」
逆境の時どう気持ちに答えるかで人生の価値が決まる
□企業の詐欺が資本主義を危うくする
エンロン、ワールドカケ
◇第十時 人生をよりよく生きるために 1 努力と創造
□天才とは努力する才能である
二宮尊徳と楠木正成 尊徳「勤勉」
◇第11時限 人生をよりよく生きるために 2 愛と信
□倫理学
… 道徳を研究する学問
□恋愛は高貴な魂を持つ人間の行い
恋は燃え上がる
□信の関係があって義務がある
家庭
~ 愛
職場
~ 信 儒教 = 信のためには仁が必要
□×「教育勅語に帰れ」
忍辱(にんにく)の徳
= 辱めを忍べ
立派な人は不遇なときに昂然とし、得意なときになにか自分の
成功はまちがいないではないかと反省しているもの
□家庭の愛と職場の信を両立させる
カント 義務が中心
|
独身 妻や子どもを愛せないような人間はどこかまずい
◇第十二時限 人生をよりよく生きるために 3 感謝と哀れみ
□この世とあの世を旅している
人間は死んでもまたいつか帰ってくる
→ 6世紀仏教 浄土教 この世とあの世の無限従順
□大切なのは永遠や絶対という考え方
キリスト教
あの世とこの世の往復は一回 裁判
近代人の信仰
自我信仰、人間信仰、と進歩信仰
□近代は人間の欲望を神とした
□近代文明には畏敬の心が欠如
□自利利他 のこころを表した四弘 際限
☆「学校の役割は終わったのか」NHK出版 2001年 ⑤【再掲載 2012.7】

◇学習指導要領・教科書検定とは何か(2)
□教科書検定は何のためにあるのか
文部科学省
「一種類の国定教科書しか認めなかった画一主義を排し、民間のつくる
多様な教科書を使っていくために内容のチェックを行う」
チェック項目
・ 学習指導要領を過不足無く取り上げているか
・ 発達段階に沿っているか
・ 政治宗教の扱いが公正か
・ 一面的見解を十分な配慮無く取り上げていないか
・ 図書の内容は厳選されているか
・ 誤り、不正確なところ、相互矛盾の場所はないか
∥
基本は学習指導要領への準拠制のチェック
□検定システムのあらまし
4年サイクル
① 申請
② 調査 教科調査官約50名
③ 審査 教科用図書検定調査審議会 120名 10部会
※ 97~98%が「合否の判定保留」
→ 検定意見の通知
※ 修正表
「最初の記述」→「検定意見」→「修正後の記述」3段階
↓
◎ 修正内容の審査
□教科書検定の法的根拠と論争
法的根拠
1947年の学校教育法
論争
東京教育大学 家永三郎「家永裁判」
教育権論争
最高裁「検定制度は合憲」しかし行きすぎがあってはならない
「杉本判決」
1982年 「侵略進出」問題
1986年「新編日本史」問題
2001年 「つくる会」問題
□教科書は誰が選んでいるのか
市町村教委
地教行法 23条6項
教科書発行法7条1項
4年に一度選択がえ
都道府県教委により採択地区が決められている
「広域採択」- 採択地区協議会 - 選定委員会(調査員)
↓
各都道府県教委に報告 → 文部大臣に報告
小中高で151000000冊
小中無償 441億円 発行社 63社
□「教師外し」か「採択手続きの適正化」か
「絞り込み」ある程度絞り込む
「学校票」 ◎廃止の動き = 教師外し
文部省 1990.3.26 通知
2000.9 学校票廃止の指導
|
重要なのは「公正さ」
任免制下の教育委員会による採択が民意に基づくと言えるのか?
□教科書問題は「教育権論争」
大人たちが「教育権」を主張しあう内に当の子供たちは教育自体にそっぽ
を向き始めている
= 「子供の置き去り」
◇悩める教師たちの現状
春政春
1949生 大阪大大学院教授(教育社会学)
黒沼克史
1955生 ノンフィクションライター 筑波大卒
□多忙によるストレス 72%の教師がストレス感
① 多忙
② 研究授業
③ 自分の力
④ 行事準備
⑤ 校務分掌
◎ 新たな指導が座布団のように積み重なる状態
□子供を取り巻く環境の変化
どこまでやってもきりがない。基準が無くゴールが見えにくい
∥
◎ 達成感を得にくい職業
コミュニケーションをとりにくい
「なめられている」感覚
□疲れ果てる教師
◎ 多様化する子供たちの問題行動を前に教師たちは疲れ果て追い詰められ
ている
「向いていない。やめたい…」
教育行政の不備
教育行政として新しいものを導入するならば当然条件整備をしなけれ
ばならない
= 制度改革とセットで
□「5時までが勝負」
課題解決のキーワードは?
①「学級王国」から「地域」へ
②「5時までが勝負」
- 優先順位を!
「こうして彼らは不登校から翔びたった」比嘉昇 ウェッジ 2011年 ②(後半) /「自分を磨く読書術」ハイブロー武蔵 2007年 ② 【再掲載 2013.6】 [読書記録 教育]
今回は、11月26日に続いて比嘉昇さんの
「こうして彼らは不登校から翔びたった」2回目(後半)の紹介です。
今回も目次のような要約になってしまった。あああとため息。
出版社の著者紹介には
「信じる、待つ、愛する−。フリースクールで10年間見守ってきた不登校の
子どもたちとの心の交流を綴る。月刊誌『ウェッジ』連載の『子どもは変わ
る大人も変わる』をもとに再編集。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「『冬』の語源は『殖ゆ』」
・「大人は子どもの時間泥棒」
・「丸ごと認めることが愛情の原点。保健室の養護教諭はテストしない、相対
評価しない」
・「『戦争とはあなたの愛する人が死ぬと言うこと』美輪明宏」
・「日本の親子、捨てたものじゃない」
もう一つ、再掲載になりますが、ハイブロー武蔵さんの
「自分を磨く読書術」②を載せます。
自分の自由になる半日があるにもかかわらず、
畑作業、片付け等に追われて読書の時間が少なくなってしまっています。
確保する工夫を考えます。まずは、隙間読書から。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「こうして彼らは不登校から翔びたった」比嘉昇 ウェッジ 2011年 ②(後半)
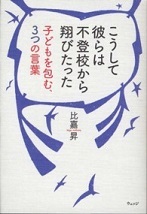
◇第2章 待つ
□久美の冬、久美の春
「冬」の語源は「殖ゆ」
□大人の建前と子どもの本音
□今日はここまでできればいい
□大人は子どもの時間泥棒
「人は人なか 木は木なか」
□宿題は「テレビを見ないこと」
□押さえつけられても生きる力は育たない
□焦らなくていい 時間という未来がある
□子どもの教育は投資じゃない
人的な「投資対象」としてとらえているのか?
□仲介役から卒業した美帆
□二人の教え子の結婚式
◇第3章 愛する
□朋玄は「わが家の居候」
□丸ごと認めることが愛情の原点
保健室 ~ 養護教諭はテストしない 相対評価しない
□駿が抱いた小さな夢
□食欲は生きる意欲
□聖平を支えた「食べるなアカン」
□働くことの意味って
□高校生だから抱く疑問
□子どもたちに誓う「命こそ宝」
□人を死に追いやる日本の現実
□平和な社会へ、大人たちの責任
「戦争とはあなたの愛する人が死ぬと言うこと」
『戦争と平和愛のメッセージ』美輪明宏 岩波書店
□親の過剰なコントロール
□外で遊べよ子どもたち
□夏休みだからできること
□井村コーチは明るく厳しく
□欲求は子どもが生きる源
□忘れちゃいけない感謝の気持ち
□損得なしに生きる人たち
「教員駆け込み寺・大阪」
□歴史を暗記科目にしないでほしい
□ねじれて親子関係
□愛情の確かなバトンタッチ
□日本の親子、捨てたものじゃない
※月刊「ウエッジ」
☆「自分を磨く読書術」ハイブロー武蔵 2007年 ② 【再掲載 2013.6】
[出版社の案内]
人は本で変われる。芽が出る人、成長する人、花を咲かせる人になる。
ハイブロー流読書指導。

◇人間関係によく効く読書
真にいい男,いい女になる
藤沢周平『蝉しぐれ』
相手が喜ぶのがうれしい…という大原則
つき合っている人と,読んでいる本で,その人が見える
つき合う異性が自分の品格を決める
本好きの明るい女性が人を伸ばす
恋する人の存在が人を伸ばす
「思いの強さ + あきらめない実践力」
広瀬武夫
キャプテン・ジャック・スパロウの魅力
華やかに見える人ほど,辛いことも多いことを知る
小林勇『人はさびしき』
◇視野を広げ心を大きくする読書
読書が国を支える 読書力は国力である
スマイルズ『自助論』(『西国立志篇』)
福沢諭吉『学問のすすめ』
文化の敵
「文筆家というのは文章の持つ温かい力を信じる人種」村上春樹
アリさんと同じ人生でいいのか
神谷美恵子『生きがいについて』
読書量を誇る人になってはならない
平凡の繰り返しが非凡になる
森信三
「一日読書を怠ると一日分人間がダメになる」
門田隆将『甲子園への遺言』
伝説の打撃コーチ 高畠氏 「平凡の繰り返しが非凡になる」
58歳で教育実習 - 福岡県・筑紫台高校
高畠さんが考える伸びる人の共通点
① 素直であること
② 好奇心旺盛であること
③ 忍耐力があり,あきらめないこと
④ 準備を怠らないこと
⑤ 几帳面であること
⑥ 気配りができること
⑦ 夢を持ち,目標を高く設定することができること
<旅+読書>が人の器を大きくする
日記と手紙を書こう
「気まま日記」
挫折を知る人の読書はひと味違う
◇人生に勇気と愛を
好きな人を励まし,社会を元気づけよ
失えばそれに見合ったパワーが生まれる。それをどう生かしていくかが
問題だ
北方謙三『水滸伝』
『風と共に去りぬ』
自分を愛すこと,人を愛すること,そして読書すること
人生を支える本 ブックガイド
松下幸之助『道をひらく』
フランクリン『フランクリン自伝』
武者小路実篤『愛と死』『友情』
藤沢周平『蝉しぐれ』
ソロ『森の生活』
カーター『リトル・トリー』
山本常朝『葉隠し』
隆慶一郎『死ぬることと見つけたり』
司馬遼太郎『龍馬がゆく』
勝海舟
◇ハイブロー武蔵 1954福岡生
「こうして彼らは不登校から翔びたった」2回目(後半)の紹介です。
今回も目次のような要約になってしまった。あああとため息。
出版社の著者紹介には
「信じる、待つ、愛する−。フリースクールで10年間見守ってきた不登校の
子どもたちとの心の交流を綴る。月刊誌『ウェッジ』連載の『子どもは変わ
る大人も変わる』をもとに再編集。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「『冬』の語源は『殖ゆ』」
・「大人は子どもの時間泥棒」
・「丸ごと認めることが愛情の原点。保健室の養護教諭はテストしない、相対
評価しない」
・「『戦争とはあなたの愛する人が死ぬと言うこと』美輪明宏」
・「日本の親子、捨てたものじゃない」
もう一つ、再掲載になりますが、ハイブロー武蔵さんの
「自分を磨く読書術」②を載せます。
自分の自由になる半日があるにもかかわらず、
畑作業、片付け等に追われて読書の時間が少なくなってしまっています。
確保する工夫を考えます。まずは、隙間読書から。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「こうして彼らは不登校から翔びたった」比嘉昇 ウェッジ 2011年 ②(後半)
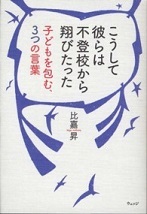
◇第2章 待つ
□久美の冬、久美の春
「冬」の語源は「殖ゆ」
□大人の建前と子どもの本音
□今日はここまでできればいい
□大人は子どもの時間泥棒
「人は人なか 木は木なか」
□宿題は「テレビを見ないこと」
□押さえつけられても生きる力は育たない
□焦らなくていい 時間という未来がある
□子どもの教育は投資じゃない
人的な「投資対象」としてとらえているのか?
□仲介役から卒業した美帆
□二人の教え子の結婚式
◇第3章 愛する
□朋玄は「わが家の居候」
□丸ごと認めることが愛情の原点
保健室 ~ 養護教諭はテストしない 相対評価しない
□駿が抱いた小さな夢
□食欲は生きる意欲
□聖平を支えた「食べるなアカン」
□働くことの意味って
□高校生だから抱く疑問
□子どもたちに誓う「命こそ宝」
□人を死に追いやる日本の現実
□平和な社会へ、大人たちの責任
「戦争とはあなたの愛する人が死ぬと言うこと」
『戦争と平和愛のメッセージ』美輪明宏 岩波書店
□親の過剰なコントロール
□外で遊べよ子どもたち
□夏休みだからできること
□井村コーチは明るく厳しく
□欲求は子どもが生きる源
□忘れちゃいけない感謝の気持ち
□損得なしに生きる人たち
「教員駆け込み寺・大阪」
□歴史を暗記科目にしないでほしい
□ねじれて親子関係
□愛情の確かなバトンタッチ
□日本の親子、捨てたものじゃない
※月刊「ウエッジ」
☆「自分を磨く読書術」ハイブロー武蔵 2007年 ② 【再掲載 2013.6】
[出版社の案内]
人は本で変われる。芽が出る人、成長する人、花を咲かせる人になる。
ハイブロー流読書指導。

◇人間関係によく効く読書
真にいい男,いい女になる
藤沢周平『蝉しぐれ』
相手が喜ぶのがうれしい…という大原則
つき合っている人と,読んでいる本で,その人が見える
つき合う異性が自分の品格を決める
本好きの明るい女性が人を伸ばす
恋する人の存在が人を伸ばす
「思いの強さ + あきらめない実践力」
広瀬武夫
キャプテン・ジャック・スパロウの魅力
華やかに見える人ほど,辛いことも多いことを知る
小林勇『人はさびしき』
◇視野を広げ心を大きくする読書
読書が国を支える 読書力は国力である
スマイルズ『自助論』(『西国立志篇』)
福沢諭吉『学問のすすめ』
文化の敵
「文筆家というのは文章の持つ温かい力を信じる人種」村上春樹
アリさんと同じ人生でいいのか
神谷美恵子『生きがいについて』
読書量を誇る人になってはならない
平凡の繰り返しが非凡になる
森信三
「一日読書を怠ると一日分人間がダメになる」
門田隆将『甲子園への遺言』
伝説の打撃コーチ 高畠氏 「平凡の繰り返しが非凡になる」
58歳で教育実習 - 福岡県・筑紫台高校
高畠さんが考える伸びる人の共通点
① 素直であること
② 好奇心旺盛であること
③ 忍耐力があり,あきらめないこと
④ 準備を怠らないこと
⑤ 几帳面であること
⑥ 気配りができること
⑦ 夢を持ち,目標を高く設定することができること
<旅+読書>が人の器を大きくする
日記と手紙を書こう
「気まま日記」
挫折を知る人の読書はひと味違う
◇人生に勇気と愛を
好きな人を励まし,社会を元気づけよ
失えばそれに見合ったパワーが生まれる。それをどう生かしていくかが
問題だ
北方謙三『水滸伝』
『風と共に去りぬ』
自分を愛すこと,人を愛すること,そして読書すること
人生を支える本 ブックガイド
松下幸之助『道をひらく』
フランクリン『フランクリン自伝』
武者小路実篤『愛と死』『友情』
藤沢周平『蝉しぐれ』
ソロ『森の生活』
カーター『リトル・トリー』
山本常朝『葉隠し』
隆慶一郎『死ぬることと見つけたり』
司馬遼太郎『龍馬がゆく』
勝海舟
◇ハイブロー武蔵 1954福岡生



