「致知」2003年12月号 ① / 森信三さんはこんなことを③「修身教授録抄」森信三 致知出版社 2006年【再掲載 2013.6】 [読書記録 一般]
今回は、月刊誌『致知』の
2003年12月より紹介します。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「読書は心の食物。肉体を養うために毎日の食事が欠かせないように心を豊
かに養う滋養分として読書は欠かせない - 森信三」
・「日本の教育の問題点は人にぬきんでて優れた者をおとしめるという怨望の
情念に市民権を与えてしまったこと - 石井勲 小堀桂一郎」
・「歴史的仮名遣い、正仮名遣いの規準は正しさ。対して、現代仮名遣いの規準
は便利さ」
・「21世紀に向けて今の日本の教育に求められていることは、子どもへの迎
合を絶対にやめろということだとわたしは考えます。子どもはとにかく鍛
えなければいけない。つまり、これは難しいだろう、子どもに負担を掛け
るだろうという配慮は、教育的配慮ではなくて、まさに非教育的配慮なの
です - 小堀桂一郎」
もう一つ、再掲載になりますが、
「森信三さんはこんなことを」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「致知」2003年12月号 ①
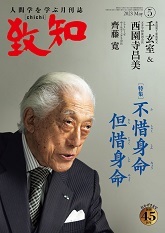
◇丘の上の町
「丘の上の町」の自覚を持て 牛尾治朗
◇特集・読書力
□程伊川
島流し時に読書
西郷隆盛 - 島流し800冊の本
□吉田松陰
野山獄
1年2か月で618冊
幽閉時も
安政3年505冊 安政4年492冊
∥
◎ 読書が人間に大きな力
□森信三
「読書は心の食物。肉体を養うために毎日の食事が欠かせないように心を
豊かに養う滋養分として読書は欠かせない」
「真の読書は人がこれまで体験してきた人生体験の内容と意味を照らし出
して統一する光です。わたしたちは平生、読書を怠らないことによって
常に自分に対する問題を深め、それによって正しい実践のできる人間に
なることが何より肝要です。言い換えれば、読書、内観、実践という段
階の繰り返しは人間が進歩し深められていくプロセスとも言えます」
□安岡正篤
「人物を磨く」ための条件
1 優れた人物に私淑すること
2 魂のこもった優れた書物を読むこと
◇日本語力を復活せよ 石井勲(日本漢字教育学会会長)小堀桂一郎(東大名誉教授)
国語の破壊で崩壊した教育
原因は新仮名遣い
幕末からあった国語問題
左翼が滅ぼす
~ 表音派
アメリカに言い返さなかった日本
GHQ教育使節団
たった3週間、さんざんかき回して帰って行った
→ 火事場泥棒的国語改革
漢字は決して難しくない
・複雑なものの方が関心を持てるし記憶できる
・漢字は「字」でなく「単語」
最初から本物に触れさせる
怨望の支配する日本教育
左翼的人間の持つ世界に向けての恨み辛みの情念から
ゆとり教育は怨望の情念の発露
ぬきんでることで恨み辛みを買うよりは何も知らないその他大勢の
中に入っていた方が気が楽
∥
※ 日本の教育の問題点
人にぬきんでて優れた者をおとしめるという怨望の情念に市民権
を与えてしまったこと
漢字でIQが高くなる
時実利彦
「記憶力は幼児期が一番優れている」
昭和38年
「漢字教育は三歳から」
漢字は想像力を養うのにいい訓練になる
教育の犠牲になった大学生
藤原正彦(お茶の水大学)
「一に国語、二に国語、三、四がなくて五が算数」
・問題は新字体
・売買 - 悪い簡略化
「漢字は心の珠を磨く道具だ」
国語は古典だけで十分
歴史的仮名遣い、正仮名遣い = 正しさが基準
現代仮名遣い = 便利さが基準
|
石井
「子どもが漢字を間違ってもバツをつけない方がよい。一番やる気を
なくさせるのがバツ。それらしく書かれていれば用は足りる」
岡潔が石井に
「あなたは日本のためにとても良いことをやってくれている。漢字は
心の珠を磨く道具だから頑張ってくれ」
国民を逞しく育てる
~ 「万葉集」「古今和歌集」から
石井
「日本中に寺子屋をつくってほしい」
小堀
「21世紀に向けて今の日本の教育に求められていることは、子どもへ
の迎合を絶対にやめろということだとわたしは考えます。子どもはと
にかく鍛えなければいけない。つまり、これは難しいだろう、子ども
に負担を掛けるだろうという配慮は、教育的配慮ではなくて、まさに
非教育的配慮なのです」
|
赤ちゃん
ハイハイ、歩行とできないことに挑戦する
→ 寝ている方が楽だなんていう赤ちゃんは一人もいないだろう
∥
◎ 伸びようとするのが本性
☆森信三さんはこんなことを③「修身教授録抄」森信三 致知出版社 2006年【再掲載 2013.6】
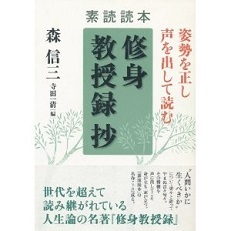
◇生を国土に受けて
<微言1>
「人間としての軌道の三箇条」
① 毎朝親に対してあいさつのできる人間になる
② 親御さんに呼ばれたら「ハイ」と返事のできること
③ 履き物をそろえ,立ったらイスを必ずきちんと言える
◎「常に腰骨を立てる」ことは性根の売る人間になる極秘伝です
◎一旦引き受けた以上,どこまでも責任を果たそうとする男性こそ頼もしい
1 天の命
2 人生態度
3 人身受けがたし
4 生を身の国土に受けて
5 教育の指名
6 安心立命の境涯
7 相手の魂に
8 我が一生の見通し
9 人生の準備期
10 志学とは
11 大学の道
「我十有五にして学に志す」
12 天分の発揮
13 読書の意義
「一日読まざれば一日衰える」
14 偉大な実践家
15 尚友とは
16 同門の友
「朋遠方より来る…」は師を共にした友
17 禽獣と異なる所以
18 真の剛者の道
道徳修養
19 捨欲即大欲
20 使命の道
21 一つの坑道を
一つの坑道を切り開こうとする(はしごを上にのぼるよりも)
22 国家民族の前途
23 偉大な光と力
24 人を植える道
「教育とは人を植える道」
- 学校教育はその地ならし
25 卒業後の指導
有志の青年たちの読書会・会員相互の輪読会
26 共に道を歩む者
- 生徒を見下してはいけない
27 松蔭先生の片鱗
28 人間としてのたしなみ
『葉隠』
29 人間形成の三大要素
① 血
② 育ち
③ 教え
30 性欲の問題
31 真独について
32 仕事の処理
自分の修養
33 成形の功徳
34 唯一人者
35 善悪導者
36 対話の心得
聞く,断定しない
37 謙遜について
我が身を慎んで己を正しく保つということ
38 上位者に対する心得
相手の地位にふさわしい
39 社会組織ということ
上下
40 目下の人に対する心得
敬愛
41 ペスタロッチの命日
42 魂そのものの覚醒
- 教師の信念
43 国民教育者の自覚
44 白河条約公伝
45 白墨の使い方
太い方から使う 芦田恵之助
46 真の誠へのあゆみ
己の務めに打ち込む所から始める
47 生死の問題
死を意識した時から
48 一後一後の種まき
49 次代を担う者たちへ
50 生命の根源を
2003年12月より紹介します。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「読書は心の食物。肉体を養うために毎日の食事が欠かせないように心を豊
かに養う滋養分として読書は欠かせない - 森信三」
・「日本の教育の問題点は人にぬきんでて優れた者をおとしめるという怨望の
情念に市民権を与えてしまったこと - 石井勲 小堀桂一郎」
・「歴史的仮名遣い、正仮名遣いの規準は正しさ。対して、現代仮名遣いの規準
は便利さ」
・「21世紀に向けて今の日本の教育に求められていることは、子どもへの迎
合を絶対にやめろということだとわたしは考えます。子どもはとにかく鍛
えなければいけない。つまり、これは難しいだろう、子どもに負担を掛け
るだろうという配慮は、教育的配慮ではなくて、まさに非教育的配慮なの
です - 小堀桂一郎」
もう一つ、再掲載になりますが、
「森信三さんはこんなことを」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「致知」2003年12月号 ①
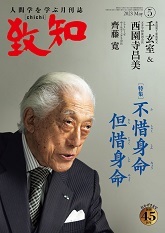
◇丘の上の町
「丘の上の町」の自覚を持て 牛尾治朗
◇特集・読書力
□程伊川
島流し時に読書
西郷隆盛 - 島流し800冊の本
□吉田松陰
野山獄
1年2か月で618冊
幽閉時も
安政3年505冊 安政4年492冊
∥
◎ 読書が人間に大きな力
□森信三
「読書は心の食物。肉体を養うために毎日の食事が欠かせないように心を
豊かに養う滋養分として読書は欠かせない」
「真の読書は人がこれまで体験してきた人生体験の内容と意味を照らし出
して統一する光です。わたしたちは平生、読書を怠らないことによって
常に自分に対する問題を深め、それによって正しい実践のできる人間に
なることが何より肝要です。言い換えれば、読書、内観、実践という段
階の繰り返しは人間が進歩し深められていくプロセスとも言えます」
□安岡正篤
「人物を磨く」ための条件
1 優れた人物に私淑すること
2 魂のこもった優れた書物を読むこと
◇日本語力を復活せよ 石井勲(日本漢字教育学会会長)小堀桂一郎(東大名誉教授)
国語の破壊で崩壊した教育
原因は新仮名遣い
幕末からあった国語問題
左翼が滅ぼす
~ 表音派
アメリカに言い返さなかった日本
GHQ教育使節団
たった3週間、さんざんかき回して帰って行った
→ 火事場泥棒的国語改革
漢字は決して難しくない
・複雑なものの方が関心を持てるし記憶できる
・漢字は「字」でなく「単語」
最初から本物に触れさせる
怨望の支配する日本教育
左翼的人間の持つ世界に向けての恨み辛みの情念から
ゆとり教育は怨望の情念の発露
ぬきんでることで恨み辛みを買うよりは何も知らないその他大勢の
中に入っていた方が気が楽
∥
※ 日本の教育の問題点
人にぬきんでて優れた者をおとしめるという怨望の情念に市民権
を与えてしまったこと
漢字でIQが高くなる
時実利彦
「記憶力は幼児期が一番優れている」
昭和38年
「漢字教育は三歳から」
漢字は想像力を養うのにいい訓練になる
教育の犠牲になった大学生
藤原正彦(お茶の水大学)
「一に国語、二に国語、三、四がなくて五が算数」
・問題は新字体
・売買 - 悪い簡略化
「漢字は心の珠を磨く道具だ」
国語は古典だけで十分
歴史的仮名遣い、正仮名遣い = 正しさが基準
現代仮名遣い = 便利さが基準
|
石井
「子どもが漢字を間違ってもバツをつけない方がよい。一番やる気を
なくさせるのがバツ。それらしく書かれていれば用は足りる」
岡潔が石井に
「あなたは日本のためにとても良いことをやってくれている。漢字は
心の珠を磨く道具だから頑張ってくれ」
国民を逞しく育てる
~ 「万葉集」「古今和歌集」から
石井
「日本中に寺子屋をつくってほしい」
小堀
「21世紀に向けて今の日本の教育に求められていることは、子どもへ
の迎合を絶対にやめろということだとわたしは考えます。子どもはと
にかく鍛えなければいけない。つまり、これは難しいだろう、子ども
に負担を掛けるだろうという配慮は、教育的配慮ではなくて、まさに
非教育的配慮なのです」
|
赤ちゃん
ハイハイ、歩行とできないことに挑戦する
→ 寝ている方が楽だなんていう赤ちゃんは一人もいないだろう
∥
◎ 伸びようとするのが本性
☆森信三さんはこんなことを③「修身教授録抄」森信三 致知出版社 2006年【再掲載 2013.6】
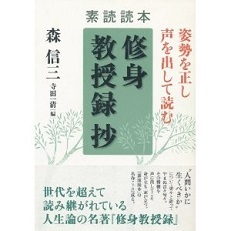
◇生を国土に受けて
<微言1>
「人間としての軌道の三箇条」
① 毎朝親に対してあいさつのできる人間になる
② 親御さんに呼ばれたら「ハイ」と返事のできること
③ 履き物をそろえ,立ったらイスを必ずきちんと言える
◎「常に腰骨を立てる」ことは性根の売る人間になる極秘伝です
◎一旦引き受けた以上,どこまでも責任を果たそうとする男性こそ頼もしい
1 天の命
2 人生態度
3 人身受けがたし
4 生を身の国土に受けて
5 教育の指名
6 安心立命の境涯
7 相手の魂に
8 我が一生の見通し
9 人生の準備期
10 志学とは
11 大学の道
「我十有五にして学に志す」
12 天分の発揮
13 読書の意義
「一日読まざれば一日衰える」
14 偉大な実践家
15 尚友とは
16 同門の友
「朋遠方より来る…」は師を共にした友
17 禽獣と異なる所以
18 真の剛者の道
道徳修養
19 捨欲即大欲
20 使命の道
21 一つの坑道を
一つの坑道を切り開こうとする(はしごを上にのぼるよりも)
22 国家民族の前途
23 偉大な光と力
24 人を植える道
「教育とは人を植える道」
- 学校教育はその地ならし
25 卒業後の指導
有志の青年たちの読書会・会員相互の輪読会
26 共に道を歩む者
- 生徒を見下してはいけない
27 松蔭先生の片鱗
28 人間としてのたしなみ
『葉隠』
29 人間形成の三大要素
① 血
② 育ち
③ 教え
30 性欲の問題
31 真独について
32 仕事の処理
自分の修養
33 成形の功徳
34 唯一人者
35 善悪導者
36 対話の心得
聞く,断定しない
37 謙遜について
我が身を慎んで己を正しく保つということ
38 上位者に対する心得
相手の地位にふさわしい
39 社会組織ということ
上下
40 目下の人に対する心得
敬愛
41 ペスタロッチの命日
42 魂そのものの覚醒
- 教師の信念
43 国民教育者の自覚
44 白河条約公伝
45 白墨の使い方
太い方から使う 芦田恵之助
46 真の誠へのあゆみ
己の務めに打ち込む所から始める
47 生死の問題
死を意識した時から
48 一後一後の種まき
49 次代を担う者たちへ
50 生命の根源を
「東三河完全攻略 はなまる本」プライズメント / ふえる一方の不登校をどうとらるか(中)「心をほどく人間関係の大切さについて」 伊藤友宣(神戸心療親子研究室・主宰) 『月刊少年育成』2001年 ⑥【再掲載 2015.4】 [読書記録 一般]
今回は、プライズメントの
「東三河完全攻略 はなまる本」を紹介します。
プライズメントからは三河地区のフリーペーパーがたくさん出ています。
その関連本だと思いますが、興味あるものを抜粋しました。
記録ミスがあるかもしれません。
御確認ください。
わたしは、巻煎餅が好きで、豊川稲荷参りの時はよく求めます。
「味のヤマスイ」では、よくメヒカリの唐揚げ(冷凍)を購入します。
メヒカリ、なんとも言えないおいしさです。
新城の「ナザレうどん」は浜松の「ナザレ」と何か関連があるのでしょうか。
浜松のナザレさん、近隣学校に勤めていた折、時々出前をしてもらいました。
現在は閉店となったようですが。
もう一つ、再掲載になりますが、伊藤友宣さんの
「心をほどく人間関係の大切さについて」⑥を載せます。
20年以上の前の分掌なのですが、不登校について、
わたしには最もしっくりくるとらえ方です。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「東三河完全攻略 はなまる本」プライズメント
◇豊橋
豊橋公会堂(国登録文化財)
豊橋ハリスト教会(国重文)
トキフ(甘党の店 大手町)
飛騨路(札木町 朴葉ステーキ)
もちや(東新町 モチ入りワラビ餅,栗蒸し羊羹)
◇豊川
喜楽(門前町 宝珠まんじゅう,巻せんべい)
たねや(豊川元町 稲荷寿司でシュー,手筒ロール)
松屋(門前町 味噌カツ稲荷,わさび稲荷)
来恩(門前町 五平餅)
◇蒲郡
えびせん工房(清田町上大内)
味のヤマスイ(形原町港町 海の幸)
◇新城
旅館 ランチ付き温泉
◇田原
伊良湖ガーデンホテル バイキング
サンパルク田原
蔵王山
◇和食
武蔵総本店 みそかつ (豊橋市藤沢町)
大鯛 豊富な料理 (豊橋市上田町新津田)
鈴幸 うなぎまぶし(田原市加治町奥見中)
魚々屋 魚々御前 (豊橋市石巻本町字西野)
くろふね 手頃なランチ(豊橋市浜道町北側)
いちょう なめし田楽 (豊橋市中野町字平)
ナザレうどん (新城市平井字原)
◇中華
茶居那 おすすめランチ (豊橋市藤沢町)
◇イタリアン・洋食
スバゲッ亭チャオ あんかけ鉄板スパ (豊橋市広小路一丁目2F)
コウヨウ館 オムライス (豊橋市二川町字ねずみ池)
こすたりか パスタランチ(豊橋市牛川町)
日付変更線180°E オムライス (豊橋市石巻本町字東野)
ふらい亭ぱん オムライス ハンバーグ (豊橋市牛川通)
オクトパス☆ガーデン (豊橋市中世古町 2F)
あんず亭 ランチ・モーニング (豊橋市天伯町美吉)
キッチンフライパン ハンバーグセット (北山町)
◇ラーメン
三河開花亭 赤ラーメン (豊橋市東岩町)
☆ふえる一方の不登校をどうとらるか(中)「心をほどく人間関係の大切さについて」 伊藤友宣(神戸心療親子研究室・主宰) 『月刊少年育成』2001年 ⑥【再掲載 2015.4】
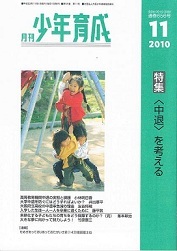
◇成り行き任せで本質を問わない
不登校についていわば親がとるべき対処の仕方に関して、多くの学校で言わ
れたり、いろいろな解説で解かれたりするのは、
おおむね、子ども自体に(あるいは、そんな子に育った成長過程に)問題や
原因があるのであり、不登校が起こった時点では、事態をとにかく受入れて、
やがては、それぞれに妥当なその先の進路を考えてやりましょう、
という向きのとらえ方が圧倒的なようです。
不登校児の分類などがなされていて、それは甘やかされタイプ、潔癖性タイ
プ、感情のない無気力タイプ、不満と不安定の非行型タイプなどだとか。
そして、不登校児がたどる時期や症状の段階が類型的にこういう経過を示す
ものだとしていて、つまり、不登校のはじまりは不機嫌で朝になると人格が変
わったように重く、休日は極端に陽気だとか。
この時期の処置法は、第一に登校刺激を与えないことだとかが強調されがち
なのです。
なったらなったで仕方がない。事を荒立ててより厄介な危機的状況に追い込
むよりは、黙って経過を見守るのがよい、と。
で、その後のたどりがちな経過として、初期は、反抗や暴力の段階、中期は
とじこもりの時期で、長い経過の末に、せめて、指導センターに通うとか、フ
リースクールとか、通信制や、高校生なら大検を受けて大学進学。あるいは学
歴の問われないフリーターへと進む、と解説します。
公的な教育現場では、不登校児のために特別なふれあい教室とか適応指導セ
ンターとかと称する施設の運営に力を入れているようですが、正規の授業から
はずれて、とにかく来さえすればそこでは何をしなくちゃならないとかの拘束
がないというのでは、その体験を生きた転機とする当人のよほどの気力が生じ
ない限り、いたずらに敗退感が強まるばかりでしょう。
前回に述べた八ツ塚実さんの口癖だった
「登校拒否ははじめの三日が勝負」
という認識の仕方とは、あまりにも違うのが、この二十年来の一般的な登校拒
否あるいは不登校のとらえ方だった、と言わざるを得ないのです。
◇「はじめの三日が勝負」とは逆に
あれこれと干渉的な力添えをしても、むしろ逆効果だと分かった結果、担任
教員が責任を感じて力むことが、登校拒否への正しい対処の仕方とも言えない
という文部省(現・文科省)からの通達も出て、今では対症療法的な散々の徒
労を、教員が強制されなくなりました。
その挙句、年々不登校はふえる一方で、その延長としての引き込もりが今や
社会問題化しているのです。
八ツ塚さんの言っておられたのは、登校拒否だと認めざるを得ぬような長い
休みになってしまう前に、教員が当人の心のこわばりをほぐして暖かに自発的
な健康さへと、本人を立ち直らせてやらねばならないということでした。
教師に責任があるかどうかどころか、特に義務教育レベルでの登校拒否の現
実は、教育の本質の問題がつきつけられているのだというのでした。
問題打開の向きへの気持の流れを共有してやれなきゃならないのだ、とする
のであったと思います。
それを、逆に「登校刺激を与えるな」などという曖昧な用語で手をつかねて
しまうのは、あまりにもなおざりに過ぎるのではありまんせんか。
だいたいこの「登校刺激」などという言葉が、もっともらしい専門用語に見
えていい加減すぎるのです。
いやがる当人にやいやいと、やたら「休んではいけない。学校へ行け」とけ
しかけることを、「登校刺激を与える」と称するのらしいのですが、「登校刺激
を与えるな」とはつまり学校とか勉強とかを口にしてはいけないということだ
ととらえられて、休みたいなら休みたいだけ休ませよ、という意味に理解され
てまかり通っているようですね。
八ツ塚さんの「はじめの三日が勝負」とは、なんという違いであろうことか、
とあきれます。
一面の気持ちが子どもの心のすべてとは違うのですからね。
学校に行くことをひるむ気持ちの反面に、平気で愉しく行けることこそ子ど
も自身の本来の願いであるといったものでしょう。
学校は、子にとっては七面倒に考える前に、とにかく年相応の仲間と群れて
おれる安心に魅かれて子どもの足が向くところですよ。
行きたいのに自分はこうして休んでしまう、ああどういうことなのだと悶々
としている子に、あっけらかんと、「休みたいだけ休みなさいね」と物分かり
のよさげな態度で、あわれみをかけてくれる親や教師に、いらだちやより一層
の反発と拒否を感じて口をとざすのは、あまりにも当然と言うべきではありま
せんか。
学校を自分から切り離してくれというのではなくて、学校についての二律背
反的な悶々とした現状の思いを正しくとらえてほしいと熱望するのです。
登校刺激の刺激というのは、いやな刺激もある反面、プラスの刺激もあるの
です。
複雑な悶々とした軋轢を明快に解析して支えてくれる刺激が、それこそが必
要なのです。
当り前の誰ものように学校へは行きたいのがやまやまなのに、どうしても行
けなくしているなにかが重層的に自分の前に立ちはだかっているのだ。
それがなにか、ということもそれを退治する方法も、よく分からない、と頭
をかかえ込んでやる気をなくす、というのが子どもの現実なわけでしょう。
「東三河完全攻略 はなまる本」を紹介します。
プライズメントからは三河地区のフリーペーパーがたくさん出ています。
その関連本だと思いますが、興味あるものを抜粋しました。
記録ミスがあるかもしれません。
御確認ください。
わたしは、巻煎餅が好きで、豊川稲荷参りの時はよく求めます。
「味のヤマスイ」では、よくメヒカリの唐揚げ(冷凍)を購入します。
メヒカリ、なんとも言えないおいしさです。
新城の「ナザレうどん」は浜松の「ナザレ」と何か関連があるのでしょうか。
浜松のナザレさん、近隣学校に勤めていた折、時々出前をしてもらいました。
現在は閉店となったようですが。
もう一つ、再掲載になりますが、伊藤友宣さんの
「心をほどく人間関係の大切さについて」⑥を載せます。
20年以上の前の分掌なのですが、不登校について、
わたしには最もしっくりくるとらえ方です。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「東三河完全攻略 はなまる本」プライズメント
◇豊橋
豊橋公会堂(国登録文化財)
豊橋ハリスト教会(国重文)
トキフ(甘党の店 大手町)
飛騨路(札木町 朴葉ステーキ)
もちや(東新町 モチ入りワラビ餅,栗蒸し羊羹)
◇豊川
喜楽(門前町 宝珠まんじゅう,巻せんべい)
たねや(豊川元町 稲荷寿司でシュー,手筒ロール)
松屋(門前町 味噌カツ稲荷,わさび稲荷)
来恩(門前町 五平餅)
◇蒲郡
えびせん工房(清田町上大内)
味のヤマスイ(形原町港町 海の幸)
◇新城
旅館 ランチ付き温泉
◇田原
伊良湖ガーデンホテル バイキング
サンパルク田原
蔵王山
◇和食
武蔵総本店 みそかつ (豊橋市藤沢町)
大鯛 豊富な料理 (豊橋市上田町新津田)
鈴幸 うなぎまぶし(田原市加治町奥見中)
魚々屋 魚々御前 (豊橋市石巻本町字西野)
くろふね 手頃なランチ(豊橋市浜道町北側)
いちょう なめし田楽 (豊橋市中野町字平)
ナザレうどん (新城市平井字原)
◇中華
茶居那 おすすめランチ (豊橋市藤沢町)
◇イタリアン・洋食
スバゲッ亭チャオ あんかけ鉄板スパ (豊橋市広小路一丁目2F)
コウヨウ館 オムライス (豊橋市二川町字ねずみ池)
こすたりか パスタランチ(豊橋市牛川町)
日付変更線180°E オムライス (豊橋市石巻本町字東野)
ふらい亭ぱん オムライス ハンバーグ (豊橋市牛川通)
オクトパス☆ガーデン (豊橋市中世古町 2F)
あんず亭 ランチ・モーニング (豊橋市天伯町美吉)
キッチンフライパン ハンバーグセット (北山町)
◇ラーメン
三河開花亭 赤ラーメン (豊橋市東岩町)
☆ふえる一方の不登校をどうとらるか(中)「心をほどく人間関係の大切さについて」 伊藤友宣(神戸心療親子研究室・主宰) 『月刊少年育成』2001年 ⑥【再掲載 2015.4】
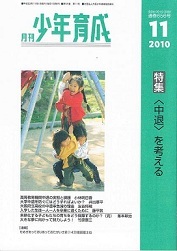
◇成り行き任せで本質を問わない
不登校についていわば親がとるべき対処の仕方に関して、多くの学校で言わ
れたり、いろいろな解説で解かれたりするのは、
おおむね、子ども自体に(あるいは、そんな子に育った成長過程に)問題や
原因があるのであり、不登校が起こった時点では、事態をとにかく受入れて、
やがては、それぞれに妥当なその先の進路を考えてやりましょう、
という向きのとらえ方が圧倒的なようです。
不登校児の分類などがなされていて、それは甘やかされタイプ、潔癖性タイ
プ、感情のない無気力タイプ、不満と不安定の非行型タイプなどだとか。
そして、不登校児がたどる時期や症状の段階が類型的にこういう経過を示す
ものだとしていて、つまり、不登校のはじまりは不機嫌で朝になると人格が変
わったように重く、休日は極端に陽気だとか。
この時期の処置法は、第一に登校刺激を与えないことだとかが強調されがち
なのです。
なったらなったで仕方がない。事を荒立ててより厄介な危機的状況に追い込
むよりは、黙って経過を見守るのがよい、と。
で、その後のたどりがちな経過として、初期は、反抗や暴力の段階、中期は
とじこもりの時期で、長い経過の末に、せめて、指導センターに通うとか、フ
リースクールとか、通信制や、高校生なら大検を受けて大学進学。あるいは学
歴の問われないフリーターへと進む、と解説します。
公的な教育現場では、不登校児のために特別なふれあい教室とか適応指導セ
ンターとかと称する施設の運営に力を入れているようですが、正規の授業から
はずれて、とにかく来さえすればそこでは何をしなくちゃならないとかの拘束
がないというのでは、その体験を生きた転機とする当人のよほどの気力が生じ
ない限り、いたずらに敗退感が強まるばかりでしょう。
前回に述べた八ツ塚実さんの口癖だった
「登校拒否ははじめの三日が勝負」
という認識の仕方とは、あまりにも違うのが、この二十年来の一般的な登校拒
否あるいは不登校のとらえ方だった、と言わざるを得ないのです。
◇「はじめの三日が勝負」とは逆に
あれこれと干渉的な力添えをしても、むしろ逆効果だと分かった結果、担任
教員が責任を感じて力むことが、登校拒否への正しい対処の仕方とも言えない
という文部省(現・文科省)からの通達も出て、今では対症療法的な散々の徒
労を、教員が強制されなくなりました。
その挙句、年々不登校はふえる一方で、その延長としての引き込もりが今や
社会問題化しているのです。
八ツ塚さんの言っておられたのは、登校拒否だと認めざるを得ぬような長い
休みになってしまう前に、教員が当人の心のこわばりをほぐして暖かに自発的
な健康さへと、本人を立ち直らせてやらねばならないということでした。
教師に責任があるかどうかどころか、特に義務教育レベルでの登校拒否の現
実は、教育の本質の問題がつきつけられているのだというのでした。
問題打開の向きへの気持の流れを共有してやれなきゃならないのだ、とする
のであったと思います。
それを、逆に「登校刺激を与えるな」などという曖昧な用語で手をつかねて
しまうのは、あまりにもなおざりに過ぎるのではありまんせんか。
だいたいこの「登校刺激」などという言葉が、もっともらしい専門用語に見
えていい加減すぎるのです。
いやがる当人にやいやいと、やたら「休んではいけない。学校へ行け」とけ
しかけることを、「登校刺激を与える」と称するのらしいのですが、「登校刺激
を与えるな」とはつまり学校とか勉強とかを口にしてはいけないということだ
ととらえられて、休みたいなら休みたいだけ休ませよ、という意味に理解され
てまかり通っているようですね。
八ツ塚さんの「はじめの三日が勝負」とは、なんという違いであろうことか、
とあきれます。
一面の気持ちが子どもの心のすべてとは違うのですからね。
学校に行くことをひるむ気持ちの反面に、平気で愉しく行けることこそ子ど
も自身の本来の願いであるといったものでしょう。
学校は、子にとっては七面倒に考える前に、とにかく年相応の仲間と群れて
おれる安心に魅かれて子どもの足が向くところですよ。
行きたいのに自分はこうして休んでしまう、ああどういうことなのだと悶々
としている子に、あっけらかんと、「休みたいだけ休みなさいね」と物分かり
のよさげな態度で、あわれみをかけてくれる親や教師に、いらだちやより一層
の反発と拒否を感じて口をとざすのは、あまりにも当然と言うべきではありま
せんか。
学校を自分から切り離してくれというのではなくて、学校についての二律背
反的な悶々とした現状の思いを正しくとらえてほしいと熱望するのです。
登校刺激の刺激というのは、いやな刺激もある反面、プラスの刺激もあるの
です。
複雑な悶々とした軋轢を明快に解析して支えてくれる刺激が、それこそが必
要なのです。
当り前の誰ものように学校へは行きたいのがやまやまなのに、どうしても行
けなくしているなにかが重層的に自分の前に立ちはだかっているのだ。
それがなにか、ということもそれを退治する方法も、よく分からない、と頭
をかかえ込んでやる気をなくす、というのが子どもの現実なわけでしょう。



