「適応障害のことがよわかる本」貝谷久宣 講談社 2018年 ① /「日本子育て物語-育児の社会史」 上笙一郎 筑摩書房 1991年 ④【再掲載 2017.2】 [読書記録 一般]
今日は5月10日、金曜日です。
今回は、貝谷久宣さんの
「適応障害のことがよくわかる本」の紹介 1回目です。
出版社の案内には、
「適応障害はストレスに適応できずに起こる、こころの病気のひとつ。環
境の変化に適応できず、心身にさまざまな症状が現れます。抑うつと不
安が主症状で、原因となるストレスが除かれれば、症状がなくなります。
また、うつ病や不安症などの精神疾患というほどではない状態につけら
れる病名という側面も。本書は、症例も多く紹介しながら原因、診断、
治療法を徹底解説。誤解されやすい、こころの病の理解を深めるために
役立つ一冊です」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「適応障害はこころの病気の一つ。病気と健康の境目ともいえるストレス、
悩み、不安、恐怖などの心因によるもの」
・「適応障害はいずれの症状も強くないが多彩でありストレスに適応でき
ない場合に付けられる。特徴のない病気ともいえ、不安、抑鬱、焦燥
感、過敏、混乱などの精神症状、倦怠感、頭痛、腹痛などの身体症状
がみられる」
もう一つ、再掲載になりますが、上笙一郎さんの
「日本子育て物語-育児の社会史」④を載せます。
☆「適応障害のことがよくわかる本」貝谷久宣 講談社 2018年 ①

◇ストレスに対応できず起こる病気(1)
□適応障害はこころの病気の一つ
病気と健康の境目
心因
- ストレス、悩み、不安、恐怖
- 適応障害
内因
- 体質、気質など内側にあるもの
外因
- 事故、病気などで脳に影響
日常生活に対応できない ←→ 辛い気持ち
□一人の人を多面的に見て診断する
適応障害
… いずれの症状も強くないが多彩
ストレスに適応できない場合に付けられる
適応障害は特徴のない病気
精神症状
- 不安、抑鬱、焦燥感、過敏、混乱など
身体症状
- 倦怠感、頭痛、腹痛など
目安は6か月間
この診断名はほぼ適応障害
・鬱状態
・睡眠障害
・否定型 鬱病・新型鬱病
ストレスの元がないところでは抑鬱や不安がなくなる
・不安神経症 不安抑鬱発作 不安抑鬱障害
□重症化すると他の病気に診断が変わる
鬱病? PTSD? 不安障害? パーソナリティ障害?
|
◎ それ未満の時が適応障害
◎ それに近い
☆「日本子育て物語-育児の社会史」 上笙一郎 筑摩書房 1991年 ④【再掲載 2017.2】
[出版社の案内]
原始時代から現代まで―子どもの歴史と子育ての歩みを、豊かな資料を引
きつつ興味深く語り、日本人の育児の知恵と子どもへの深い思いを明らか
にする。
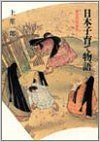
≪原始時代≫④
◇「抱っこ」と「負んぶ」 - そのスタイルの人類学
□動物園の猿山に見る
定住生活
男性
- 労働
女性
- -家事と育児
◎ 同時に果たす手だてが抱っこと負んぶ
□地域・民族に見る様々なタイプ
西村真琴
① 首かせ式
② カンガルー式
③ コアラ式
④ 横だすき式
⑤ 装置使用式
⑥ その他
<抱っこ社会>
- ヨーロッパ・アメリカ
<負んぶ社会>
- アジア・日本
□「日本式負んぶ法」の完成
負んぶ文化圏
= 日本
手と道具
縄文中期より
明治 西欧人
「日本の親は負んぶという方法によって子供を手厚く保育しており,
したがって日本は子供にとって天国である」
□ベビーカーが登場して
乳母車
= 互いに顔を見合える
ベビーカー
「地獄の乗り物」
負んぶの衰退
~ 「たすき掛け負んぶ法」の野暮ったい印象
今回は、貝谷久宣さんの
「適応障害のことがよくわかる本」の紹介 1回目です。
出版社の案内には、
「適応障害はストレスに適応できずに起こる、こころの病気のひとつ。環
境の変化に適応できず、心身にさまざまな症状が現れます。抑うつと不
安が主症状で、原因となるストレスが除かれれば、症状がなくなります。
また、うつ病や不安症などの精神疾患というほどではない状態につけら
れる病名という側面も。本書は、症例も多く紹介しながら原因、診断、
治療法を徹底解説。誤解されやすい、こころの病の理解を深めるために
役立つ一冊です」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「適応障害はこころの病気の一つ。病気と健康の境目ともいえるストレス、
悩み、不安、恐怖などの心因によるもの」
・「適応障害はいずれの症状も強くないが多彩でありストレスに適応でき
ない場合に付けられる。特徴のない病気ともいえ、不安、抑鬱、焦燥
感、過敏、混乱などの精神症状、倦怠感、頭痛、腹痛などの身体症状
がみられる」
もう一つ、再掲載になりますが、上笙一郎さんの
「日本子育て物語-育児の社会史」④を載せます。
☆「適応障害のことがよくわかる本」貝谷久宣 講談社 2018年 ①

◇ストレスに対応できず起こる病気(1)
□適応障害はこころの病気の一つ
病気と健康の境目
心因
- ストレス、悩み、不安、恐怖
- 適応障害
内因
- 体質、気質など内側にあるもの
外因
- 事故、病気などで脳に影響
日常生活に対応できない ←→ 辛い気持ち
□一人の人を多面的に見て診断する
適応障害
… いずれの症状も強くないが多彩
ストレスに適応できない場合に付けられる
適応障害は特徴のない病気
精神症状
- 不安、抑鬱、焦燥感、過敏、混乱など
身体症状
- 倦怠感、頭痛、腹痛など
目安は6か月間
この診断名はほぼ適応障害
・鬱状態
・睡眠障害
・否定型 鬱病・新型鬱病
ストレスの元がないところでは抑鬱や不安がなくなる
・不安神経症 不安抑鬱発作 不安抑鬱障害
□重症化すると他の病気に診断が変わる
鬱病? PTSD? 不安障害? パーソナリティ障害?
|
◎ それ未満の時が適応障害
◎ それに近い
☆「日本子育て物語-育児の社会史」 上笙一郎 筑摩書房 1991年 ④【再掲載 2017.2】
[出版社の案内]
原始時代から現代まで―子どもの歴史と子育ての歩みを、豊かな資料を引
きつつ興味深く語り、日本人の育児の知恵と子どもへの深い思いを明らか
にする。
≪原始時代≫④
◇「抱っこ」と「負んぶ」 - そのスタイルの人類学
□動物園の猿山に見る
定住生活
男性
- 労働
女性
- -家事と育児
◎ 同時に果たす手だてが抱っこと負んぶ
□地域・民族に見る様々なタイプ
西村真琴
① 首かせ式
② カンガルー式
③ コアラ式
④ 横だすき式
⑤ 装置使用式
⑥ その他
<抱っこ社会>
- ヨーロッパ・アメリカ
<負んぶ社会>
- アジア・日本
□「日本式負んぶ法」の完成
負んぶ文化圏
= 日本
手と道具
縄文中期より
明治 西欧人
「日本の親は負んぶという方法によって子供を手厚く保育しており,
したがって日本は子供にとって天国である」
□ベビーカーが登場して
乳母車
= 互いに顔を見合える
ベビーカー
「地獄の乗り物」
負んぶの衰退
~ 「たすき掛け負んぶ法」の野暮ったい印象



