キーワード 読書について68-「はじめて学ぶ日本児童文学史」鳥越信 ミネルヴァ書房 2001年 (2) /「世間に学ぶ」 加藤秀俊 中央公論社 2006年 ②【再掲載 2017.5】 [読書記録 教育]
今日は5月1日、水曜日です。
今回は4月21日に続いて、
「キーワード 読書について」68回目、鳥越信さんの
「はじめて学ぶ日本児童文学史」の紹介 2回目です。
出版社の案内には、
「明治維新から昭和期にかけての日本児童文学の歩みを最も初期の時代
(草創期)を起点に、科学読み物・知識読み物の歴史およびキリスト教
児童文学の歴史、外国作品の歴史と幅広い視点から考察する。
【ここがポイント!!】
◎ 日本における児童文学研究の最新成果をとりこむ
◎ 好戦的・侵略的児童文学の解明を試みる
◎ 1868年から約120年間を6部に分ける」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「東洋になきものは,有形において数理学と無形において独立心とこの
二点である『福翁自伝』」
・「少年雑誌類興隆の時代 1888年『少年団』1889年『日本之少年』
1889年『小国民』」
・「日本の創作童話はアンデルセンより半世紀遅れて1890年から」
もう一つ、再掲載になりますが、加藤秀俊さんの
「世間に学ぶ」②を載せます。
☆キーワード 読書について68-「はじめて学ぶ日本児童文学史」鳥越信 ミネルヴァ書房 2001年 (2)
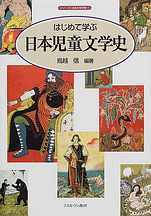
◇日本の近代化と科学読み物
福沢諭吉
「福翁自伝」
東洋になきものは,有形において数理学と無形において独立
心とこの二点である
科学読み物とは何か
板倉聖宣(1930~)
仮設実験の論理で積み上げられた法則的・概念的知識体系
仮設実験授業学派
日本最初の科学読み物
「訓蒙 窮理図解」 福沢諭吉 理を窮める
「天変地異」 小幡篤次郎(慶應義塾塾長)1876年
窮理ブームの中の科学読み物
窮理熱
文部省 - 窮理重視のカリキュラム
「理科」の誕生と「理科仙郷」
1886年
山県悌三郎 「理科仙郷」
バックレー著・山県訳 全10冊 736頁
少年雑誌類興隆の時代の科学読み物
1888年 「少年団」
1889年 「日本之少年」
1889年 「小国民」
科学読み物の目的多様化
石井研堂 「少年工芸文庫」
樋口勘次郎 「理科適話」同文館 1900年
木村小舟 「理科春秋」
科学読み物の歴史から見えてくるもの
「科学する心」の重要性
身近な動植物テーマでなく物理学中心か
◇<異文化>移入としての翻訳
鎖国による統制
1593年
「エソポノハブラス」イソップ物語70編 俗文体(口語体)
「伊曽保物語」9種刊行
黒田麺虚訳「凛荒紀事」ロビンソン・クルーソー 1648年
横山由清訳「魯敏遜浮行紀略」1857年
文明開化と啓蒙主義
1868~1888年
70点の内1/2が翻訳書-多くは啓蒙書
新モラル スマイルス・中村正直「西国立志編」1870年
外国歴史地理
学校教育の普及と翻訳書
J.ベルヌが受ける
翻訳文学の役割
日本の創作童話
1890年~ アンデルセンより半世紀の遅れ
言文一致
変換点
1890年 若松賤子「小公子」バーネット
☆「世間に学ぶ」 加藤秀俊 中央公論社 2006年 ②【再掲載 2017.5】
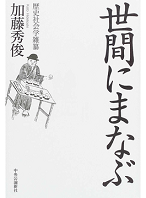
◇ニュータウン進化論
□江戸の14変 1590年~幕末 三田村鳶魚
火事の度に
明暦の大火(1657) 第7変
→ 大名邸は曲輪の外に,寺社も外周部に移転
天和2年(1682) 決定的なニュータウン
→ 屋敷町(赤坂,青山,四谷,本郷)
ごちゃ混ぜ式
□小林一三
明治43(1910)年理想的ニュータウン
~ 池田
池田
→ 豊中,岡本,高槻
渋沢栄吉の招聘により東京にも(顧問として)
田園調布
池田や田園調布は高級住宅街のイメージ
私鉄中核に
□団地 昭和30(1955)年~
建設行政のイニシアチブ
しかし,駅が遠かった → 孤立化
◇氷室から冷蔵庫まで
□日本書紀
仁徳62年 額田大中彦皇子 - 氷室
氷室(天理市福住町)
- 氷室神社
6月1日 賜氷節
日本各地に主要な氷室
□近世も氷室の技術伝承
前田候「御雪献上」
中川家兵衛が函館氷
◇ペルソナと変身願望
□人類文化における仮面の普遍性
□仮面の宗教性
扮装,化粧
= 人体のカモフラージュ
□変身願望
◇長屋文化論
□裏長屋
9尺2間
間口9尺 奥行き2間
= 計3坪
山城の建設事業モジュール
「寝小屋」形式が半永久的住居に
□バラック
仮設小屋
火事の問題
- 3年で消却できる普請で十分だった
一戸建てに固執しない
→ 透明な連帯・心理的裸
◇源氏物語考現学
□清源寺
源融(嵯峨天皇皇子-左大臣)
- 光源氏のモデル?
□源氏物語
書かれたのは廬山寺
今回は4月21日に続いて、
「キーワード 読書について」68回目、鳥越信さんの
「はじめて学ぶ日本児童文学史」の紹介 2回目です。
出版社の案内には、
「明治維新から昭和期にかけての日本児童文学の歩みを最も初期の時代
(草創期)を起点に、科学読み物・知識読み物の歴史およびキリスト教
児童文学の歴史、外国作品の歴史と幅広い視点から考察する。
【ここがポイント!!】
◎ 日本における児童文学研究の最新成果をとりこむ
◎ 好戦的・侵略的児童文学の解明を試みる
◎ 1868年から約120年間を6部に分ける」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「東洋になきものは,有形において数理学と無形において独立心とこの
二点である『福翁自伝』」
・「少年雑誌類興隆の時代 1888年『少年団』1889年『日本之少年』
1889年『小国民』」
・「日本の創作童話はアンデルセンより半世紀遅れて1890年から」
もう一つ、再掲載になりますが、加藤秀俊さんの
「世間に学ぶ」②を載せます。
☆キーワード 読書について68-「はじめて学ぶ日本児童文学史」鳥越信 ミネルヴァ書房 2001年 (2)
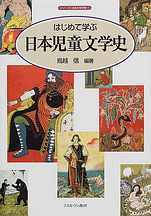
◇日本の近代化と科学読み物
福沢諭吉
「福翁自伝」
東洋になきものは,有形において数理学と無形において独立
心とこの二点である
科学読み物とは何か
板倉聖宣(1930~)
仮設実験の論理で積み上げられた法則的・概念的知識体系
仮設実験授業学派
日本最初の科学読み物
「訓蒙 窮理図解」 福沢諭吉 理を窮める
「天変地異」 小幡篤次郎(慶應義塾塾長)1876年
窮理ブームの中の科学読み物
窮理熱
文部省 - 窮理重視のカリキュラム
「理科」の誕生と「理科仙郷」
1886年
山県悌三郎 「理科仙郷」
バックレー著・山県訳 全10冊 736頁
少年雑誌類興隆の時代の科学読み物
1888年 「少年団」
1889年 「日本之少年」
1889年 「小国民」
科学読み物の目的多様化
石井研堂 「少年工芸文庫」
樋口勘次郎 「理科適話」同文館 1900年
木村小舟 「理科春秋」
科学読み物の歴史から見えてくるもの
「科学する心」の重要性
身近な動植物テーマでなく物理学中心か
◇<異文化>移入としての翻訳
鎖国による統制
1593年
「エソポノハブラス」イソップ物語70編 俗文体(口語体)
「伊曽保物語」9種刊行
黒田麺虚訳「凛荒紀事」ロビンソン・クルーソー 1648年
横山由清訳「魯敏遜浮行紀略」1857年
文明開化と啓蒙主義
1868~1888年
70点の内1/2が翻訳書-多くは啓蒙書
新モラル スマイルス・中村正直「西国立志編」1870年
外国歴史地理
学校教育の普及と翻訳書
J.ベルヌが受ける
翻訳文学の役割
日本の創作童話
1890年~ アンデルセンより半世紀の遅れ
言文一致
変換点
1890年 若松賤子「小公子」バーネット
☆「世間に学ぶ」 加藤秀俊 中央公論社 2006年 ②【再掲載 2017.5】
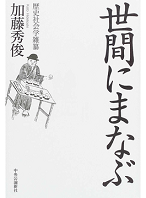
◇ニュータウン進化論
□江戸の14変 1590年~幕末 三田村鳶魚
火事の度に
明暦の大火(1657) 第7変
→ 大名邸は曲輪の外に,寺社も外周部に移転
天和2年(1682) 決定的なニュータウン
→ 屋敷町(赤坂,青山,四谷,本郷)
ごちゃ混ぜ式
□小林一三
明治43(1910)年理想的ニュータウン
~ 池田
池田
→ 豊中,岡本,高槻
渋沢栄吉の招聘により東京にも(顧問として)
田園調布
池田や田園調布は高級住宅街のイメージ
私鉄中核に
□団地 昭和30(1955)年~
建設行政のイニシアチブ
しかし,駅が遠かった → 孤立化
◇氷室から冷蔵庫まで
□日本書紀
仁徳62年 額田大中彦皇子 - 氷室
氷室(天理市福住町)
- 氷室神社
6月1日 賜氷節
日本各地に主要な氷室
□近世も氷室の技術伝承
前田候「御雪献上」
中川家兵衛が函館氷
◇ペルソナと変身願望
□人類文化における仮面の普遍性
□仮面の宗教性
扮装,化粧
= 人体のカモフラージュ
□変身願望
◇長屋文化論
□裏長屋
9尺2間
間口9尺 奥行き2間
= 計3坪
山城の建設事業モジュール
「寝小屋」形式が半永久的住居に
□バラック
仮設小屋
火事の問題
- 3年で消却できる普請で十分だった
一戸建てに固執しない
→ 透明な連帯・心理的裸
◇源氏物語考現学
□清源寺
源融(嵯峨天皇皇子-左大臣)
- 光源氏のモデル?
□源氏物語
書かれたのは廬山寺



