「子どもを変えた親の一言作文25選」明治図書出版 1998年 ② /「古代日本の発掘発見物語」玉利勲 国土社 1985年 ②【再掲載 2012.1】 [読書記録 教育]
今回は、8月 7日に続いて、明治図書出版の
「子どもを変えた親の一言作文25選」の紹介 2回目です。
編集は野口芳宏さん、水野茂一さん、向山洋一さん。
サブタイトルに「教室で読み聞かせ:子どもの作文珠玉集」とあります。
子どもの素直な文章、いいですね。
もう一つ、再掲載となりますが、玉利勲さんの
「古代日本の発掘発見物語」②を載せます。
発掘、ロマンがあってわたしは大好きです。
考古学者の斎藤忠さんの本には、
よく坪井正五郎さんのお名前が出ていました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「子どもを変えた親の一言作文25選」明治図書出版 1998年 ②
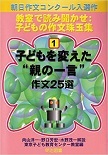
3.けんけつ MSさん(5歳)
きょうは、ききゅうきゅうしゃみたいなバスにのりました。おかあさんのちをわけてあ
げるためです。
そのちは、けがをしたひとやびょうきのひとや、ちがすくないひとのためにつかっても
らうそうです。
おかあさんは、
「かぞくが、げんきでいることがうれしいの。だから、ほかのひとにもそのきもちを、わ
けてあげたいのよ。」
と、はりをさしているのにわらってた。
ぜったいみんなげんきになるよ。おかあさんのちは、げんきだからね。
わたしも、大きくなったらあげたいな。だって、わたしげんきだもん。
4 あそばない KSさん(5歳)
公えんでけんちゃんに
「ちがうようちえんの子とはあそばない」
っていじわる、された。
すごくくやしくて(ぼくだってもうけんちゃんとはあそぶものか)って思った。
いえにかえると中、今までけんちゃんにいじわるされたことばっかり思い出してぼぐの
心の中のおこり虫がバクハツしそうだった。
いえにかえってお母さんにはなしたら
「じゃあ、けんちゃんにやさしくしてもらったことをかんがえてみれば。」
といわれた。
(けんちゃんこのまえぼくが公えんにボールをわすれたとき、おうちまでとどけてくれ
たなあ。それからほじょなし自てん車のうしろをもってくれたなあ。けんちゃんってや
っぱりやさしいなあ。)
ぼくの心のおこり虫はどこかへきえていった。(あしたなかなおりしよう)と思った。
5.まほうのことば IAさん(6歳)
「あ-ちゃん、せんたくばさみとってくれる。」
と、ママがベランダでいいました。
わたしはぬりえをしてたから、すこしめんどくさいこえでいいました。
「いくつ。」
「二つおねがいね。」
わたしは、せんめんじょからせんたくばさみをとってきて、ママにわたしました。
「ありがとう。どうもありがとう。」
ママがとてもうれしそうにいいました。
そしたらなんだかすごくくすぐったくなって、こんどは、はしってせんめんじょにいっ
て、もう二つせんたくばさみをもってきました。
「あら、どうもありがとう。」
と、ママはわらって、せんたくばさみを、もうついているのに、シャツにまた、パチッパ
チッってつけました。
ほんとは、もっととってきたかったけど、シャツがせんたくばさみだらけになりそうだ
から、がまんしました。
「ありがとう。」はもっとおてつだいしたくなっちゃう、もっとやさしくしたくなっちゃ
うまほうのことばだね。
☆「古代日本の発掘発見物語」玉利勲 国土社 1985年 ②【再掲載 2012.1】

◇日本考古学のあけぼの - モースと大森貝塚
□汽車の窓から貝塚発見
明治10(1877)6.19
エドワード・シルベイター・モース
39歳 「腕足類」海の生物の研究者
大森駅近くで貝塚発見
□思いがけない運命
マレー博士
モースを文部大輔(次官)田中不二麿に紹介
哲学者 外山正一も同席
東大教授に任命 7月12日
新学期は9月 7.21~8.28
江ノ島漁師小屋で腕足類の採集と研究 松村任三郎助手
教壇は9月12日から
9月16日初めて貝塚を訪ねる
□最初の発掘
モース、松村任三郎、松浦佐用彦、佐々木忠次郎
10月9日3回目
松村助手、松浦、佐々木、2学生、外山正和教授
矢田部良吉教授(植物学)、マレー博士等3人の外国人
作業員6名
□最初の調査報告書
明治12(1879)夏 「大森貝塚」 12月 矢田部訳『大森介墟古物編』
明治12.9.2 モース日本を離れる(日本在約2年)
→ ボストン北のセーラム ビーボディ博物館長に
1925.12.20没
□二つの記念碑
昭和4年(1929) 「大森貝塚」品川区大井6丁目21 ◎
昭和5年(1930) 「大森貝墟」大田区山王1丁目3-1
◇歩み始めた考古学 - 明治時代と坪井正五郎
□自信に満ちたイギリス留学
坪井正五郎
文久3(1863)年1.5 両国 矢ノ倉生
父は幕府の医者 正月5日生まれで「正五」
明治10 1877 14歳で東大予備門
14 1881 東京大学理学部動物学科入学
15 1882 友人と連名で土器についての論文
19 1886 動物学科卒業 → 大学院・人類学
22 1889.6 大学助手 イギリス・フランス留学
三年間 大英博物館 人類学
25 1893.10 帰国 東大理学部教授 29歳
26 1894 人類学講座 初代教授
大正2(1913)5月 ロシアにて病没 50歳
□人類学会の始まり
人類学創設
一般にも普及
有坂
坪井と白井光太郎を誘い本郷・向ケ岡貝塚
明治17(1884)3.2 弥生式土器第一発見
↓
◎人類学会 毎月一回遠足 ~ 遺物採集
|
まね 考古学研究 = 外国人への対抗
明治19(1886)2月 会誌『人類学報告』創刊
5月 東京人類学会『東京人類学報告』
明治20(1887) 『東京人類学会報告』
明治21(1888) 『東京人類学会雑誌』
坪井自身 人類学 幅広い - 本質研究、現状研究、由来研究
□最初の古墳発掘
古墳研究重視
明治19(1886)栃木県足利市二つの円墳の調査
明治21(1888)8月 『足利古墳発掘報告』
□コロボックルかアイヌ人か
坪井 先住民コロボックル説 論争
小金井良精教授 アイヌ人説
坪井の死により終止符
「子どもを変えた親の一言作文25選」の紹介 2回目です。
編集は野口芳宏さん、水野茂一さん、向山洋一さん。
サブタイトルに「教室で読み聞かせ:子どもの作文珠玉集」とあります。
子どもの素直な文章、いいですね。
もう一つ、再掲載となりますが、玉利勲さんの
「古代日本の発掘発見物語」②を載せます。
発掘、ロマンがあってわたしは大好きです。
考古学者の斎藤忠さんの本には、
よく坪井正五郎さんのお名前が出ていました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「子どもを変えた親の一言作文25選」明治図書出版 1998年 ②
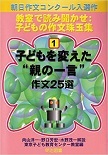
3.けんけつ MSさん(5歳)
きょうは、ききゅうきゅうしゃみたいなバスにのりました。おかあさんのちをわけてあ
げるためです。
そのちは、けがをしたひとやびょうきのひとや、ちがすくないひとのためにつかっても
らうそうです。
おかあさんは、
「かぞくが、げんきでいることがうれしいの。だから、ほかのひとにもそのきもちを、わ
けてあげたいのよ。」
と、はりをさしているのにわらってた。
ぜったいみんなげんきになるよ。おかあさんのちは、げんきだからね。
わたしも、大きくなったらあげたいな。だって、わたしげんきだもん。
4 あそばない KSさん(5歳)
公えんでけんちゃんに
「ちがうようちえんの子とはあそばない」
っていじわる、された。
すごくくやしくて(ぼくだってもうけんちゃんとはあそぶものか)って思った。
いえにかえると中、今までけんちゃんにいじわるされたことばっかり思い出してぼぐの
心の中のおこり虫がバクハツしそうだった。
いえにかえってお母さんにはなしたら
「じゃあ、けんちゃんにやさしくしてもらったことをかんがえてみれば。」
といわれた。
(けんちゃんこのまえぼくが公えんにボールをわすれたとき、おうちまでとどけてくれ
たなあ。それからほじょなし自てん車のうしろをもってくれたなあ。けんちゃんってや
っぱりやさしいなあ。)
ぼくの心のおこり虫はどこかへきえていった。(あしたなかなおりしよう)と思った。
5.まほうのことば IAさん(6歳)
「あ-ちゃん、せんたくばさみとってくれる。」
と、ママがベランダでいいました。
わたしはぬりえをしてたから、すこしめんどくさいこえでいいました。
「いくつ。」
「二つおねがいね。」
わたしは、せんめんじょからせんたくばさみをとってきて、ママにわたしました。
「ありがとう。どうもありがとう。」
ママがとてもうれしそうにいいました。
そしたらなんだかすごくくすぐったくなって、こんどは、はしってせんめんじょにいっ
て、もう二つせんたくばさみをもってきました。
「あら、どうもありがとう。」
と、ママはわらって、せんたくばさみを、もうついているのに、シャツにまた、パチッパ
チッってつけました。
ほんとは、もっととってきたかったけど、シャツがせんたくばさみだらけになりそうだ
から、がまんしました。
「ありがとう。」はもっとおてつだいしたくなっちゃう、もっとやさしくしたくなっちゃ
うまほうのことばだね。
☆「古代日本の発掘発見物語」玉利勲 国土社 1985年 ②【再掲載 2012.1】

◇日本考古学のあけぼの - モースと大森貝塚
□汽車の窓から貝塚発見
明治10(1877)6.19
エドワード・シルベイター・モース
39歳 「腕足類」海の生物の研究者
大森駅近くで貝塚発見
□思いがけない運命
マレー博士
モースを文部大輔(次官)田中不二麿に紹介
哲学者 外山正一も同席
東大教授に任命 7月12日
新学期は9月 7.21~8.28
江ノ島漁師小屋で腕足類の採集と研究 松村任三郎助手
教壇は9月12日から
9月16日初めて貝塚を訪ねる
□最初の発掘
モース、松村任三郎、松浦佐用彦、佐々木忠次郎
10月9日3回目
松村助手、松浦、佐々木、2学生、外山正和教授
矢田部良吉教授(植物学)、マレー博士等3人の外国人
作業員6名
□最初の調査報告書
明治12(1879)夏 「大森貝塚」 12月 矢田部訳『大森介墟古物編』
明治12.9.2 モース日本を離れる(日本在約2年)
→ ボストン北のセーラム ビーボディ博物館長に
1925.12.20没
□二つの記念碑
昭和4年(1929) 「大森貝塚」品川区大井6丁目21 ◎
昭和5年(1930) 「大森貝墟」大田区山王1丁目3-1
◇歩み始めた考古学 - 明治時代と坪井正五郎
□自信に満ちたイギリス留学
坪井正五郎
文久3(1863)年1.5 両国 矢ノ倉生
父は幕府の医者 正月5日生まれで「正五」
明治10 1877 14歳で東大予備門
14 1881 東京大学理学部動物学科入学
15 1882 友人と連名で土器についての論文
19 1886 動物学科卒業 → 大学院・人類学
22 1889.6 大学助手 イギリス・フランス留学
三年間 大英博物館 人類学
25 1893.10 帰国 東大理学部教授 29歳
26 1894 人類学講座 初代教授
大正2(1913)5月 ロシアにて病没 50歳
□人類学会の始まり
人類学創設
一般にも普及
有坂
坪井と白井光太郎を誘い本郷・向ケ岡貝塚
明治17(1884)3.2 弥生式土器第一発見
↓
◎人類学会 毎月一回遠足 ~ 遺物採集
|
まね 考古学研究 = 外国人への対抗
明治19(1886)2月 会誌『人類学報告』創刊
5月 東京人類学会『東京人類学報告』
明治20(1887) 『東京人類学会報告』
明治21(1888) 『東京人類学会雑誌』
坪井自身 人類学 幅広い - 本質研究、現状研究、由来研究
□最初の古墳発掘
古墳研究重視
明治19(1886)栃木県足利市二つの円墳の調査
明治21(1888)8月 『足利古墳発掘報告』
□コロボックルかアイヌ人か
坪井 先住民コロボックル説 論争
小金井良精教授 アイヌ人説
坪井の死により終止符



