「新鮮な気づき」と「思考」(中学校社会科)-和歌山県湯浅町立湯浅中学校教頭 御前充司 『教師のチカラ』/「辺境を歩いた人々」宮本常一 河出書房新社 2005年 ②【再掲載 2013.5】 [読書記録 教育]
今回は、『教師のチカラ』より御前充司さんの
「『新鮮な気づき』と『思考』(中学校社会科)」を紹介します。
『教師のチカラ』は、日本標準から出されている季刊の教育雑誌です。
出典年度、号は不明です。
授業作りの一端をよく分からせてくれる文章です。
もう一つ、再掲載となりますが、宮本常一さんの
「辺境を歩いた人々」②を載せます。
子ども向けて書かれた、大変わかりやすくおもしろい本です。
この本を読むと歴史、民俗好きになるのではないかとおもってしまいます。
松浦武四郎、菅江真澄の項の紹介です。
今日は記事のアップが遅くなってしまいました。
前日に記事を予約投稿しているのですが、うっかり忘れていました。
年休を取っているので、早朝より畑に出ていて、帰ってきて一段落。
ブログを見て気づきました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「新鮮な気づき」と「思考」(中学校社会科)-和歌山県湯浅町立湯浅中学校教頭 御前充司 『教師のチカラ』(発行年月号不明)
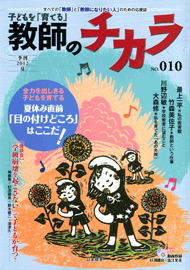
教材研究が、教科書の内容の理解と整理にとどまると、その授業は、つまらないものに
なってしまうことが多い。
例えば、板書をノートに写させたり、穴埋めのワークシートを完成させたりした後、教
師が一方的に脱明するような授業は退屈である。
教材研究は、生徒にとって、知的好奇心が喚起され、さらによく分かる授業の研究でな
ければいけない。
本稿では、その授業の要素として「新鮮な気づき」と「思考」というキーワードを挙げたい。
「新鮮な気づき」のある授業とは、生徒にとって、ちょっとした驚きを伴った発見、納
得、おかしみのある授業である。
生徒が思わず、「深イイ~」と言いたくなるような山場を、一つの授業に一回は準備し
たい。
そのために、教科書を研究するときは、生徒の立場で、「オヤッ?」と思えるところを
探すことから始める。
これには、授業を行う者としてのセンスが必要だが、慣れてくると自分のパターンがで
きあがってくる。
それまでは、数多くある先行実践をマネすればいいのである。
「オヤッ?」と引っかかるところが見つかったら、生徒と一緒に謎解きをするための「発
問」を考える。
正解を発表させるための問いではなく、多様な予想を出させるための問いである。
地理の教科書には、様々な統計資料がある。
例えば、牛の飼育頭数世界一はインドであることが分かるグラフを示す。
豚の飼育頭数世界一が、圧倒的に中国であるのは、それを食するからである。
しかし、ヒンズー教の国「インド」では、聖なる動物である牛を食べない。
なのに世界一牛が多いことがおもしろい。
「なぜ牛が多いのですか」という問い方もあるが、「牛が多いとどんないいことがありま
すか」と問う方が、多様な発言が得られる。
インドでは、牛は重要な農業の働き手であり、乳製品は欠かせない食品であり、糞は燃
料となる。
このことを入り口にして、インドの人口、歴史、宗教、貧しい人々のことなどを学ぶこ
とになる。
そして、この学習は、他の国々の人々の生活を比較して考えるための土台となる。
適切な「発問」によって、生徒は「思考」する。
生徒は、教えられるのではなく、自ら解を求めようという気分になる。
いわゆる「主体的な授業への参加」の形が生まれる。「なるほど、そんな考え方もある
のか」「友達はそんなところに目が届いていたのか」と感心しながら授業に参加すること
は楽しい。
教師は、一緒に考えたり、驚いたり、おもしろがったりしながら、生徒の発言を受け止
める態度を示す。
社会科は、特にそんな授業作りが可能な教科ではないかと思う。
☆「辺境を歩いた人々」宮本常一 河出書房新社 2005年 ②【再掲載 2013.5】
<出版社の案内>
江戸後期から戦前まで、辺境を民俗調査した、民俗学の先駆者とも言える四人の先達の仕
事と生涯。千島、蝦夷地から沖縄、先島諸島まで。近藤富蔵、菅江真澄、松浦武四郎、笹
森儀助。
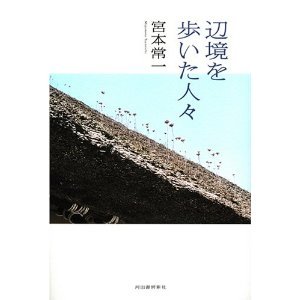
◇松浦武四郎
未開の大陸・北海道をくまなく歩いて内陸の地形を詳しく記した『蝦夷図』を見事に完
成。彼は北海道の名付け親でもある。
1 蝦夷地探検
ロシア 1632年~
1639年 オホーツク
1648年 ベーリング
1706年 カムチャッカ半島南
1766年 エトロフ島
間宮林蔵 - 伊能忠敬
松浦『北加伊道』がよい
→ 北海道の名付け親
2 生い立ちと諸国名めぐり
1818.2.6 伊勢国 一 志郡須川村
郷士の子
父 桂介時春(宣長の門下)
16~26歳まで諸国の旅
一日に60~70㎞
野宿も度々
3 蝦夷地探検を志す
1844年 27歳 水戸との繋がり
4 2回目の蝦夷地探検
5 国後からエトロフへ
6 4回目の旅
◇菅江真澄
みちのくの風土を愛し,底に流れる人の心の美しさに魅せられながら,一生を旅に過ご
し,江戸後期の民衆の生活を細かに記録した。
1 じょうかぶりの真澄
真澄 1788年 北海道に
いつも黒いずきん
→ 「じょうかぶりの真澄」
◎ 人の関心を惹き付けるため
生涯の半ばを秋田藩で
生まれは三河豊橋の牟呂 宝暦4年(1754)生
本名・白井秀雄(幼名・英二) 菅原道真に使えた太夫の子孫
父も神主 ~ 名所旧跡好きに
白井又三郎が吉田藩のお家騒動で岡崎に
植田義方より国文・和歌のてほどき
岡崎から名古屋に出て本草学(薬学)・医学の修行
もともと白井家には「金花香油」皮膚膏薬の作り方伝
医学の知識
天明3(1783)年2月末 生涯の旅へ 30歳~ それまでも各地へ
30歳 信州→越後→羽前(山形)~東北地方
『遊覧記』70冊 雑誌・スケッチ
2 浅間山の噴火
1783.3 信州飯田へ
本洗馬「伊那の中路」
浅間山噴火 6.28~7.8
天明の大飢饉
1784(天明4)年6月 越後へ
9月上旬 西馬音肉(にしもない)柳田村で冬越
老人の家に
3 飢饉の中を行く
津軽 ひどい状況 「外が浜風」
→ 塩不足も原因
塩は毒消し
1610年~1947年
340年間に
4 北上川に沿って
錦塚の話
めくら暦(岩手 秋田 青森)農民
5 真澄にあった旅人
1786(天明6)年 33歳 胆沢村
1784(天明4)年9月 象潟
6 恐山に登る
1792(寛政4)年10月 恐山登山 死火山
7 陸奥の牧
1793(寛政5)年12月 田名部の町を出る
8 氷の上で魚を捕る
1810(文化7)年 57歳
八郎潟 氷に穴を空け魚を捕る
諏訪湖から学んだ網漁
蜃気楼を見る
9 「花の出羽路」
1813(文化10)年
秋田より出羽6郡の地誌をつくる命 秋田の地誌編纂
→ 秋田に定住
「『新鮮な気づき』と『思考』(中学校社会科)」を紹介します。
『教師のチカラ』は、日本標準から出されている季刊の教育雑誌です。
出典年度、号は不明です。
授業作りの一端をよく分からせてくれる文章です。
もう一つ、再掲載となりますが、宮本常一さんの
「辺境を歩いた人々」②を載せます。
子ども向けて書かれた、大変わかりやすくおもしろい本です。
この本を読むと歴史、民俗好きになるのではないかとおもってしまいます。
松浦武四郎、菅江真澄の項の紹介です。
今日は記事のアップが遅くなってしまいました。
前日に記事を予約投稿しているのですが、うっかり忘れていました。
年休を取っているので、早朝より畑に出ていて、帰ってきて一段落。
ブログを見て気づきました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「新鮮な気づき」と「思考」(中学校社会科)-和歌山県湯浅町立湯浅中学校教頭 御前充司 『教師のチカラ』(発行年月号不明)
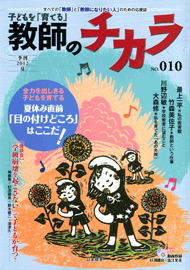
教材研究が、教科書の内容の理解と整理にとどまると、その授業は、つまらないものに
なってしまうことが多い。
例えば、板書をノートに写させたり、穴埋めのワークシートを完成させたりした後、教
師が一方的に脱明するような授業は退屈である。
教材研究は、生徒にとって、知的好奇心が喚起され、さらによく分かる授業の研究でな
ければいけない。
本稿では、その授業の要素として「新鮮な気づき」と「思考」というキーワードを挙げたい。
「新鮮な気づき」のある授業とは、生徒にとって、ちょっとした驚きを伴った発見、納
得、おかしみのある授業である。
生徒が思わず、「深イイ~」と言いたくなるような山場を、一つの授業に一回は準備し
たい。
そのために、教科書を研究するときは、生徒の立場で、「オヤッ?」と思えるところを
探すことから始める。
これには、授業を行う者としてのセンスが必要だが、慣れてくると自分のパターンがで
きあがってくる。
それまでは、数多くある先行実践をマネすればいいのである。
「オヤッ?」と引っかかるところが見つかったら、生徒と一緒に謎解きをするための「発
問」を考える。
正解を発表させるための問いではなく、多様な予想を出させるための問いである。
地理の教科書には、様々な統計資料がある。
例えば、牛の飼育頭数世界一はインドであることが分かるグラフを示す。
豚の飼育頭数世界一が、圧倒的に中国であるのは、それを食するからである。
しかし、ヒンズー教の国「インド」では、聖なる動物である牛を食べない。
なのに世界一牛が多いことがおもしろい。
「なぜ牛が多いのですか」という問い方もあるが、「牛が多いとどんないいことがありま
すか」と問う方が、多様な発言が得られる。
インドでは、牛は重要な農業の働き手であり、乳製品は欠かせない食品であり、糞は燃
料となる。
このことを入り口にして、インドの人口、歴史、宗教、貧しい人々のことなどを学ぶこ
とになる。
そして、この学習は、他の国々の人々の生活を比較して考えるための土台となる。
適切な「発問」によって、生徒は「思考」する。
生徒は、教えられるのではなく、自ら解を求めようという気分になる。
いわゆる「主体的な授業への参加」の形が生まれる。「なるほど、そんな考え方もある
のか」「友達はそんなところに目が届いていたのか」と感心しながら授業に参加すること
は楽しい。
教師は、一緒に考えたり、驚いたり、おもしろがったりしながら、生徒の発言を受け止
める態度を示す。
社会科は、特にそんな授業作りが可能な教科ではないかと思う。
☆「辺境を歩いた人々」宮本常一 河出書房新社 2005年 ②【再掲載 2013.5】
<出版社の案内>
江戸後期から戦前まで、辺境を民俗調査した、民俗学の先駆者とも言える四人の先達の仕
事と生涯。千島、蝦夷地から沖縄、先島諸島まで。近藤富蔵、菅江真澄、松浦武四郎、笹
森儀助。
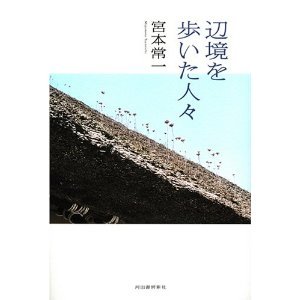
◇松浦武四郎
未開の大陸・北海道をくまなく歩いて内陸の地形を詳しく記した『蝦夷図』を見事に完
成。彼は北海道の名付け親でもある。
1 蝦夷地探検
ロシア 1632年~
1639年 オホーツク
1648年 ベーリング
1706年 カムチャッカ半島南
1766年 エトロフ島
間宮林蔵 - 伊能忠敬
松浦『北加伊道』がよい
→ 北海道の名付け親
2 生い立ちと諸国名めぐり
1818.2.6 伊勢国 一 志郡須川村
郷士の子
父 桂介時春(宣長の門下)
16~26歳まで諸国の旅
一日に60~70㎞
野宿も度々
3 蝦夷地探検を志す
1844年 27歳 水戸との繋がり
4 2回目の蝦夷地探検
5 国後からエトロフへ
6 4回目の旅
◇菅江真澄
みちのくの風土を愛し,底に流れる人の心の美しさに魅せられながら,一生を旅に過ご
し,江戸後期の民衆の生活を細かに記録した。
1 じょうかぶりの真澄
真澄 1788年 北海道に
いつも黒いずきん
→ 「じょうかぶりの真澄」
◎ 人の関心を惹き付けるため
生涯の半ばを秋田藩で
生まれは三河豊橋の牟呂 宝暦4年(1754)生
本名・白井秀雄(幼名・英二) 菅原道真に使えた太夫の子孫
父も神主 ~ 名所旧跡好きに
白井又三郎が吉田藩のお家騒動で岡崎に
植田義方より国文・和歌のてほどき
岡崎から名古屋に出て本草学(薬学)・医学の修行
もともと白井家には「金花香油」皮膚膏薬の作り方伝
医学の知識
天明3(1783)年2月末 生涯の旅へ 30歳~ それまでも各地へ
30歳 信州→越後→羽前(山形)~東北地方
『遊覧記』70冊 雑誌・スケッチ
2 浅間山の噴火
1783.3 信州飯田へ
本洗馬「伊那の中路」
浅間山噴火 6.28~7.8
天明の大飢饉
1784(天明4)年6月 越後へ
9月上旬 西馬音肉(にしもない)柳田村で冬越
老人の家に
3 飢饉の中を行く
津軽 ひどい状況 「外が浜風」
→ 塩不足も原因
塩は毒消し
1610年~1947年
340年間に
4 北上川に沿って
錦塚の話
めくら暦(岩手 秋田 青森)農民
5 真澄にあった旅人
1786(天明6)年 33歳 胆沢村
1784(天明4)年9月 象潟
6 恐山に登る
1792(寛政4)年10月 恐山登山 死火山
7 陸奥の牧
1793(寛政5)年12月 田名部の町を出る
8 氷の上で魚を捕る
1810(文化7)年 57歳
八郎潟 氷に穴を空け魚を捕る
諏訪湖から学んだ網漁
蜃気楼を見る
9 「花の出羽路」
1813(文化10)年
秋田より出羽6郡の地誌をつくる命 秋田の地誌編纂
→ 秋田に定住



