「池波正太郎のそうざい料理帖」矢吹申彦 平凡社 2003年 /『日本例話大全書』有馬朗人・中西進他 四季社 2001年 ③【再掲載 2015.3】 [読書記録 一般]
今回は、矢吹申彦さんの
「池波正太郎のそうざい料理帖」を紹介します。
最初のさわり部分の要約だけですが。
出版社の著者紹介には
「池波正太郎の酒と食の道楽は、小学校時代にまでさかのぼる。本書はその道
楽作法を、まず師のエッセイに学びとり、つぎに包丁さばきを盗み(矢吹申
彦画伯が再現)、さらにその江戸・東京の味を自ら相伴しようという、まこ
とに天晴れな虎の巻。酒家の手なぐさみに四季折々の味が愉しめ、即席食通、
にわか料理自慢になれる、本邦初の酒食料理帖。」
とあります。
「料理に挑戦」のヒントになりそうです。
もう一つ、再掲載になりますが、有馬朗人さん、中西進さんらによる
「日本例話大全書」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「池波正太郎のそうざい料理帖」矢吹申彦 平凡社 2003年
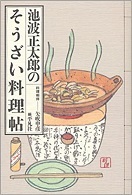
◇蛤の湯豆腐
鍋に昆布を敷いて
大根を薄く切ったものを入れると豆腐が白くふっくらと
湯豆腐の薬味は醤油と刻みネギと鰹節
◇鯛の塩焼き鍋
折り詰めの鯛の塩焼きを鍋に
調味は酒・塩 加えるは豆腐のみ
薬味は刻みネギのみ
◇浅蜊のぶっかけ飯
「浅蜊のむき身 + 大根の千切り + 七味」 をぶっかけ
昆布と醤油、酒、みりんで調味
◇ポテト・フライ
パン粉あげ
ポテトは親指の先ほど
生キャベツにウスターソース
◇豚肉のうどんすき
鍋に湯(酒半カップ)
- 酒3 水7 豚肉を750グラム
うどんをさっと入れ、玉が崩れたところへ下地
つゆ(醤油1、みりん1、だし昆布4)
◇和風オムレツ
細切れ(ジャガイモ、タマネギ、牛肉細切れ)
醤油と少しの砂糖でフライパンで炒め煮
具を卵で包む
ウスターソースで
☆『日本例話大全書』有馬朗人・中西進他 四季社 2001年 ③【再掲載 2015.3】

<生老病死>
□行基(668~749)
行基
法相宗の僧
人々に因果応報の教えを説く
公共事業を行う指導
- 社会事業と結びつく
政府
最初は弾圧するも、のち協力依頼
→ 大僧正に
□死に正面から立ち向かう 森徹
森徹(1973~1998)
スキーモーグル
平成10年
長野オリンピックモーグル代表
進行性胃ガン
◇人生の道しるべ
□張り子の虎に人生を学ぶ 谷文眺
張り子の虎
- いつも思うままに首を振っている
|
「他人の思惑で動くのではなくすべて自分の意志に従って動く。張り子の虎
は人生師」
□自分を知ることが基本 吉田兼好
吉田兼好
「いのちの終わりがいま目の前に来ていることを自覚して生きよ」
□自分の影に学ぶ 青砥藤綱
青砥藤綱(鎌倉中期武士)
滑川に落とした銭十文を五十文を費やして探し出させた逸話で有名
自分の影法師と戦う
□常に用心深く慎重に 徳川家康
徳川家康(1542~1616)
桶狭間の戦い
義元の戦死
- なかなか信ぜず 撤兵せず
完全に義元の死を確認してから
常に用心深く
「少し危うきと思うところにて馬に乗らぬものなり」
|
用心深き対処 ←→ 猪突猛進
□一遍(1239~1289)
鎌倉時代中期 時宗開祖
伊予国豪族・河野氏の出身
- 法然の弟子もと浄土教
信濃善光寺
「二河白道の図」
妻と娘
かつての従者一人を伴って遊行の旅に熊野本社百日参籠
日本各地を遊行
札を配る
「南無阿弥陀仏決定往生六十万人」
念仏を唱えながら踊る
□訓戒12箇条 醍醐天皇
醍醐天皇(在位897~930)
藤原時平と菅原道真を大臣にして天皇親政
訓戒12箇条
① 酒はたしなむ程度にとどめること
② 多言を慎むこと
③ 自分の家のことをみだりに他人に語ってはならない
④ 他人の不善を言い立てる者には近寄らないこと
⑤ 甲乙間紛争時、自分が乙と親しいときには行動を起こさずに、ただ
じっとして甲の言動に注意すること
⑥ ばかげた振る舞いをする人を友にしてはならない
⑦ 激怒してはならない
⑧ 誠実に働きおごり高ぶってはならない
⑨ 乗り物や衣服の華美を競わないこと
⑩ なるべく他人のものを借りないこと。やむを得ないときは返す日を
決めてから借りること
⑪ 知っていることと知らないことをはっきり区別しなさい
⑫ 人と対話しているときは他のことを考えないこと
「池波正太郎のそうざい料理帖」を紹介します。
最初のさわり部分の要約だけですが。
出版社の著者紹介には
「池波正太郎の酒と食の道楽は、小学校時代にまでさかのぼる。本書はその道
楽作法を、まず師のエッセイに学びとり、つぎに包丁さばきを盗み(矢吹申
彦画伯が再現)、さらにその江戸・東京の味を自ら相伴しようという、まこ
とに天晴れな虎の巻。酒家の手なぐさみに四季折々の味が愉しめ、即席食通、
にわか料理自慢になれる、本邦初の酒食料理帖。」
とあります。
「料理に挑戦」のヒントになりそうです。
もう一つ、再掲載になりますが、有馬朗人さん、中西進さんらによる
「日本例話大全書」③を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「池波正太郎のそうざい料理帖」矢吹申彦 平凡社 2003年
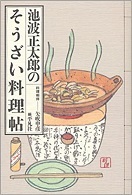
◇蛤の湯豆腐
鍋に昆布を敷いて
大根を薄く切ったものを入れると豆腐が白くふっくらと
湯豆腐の薬味は醤油と刻みネギと鰹節
◇鯛の塩焼き鍋
折り詰めの鯛の塩焼きを鍋に
調味は酒・塩 加えるは豆腐のみ
薬味は刻みネギのみ
◇浅蜊のぶっかけ飯
「浅蜊のむき身 + 大根の千切り + 七味」 をぶっかけ
昆布と醤油、酒、みりんで調味
◇ポテト・フライ
パン粉あげ
ポテトは親指の先ほど
生キャベツにウスターソース
◇豚肉のうどんすき
鍋に湯(酒半カップ)
- 酒3 水7 豚肉を750グラム
うどんをさっと入れ、玉が崩れたところへ下地
つゆ(醤油1、みりん1、だし昆布4)
◇和風オムレツ
細切れ(ジャガイモ、タマネギ、牛肉細切れ)
醤油と少しの砂糖でフライパンで炒め煮
具を卵で包む
ウスターソースで
☆『日本例話大全書』有馬朗人・中西進他 四季社 2001年 ③【再掲載 2015.3】

<生老病死>
□行基(668~749)
行基
法相宗の僧
人々に因果応報の教えを説く
公共事業を行う指導
- 社会事業と結びつく
政府
最初は弾圧するも、のち協力依頼
→ 大僧正に
□死に正面から立ち向かう 森徹
森徹(1973~1998)
スキーモーグル
平成10年
長野オリンピックモーグル代表
進行性胃ガン
◇人生の道しるべ
□張り子の虎に人生を学ぶ 谷文眺
張り子の虎
- いつも思うままに首を振っている
|
「他人の思惑で動くのではなくすべて自分の意志に従って動く。張り子の虎
は人生師」
□自分を知ることが基本 吉田兼好
吉田兼好
「いのちの終わりがいま目の前に来ていることを自覚して生きよ」
□自分の影に学ぶ 青砥藤綱
青砥藤綱(鎌倉中期武士)
滑川に落とした銭十文を五十文を費やして探し出させた逸話で有名
自分の影法師と戦う
□常に用心深く慎重に 徳川家康
徳川家康(1542~1616)
桶狭間の戦い
義元の戦死
- なかなか信ぜず 撤兵せず
完全に義元の死を確認してから
常に用心深く
「少し危うきと思うところにて馬に乗らぬものなり」
|
用心深き対処 ←→ 猪突猛進
□一遍(1239~1289)
鎌倉時代中期 時宗開祖
伊予国豪族・河野氏の出身
- 法然の弟子もと浄土教
信濃善光寺
「二河白道の図」
妻と娘
かつての従者一人を伴って遊行の旅に熊野本社百日参籠
日本各地を遊行
札を配る
「南無阿弥陀仏決定往生六十万人」
念仏を唱えながら踊る
□訓戒12箇条 醍醐天皇
醍醐天皇(在位897~930)
藤原時平と菅原道真を大臣にして天皇親政
訓戒12箇条
① 酒はたしなむ程度にとどめること
② 多言を慎むこと
③ 自分の家のことをみだりに他人に語ってはならない
④ 他人の不善を言い立てる者には近寄らないこと
⑤ 甲乙間紛争時、自分が乙と親しいときには行動を起こさずに、ただ
じっとして甲の言動に注意すること
⑥ ばかげた振る舞いをする人を友にしてはならない
⑦ 激怒してはならない
⑧ 誠実に働きおごり高ぶってはならない
⑨ 乗り物や衣服の華美を競わないこと
⑩ なるべく他人のものを借りないこと。やむを得ないときは返す日を
決めてから借りること
⑪ 知っていることと知らないことをはっきり区別しなさい
⑫ 人と対話しているときは他のことを考えないこと



