「致知」2002年12月号 ①(前半) /「哀しみを語りつぐ日本人」齋藤孝・山折哲雄 PHP 2003年 ④【再掲載 2013.7】 [読書記録 一般]
今回は、月刊誌「致知」2002年12月号の紹介1回目(前半)です。
いろいろな人へのインタビュー記事が載せられた雑誌です。
幅広い「生き方」を知ることができます。
なるほどと感心することが多いのですが、
わたしが不勉強なためでしょう、よく理解できないものも…
もう一つ、再掲載になりますが、齋藤孝さん、山折哲雄さんの
「哀しみを語りつぐ日本人」④を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「致知」2002年12月号 ①(前半)
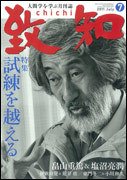
◇牛尾治朗
老子
「子の驕気 多欲 態色 淫志 いずれも子の身に益することなし」
= 自惚れたり何にでもすぐ手を出したり、もったいぶった態度をとっ
たり偏った思考をもつことをやめなさい
|
掌中の珠は最後には一つになる
「自分に最もふさわしい珠を見つけること」
◇特集:なぜ哲学が必要なのか
エピクトテス
若い頃奴隷
→ 解放されギリシャで学校
弟子の一人が「語録」
哲学の核心
「自分の意志で自由になる範囲と成らない範囲を厳密に認識」
福沢諭吉「学問のすすめ」
新鮮
明治4~9年
17編 - 各編20万部 → 総計400万部
◇「食の堕落は日本の堕落につながる」
小泉武夫(東農大教授)中條高徳(アサヒビール特別顧問)
食文化の急変
クローン病発症
キレル
戦勝国の論理に今でも支配されている国・日本
銅・亜鉛不足
→ 闘争心が強くなる
クローン症
→ ファストフードのつながり
伝承されてきた食は民族をいちばん強くする
農林省と文部省の責任大
下ごしらえの大切さ
「五思」
① 与えてくれた人に感謝
② 農民に感謝
③ 今食べていることに感謝
④ おいしさに感謝
⑤ 保存の仕方を考えてくれた人に感謝
∥
感謝することの大切さ
その国の若者を見れば20年後が分かる
悲しい予測
中立主義は食糧100%から
大切な食の伝承
うんこ製造機ではない
O157をも負かす納豆菌の威力
納豆とひじき
国力は農の力
農は国の基なり
岐阜県 梶原知事 農業活性化案
◇すべてはお客様の喜びのために 青木定雄(MKグループオーナー)
日本経済は今が最高
原点(質素と勤勉)にかえれ!
= 耐える気持ちを社会全体が
サービス向上のため従業員に家を提供
高賃金高能率
タクシーの団地営業所誕生
十年目にして返ってきた「おはようございます」
毎日が苦しかったからそれが当たり前になった
経営者は現場を離れるな
お客さんに喜ばれたら絶対につぶれない
まず経営者の人格モラルが大事
「親よりも早く寝るな。親よりも遅く起きるな。親の資産を引き継ぐので
はなく親が流した汗と脂を引き継げ」
◇田村一村 孤高の哲学を貫いた人生 湯原かの子(淑徳大学教授)
絵の中の魂
一村記念館 2001.10奄美大島
千葉時代
旅への誘い
奄美での生活
画業の完成「飢駆我」
一村絵画の美的境地 静かな死
◇人生になぜ哲学は必要か 芳村思風 思風哲学研究所
理想
① 理想に燃えて人生を生きるため
② 理性の能力をもつため
③ 幸福欲実現のため
④ 意味を問うため
⑤ 選択力を増すため
事実を探究する科学 意味を探究する哲学
もっと知りたい(認識欲) もっと幸せになりたい(幸福欲)
現実
現 = 時間
実 = 空間
科学は発見し哲学は創造する
理論と論理
理論 … 「真理は一つ」
論理 … 理論を超えた力
理性の支配を脱却し感性の本質に立つ
◇95歳剣一筋のわが人生 井上正孝(明治40年福岡生)
心掛け次第
剣の理は天の理にして人倫の大本なり
「打って反省 打たれて感謝」
「試合は神さまに対する掛かり稽古」
◇遊び心で何でもやってみる
菅原勇継 昭和41年茨城県生 玉子屋社長
一日平均五万食
企業向け仕出し弁当
銀行員から飲食業に
事業に失敗するコツ12か条
◇21世紀癒しの国のアリス 高柳和江(日本医大教授)
医者と患者のあり方
病院こそ理念が必要
人間の尊厳
死を受容し行き場を決める
死ぬ瞬間
- 脳からエンドルフィン、エンケファリン「えもいわれぬ心地よさ」
死んだあと
- どこへ行くか自分で決めてしまえばよい
「わたし お父さんの胸の中に行く」
生きる目的をもて
☆「哀しみを語りつぐ日本人」齋藤孝・山折哲雄 PHP 2003年 ④【再掲載 2013.7】
[出版社の案内]
長崎での少年による殺人事件を見るまでもなく、ここ10年ほど、子どもたち
による「感情の感じられない」犯罪が目立って報道されるようになってきた。
少年だけではない。大人も、すぐにキレ、人から注意されたらすぐに殴る事
件が多発している。▼本書は、日本的感情とでも呼ぶべきものがいまどのよ
うに衰退しているか、そしてそれを取り戻すためにはどうすればいいのかに
ついて考えた対論である。▼齋藤氏は、「喜怒哀楽」に替わる新たな感情の
分類方法として、「感情の三原色」(哀しみ・憧れ・張り)という考え方を提
唱する。また、山折氏は、さまざまな文学作品や歌などから、ことに日本的
と考えられる「哀しみ」に焦点を当て、そうした感情は文化のなかで模倣し、
学習されていくものであることを明らかにしている。▼「日本的感情のふる
さと」を訪ねる作業を通じて、いま私たちが意識的に語りつぎ、受け継ぐべ
きことは何かが浮かび上がってくる一冊である。
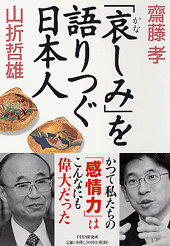
5 感情のふるさとは「身体感覚」にあり
「感情の力」が必要のない社会になってきた
子どもを抱けない母親
身体的接触の苦手な日本人
哀しみの前提は「心が一つになる」感覚にある
ヘレンケラーの運命を決めたもの
岡潔 赤ちゃんは生後18か月目に自然に運動を始める
= 1の発見
~ 全体の発見へ
|
ヘレンケラーは生後19か月目に失った
∥
◎ ヘレンケラーは岡理論を適用すると「1」を彼女が体得していたこ
とになる。だから、その後も人間的な成長が可能となったのではない
かと考えられる。
|
◎ 観念と身体運動の関連
子どもは全能感をいつ感じるのか
「自己」と「他者」の区別が始まるのはいつからか
仏精神分析学者 ジャック・ラカン
鏡像段階
生後6か月から18か月にあたる
∥
◎ 自我意識の芽生え
全能感と凶悪犯罪
幼児の全能感
~ 宇宙全体を相手にしたもの
↓
◎ 全能感は一度失われなければならない
|
自分の力に限りがあることを知る
※ 父母が「過度の全能感は絶対いけない」ことを教えなければなら
ない
|
◎「羊たちの沈黙」
歪んだ全能感によって引き起こされる犯罪
テレビゲームの罠
オウム 松本智津夫の歪んだ全能感
∥
◎ バーチャルの世界に生きている全能感
「ドラゴンボール」的末期症状
強いヤツが次々に現れる
◎日本人の心からリアリティが失われつつある
腹を抱える・たたく
- 笑いの身体感覚
微笑だけで通じ合った釈迦と弟子の心
「腹で考える」ことをやめた日本人
内臓感覚の鈍り
呼吸が作る「心の構え」
日本は「呼吸を大切にする文化」
「3秒吸って2秒止め15秒はく」呼吸法の型
声を絞り出せない若者たち
重量感と存在感
饒舌の勝海舟と溜の西郷隆盛
視聴覚教育によって教師は教師でなくなった
◎ 生徒に何も見せなくても文学や芸術そして歴史の話をできると
いうのが大切
= 「語り」の技術
絞り上げられた歌声の復活
元ちとせ
雑巾すら絞れない子どもが多い
顔を洗うのは素手かタオル?
タオルの出番は減ってしまった
いろいろな人へのインタビュー記事が載せられた雑誌です。
幅広い「生き方」を知ることができます。
なるほどと感心することが多いのですが、
わたしが不勉強なためでしょう、よく理解できないものも…
もう一つ、再掲載になりますが、齋藤孝さん、山折哲雄さんの
「哀しみを語りつぐ日本人」④を載せます。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「致知」2002年12月号 ①(前半)
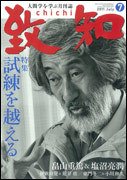
◇牛尾治朗
老子
「子の驕気 多欲 態色 淫志 いずれも子の身に益することなし」
= 自惚れたり何にでもすぐ手を出したり、もったいぶった態度をとっ
たり偏った思考をもつことをやめなさい
|
掌中の珠は最後には一つになる
「自分に最もふさわしい珠を見つけること」
◇特集:なぜ哲学が必要なのか
エピクトテス
若い頃奴隷
→ 解放されギリシャで学校
弟子の一人が「語録」
哲学の核心
「自分の意志で自由になる範囲と成らない範囲を厳密に認識」
福沢諭吉「学問のすすめ」
新鮮
明治4~9年
17編 - 各編20万部 → 総計400万部
◇「食の堕落は日本の堕落につながる」
小泉武夫(東農大教授)中條高徳(アサヒビール特別顧問)
食文化の急変
クローン病発症
キレル
戦勝国の論理に今でも支配されている国・日本
銅・亜鉛不足
→ 闘争心が強くなる
クローン症
→ ファストフードのつながり
伝承されてきた食は民族をいちばん強くする
農林省と文部省の責任大
下ごしらえの大切さ
「五思」
① 与えてくれた人に感謝
② 農民に感謝
③ 今食べていることに感謝
④ おいしさに感謝
⑤ 保存の仕方を考えてくれた人に感謝
∥
感謝することの大切さ
その国の若者を見れば20年後が分かる
悲しい予測
中立主義は食糧100%から
大切な食の伝承
うんこ製造機ではない
O157をも負かす納豆菌の威力
納豆とひじき
国力は農の力
農は国の基なり
岐阜県 梶原知事 農業活性化案
◇すべてはお客様の喜びのために 青木定雄(MKグループオーナー)
日本経済は今が最高
原点(質素と勤勉)にかえれ!
= 耐える気持ちを社会全体が
サービス向上のため従業員に家を提供
高賃金高能率
タクシーの団地営業所誕生
十年目にして返ってきた「おはようございます」
毎日が苦しかったからそれが当たり前になった
経営者は現場を離れるな
お客さんに喜ばれたら絶対につぶれない
まず経営者の人格モラルが大事
「親よりも早く寝るな。親よりも遅く起きるな。親の資産を引き継ぐので
はなく親が流した汗と脂を引き継げ」
◇田村一村 孤高の哲学を貫いた人生 湯原かの子(淑徳大学教授)
絵の中の魂
一村記念館 2001.10奄美大島
千葉時代
旅への誘い
奄美での生活
画業の完成「飢駆我」
一村絵画の美的境地 静かな死
◇人生になぜ哲学は必要か 芳村思風 思風哲学研究所
理想
① 理想に燃えて人生を生きるため
② 理性の能力をもつため
③ 幸福欲実現のため
④ 意味を問うため
⑤ 選択力を増すため
事実を探究する科学 意味を探究する哲学
もっと知りたい(認識欲) もっと幸せになりたい(幸福欲)
現実
現 = 時間
実 = 空間
科学は発見し哲学は創造する
理論と論理
理論 … 「真理は一つ」
論理 … 理論を超えた力
理性の支配を脱却し感性の本質に立つ
◇95歳剣一筋のわが人生 井上正孝(明治40年福岡生)
心掛け次第
剣の理は天の理にして人倫の大本なり
「打って反省 打たれて感謝」
「試合は神さまに対する掛かり稽古」
◇遊び心で何でもやってみる
菅原勇継 昭和41年茨城県生 玉子屋社長
一日平均五万食
企業向け仕出し弁当
銀行員から飲食業に
事業に失敗するコツ12か条
◇21世紀癒しの国のアリス 高柳和江(日本医大教授)
医者と患者のあり方
病院こそ理念が必要
人間の尊厳
死を受容し行き場を決める
死ぬ瞬間
- 脳からエンドルフィン、エンケファリン「えもいわれぬ心地よさ」
死んだあと
- どこへ行くか自分で決めてしまえばよい
「わたし お父さんの胸の中に行く」
生きる目的をもて
☆「哀しみを語りつぐ日本人」齋藤孝・山折哲雄 PHP 2003年 ④【再掲載 2013.7】
[出版社の案内]
長崎での少年による殺人事件を見るまでもなく、ここ10年ほど、子どもたち
による「感情の感じられない」犯罪が目立って報道されるようになってきた。
少年だけではない。大人も、すぐにキレ、人から注意されたらすぐに殴る事
件が多発している。▼本書は、日本的感情とでも呼ぶべきものがいまどのよ
うに衰退しているか、そしてそれを取り戻すためにはどうすればいいのかに
ついて考えた対論である。▼齋藤氏は、「喜怒哀楽」に替わる新たな感情の
分類方法として、「感情の三原色」(哀しみ・憧れ・張り)という考え方を提
唱する。また、山折氏は、さまざまな文学作品や歌などから、ことに日本的
と考えられる「哀しみ」に焦点を当て、そうした感情は文化のなかで模倣し、
学習されていくものであることを明らかにしている。▼「日本的感情のふる
さと」を訪ねる作業を通じて、いま私たちが意識的に語りつぎ、受け継ぐべ
きことは何かが浮かび上がってくる一冊である。
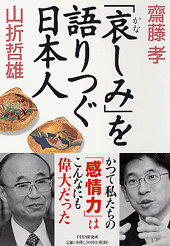
5 感情のふるさとは「身体感覚」にあり
「感情の力」が必要のない社会になってきた
子どもを抱けない母親
身体的接触の苦手な日本人
哀しみの前提は「心が一つになる」感覚にある
ヘレンケラーの運命を決めたもの
岡潔 赤ちゃんは生後18か月目に自然に運動を始める
= 1の発見
~ 全体の発見へ
|
ヘレンケラーは生後19か月目に失った
∥
◎ ヘレンケラーは岡理論を適用すると「1」を彼女が体得していたこ
とになる。だから、その後も人間的な成長が可能となったのではない
かと考えられる。
|
◎ 観念と身体運動の関連
子どもは全能感をいつ感じるのか
「自己」と「他者」の区別が始まるのはいつからか
仏精神分析学者 ジャック・ラカン
鏡像段階
生後6か月から18か月にあたる
∥
◎ 自我意識の芽生え
全能感と凶悪犯罪
幼児の全能感
~ 宇宙全体を相手にしたもの
↓
◎ 全能感は一度失われなければならない
|
自分の力に限りがあることを知る
※ 父母が「過度の全能感は絶対いけない」ことを教えなければなら
ない
|
◎「羊たちの沈黙」
歪んだ全能感によって引き起こされる犯罪
テレビゲームの罠
オウム 松本智津夫の歪んだ全能感
∥
◎ バーチャルの世界に生きている全能感
「ドラゴンボール」的末期症状
強いヤツが次々に現れる
◎日本人の心からリアリティが失われつつある
腹を抱える・たたく
- 笑いの身体感覚
微笑だけで通じ合った釈迦と弟子の心
「腹で考える」ことをやめた日本人
内臓感覚の鈍り
呼吸が作る「心の構え」
日本は「呼吸を大切にする文化」
「3秒吸って2秒止め15秒はく」呼吸法の型
声を絞り出せない若者たち
重量感と存在感
饒舌の勝海舟と溜の西郷隆盛
視聴覚教育によって教師は教師でなくなった
◎ 生徒に何も見せなくても文学や芸術そして歴史の話をできると
いうのが大切
= 「語り」の技術
絞り上げられた歌声の復活
元ちとせ
雑巾すら絞れない子どもが多い
顔を洗うのは素手かタオル?
タオルの出番は減ってしまった



