「知的複眼思考法」苅谷剛彦 講談社+α文庫 2002年 ② /「あるがままに老いる」大原健士郎 毎日新聞社 2001年 ②【再掲載 2016.6】 [読書記録 一般]
今回は3月14日に続いて苅谷剛彦さんの、
「知的複眼思考」の紹介 2回目です。
出版社の案内には、
「常識にとらわれた単眼思考を行っていては、いつまでたっても『自分
の頭で考える』ことはできない。自分自身の視点からものごとを多角
的に捉えて考え抜く、それが知的複眼思考法だ。情報を正確に読みと
る力。ものごとの筋道を追う力。受け取った情報をもとに自分の論理
をきちんと組み立てられる力。こうした基本的な考える力を基礎にし
てこそ、自分の頭で考えていくことができる。ベストティーチャーの
奥義!!
全国3万人の大学生が選んだベストティーチャーの奥義!!
逆風の時代を生き抜くには、知識を超える「何か」が必要になる。
正解を見つける力より問題点を見出す力を。
真実が見える瞬間のスリルが人生を変える!!
常識にとらわれた単眼思考を行っていては、いつまでたっても『自分
の頭で考える』ことはできない。自分自身の視点からものごとを多角
的に捉えて考え抜く-それが知的複眼思考法だ。情報を正確に読みと
る力。ものごとの筋道を追う力。受け取った情報をもとに自分の論理
をきちんと組み立てられる力。こうした基本的な考える力を基礎にし
てこそ、自分の頭で考えていくことができる。全国3万人の大学生が
選んだ日本のベストティーチャーによる思考法の真髄!」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「考える力を養うための情報や知識との確答の時間を耐えてくれるの
が読書の効用ということができる」
・「行間に目を向け論の集め方をじっくりとらえて著者と対等な立場に
立つ」
・「受け入れる読書だけでは自分で考えるようにならない。批判的に読
み吟味することが大切。」
・「著者の考える筋道を追体験すると自分の思考力強化になる」
もう一つ、再掲載になりますが、大原健士郎さんの
「あるがままに老いる」②を載せます。
☆「知的複眼思考法」苅谷剛彦 講談社+α文庫 2002年 ②

<創造的読書で思考力を鍛える>
◇著者の立場・読者の立場
□STEP1 読書の効用
本でなければ得られないものは?
- 考える力を養うための情報や知識との確答の時間を耐えてく
れる
受け手のペースに合わせて!
<時間の掛け方が自由>~余裕
□STEP2 著者と対等な立場に立つ
行間に目を向け論の集め方をじっくり捉える
◇知識の受容から知識の創造へ
□STEP1 批判的に読む
受け入れる読書だけでは自分で考えるようにならない
批判的に読む
= 吟味
著者の考える筋道を追体験する
→ 自分の思考力強化
□STEP2 鵜呑みにしない態度を身に付ける
① 眉に唾して本を読む
批判的読書のコツ 20のポイント P92
② 著者のねらいをつかむ
③ 論理を追う
根拠がどれだけあるか
流行の言い回しに注意
④ 著者の前提を知る
□STEP3 批判的読書の実践法
数字にダマされるな
□STEP2 批判的読書にチャレンジ
考える読書4つのヒント
① 論理を読む
② 先を読む読書
③ 古い文章の○○(不明)
④ 書評のすすめ
☆「あるがままに老いる」大原健士郎 毎日新聞社 2001年 ②【再掲載 2016.6】
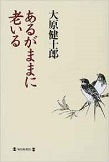
◇安楽死
高良竹久(~1996)
森田正馬の高弟(大原の師)
森田と違い,自殺・安楽死を肯定
安楽死
「一日も一秒も長く生きてほしい」
「苦しむだけならできるだけ早く死なせてほしい」
- 矛盾した二つの気持ちを内包
殺人の中に許される殺人があるかどうかの問題
←→ 患者自身が役割意識を持ち,周囲の人々が役割期待を持
つ限り安楽死は起こってこない。
◇臨死患者の精神療法
キューブラー・ロス博士
死を受け入れるまでの五段階
① 不安と疑惑
② 不安と焦燥
③ 怒りと恨み
④ 悲哀
⑤ あきらめ
- 注目:生きる希望を抱き続けている
近年,ネオ・モリタセラピーの台頭(神経症以外の患者にも)
森田 「己の性をつくす」
自分の存在意義を改めて自己表現しよう
倉敷 伊丹仁郎 「生き甲斐療法」
◇老人の生き甲斐
努力家のおかげで社会が進歩し人々が幸せな生活を送れる(頑張る人)。
遊びは生き甲斐にはなれない
= 遊びは遊び,人生の潤滑油
生き甲斐
= 自己実現の歓び
① 生涯持ち続けている生き甲斐 社会性を含ませる必要
② その場その場での当面の生き甲斐 実用的,次から次へ
◇記念日自殺
老人に自殺が多い
① 弱い存在-他に依存
② 孤独になりやすい
③ 鬱病的 精神障害が多い
④ 身体的持病が多い
⑤ 人生に希望が見出せない
自殺の心理学的特徴
「孤独」
老人の自殺
- アニバーサル自殺
催し物の日 配偶者の命日等
米国
- クールな自殺
日本
- ホットな自殺
熱い身内との争い - 敗北
恨み辛みを抱き続けて
◎ 老人は生き甲斐を持ち,温かい対人関係を求め,役割意識に目覚
めることである。
- 役割期待
◎ 老人に余暇と経済を保証するだけでは,決して老人を幸せにするこ
とはできない。
「知的複眼思考」の紹介 2回目です。
出版社の案内には、
「常識にとらわれた単眼思考を行っていては、いつまでたっても『自分
の頭で考える』ことはできない。自分自身の視点からものごとを多角
的に捉えて考え抜く、それが知的複眼思考法だ。情報を正確に読みと
る力。ものごとの筋道を追う力。受け取った情報をもとに自分の論理
をきちんと組み立てられる力。こうした基本的な考える力を基礎にし
てこそ、自分の頭で考えていくことができる。ベストティーチャーの
奥義!!
全国3万人の大学生が選んだベストティーチャーの奥義!!
逆風の時代を生き抜くには、知識を超える「何か」が必要になる。
正解を見つける力より問題点を見出す力を。
真実が見える瞬間のスリルが人生を変える!!
常識にとらわれた単眼思考を行っていては、いつまでたっても『自分
の頭で考える』ことはできない。自分自身の視点からものごとを多角
的に捉えて考え抜く-それが知的複眼思考法だ。情報を正確に読みと
る力。ものごとの筋道を追う力。受け取った情報をもとに自分の論理
をきちんと組み立てられる力。こうした基本的な考える力を基礎にし
てこそ、自分の頭で考えていくことができる。全国3万人の大学生が
選んだ日本のベストティーチャーによる思考法の真髄!」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「考える力を養うための情報や知識との確答の時間を耐えてくれるの
が読書の効用ということができる」
・「行間に目を向け論の集め方をじっくりとらえて著者と対等な立場に
立つ」
・「受け入れる読書だけでは自分で考えるようにならない。批判的に読
み吟味することが大切。」
・「著者の考える筋道を追体験すると自分の思考力強化になる」
もう一つ、再掲載になりますが、大原健士郎さんの
「あるがままに老いる」②を載せます。
☆「知的複眼思考法」苅谷剛彦 講談社+α文庫 2002年 ②

<創造的読書で思考力を鍛える>
◇著者の立場・読者の立場
□STEP1 読書の効用
本でなければ得られないものは?
- 考える力を養うための情報や知識との確答の時間を耐えてく
れる
受け手のペースに合わせて!
<時間の掛け方が自由>~余裕
□STEP2 著者と対等な立場に立つ
行間に目を向け論の集め方をじっくり捉える
◇知識の受容から知識の創造へ
□STEP1 批判的に読む
受け入れる読書だけでは自分で考えるようにならない
批判的に読む
= 吟味
著者の考える筋道を追体験する
→ 自分の思考力強化
□STEP2 鵜呑みにしない態度を身に付ける
① 眉に唾して本を読む
批判的読書のコツ 20のポイント P92
② 著者のねらいをつかむ
③ 論理を追う
根拠がどれだけあるか
流行の言い回しに注意
④ 著者の前提を知る
□STEP3 批判的読書の実践法
数字にダマされるな
□STEP2 批判的読書にチャレンジ
考える読書4つのヒント
① 論理を読む
② 先を読む読書
③ 古い文章の○○(不明)
④ 書評のすすめ
☆「あるがままに老いる」大原健士郎 毎日新聞社 2001年 ②【再掲載 2016.6】
◇安楽死
高良竹久(~1996)
森田正馬の高弟(大原の師)
森田と違い,自殺・安楽死を肯定
安楽死
「一日も一秒も長く生きてほしい」
「苦しむだけならできるだけ早く死なせてほしい」
- 矛盾した二つの気持ちを内包
殺人の中に許される殺人があるかどうかの問題
←→ 患者自身が役割意識を持ち,周囲の人々が役割期待を持
つ限り安楽死は起こってこない。
◇臨死患者の精神療法
キューブラー・ロス博士
死を受け入れるまでの五段階
① 不安と疑惑
② 不安と焦燥
③ 怒りと恨み
④ 悲哀
⑤ あきらめ
- 注目:生きる希望を抱き続けている
近年,ネオ・モリタセラピーの台頭(神経症以外の患者にも)
森田 「己の性をつくす」
自分の存在意義を改めて自己表現しよう
倉敷 伊丹仁郎 「生き甲斐療法」
◇老人の生き甲斐
努力家のおかげで社会が進歩し人々が幸せな生活を送れる(頑張る人)。
遊びは生き甲斐にはなれない
= 遊びは遊び,人生の潤滑油
生き甲斐
= 自己実現の歓び
① 生涯持ち続けている生き甲斐 社会性を含ませる必要
② その場その場での当面の生き甲斐 実用的,次から次へ
◇記念日自殺
老人に自殺が多い
① 弱い存在-他に依存
② 孤独になりやすい
③ 鬱病的 精神障害が多い
④ 身体的持病が多い
⑤ 人生に希望が見出せない
自殺の心理学的特徴
「孤独」
老人の自殺
- アニバーサル自殺
催し物の日 配偶者の命日等
米国
- クールな自殺
日本
- ホットな自殺
熱い身内との争い - 敗北
恨み辛みを抱き続けて
◎ 老人は生き甲斐を持ち,温かい対人関係を求め,役割意識に目覚
めることである。
- 役割期待
◎ 老人に余暇と経済を保証するだけでは,決して老人を幸せにするこ
とはできない。



