「悲しみの精神史」山折哲雄 PHP研究所 2002年 ① /「学級再生」小林正幸 講談社現代新書 2001年 ④【再掲載 2015.12】 [読書記録 一般]
今回は、山折哲雄さんの
「悲しみの精神史」の紹介 1回目です。
出版社の紹介には
「国際日本文化研究センター所長にして宗教学の権威でもある著者は問う。
『幸福と成功を追い求めるだけが人生なのか』と。むしろ著者は『不幸な悲
しみに耐えている人間に尊敬を抱く』とも。その問題意識のもと、自らの死
を予感していた源実朝、親族を皆殺しにした北条時頼、乞食願望を持ち続け
た松尾芭蕉、キリスト教に入信した支倉常長、死んだ妹の魂を追いかけて旅
した宮沢賢治、殉死の予行演習をしていた乃木希典、晩年の著作に執着した
松本清張、死後も自分の欲望を満たそうとした谷崎潤一郎、『黒い雨』に慟
哭の通奏低音を挿入した井伏鱒二、上官の罪を背負って処刑された青年学徒
などを取り上げつつ、縄文の昔から日本人の底流に流れ続ける『悲しみ』の
旋律を描いた渾身の作品。幸福願望ばかりが肥大化する現代において、『孤
独とは何か』『人生の無常とは何か』を考えるうえで大切な視点を提示して
くれる一冊でもある。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「1 人間について比較することをやめる
2 だます人間よりだまされる人間になる
3 一人で歩く(群れからの脱出)」
・「『永訣の朝』-なぜ賢治の言葉は標準語なのか」
・「富士山は世にも恐ろしい異界の山だった」
・「折口信夫の『ねちっこい愛』
ねちっこい愛は酷薄・非情の愛の仕打ちと背中合わせ」
・「判官贔屓は怨念を融和しようとする同情の念」
もう一つ、再掲載になりますが、小林正幸さんの
「学級再生」④を載せます。
学級づくり、学級経営に悩んだときのヒントを教えてくれる本です。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「悲しみの精神史」山折哲雄 PHP研究所 2002年 ①
◇まえがき
「幸福を売る宗教」「99%の幸福を広告宣伝する経済」
|
1 人間について比較することをやめる
2 だます人間よりだまされる人間になる
3 一人で歩く(群れからの脱出)
◇宮澤賢治の挽歌
なぜ賢治の言葉は標準語なのか
「永訣の朝」
とし子の魂の行方を追いかける旅へ
標準語で呼び掛ける賢治と岩手弁で応答するとし子
「あめゆじゃとてちてけんじゃ」の悲傷
◇寂寥(せきりょう)に生きた万葉人
仏教という哲学が歌を滅ぼした
折口
- 古代の唯一の主人公は「まれびと」
富士山は世にも恐ろしい異界の山だった
無際限の孤独の中で燃えさかるもの
縄文の神であり蝦夷の神であった富士
|
古代人の恐怖、万葉人の寂寥
◇「もののあはれ」と「もののけ」
「源氏物語」に陶酔した川端康成
悪徳も美徳もみな悲しみに紛れ入る
相聞の美しさと挽歌の悲しみと…
◇「徒然草」に吹く無常の風
折口信夫の「ねちっこい愛」
師・折口信夫と弟子・穂積生萩
ねちっこい愛は酷薄・非情の愛の仕打ちと背中合わせ
吉田兼好もまた執念深い心を持っていた
独り住まいこそ真に奥ゆかしい生き方
◇源義経は祟らず
道真も将門も正成も怨霊化した
源九郎判官義経(1156-1189)
理不尽な非業の死
なぜ舞台の義経は「子方」なのか
子方ヒーロー・悲運に涙する多感な貴公子
判官贔屓の勢いに押されて…
|
弱小,可憐なるものへの同情を浴び,イメージは無力な主君の地位
へと後退していった → 共感,哀傷の対象,薄命の英雄
◎ 判官という官職の故悲運の英雄へ(後白河法皇の策)
|
判官物と判官びいきの美意識
◎判官贔屓は怨念を融和しようとする同情の念
東北感情
-「平家物語」の西国感情と対偶
☆「学級再生」小林正幸 講談社現代新書 2001年 ④【再掲載 2015.12】
[出版社の案内]
「学級崩壊」はなぜかくも広がったか。問題解決と予防のコツとは何か―。
教育臨床心理学の現場から説く、画期的「教育再生論」。
「学級崩壊」を予防し、解決する必須ノウハウ!学校は子どもを守れるか
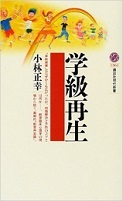
◇問題が深刻な段階で教師が行うこと
大人の都合で方針を変えない
仕切り直しをする(再契約法)
「どういう学級になってほしいのか」
「学級にどのようなことを思っているのか」
「どうすればよいと思うか」
→ 声なき声を
アンケート
→ アンケート結果を子どもに紹介
→ 目標を提示
→ 対策を提案
◎「学級目標の再確認」「再設定」
ルールの再確認
「学級,学校が楽しくなるために定めるもの」
① 人の話を最後まで聞く
② 問題が起きたら相手の気持ちを考える
③ 係の責任を果たす
④ みんなで使う物を大切にする
⑤ 人の嫌がることや体のことを言わない
= 標準的な5つのルール(河村 2000)
仕切り直しのタイミング
問題への危機介入の手順を決めておく
個別指導
その行動で何を得たかったのか確認する
①「今どんな気持ち」
②「そうなってしまったのはなぜ」
③「この次どうすればいいの」
危機場面で問題を起こしていない子どもに行うこと
「○○があったので△△さんは今別なところにいます。みんなは心配
しないでください」
「本人からではなく 満たされない気持ち」
- 心配です
「けれどもこのように教室にいる君たちの気持ちを先生は大切にした
いのです。ですから,いつもと同じように授業をします。」
楽しいイベントを繰り返し行う
イベントゲームの組み方
「王様じゃんけん」
教師対じゃんけん
「サケとサメ」
サケ組とサメ組
「何でもバスケット」
体育館で行う
休み時間の活用
子どもと遊ぶ
- 何人かでよい
← ◎ 全員には声を掛けない
数名にだけ声 校庭教室の片隅で
「みんなで一緒に」を目指さないこと
オプションの用意を
個別相談の回数を増やす
「いつでも誰でも相談したいときには相談に来てほしい」
× アドバイス
◎ ほめる
「今まで一人でそのことを考えながらよく頑張ったね」
「勇気がいったでしょう」
学習の場面での工夫も小さな集団から
二人のペアから
ゲーム仕立てで作業
壊してはつくる
2~4人でコミュニケーション
授業での子どもへの応答
応答スキルの磨き方
= 聞く
10分でよいトレーニング
プロは凡ミスをしない「相手の発言を繰り返す」
~ 子どもの発言を繰り返すだけでよい
相手の感情,願いに注目した応答
先生への個人攻撃,罵声
→ 挑発に乗らない
その瞬間には応じない
= きりのいいところまで1分間程度続ける
1分は無視して、その子の傍らに一直線
背筋を伸ばして足を開いて立つ
「さっき何と言ったかな」
「もう一度言ってください」
|
にっこり
「君は先生やみんなに見てもらいたいからこんな風にいうのだと思って
います」 (穏やかに優しく本心から)
→ 本人の言葉を制限してコメント
自己評価が的確にできるように援助する
大切 教師の応答スキル
授業後の自己評価
授業は
おもしろかった・ふつう・つまらなかった
授業を
一生懸命した・ふつう・あまりできなかった
授業で学んだことは何か
自由記述
↓
提出で終わり
「悲しみの精神史」の紹介 1回目です。
出版社の紹介には
「国際日本文化研究センター所長にして宗教学の権威でもある著者は問う。
『幸福と成功を追い求めるだけが人生なのか』と。むしろ著者は『不幸な悲
しみに耐えている人間に尊敬を抱く』とも。その問題意識のもと、自らの死
を予感していた源実朝、親族を皆殺しにした北条時頼、乞食願望を持ち続け
た松尾芭蕉、キリスト教に入信した支倉常長、死んだ妹の魂を追いかけて旅
した宮沢賢治、殉死の予行演習をしていた乃木希典、晩年の著作に執着した
松本清張、死後も自分の欲望を満たそうとした谷崎潤一郎、『黒い雨』に慟
哭の通奏低音を挿入した井伏鱒二、上官の罪を背負って処刑された青年学徒
などを取り上げつつ、縄文の昔から日本人の底流に流れ続ける『悲しみ』の
旋律を描いた渾身の作品。幸福願望ばかりが肥大化する現代において、『孤
独とは何か』『人生の無常とは何か』を考えるうえで大切な視点を提示して
くれる一冊でもある。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「1 人間について比較することをやめる
2 だます人間よりだまされる人間になる
3 一人で歩く(群れからの脱出)」
・「『永訣の朝』-なぜ賢治の言葉は標準語なのか」
・「富士山は世にも恐ろしい異界の山だった」
・「折口信夫の『ねちっこい愛』
ねちっこい愛は酷薄・非情の愛の仕打ちと背中合わせ」
・「判官贔屓は怨念を融和しようとする同情の念」
もう一つ、再掲載になりますが、小林正幸さんの
「学級再生」④を載せます。
学級づくり、学級経営に悩んだときのヒントを教えてくれる本です。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「悲しみの精神史」山折哲雄 PHP研究所 2002年 ①
◇まえがき
「幸福を売る宗教」「99%の幸福を広告宣伝する経済」
|
1 人間について比較することをやめる
2 だます人間よりだまされる人間になる
3 一人で歩く(群れからの脱出)
◇宮澤賢治の挽歌
なぜ賢治の言葉は標準語なのか
「永訣の朝」
とし子の魂の行方を追いかける旅へ
標準語で呼び掛ける賢治と岩手弁で応答するとし子
「あめゆじゃとてちてけんじゃ」の悲傷
◇寂寥(せきりょう)に生きた万葉人
仏教という哲学が歌を滅ぼした
折口
- 古代の唯一の主人公は「まれびと」
富士山は世にも恐ろしい異界の山だった
無際限の孤独の中で燃えさかるもの
縄文の神であり蝦夷の神であった富士
|
古代人の恐怖、万葉人の寂寥
◇「もののあはれ」と「もののけ」
「源氏物語」に陶酔した川端康成
悪徳も美徳もみな悲しみに紛れ入る
相聞の美しさと挽歌の悲しみと…
◇「徒然草」に吹く無常の風
折口信夫の「ねちっこい愛」
師・折口信夫と弟子・穂積生萩
ねちっこい愛は酷薄・非情の愛の仕打ちと背中合わせ
吉田兼好もまた執念深い心を持っていた
独り住まいこそ真に奥ゆかしい生き方
◇源義経は祟らず
道真も将門も正成も怨霊化した
源九郎判官義経(1156-1189)
理不尽な非業の死
なぜ舞台の義経は「子方」なのか
子方ヒーロー・悲運に涙する多感な貴公子
判官贔屓の勢いに押されて…
|
弱小,可憐なるものへの同情を浴び,イメージは無力な主君の地位
へと後退していった → 共感,哀傷の対象,薄命の英雄
◎ 判官という官職の故悲運の英雄へ(後白河法皇の策)
|
判官物と判官びいきの美意識
◎判官贔屓は怨念を融和しようとする同情の念
東北感情
-「平家物語」の西国感情と対偶
☆「学級再生」小林正幸 講談社現代新書 2001年 ④【再掲載 2015.12】
[出版社の案内]
「学級崩壊」はなぜかくも広がったか。問題解決と予防のコツとは何か―。
教育臨床心理学の現場から説く、画期的「教育再生論」。
「学級崩壊」を予防し、解決する必須ノウハウ!学校は子どもを守れるか
◇問題が深刻な段階で教師が行うこと
大人の都合で方針を変えない
仕切り直しをする(再契約法)
「どういう学級になってほしいのか」
「学級にどのようなことを思っているのか」
「どうすればよいと思うか」
→ 声なき声を
アンケート
→ アンケート結果を子どもに紹介
→ 目標を提示
→ 対策を提案
◎「学級目標の再確認」「再設定」
ルールの再確認
「学級,学校が楽しくなるために定めるもの」
① 人の話を最後まで聞く
② 問題が起きたら相手の気持ちを考える
③ 係の責任を果たす
④ みんなで使う物を大切にする
⑤ 人の嫌がることや体のことを言わない
= 標準的な5つのルール(河村 2000)
仕切り直しのタイミング
問題への危機介入の手順を決めておく
個別指導
その行動で何を得たかったのか確認する
①「今どんな気持ち」
②「そうなってしまったのはなぜ」
③「この次どうすればいいの」
危機場面で問題を起こしていない子どもに行うこと
「○○があったので△△さんは今別なところにいます。みんなは心配
しないでください」
「本人からではなく 満たされない気持ち」
- 心配です
「けれどもこのように教室にいる君たちの気持ちを先生は大切にした
いのです。ですから,いつもと同じように授業をします。」
楽しいイベントを繰り返し行う
イベントゲームの組み方
「王様じゃんけん」
教師対じゃんけん
「サケとサメ」
サケ組とサメ組
「何でもバスケット」
体育館で行う
休み時間の活用
子どもと遊ぶ
- 何人かでよい
← ◎ 全員には声を掛けない
数名にだけ声 校庭教室の片隅で
「みんなで一緒に」を目指さないこと
オプションの用意を
個別相談の回数を増やす
「いつでも誰でも相談したいときには相談に来てほしい」
× アドバイス
◎ ほめる
「今まで一人でそのことを考えながらよく頑張ったね」
「勇気がいったでしょう」
学習の場面での工夫も小さな集団から
二人のペアから
ゲーム仕立てで作業
壊してはつくる
2~4人でコミュニケーション
授業での子どもへの応答
応答スキルの磨き方
= 聞く
10分でよいトレーニング
プロは凡ミスをしない「相手の発言を繰り返す」
~ 子どもの発言を繰り返すだけでよい
相手の感情,願いに注目した応答
先生への個人攻撃,罵声
→ 挑発に乗らない
その瞬間には応じない
= きりのいいところまで1分間程度続ける
1分は無視して、その子の傍らに一直線
背筋を伸ばして足を開いて立つ
「さっき何と言ったかな」
「もう一度言ってください」
|
にっこり
「君は先生やみんなに見てもらいたいからこんな風にいうのだと思って
います」 (穏やかに優しく本心から)
→ 本人の言葉を制限してコメント
自己評価が的確にできるように援助する
大切 教師の応答スキル
授業後の自己評価
授業は
おもしろかった・ふつう・つまらなかった
授業を
一生懸命した・ふつう・あまりできなかった
授業で学んだことは何か
自由記述
↓
提出で終わり



