「発達障害サポートマニュアル」榊原洋一 上原芳枝 PHP 2011年 ⑤(最終) /「地域住民から福祉・教育関係者等への無理難題要求をどう読み解き対応するか」~イチャモン研究の到達点~ 大阪大学教授 小野田正利 2008年 ⑨【再掲載 2015.11】 [読書記録 教育]
今回は、6月23日に続いて、榊原洋一さん、上原芳枝さんの
「発達障害サポートマニュアル」5回目の紹介 最終です。
要約に疲れたのか、「事情」や「サポート」があまりメモされていませんでし
た。
わたしも何らかの発達上の障害-くせがあると感じています。
子育て、教育にたずさわる方には、「発達障害」という言葉にとらわれず、
ヒントが載っている本書を読むことをおすすめします。
出版社の紹介には
「意外なことですが、『しかる・ほめる・慣れさせる』という方法では、発達
障害の子どもの場合、効果は期待できないのです。では、親も子も先生も楽
になるような、気になる子の育て方とは。発達障害をかかえる子どもに対し
て、実際にどのように対処するのが最善なのか。具体的な例とともに、いま
すぐできる接し方を詳細に解説
内容例【幼稚園・保育園】朝、園に入るのを嫌がる/いちばん前に並びたが
る/人のものを取ってしまう/ものを壊す/お片付けができない/視線が宙
に浮く……【学校生活】文字が読めない/計算ができない/音楽の授業が苦
手/離籍や飛び出しをする/全体に向けての話を聞けない/体に触れられる
と怒る……【家庭生活】お出かけすると問題が起こる一方的に興味があるこ
とを話す/こだわりが強い/衣服への固執、無頓着/時間を守れない/宿題
ができない…… 幼稚園・保育園・小学校の教育関係者、医療従事者、家族
の方々必携の一冊。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「文字が整わない子供には大きなますをノート(プリント)に描き入れる」
・「繰り上がりや繰り下がりの計算ができない子供には○や□で囲む」
・「文章題が解けない」
- 苦手な子供には、「わかたず」が有効でした。
・「泣いたり、暴れたりパニックになった時には、落ち着いた場所に連れて
行ったり、事前に別室、トイレ、隙間、机の下に連れて行くなどすると
落ち着くことが多い」
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「発達障害サポートマニュアル」榊原洋一 上原芳枝 PHP 2011年 ⑤(最終)

◇学校生活でのサポート 実例
ケース⑬
◎文字が読めない
事情① 視覚認知の問題
サポート① 拡大コピー
事情② 記憶の問題
サポート② 本人の特性
ケース⑭
◎文字が書けない
ケース⑮
◎文字が整わない
大きなます
ことば
ケース⑯
◎文字が読めない
区切り線
ケース⑰
◎文章の中で漢字が書けない
後で直す
ケース⑱
◎計算ができない
○や□で囲む
- 繰り上がり、繰り下がり
ケース⑲
◎文章題が解けない
ケース⑳
◎作文が書けない
ひな型 パターン
ケース21
◎黒板の文字を書き写さない
ワーキングメモリー不足
→ 小声で
ケース22
◎体育に参加しない
部分で参加
ケース23
◎音楽が苦手
ケース24
◎図工が苦手
ケース25
◎休み時間に遊ばない
◇家庭生活でのサポート 実例
パニック時の対処
①落ち着いた場所に連れて行く
別室、トイレ、隙間、机の下
or 他の児童を他の場所に
②安心グッズの用意
本、石
③空気転換
④他の子への対応
⑤自分で対処させる
◇榊原洋一
お茶の水大学大学院教授 医学博士 発達神経学
◇上原芳枝
☆「地域住民から福祉・教育関係者等への無理難題要求をどう読み解き対応するか」~イチャモン研究の到達点~ 大阪大学教授 小野田正利 2008年 ⑨【再掲載 2015.11】
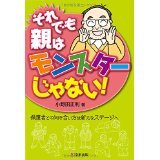
◇悲鳴をあげる学校
「私はAさんと仲が悪いから、私の子とAさんの子は別々のクラスにしてほ
しい。」
「同じオモチャをとりあってケンカになるぐらいなら、そんなオモチャは園
に置かなでほしい。」
「ウチの子は自己紹介が苦手だから、クラスの中で自己紹介をする場面をつ
くらないでほしい。どうしてもさせるというのなら休ませます。」
「運動会ではマイクを使うな。」
「ブラスバンドは窓を閉めて練習して欲しい。」
いま全国の学校が、こめような多様な要求に悩まされています。
私は、保護者や地域から学校に寄せられる要求を三段階に分けています。
「学校がやるべきことに対するまっとうな要求」が「要望」、「学校がある程
度まで対応すべき要求」が「苦情」、そして「学校にもどうにでもできない
要求」が「イチャモン(無理難題要求)」です。
私は、多くのインタビュー調査とともに、この4年間に3回のアンケート調
査もおこなってきました。
無理難題的要求が本当に増えてきているのかについての明確な数字は示すこ
とはできませんが、確実に言えることは、「要望]よりも「苦情」が急増し、さ
らには「無理難題要求」が多くなってきたと感じる(実感値)教員が多数いる
ということです)。
学校に対する要求が拡大し続け、学校の責任領域や守備範囲を超えることま
でが求められる中で、学校側は一度もミスをすることを許されない存在、とし
て理解されはじめます。
受け止めきれなくなった学校側は「突っ込まれた」時に説明できるように証
拠記録を残し、ありとあらゆる防御策を張りめぐらせ、時には不必要と思われ
るような防御策まで講じる状況が進んでいます。
「突っ込み」→「自信喪失」→「過剰防衛」の繰り返しともいえますが、本来
的な子どもとの触れ合いや学校教育に時間や精力を割くということよりは、ト
ラブル対策に心砕くしんどさが最もつらい、と多くの教師は言います。
「発達障害サポートマニュアル」5回目の紹介 最終です。
要約に疲れたのか、「事情」や「サポート」があまりメモされていませんでし
た。
わたしも何らかの発達上の障害-くせがあると感じています。
子育て、教育にたずさわる方には、「発達障害」という言葉にとらわれず、
ヒントが載っている本書を読むことをおすすめします。
出版社の紹介には
「意外なことですが、『しかる・ほめる・慣れさせる』という方法では、発達
障害の子どもの場合、効果は期待できないのです。では、親も子も先生も楽
になるような、気になる子の育て方とは。発達障害をかかえる子どもに対し
て、実際にどのように対処するのが最善なのか。具体的な例とともに、いま
すぐできる接し方を詳細に解説
内容例【幼稚園・保育園】朝、園に入るのを嫌がる/いちばん前に並びたが
る/人のものを取ってしまう/ものを壊す/お片付けができない/視線が宙
に浮く……【学校生活】文字が読めない/計算ができない/音楽の授業が苦
手/離籍や飛び出しをする/全体に向けての話を聞けない/体に触れられる
と怒る……【家庭生活】お出かけすると問題が起こる一方的に興味があるこ
とを話す/こだわりが強い/衣服への固執、無頓着/時間を守れない/宿題
ができない…… 幼稚園・保育園・小学校の教育関係者、医療従事者、家族
の方々必携の一冊。」
とあります。
本日紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「文字が整わない子供には大きなますをノート(プリント)に描き入れる」
・「繰り上がりや繰り下がりの計算ができない子供には○や□で囲む」
・「文章題が解けない」
- 苦手な子供には、「わかたず」が有効でした。
・「泣いたり、暴れたりパニックになった時には、落ち着いた場所に連れて
行ったり、事前に別室、トイレ、隙間、机の下に連れて行くなどすると
落ち着くことが多い」
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「発達障害サポートマニュアル」榊原洋一 上原芳枝 PHP 2011年 ⑤(最終)

◇学校生活でのサポート 実例
ケース⑬
◎文字が読めない
事情① 視覚認知の問題
サポート① 拡大コピー
事情② 記憶の問題
サポート② 本人の特性
ケース⑭
◎文字が書けない
ケース⑮
◎文字が整わない
大きなます
ことば
ケース⑯
◎文字が読めない
区切り線
ケース⑰
◎文章の中で漢字が書けない
後で直す
ケース⑱
◎計算ができない
○や□で囲む
- 繰り上がり、繰り下がり
ケース⑲
◎文章題が解けない
ケース⑳
◎作文が書けない
ひな型 パターン
ケース21
◎黒板の文字を書き写さない
ワーキングメモリー不足
→ 小声で
ケース22
◎体育に参加しない
部分で参加
ケース23
◎音楽が苦手
ケース24
◎図工が苦手
ケース25
◎休み時間に遊ばない
◇家庭生活でのサポート 実例
パニック時の対処
①落ち着いた場所に連れて行く
別室、トイレ、隙間、机の下
or 他の児童を他の場所に
②安心グッズの用意
本、石
③空気転換
④他の子への対応
⑤自分で対処させる
◇榊原洋一
お茶の水大学大学院教授 医学博士 発達神経学
◇上原芳枝
☆「地域住民から福祉・教育関係者等への無理難題要求をどう読み解き対応するか」~イチャモン研究の到達点~ 大阪大学教授 小野田正利 2008年 ⑨【再掲載 2015.11】
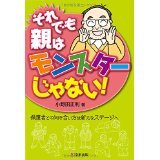
◇悲鳴をあげる学校
「私はAさんと仲が悪いから、私の子とAさんの子は別々のクラスにしてほ
しい。」
「同じオモチャをとりあってケンカになるぐらいなら、そんなオモチャは園
に置かなでほしい。」
「ウチの子は自己紹介が苦手だから、クラスの中で自己紹介をする場面をつ
くらないでほしい。どうしてもさせるというのなら休ませます。」
「運動会ではマイクを使うな。」
「ブラスバンドは窓を閉めて練習して欲しい。」
いま全国の学校が、こめような多様な要求に悩まされています。
私は、保護者や地域から学校に寄せられる要求を三段階に分けています。
「学校がやるべきことに対するまっとうな要求」が「要望」、「学校がある程
度まで対応すべき要求」が「苦情」、そして「学校にもどうにでもできない
要求」が「イチャモン(無理難題要求)」です。
私は、多くのインタビュー調査とともに、この4年間に3回のアンケート調
査もおこなってきました。
無理難題的要求が本当に増えてきているのかについての明確な数字は示すこ
とはできませんが、確実に言えることは、「要望]よりも「苦情」が急増し、さ
らには「無理難題要求」が多くなってきたと感じる(実感値)教員が多数いる
ということです)。
学校に対する要求が拡大し続け、学校の責任領域や守備範囲を超えることま
でが求められる中で、学校側は一度もミスをすることを許されない存在、とし
て理解されはじめます。
受け止めきれなくなった学校側は「突っ込まれた」時に説明できるように証
拠記録を残し、ありとあらゆる防御策を張りめぐらせ、時には不必要と思われ
るような防御策まで講じる状況が進んでいます。
「突っ込み」→「自信喪失」→「過剰防衛」の繰り返しともいえますが、本来
的な子どもとの触れ合いや学校教育に時間や精力を割くということよりは、ト
ラブル対策に心砕くしんどさが最もつらい、と多くの教師は言います。



