小浜逸郎さんはこんなことを⑨-「14歳 日本の子どもの謎」イースト・ブック 1997年 (3) /「遠江の里」ひくまの出版 1979年 ②【再掲載 2014.8】 [読書記録 教育]
今回は、11月27日に続いて、
「小浜逸郎さんはこんなことを」9回目、
「14歳 日本の子どもの謎」3回目の紹介です。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「『性に目覚めるころ』の危うさ」
・「近代以降、労働現場と家庭が切り離され、学校という特別な場ができ、子供が囲い込
まれた。」
・「通過儀礼が教育課程に置き換えられたことで,大人と子供の境界が曖昧になり,本当
に大人になったと思える時期が無期延期される。」
・「第三次産業(サービス業)中心の社会になったことが、大人になったと思える時期の
無限延期や,大人であることの確信の得られなさにつながった。三次産業は扱いにく い対象である『ひと』が相手だから」
もう一つ、再掲載となりますが、ひくまの出版の
「遠江の里」②を載せます。
地域の歴史を知ろうとすることは楽しいことです。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆小浜逸郎さんはこんなことを⑨-「14歳 日本の子どもの謎」イースト・ブック 1997年 (3)

◇「性に目覚めるころ」の危うさ①
□子供はいつから「未熟で保護と育成を必要とされる存在」になったのか
「大人-子供」関係の枠組み 経緯と意味
近代以前の通過儀礼
元服・若者宿,娘宿
= 上からの強制力
↓
近代以降
① 労働現場と家庭が切り離される
② 学校という特別な場ができる
↓
◎子供囲い込み
「未熟で保護と育成を必要とされる存在」
∥
◎親や教師がクローズアップ
= 子供は外側へ飛び出しにくくなる
□「子供」とも「大人」とも呼べない「ヘンな存在」
近代以前
◎適当に遊ばせておいて幼年期を脱するくらいになると早々に大人の労働に参加させた
↓
近代以降
◎「子供」を「子供」として意識的に見るようになり次第に繊細な視線を注ぐようにな
る
|
◎教育への関心が高くなる
- 細かく区分
|
◎教育課程が長くなる
※ 子供はいったいいつになれば自分が大人になるのか分からなくなってきた
∥
※ 通過儀礼が教育課程に置き換えられたことで,大人と子供の境界が曖昧になり,
本当に大人になったと思える時期が無期延期される。
□ 大人になったと思える時期の無限延期や,大人であることの確信の得られなさには
それなりの理由がある。
↑
◎産業構造の変化
※第三次産業(サービス業)中心の社会になったから
第一次産業 自然相手 一人前のイメージ
第二次産業 モノ相手
∥
◎個人の扱う対象・作業がはっきりしているので,自分の仕事に自信が持てる
↑↓
◎三次産業 「ひと」相手 扱いにくい対象
☆「遠江の里」ひくまの出版 1979年 ②【再掲載 2014.8】
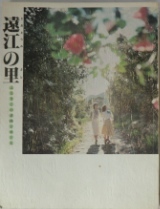
◇野と人と 那須田稔
<三方原合戦>
□元亀3(1572)年10月
武田信玄
元亀3(1572)年10月
犬居城に入る(京を目指す大進撃)
もう一軍は気賀から井伊谷へ
家康の部下・懸城の石川家成、高天神城の小笠原長忠
信玄は懸城、高天神城をそのままにして突然森、袋井、磐田
↑
徳川家康
あわてて磐田見附に出陣
三箇野から一言坂へと退却に次ぐ退却
□元亀3(1572)年12月
武田信玄
二俣城が信玄の手に墜ちる
信玄軍は南進
有玉 → 西へ 追分で全軍統一
→ 北進 根洗松 → 礼田の坂で軍を留めた
徳川家康
浜松城を無視して京へ向かう信玄に腹を立てる
・信長の意見も退けて出陣
◎三方ヶ原の戦い
<徳川家康軍> VS <武田信玄軍>
1万騎 3万騎
31歳 52歳
鶴翼の陣 魚鱗の陣
↓
◎家康軍総崩れ
家康は浜松城に逃げ帰り全門を開けて篝火を焚き大太鼓
↑ 大太鼓・酒井忠次「酒井の大太鼓」
↑ 太鼓は見付学校→磐田北小→見付天神社
信玄は奇計をおそれて引き返す
家康は百人の陣で犀ケ崖に奇襲
信玄軍兵、驚きあわてて崖の谷に墜ちる
犀ケ崖 深さ40m幅50m長さ2㎞
現在 宗円堂
◇掘留川 亘理宏
掘留運河
井ノ田川掘割850間=1.5㎞
悪水堀 ~ 田の灌漑用悪水放出用水路
|
田尻排水路
次計池(現体育センター北)
明治4年開通 田圃の中を蒸気船が行く
掘割事業 村人が無給奉仕
↑
井上氏 運河経営者となる
明治14年浜名橋
明治20年 東海道線開通 → 衰退
菅原町 ~ 浜二塗料わき
伊場道路橋下
田尻からの悪水と合する出会いの場所
→ 共に入野へと悪水は「悪水堀」
◇大刀洗池のことなど 平松實
東京大学・高柳光寿博士
昭和36(1961)年 週刊朝日に「家康史跡の物語」
大刀洗池
コンクリートで市会議長に壊される
→ 揮毫・高柳博士 昭和39(1964)年12月
◇築山殿月窟廟の再興 大澤稔
高松山西来院(浜松市広沢)
昭和51(1971)年多額の寄付を一女性が
→ 家康の命によって命を絶った野中三五郎重政燈籠奉献
「小浜逸郎さんはこんなことを」9回目、
「14歳 日本の子どもの謎」3回目の紹介です。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「『性に目覚めるころ』の危うさ」
・「近代以降、労働現場と家庭が切り離され、学校という特別な場ができ、子供が囲い込
まれた。」
・「通過儀礼が教育課程に置き換えられたことで,大人と子供の境界が曖昧になり,本当
に大人になったと思える時期が無期延期される。」
・「第三次産業(サービス業)中心の社会になったことが、大人になったと思える時期の
無限延期や,大人であることの確信の得られなさにつながった。三次産業は扱いにく い対象である『ひと』が相手だから」
もう一つ、再掲載となりますが、ひくまの出版の
「遠江の里」②を載せます。
地域の歴史を知ろうとすることは楽しいことです。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆小浜逸郎さんはこんなことを⑨-「14歳 日本の子どもの謎」イースト・ブック 1997年 (3)

◇「性に目覚めるころ」の危うさ①
□子供はいつから「未熟で保護と育成を必要とされる存在」になったのか
「大人-子供」関係の枠組み 経緯と意味
近代以前の通過儀礼
元服・若者宿,娘宿
= 上からの強制力
↓
近代以降
① 労働現場と家庭が切り離される
② 学校という特別な場ができる
↓
◎子供囲い込み
「未熟で保護と育成を必要とされる存在」
∥
◎親や教師がクローズアップ
= 子供は外側へ飛び出しにくくなる
□「子供」とも「大人」とも呼べない「ヘンな存在」
近代以前
◎適当に遊ばせておいて幼年期を脱するくらいになると早々に大人の労働に参加させた
↓
近代以降
◎「子供」を「子供」として意識的に見るようになり次第に繊細な視線を注ぐようにな
る
|
◎教育への関心が高くなる
- 細かく区分
|
◎教育課程が長くなる
※ 子供はいったいいつになれば自分が大人になるのか分からなくなってきた
∥
※ 通過儀礼が教育課程に置き換えられたことで,大人と子供の境界が曖昧になり,
本当に大人になったと思える時期が無期延期される。
□ 大人になったと思える時期の無限延期や,大人であることの確信の得られなさには
それなりの理由がある。
↑
◎産業構造の変化
※第三次産業(サービス業)中心の社会になったから
第一次産業 自然相手 一人前のイメージ
第二次産業 モノ相手
∥
◎個人の扱う対象・作業がはっきりしているので,自分の仕事に自信が持てる
↑↓
◎三次産業 「ひと」相手 扱いにくい対象
☆「遠江の里」ひくまの出版 1979年 ②【再掲載 2014.8】
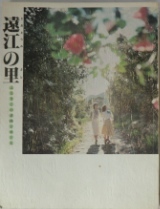
◇野と人と 那須田稔
<三方原合戦>
□元亀3(1572)年10月
武田信玄
元亀3(1572)年10月
犬居城に入る(京を目指す大進撃)
もう一軍は気賀から井伊谷へ
家康の部下・懸城の石川家成、高天神城の小笠原長忠
信玄は懸城、高天神城をそのままにして突然森、袋井、磐田
↑
徳川家康
あわてて磐田見附に出陣
三箇野から一言坂へと退却に次ぐ退却
□元亀3(1572)年12月
武田信玄
二俣城が信玄の手に墜ちる
信玄軍は南進
有玉 → 西へ 追分で全軍統一
→ 北進 根洗松 → 礼田の坂で軍を留めた
徳川家康
浜松城を無視して京へ向かう信玄に腹を立てる
・信長の意見も退けて出陣
◎三方ヶ原の戦い
<徳川家康軍> VS <武田信玄軍>
1万騎 3万騎
31歳 52歳
鶴翼の陣 魚鱗の陣
↓
◎家康軍総崩れ
家康は浜松城に逃げ帰り全門を開けて篝火を焚き大太鼓
↑ 大太鼓・酒井忠次「酒井の大太鼓」
↑ 太鼓は見付学校→磐田北小→見付天神社
信玄は奇計をおそれて引き返す
家康は百人の陣で犀ケ崖に奇襲
信玄軍兵、驚きあわてて崖の谷に墜ちる
犀ケ崖 深さ40m幅50m長さ2㎞
現在 宗円堂
◇掘留川 亘理宏
掘留運河
井ノ田川掘割850間=1.5㎞
悪水堀 ~ 田の灌漑用悪水放出用水路
|
田尻排水路
次計池(現体育センター北)
明治4年開通 田圃の中を蒸気船が行く
掘割事業 村人が無給奉仕
↑
井上氏 運河経営者となる
明治14年浜名橋
明治20年 東海道線開通 → 衰退
菅原町 ~ 浜二塗料わき
伊場道路橋下
田尻からの悪水と合する出会いの場所
→ 共に入野へと悪水は「悪水堀」
◇大刀洗池のことなど 平松實
東京大学・高柳光寿博士
昭和36(1961)年 週刊朝日に「家康史跡の物語」
大刀洗池
コンクリートで市会議長に壊される
→ 揮毫・高柳博士 昭和39(1964)年12月
◇築山殿月窟廟の再興 大澤稔
高松山西来院(浜松市広沢)
昭和51(1971)年多額の寄付を一女性が
→ 家康の命によって命を絶った野中三五郎重政燈籠奉献
「すごい本Index」日経BP 2011年 ③(最終) /「ヘレン・ケラーはどう教育されたか-サリバン先生」サリバン 明治図書 1995年【再掲載 2015.7】 [読書記録 一般]
今回は、11月19日に続いて、日経BPの
「すごい本Index」の紹介 3回目最終です。
出版社の案内には、
「ビジネスから教養、マネーまで69テーマ、540冊を徹底紹介。 今日の仕事に役に立つ。10
年後の人生に変化をもたらす―。 それぞれの現場で活躍するプロフェッショナルが、
自らの経験から選んだ『すごい本』。 仕事に効くビジネススキルや知らないと恥ずか
しい仕事の知識から、話題が広がる教養、不況を乗り切るためのマネー知識まで、69
テーマを幅広く特集。 本選びに失敗したくないあなたのための、『本を選ぶための名
著カタログ』です。 今、読むべき本が必ず見つかります。」
とあります。
本書を参考に幾冊か読むことができました。
ジャンル別に選りすぐりの本が紹介されています。
10年後の今、2021年版が出されればいいなと希望します。
もう一つ、再掲載となりますが、サリバンさんによる
「ヘレン・ケラーはどう教育されたか-サリバン先生」を載せます。
あまりにも有名な「water」。
- 服従と愛
このように記されると誤解を生むようにも感じますが、
サリバンさんが教育にとって大切なことをわたしに教えてくれました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「すごい本Index」日経BP 2011年 ③(最終)
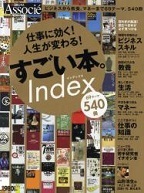
□酒
「うまい日本酒はどこにある」 増田晶文 草思社
「ビールと日本人」 キリンビール 河出文庫
□地方
「ヤ・キ・ソ・バ・イ・ブ・ル 面白くて役に立つまちづくりの聖書」
渡辺英彦 静岡新聞社
「先着順採用 会議自由参加で世界一の小企業をつくった」 松浦元男 講談社+α文庫
「テレビでは分からないジャパネットたかたのすべて」モーターマガジン社
□米
「日本の米」 富山和子 中公新書
「コメのすべて」 有坪民雄 日本実業出版社
「ご飯の底力」 集英社
「ちゃんと食べたいひとりごはんかんたんおいしいからだにいい」石原洋子 日本文芸社
□パン
「日々のパン手帖」 清水美穂子 メディアファクトリー
「BREAD」 ジェフリー・ハメルマン 旭屋出版
□チョコレート
「チョコレートの事典」 成美堂出版
「チョコレートダイエット」 楠田枝里子 幻冬舎
□コーヒー
「珈琲事典」 新星出版社
「それでも珈琲を楽しむための100の知恵」 朝日新聞出版
「マンガ 珈琲どりーむ」 花形玲 芳文社コミックス
「オール・アバウト・コーヒー」 阪急コミュニケーションズ
□お茶
「お茶の入れ方とマナー」 新名庸子 小学館
「茶楽」 ワールドフォトプレス
「日本茶・紅茶・中国茶・健康茶」 日本文芸社
□北欧
「教育立国フィンランド流教師の育て方」増田ユリア 岩波書店
「IKEAのすべてがわかる本」 枻出版社
「青い光が見えたから留学記」 高橋絵里香 講談社
□デザイン
「ヒット企業のデザイン戦略」 クレイグ・M・ホーケル 英治出版
□睡眠
「寝床術」 ポプラ社
「快適睡眠のすすめ」 堀忠雄 岩波新書
「早起きは生きる力」 陰山英男・神山潤 晶文社
「ヒトはなぜ夢を見るのか」 北浜邦大 文春新書
□疲労
「枕革命 ひと晩で体が変わる」 山田朱織 講談社+α新書
「仕事の疲れ予防法」 檜垣暁子 明日香出版
「ココロとカラダにやさしい今夜の飲み物」藤井和江 日本書院
□手紙
「手づくりする手紙」 木下綾乃 文化出版局
「手紙手帖」 木村衣有子 祥伝社
□コンビニ
「ついこの店で買ってしまう理由」 日経新聞社
「コンビニのしくみ」 笠井清志
「月刊コンビニ」 商業界
□自転車
「自転車で痩せた人」 高千穂遥 生活人新書
「大人のための自転車入門」 丹羽隆 日経新社
□自然災害
「不都合な真実」 アル・ゴア ランダムハウス講談社
「異常気象と地震の謎と不安に答える本」 河出書房新社
「大地震から家族を救う方法」 和田隆昌 白夜書房
「本当に使える企業防災」 山村武彦 金融財政事情研究会
「新冒険手帳」 主婦と生活社
□天気
「雨と日本人」 宮尾孝 丸善ブックス
「雲の楽しみ方」 河出書房新社
「お天気おじさんへの道」 泉麻人 講談社文庫
◇書皮の世界
書皮 = 書店の無料カバー
書店友好協会 1983~
文祥堂(京都・ネコ)、丸善、有隣堂、文星堂、三省堂、紀伊國屋書店
治左右衛門(大阪)、ブックスルーエ(東京)、月と6ペンス(京都)
真光書店 「カバーおかけしますか」 出版ニュース社
☆「ヘレン・ケラーはどう教育されたか-サリバン先生」サリバン 明治図書 1995年【再掲載 2015.7】
<出版社の案内>
障害児が十分に教育可能であることを事実で証明した本記録は障害児教育に
携わる人々や全ての子らを賢くしたいと願う人々に大きな示唆を与える。

◇はしがき
□ヘレン・ケラー
恵まれた条件
① 脳は大丈夫
② サリバンの優秀さ
◎「この人を見よ。ここにすばらしい2人の人がいる」(遠山啓)
◇サリバン女子の手紙 親友のホプキンス夫人宛
アン・マンスフィールド・サリバン
スプリングフィールド アイルランド移民貧家
10歳で救貧院 悲惨な少女時代
14歳 1880.10 パーキンス盲学校入学
1886 卒業
アナグノス校長よりヘレンの教師に推薦
1886~1887.1 半年間
ローラ・フリズマン教育に当たったハウ博士報告書より学ぶ
↓
1887.3~ ヘレンの教育
◇1887.3.6 月曜の午後
最大の課題 … どうやって彼女と訓練し続けるか
食事の時のケンカ
<服従> <愛>を学ぶまでけんか
◇アラバマ州タスカンビア 1887.3.11
一軒家で2人だけの生活
「つたみどりの家」
暴君のような振る舞い
→ 分かってもらえないことが感情の爆発のきっかけ
↓
◎ 成長するにつれ癇癪もひどくなった
↑
◎ 平和を守るため、(家族は)皆喜んで降参した
↓
◎ヘレン
やりたいかやりたくないか一つだけ
寝かせるだけで2時間のとっくみあい
→ 何とか引きずり込んだ
ヘレンは驚くほど賢く、活動的で、敏捷
◇1887.3.20
小さな野生動物
→ やさしい子どもに
= 服従という最初の教訓
◇1887.3.28
家に戻る
◇1887.4.3
編み物
3月31日
◎ 18の名詞と3つの動詞
◇1887.4.5
名前があることと指文字が手がかりになることを知った
Waterから → ものに名前があることを知る 30の単語
◇1887.4.10
ものの名前を尋ねる
「赤ちゃんの耳に話しかけるようにヘレンの手に話しかける」 = 刺激
◇1887.4.24
百以上のに単語を知った
規則正しい授業をやめた
◇1887.5.8
形容詞・副詞も
5匹の犬 → Five
◇1887.5.16
彼女に話をさせる
◇1887.5.22
300単語 + たくさんの慣用語 しかし、ものを壊す癖
◇1887.6.2
神経質で興奮しやすい
◇1887.6.19
27日で7歳 400単語
◇1887.7.3
癇癪
◇1887.7.31
一日中 「何か?」「なぜ?」「いつ?」連発
素晴らしい記憶力、想像力、連想能力
◇1887.8.28
生命への疑問 ~ 生命の偉大さ
◇1887.9.18
600単語 色への興味
◇1887.10.25
代名詞
◇1887.11.13
サーカス
◇1887.12.12
時計が読めるようになった
◇1888.3.5
900単語 日記づくり
◇1888.4.16
教会で大騒ぎ
◇1889.10
正規の勉強に
「すごい本Index」の紹介 3回目最終です。
出版社の案内には、
「ビジネスから教養、マネーまで69テーマ、540冊を徹底紹介。 今日の仕事に役に立つ。10
年後の人生に変化をもたらす―。 それぞれの現場で活躍するプロフェッショナルが、
自らの経験から選んだ『すごい本』。 仕事に効くビジネススキルや知らないと恥ずか
しい仕事の知識から、話題が広がる教養、不況を乗り切るためのマネー知識まで、69
テーマを幅広く特集。 本選びに失敗したくないあなたのための、『本を選ぶための名
著カタログ』です。 今、読むべき本が必ず見つかります。」
とあります。
本書を参考に幾冊か読むことができました。
ジャンル別に選りすぐりの本が紹介されています。
10年後の今、2021年版が出されればいいなと希望します。
もう一つ、再掲載となりますが、サリバンさんによる
「ヘレン・ケラーはどう教育されたか-サリバン先生」を載せます。
あまりにも有名な「water」。
- 服従と愛
このように記されると誤解を生むようにも感じますが、
サリバンさんが教育にとって大切なことをわたしに教えてくれました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「すごい本Index」日経BP 2011年 ③(最終)
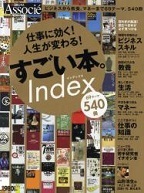
□酒
「うまい日本酒はどこにある」 増田晶文 草思社
「ビールと日本人」 キリンビール 河出文庫
□地方
「ヤ・キ・ソ・バ・イ・ブ・ル 面白くて役に立つまちづくりの聖書」
渡辺英彦 静岡新聞社
「先着順採用 会議自由参加で世界一の小企業をつくった」 松浦元男 講談社+α文庫
「テレビでは分からないジャパネットたかたのすべて」モーターマガジン社
□米
「日本の米」 富山和子 中公新書
「コメのすべて」 有坪民雄 日本実業出版社
「ご飯の底力」 集英社
「ちゃんと食べたいひとりごはんかんたんおいしいからだにいい」石原洋子 日本文芸社
□パン
「日々のパン手帖」 清水美穂子 メディアファクトリー
「BREAD」 ジェフリー・ハメルマン 旭屋出版
□チョコレート
「チョコレートの事典」 成美堂出版
「チョコレートダイエット」 楠田枝里子 幻冬舎
□コーヒー
「珈琲事典」 新星出版社
「それでも珈琲を楽しむための100の知恵」 朝日新聞出版
「マンガ 珈琲どりーむ」 花形玲 芳文社コミックス
「オール・アバウト・コーヒー」 阪急コミュニケーションズ
□お茶
「お茶の入れ方とマナー」 新名庸子 小学館
「茶楽」 ワールドフォトプレス
「日本茶・紅茶・中国茶・健康茶」 日本文芸社
□北欧
「教育立国フィンランド流教師の育て方」増田ユリア 岩波書店
「IKEAのすべてがわかる本」 枻出版社
「青い光が見えたから留学記」 高橋絵里香 講談社
□デザイン
「ヒット企業のデザイン戦略」 クレイグ・M・ホーケル 英治出版
□睡眠
「寝床術」 ポプラ社
「快適睡眠のすすめ」 堀忠雄 岩波新書
「早起きは生きる力」 陰山英男・神山潤 晶文社
「ヒトはなぜ夢を見るのか」 北浜邦大 文春新書
□疲労
「枕革命 ひと晩で体が変わる」 山田朱織 講談社+α新書
「仕事の疲れ予防法」 檜垣暁子 明日香出版
「ココロとカラダにやさしい今夜の飲み物」藤井和江 日本書院
□手紙
「手づくりする手紙」 木下綾乃 文化出版局
「手紙手帖」 木村衣有子 祥伝社
□コンビニ
「ついこの店で買ってしまう理由」 日経新聞社
「コンビニのしくみ」 笠井清志
「月刊コンビニ」 商業界
□自転車
「自転車で痩せた人」 高千穂遥 生活人新書
「大人のための自転車入門」 丹羽隆 日経新社
□自然災害
「不都合な真実」 アル・ゴア ランダムハウス講談社
「異常気象と地震の謎と不安に答える本」 河出書房新社
「大地震から家族を救う方法」 和田隆昌 白夜書房
「本当に使える企業防災」 山村武彦 金融財政事情研究会
「新冒険手帳」 主婦と生活社
□天気
「雨と日本人」 宮尾孝 丸善ブックス
「雲の楽しみ方」 河出書房新社
「お天気おじさんへの道」 泉麻人 講談社文庫
◇書皮の世界
書皮 = 書店の無料カバー
書店友好協会 1983~
文祥堂(京都・ネコ)、丸善、有隣堂、文星堂、三省堂、紀伊國屋書店
治左右衛門(大阪)、ブックスルーエ(東京)、月と6ペンス(京都)
真光書店 「カバーおかけしますか」 出版ニュース社
☆「ヘレン・ケラーはどう教育されたか-サリバン先生」サリバン 明治図書 1995年【再掲載 2015.7】
<出版社の案内>
障害児が十分に教育可能であることを事実で証明した本記録は障害児教育に
携わる人々や全ての子らを賢くしたいと願う人々に大きな示唆を与える。

◇はしがき
□ヘレン・ケラー
恵まれた条件
① 脳は大丈夫
② サリバンの優秀さ
◎「この人を見よ。ここにすばらしい2人の人がいる」(遠山啓)
◇サリバン女子の手紙 親友のホプキンス夫人宛
アン・マンスフィールド・サリバン
スプリングフィールド アイルランド移民貧家
10歳で救貧院 悲惨な少女時代
14歳 1880.10 パーキンス盲学校入学
1886 卒業
アナグノス校長よりヘレンの教師に推薦
1886~1887.1 半年間
ローラ・フリズマン教育に当たったハウ博士報告書より学ぶ
↓
1887.3~ ヘレンの教育
◇1887.3.6 月曜の午後
最大の課題 … どうやって彼女と訓練し続けるか
食事の時のケンカ
<服従> <愛>を学ぶまでけんか
◇アラバマ州タスカンビア 1887.3.11
一軒家で2人だけの生活
「つたみどりの家」
暴君のような振る舞い
→ 分かってもらえないことが感情の爆発のきっかけ
↓
◎ 成長するにつれ癇癪もひどくなった
↑
◎ 平和を守るため、(家族は)皆喜んで降参した
↓
◎ヘレン
やりたいかやりたくないか一つだけ
寝かせるだけで2時間のとっくみあい
→ 何とか引きずり込んだ
ヘレンは驚くほど賢く、活動的で、敏捷
◇1887.3.20
小さな野生動物
→ やさしい子どもに
= 服従という最初の教訓
◇1887.3.28
家に戻る
◇1887.4.3
編み物
3月31日
◎ 18の名詞と3つの動詞
◇1887.4.5
名前があることと指文字が手がかりになることを知った
Waterから → ものに名前があることを知る 30の単語
◇1887.4.10
ものの名前を尋ねる
「赤ちゃんの耳に話しかけるようにヘレンの手に話しかける」 = 刺激
◇1887.4.24
百以上のに単語を知った
規則正しい授業をやめた
◇1887.5.8
形容詞・副詞も
5匹の犬 → Five
◇1887.5.16
彼女に話をさせる
◇1887.5.22
300単語 + たくさんの慣用語 しかし、ものを壊す癖
◇1887.6.2
神経質で興奮しやすい
◇1887.6.19
27日で7歳 400単語
◇1887.7.3
癇癪
◇1887.7.31
一日中 「何か?」「なぜ?」「いつ?」連発
素晴らしい記憶力、想像力、連想能力
◇1887.8.28
生命への疑問 ~ 生命の偉大さ
◇1887.9.18
600単語 色への興味
◇1887.10.25
代名詞
◇1887.11.13
サーカス
◇1887.12.12
時計が読めるようになった
◇1888.3.5
900単語 日記づくり
◇1888.4.16
教会で大騒ぎ
◇1889.10
正規の勉強に



