大村はまさんはこんなことを ㉔(最終)-『教えるということ』大村はま 共文社 1973年 (3) /「図説 ふるさとの歴史シリーズ 浜松浜名湖周辺」上巻 郷土出版社 1992年 ① 古墳時代まで 【再掲載 2011.6】 [読書記録 教育]
「教師は仏様の指のような存在に!」
今回は、12月21日に続いて、大村はまさんの
「教えるということ」の3回目、
「大村はまさんはこんなことを」の紹介 24回目 です。
出版社の案内には、
「教えない先生が多すぎる。『教える』とはどういうことか。教師・父母必読、問題の書。」
とあります。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「『研究することは先生の資格』
学ぶ苦しみを子どもと共に味わう教師でありたい」
・「教えない教師は『読んできましたか』という検査官であり黙って書かせる批評家だ」
- 大先輩の山本部長から言われた言葉「教師は批評家にならないように」の言葉を思い
出しました。
・「ほんものの教師
① 尊敬される先生 ◎ 厳しい自己規制が大切
② 子どもに乗り越えられる教師の喜び ◎ 教師は渡し守役
③ 教師の禁句は『静かにしなさい』 」
・「職業意識に徹して、 一人で判断するようにしつける。常に研修によって技術を磨く。」
教えるとはどんなことか、ほんものの教師とは何かということを
短い言葉で厳しく教えてくれた大村はまさんの本、おすすめです。
もう一つ、再掲載となりますが、
「図説ふるさとの歴史シリーズ 浜松浜名湖周辺」上巻①を載せます。
今回の再掲載にあたり、もう一度要約を読み直しましたが、
図で説明されたいる、浜松浜名湖周辺の歴史を知るのに役立つ本だと改めて思いました。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆大村はまさんはこんなことを ㉔(最終)-『教えるということ』大村はま 共文社 1973年 (3)
◇教えるということ
信州-東女出身
教師の資格
-「研究することは先生の資格」
= 学ぶ苦しみを子どもと共に味わう
20代のアイデアを大切に
教えない教師
-「読んできましたか」という検査官
読むことを教える
黙って書かせる批評家
無責任な教師
「一生懸命に指導したんですけどね」
「あなたのお子さん,勉強が足りませんね」 甘い世界
↓
◎ 教師の仕事は子どもに力を付けること
ほんものの教師
尊敬される先生 = 厳しい自己規制
子どもに乗り越えられる教師の喜び = 教師は渡し守
教師の禁句「静かにしなさい」
◎ 覚悟を新たに
◇教師の仕事
教師志望の動機
理想は担任の先生
「子ども好き」だけでは× - 先生バカ
素人教師と玄人教師
「いい人」なんて当たり前 真の愛情とは何か
禁句「分かりましたか」
専門職としての実力
職業人としての技術
素人でも言える指示する言い方
専門職としての技術
- 書かせる工夫
いいわけコンクール
- タネ探しの苦労
職業意識に徹する
職業人の目で見る
一人で判断するようにしつける
研修によって技術を磨く
教師の仕事の成果
「仏様の指」 - 教師の本懐 = 子どもの重荷にならない
◎ 教師は仏様の指のような存在に!
◇言葉について
言葉を考える
流行語は悪い言葉か
子どもたちの感覚は鋭い
「カッコイイ」使用禁止同盟
- 言葉を豊かに
☆「図説 ふるさとの歴史シリーズ 浜松浜名湖周辺」上巻 郷土出版社 1992年 ① 古墳時代まで 【再掲載 2011.6】
<縄文時代>
◇縄文海進
□1万2千年前
海面が上昇 → 海進 → 三方原台地が海食崖に
5千年前
現在より2~3m上昇
海進海退を繰り返した
関東は65km内陸部まで
□動物相の変化
大型動物 ナウマンゾウ,オオヅノシカ,トラ
↓
中型・小型 シカ,イノシシ,ウサギ ← 狩猟の対象
□海進により遠浅の海ひろがり
干潟 - 牡蠣や蛤
豊富な種類 - 干潟の水鳥
|
◎ 海進により海から豊富な食糧 + 土器使用
↓
◎ 海岸部に生活の場
弁天島湖底遺跡(渚園付近)
◇貝塚とムラ
□江戸期(1678)
「青山御領分絵図」に蜆塚初見
□明治22(1889)年、若林勝邦により「蜆塚遺跡」
2~30人のムラ
貝塚 = 数百年間のごみ
縄文カレンダー マツリの遺跡
<弥生時代>
◇米づくりの始まり
□紀元前3世紀
三ヶ日町・殿畑遺跡-遠賀川式土器(稲作のムラ)
□紀元前1世紀
舞阪町・大山遺跡 浜松市・梶子遺跡
瓜郷式土器 ~ 濃尾平野から移住してきた人々?
◇戦うムラ
□伊場遺跡 2世紀~
三重の濠
防御的集落=「戦うムラ」
◎ 日本の歴史の中で,村の周りに濠,柵,土塁などの防御施設を巡らすのは弥生時代
と戦国時代の二つだけ。
↓
※利害 水利権,耕作権,所有権,領有権,通行権
梶子遺跡 も 濠
向山遺跡
紀元前2~3世紀 都田・丘陵上
監視所や烽火所
水城
平野部濠
山城
高所のムラ
◎ 竪穴住居,掘立柱建物,高床式倉庫,鋤や鍬などの材料を水漬けで保管する穴,
ゴミ捨て用穴,濠には橋
墓はムラ外れ,郷の外側・丘陵上
◇炊く・盛る・蓄える
□伊場遺跡
2世紀の弥生土器が多数出土
甕型25%,壺型40%,高坏型32%,鉢型3%
甕型 外面内面に煤やお焦げ~米
壺 - 貯蔵
高坏 - 食物を盛る
◇鳥・船・鹿
□弥生時代
鳥は特別な動物
長い竿をつけた木製の鳥
-ムラの入口門の上に(鳥居に鳥が居た)
鳥 - 穀霊が扮装したもの
船 - 海の彼方から穀霊を運んでくる
※ ミニチュア木製船(浜松市・梶子遺跡)
※ 土器に外航用船の絵(浜松市三和町・村前遺跡)
鹿 悪ヶ谷銅鐸にも
鹿を犠牲獣とする種籾賦活儀礼
↓
※ 鳥,船,鹿は豊作を祈念したり感謝したりするもの
◇銅鐸のマツリ
□弥生時代の楽器
土笛,弦楽器の琴,体鳴楽器の銅鐸
西遠-「見る銅鐸」祭具の中心へ
正式発掘
前原銅鐸(浜松)
滝峯才四郎銅鐸(細江町)-「銅鐸の谷」
横たえて埋められた
青銅の本来のいろは金色
◇階級社会への道
□浜松市・松東遺跡
3~4mの濠 4000㎡
東西20m南北30m区画
□浜松市・山の神遺跡
方形周溝墓 - 差別化志向
□浜松市三和町・村前遺跡 弥生末3世紀
特殊文様土器
直線と弧線を組み合わせ→古墳時代・直孤紋
直孤紋 = 支配階級専用の文様
|
◎紋様の世界にも独占が始まる
◇邪馬台国と狗奴国
□狗奴国
① 伊勢湾沿岸説
② 原野谷川流域説
2~3世紀
伊勢湾周辺に一つの文化圏(東限が西遠)
袋井市周辺
久努(くの)
8世紀 久努豪族 ~ 狗奴国有力候補地 - 菊川式土器が分布
2~3世紀銅鐸
西遠江21点 うち8点は近畿式
↑↓
東遠江には敵対する勢力
◎ 西遠江 VS 東遠江
<古墳時代>
◇古墳が造られた時代
□浜北市内野・赤門上古墳
1954内野地区分布調査
山下・通称赤門寺の竜泉院にちなむ
1961発掘 木棺
三角縁神獣鏡,大刀,管玉,銅鏃,鉄鏃,鎌,ヤリガンナ,刀子
全長56m
◇ムラのすがた
□集落 浜松市西鴨江町・中平遺跡(4世紀)竪穴165,掘立4
入野町・大平遺跡
→ 伊勢・尾張の影響
◇井伊谷の古墳群
神宮寺川 井伊谷の盆地
北岡大塚古墳,馬場平古墳,馬場平3号墳,陣座ヶ谷古墳
◇大型円墳と中期古墳
□古墳造営規制
大型は円墳に → 千人塚古墳 三方原学園内 1965発掘
大漁の武器類,農工具類
瓢箪塚古墳,2号墳 1世紀に渡る首長墓
谷津古墳 入野古墳
◇内野積石塚と渡来人
※以下略 → 2011.6の記事へ</ins>
「孤独のすすめ」ひろさちや SB新書 2016年 ④(最終) /「教師のための66の語録」杉山正一 東洋館出版社 1995年 ②【再掲載 2014.9】 [読書記録 宗教]
今回は、12月27日に続いてひろさちやさんの
「孤独のすすめ」4回目の紹介 最終です。
出版社の案内には、
「そもそも孤独を癒そうとするのが大間違い!現代日本がつくり出した、本当は誰しも感
じている『孤独』な状況-。昔の共同体のような『閉じた社会』での密な関係はなくな
り、今はネットで不特定多数とも広く繋がれる希薄な人間関係の中に生きています。い
つでも人と繋がれる時代に生きていながらも、昔に増して孤立感・疎外感を抱いている
人は多いようです。そして厳しい世間の荒波にもまれ、人間関係をこじらせ、ときに一
個人としての孤立や無力さを感じたり、孤独に苛まれることがよくあります。そもそも
今の世の中は狂っているともいえます。人は世間の物差し(常識)を押しつけられて生
きており、かえって疎外感や生きづらさ、孤立感を感じることにつながっているのです。
そう、そんな狂った世の中で、現代人が寂しくなく「孤独を生きる」には、実はほんの
ちょっとコツが入るのです。本書は、『孤独』というものの本質に立ち返り、般若をは
じめ古今東西の偉人賢人の考えも参照しつつ、ついつい癒(解消)しがちな『孤独』を
恥や悩みとせず、むしろおかしな世の中で自分の状況をしっかりと肯定し、孤独と上手
に向き合うことで、楽しく生きていく術を書き下ろすものです。」
とあります。
昨日おしらせしたように、しばらくの間、記事をアップするのみにします。
残念ですが、皆さんのブログ訪問できないことを御承知願います。
がまんがまんの年末年始となりそうです。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「我々が悩むのは『孤独』の状態ではなしに、『孤独感』である。」
・「絆・束縛を断ち去れ!浮世のしがらみを断ち切って自由になって独りで進め!(釈迦)」
・「馬鹿な蛙と阿呆な狐」
- どちらがいいでしょうか。
ひろさちやさんの本を読むと、くよくよしなくていいと慰められます。
新しい視点を与えてくれるひろさんの本、おすすめです。
もう一つ、再掲載となりますが、杉山正一さんの
「教師のための66の語録」②を載せます。
なるほどと気付かせてくれることがあります。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「孤独のすすめ」ひろさちや SB新書 2016年 ④(最終)

◇Ⅲ 絶対の孤独
14 愛を超えたもの
三浦綾子(1922-1999)
朝鮮戦争 米国青年 両足切断 ピストル自殺
『藍色の便せん』小学館
15 「孤独」と「孤独感」
「老いて子なくを独といい、幼にして父亡きを孤という」
孟子
我々が悩むのは「孤独」の状態ではなしに、「孤独感」である。
→ 仏教 「愛するな」
◎ 絆は「連帯」ではなく「束縛」の意味、「浮世のしがらみ」ひろさちや
釈迦
絆・束縛を断ち去れ!
= 浮世のしがらみを断ち切って自由になって独りで進め!
※ 本当の出家とはホームレスになること
16 世間を馬鹿にする
世間を馬鹿にすればよい
聖徳太子(574-622)
世間虚仮、唯仏是真(せけんこけ、ゆいぶつぜしん)
カント
「自分は流行を追う馬鹿」
17 人生の孤独と生活の孤独
「無量寿経」
独生独死、独去独来
人生の孤独(絶対的な孤独) - 生老病死
ドイツのヤスパース(1883-1969)
「限界状況」 - 努力しても絶対に変えることのできない状況
◇Ⅳ 阿呆の孤独
18 馬鹿な蛙と阿呆な狐
◎馬鹿
… 問題状況を打開し、解決しようとあれこれ努力して、結局はそれに失敗する人。
失敗せずに成功した人は、賢い人。
◎阿呆
… 問題状況を打開し、解決することは自分には不可能だと思って、問題があるま
ま、そのまま楽しく過ごす
『イソップ物語』の狐「負け惜しみ」
19 思うがままにならないこと
20 愛する妻との別れ
☆「教師のための66の語録」杉山正一 東洋館出版社 1995年 ②【再掲載 2014.9】
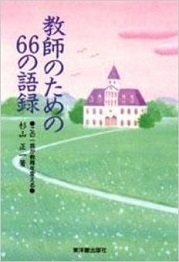
<教師を問い直す眼>
◇カント 独近代哲学(1742-1804)
「人は人によってのみ人となり得べし 人から教育の結果を取り除けば全く無とならん」
「アベロンの野生児」「オオカミに育てられた少女」
- 人間を人間たらしめるのは教育の仕事
◇吉田松陰
「師導を興さんならば妄(みだ)りに人の師となるべからず 真に学ぶべきことありて師と
すべし」
- 教師としての専門技術と教師としての人格
◇セネカ ローマ・ストア派哲人(54DC-65AC)
「人間は教えている間に学ぶ」
- 教える立場にある教師は自らも学ぶ教師でなければならない
|
◎ 教材研究すればするほど教材への理解が深まってくる
「教えることは学ぶことの半(なかば)」
「教師も学生なり」
ジューベル
「教えることは二度学ぶことである」
∥
◎ 教師よ、教師は勉強しなければならない
◇スタール夫人 仏文学者(1766-1817)
「子どもと戯れることのできる人だけが教育者となる権利がある」
- 子どもをよく知り、よく理解し、子どもの心をよくとらえている教師
◇バーナード・ショウ イギリス劇作家(1856-1950)ノーベル文学賞受賞者
「できる者は行う できない者が教える」
- 口先だけで教えている学習指導では子どもが離れてしまう
|
◎ 本当の学習指導 = 子どもが喜んで取り組む学習こそ大事
◇アインシュタイン(1879-1955)
「独創的な表現と知識の悦びを喚起させることが教師の最高の術である」
- 学ぶ喜び、学習の楽しさ = 終わりのベルを恨むような
「孤独のすすめ」4回目の紹介 最終です。
出版社の案内には、
「そもそも孤独を癒そうとするのが大間違い!現代日本がつくり出した、本当は誰しも感
じている『孤独』な状況-。昔の共同体のような『閉じた社会』での密な関係はなくな
り、今はネットで不特定多数とも広く繋がれる希薄な人間関係の中に生きています。い
つでも人と繋がれる時代に生きていながらも、昔に増して孤立感・疎外感を抱いている
人は多いようです。そして厳しい世間の荒波にもまれ、人間関係をこじらせ、ときに一
個人としての孤立や無力さを感じたり、孤独に苛まれることがよくあります。そもそも
今の世の中は狂っているともいえます。人は世間の物差し(常識)を押しつけられて生
きており、かえって疎外感や生きづらさ、孤立感を感じることにつながっているのです。
そう、そんな狂った世の中で、現代人が寂しくなく「孤独を生きる」には、実はほんの
ちょっとコツが入るのです。本書は、『孤独』というものの本質に立ち返り、般若をは
じめ古今東西の偉人賢人の考えも参照しつつ、ついつい癒(解消)しがちな『孤独』を
恥や悩みとせず、むしろおかしな世の中で自分の状況をしっかりと肯定し、孤独と上手
に向き合うことで、楽しく生きていく術を書き下ろすものです。」
とあります。
昨日おしらせしたように、しばらくの間、記事をアップするのみにします。
残念ですが、皆さんのブログ訪問できないことを御承知願います。
がまんがまんの年末年始となりそうです。
今回紹介分より強く印象に残った言葉は…
・「我々が悩むのは『孤独』の状態ではなしに、『孤独感』である。」
・「絆・束縛を断ち去れ!浮世のしがらみを断ち切って自由になって独りで進め!(釈迦)」
・「馬鹿な蛙と阿呆な狐」
- どちらがいいでしょうか。
ひろさちやさんの本を読むと、くよくよしなくていいと慰められます。
新しい視点を与えてくれるひろさんの本、おすすめです。
もう一つ、再掲載となりますが、杉山正一さんの
「教師のための66の語録」②を載せます。
なるほどと気付かせてくれることがあります。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆「孤独のすすめ」ひろさちや SB新書 2016年 ④(最終)

◇Ⅲ 絶対の孤独
14 愛を超えたもの
三浦綾子(1922-1999)
朝鮮戦争 米国青年 両足切断 ピストル自殺
『藍色の便せん』小学館
15 「孤独」と「孤独感」
「老いて子なくを独といい、幼にして父亡きを孤という」
孟子
我々が悩むのは「孤独」の状態ではなしに、「孤独感」である。
→ 仏教 「愛するな」
◎ 絆は「連帯」ではなく「束縛」の意味、「浮世のしがらみ」ひろさちや
釈迦
絆・束縛を断ち去れ!
= 浮世のしがらみを断ち切って自由になって独りで進め!
※ 本当の出家とはホームレスになること
16 世間を馬鹿にする
世間を馬鹿にすればよい
聖徳太子(574-622)
世間虚仮、唯仏是真(せけんこけ、ゆいぶつぜしん)
カント
「自分は流行を追う馬鹿」
17 人生の孤独と生活の孤独
「無量寿経」
独生独死、独去独来
人生の孤独(絶対的な孤独) - 生老病死
ドイツのヤスパース(1883-1969)
「限界状況」 - 努力しても絶対に変えることのできない状況
◇Ⅳ 阿呆の孤独
18 馬鹿な蛙と阿呆な狐
◎馬鹿
… 問題状況を打開し、解決しようとあれこれ努力して、結局はそれに失敗する人。
失敗せずに成功した人は、賢い人。
◎阿呆
… 問題状況を打開し、解決することは自分には不可能だと思って、問題があるま
ま、そのまま楽しく過ごす
『イソップ物語』の狐「負け惜しみ」
19 思うがままにならないこと
20 愛する妻との別れ
☆「教師のための66の語録」杉山正一 東洋館出版社 1995年 ②【再掲載 2014.9】
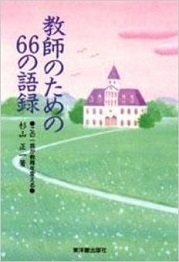
<教師を問い直す眼>
◇カント 独近代哲学(1742-1804)
「人は人によってのみ人となり得べし 人から教育の結果を取り除けば全く無とならん」
「アベロンの野生児」「オオカミに育てられた少女」
- 人間を人間たらしめるのは教育の仕事
◇吉田松陰
「師導を興さんならば妄(みだ)りに人の師となるべからず 真に学ぶべきことありて師と
すべし」
- 教師としての専門技術と教師としての人格
◇セネカ ローマ・ストア派哲人(54DC-65AC)
「人間は教えている間に学ぶ」
- 教える立場にある教師は自らも学ぶ教師でなければならない
|
◎ 教材研究すればするほど教材への理解が深まってくる
「教えることは学ぶことの半(なかば)」
「教師も学生なり」
ジューベル
「教えることは二度学ぶことである」
∥
◎ 教師よ、教師は勉強しなければならない
◇スタール夫人 仏文学者(1766-1817)
「子どもと戯れることのできる人だけが教育者となる権利がある」
- 子どもをよく知り、よく理解し、子どもの心をよくとらえている教師
◇バーナード・ショウ イギリス劇作家(1856-1950)ノーベル文学賞受賞者
「できる者は行う できない者が教える」
- 口先だけで教えている学習指導では子どもが離れてしまう
|
◎ 本当の学習指導 = 子どもが喜んで取り組む学習こそ大事
◇アインシュタイン(1879-1955)
「独創的な表現と知識の悦びを喚起させることが教師の最高の術である」
- 学ぶ喜び、学習の楽しさ = 終わりのベルを恨むような



