小浜逸郎さんはこんなことを⑱-「家族を考える30日」JICC出版局 1993年 (3) /「にほん語観察ノート」井上ひさし 中央公論社 2002年 ①【再掲載 2012.10】 [読書記録 一般]
今回は、1月9日に続いて、
「小浜逸郎さんはこんなことを」18回目、「家族を考える30日」3回目の紹介です。
出版社の案内には
「家族を概念で語るのではなく、あたかも日めくりをめくるように、家族を普通にやって
いればどこかでぶつかる出来事を、1日1項目のスタイルで、さりげなく提出し、繊細
な倍率で照らし出す。家族を考えるヒントに満ちた新機軸のエッセイ集。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「現代の都市家族は消費共同体」
・「大事なこととは,情報に振り回されず,自分の本来的な欲望や傾向がどこにあるかを
吟味することである」
・「『働く』ことはかっこいいことでも美しいことでもない。つらさや退屈さに耐えて,
日常の時間の中に与えられた仕事の運びをくみこんでしまうこと。」
・「結婚生活の安定は自分たちの不断の努力によって作り出すものと考えるべき」
もう一つ、再掲載となりますが、井上ひさしさんの
「にほん語観察ノート」①を載せます。
役人の言葉に関する記述、なるほどとわたしは感じました。
昨夜は自治会の定例会がありました。
地域の神社にある町の公民館に役員が集まって話し合いがもたれます。
1年目ももうすぐ終わりますが、ようやく動きがわかってきました。
5月の浜松まつりには参加する方向で進んでいますが、
コロナ感染の広がりが悩ましいところです。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆小浜逸郎さんはこんなことを⑱-「家族を考える30日」JICC出版局 1993年 (3)
◇状況に接しながら
□年を世代的に住み分ける
現代の都市家族 = 消費共同体
<食事を共にする>
<子供の養育>
□女よスーパーウーマンを目指すな!
この人たちは立派すぎる
経験を自信を力強い言葉で表現できる人
「完全なる女性」のイメージ
「完全なる女性」というイメージに制約されることの根本的な危うさ
↑
スーパーウーマンのいかがわしさ
表向きほどかっこいいものではありえない
|
パワフルでビューティフルな部分のイメージだけに振り回されるのはばかげている
↑
誰がどこでどういう生き方をしようと自由である
|
人はただ自分に与えられた条件に制約されながら無理をしない選択の道を探るほかない
自由な人たちが存在していい
◎ 大事なこととは,情報に振り回されず,自分の本来的な欲望や傾向がどこにあるか
を吟味することである
□古くて新しい「働く」イメージ
「働く」ことはかっこいいことでも美しいことでもない。つらさや退屈さに耐えて,日
常の時間の中に与えられた仕事の運びをくみこんでしまうこと。
□コードレスの魔力
家族的共同性の意識との折り合いの問題
□みんな幸福と不幸のボーダーライン
滝川一広・竹内洋 バランスを取っていきのびる
□ポスト子育て期を夫婦で乗り切る
晩婚化と平均寿命の延び
① 自分が家族に育てられる時期
② 自ら家族をつくって人を育てる時期
③ それ以後の時期
◎ 第三の時期が人間としての成熟度が測られる試練の時期
↓
結婚生活の安定は自分たちの不断の努力によって作り出すものと考えるべき
□どこで家族を確認できるか
「となりのトトロ」
家族のメンバーの一人がはじめから全く存在しないのではなく,どこかにいながら
その場に不在であること,不在であることによって存在を知らせること,それが家族
の意識空間に大きな意味をと影響力をもたらす
|
「ゆきがかりの体系」なかなかもとにはもどれない
□「となりのトトロ」は家族を救えるか
日常生活一般の時間の流れ方 → 家族 失われた生活
お母さん「存在しているが不在である」
◎必須の条件
= 共感
とぼけた雰囲気 融和的~闘いの観念がない
|
◎ 家族生活を通して求められる。
<神>
<超人>
↑
危機の特質に求められる
☆「にほん語観察ノート」井上ひさし 中央公論社 2002年 ①【再掲載 2012.10】
<出版社の案内>
人生の難局を切り抜け、難問を乗り越える。その力が「ことば」である。新聞投書から首
相の答弁まで、著者が感銘を受けた言葉や迷言を幅広く取り上げる。『読売新聞』日曜版
連載を単行本化。
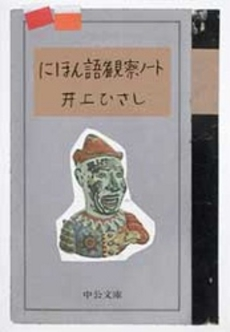
◇敬語壊滅現象
□マニュアル敬語全盛 ~ 「商業敬語」
現代の日本社会は、他人との関係を、お金を介在させた売り手と買い手の関係で、し
かも把握できなくなっている - 親の態度
◇「わからないけど」
□「わからないけど」半敬語法 ~ 言葉のクッション
半疑問形の流行 = 半敬語法の一種か?
|
◎ 日本人はようやく他人に自分の意見を言うようになってきた
しかし、その場合の敬語法がない
◇一語一義
科学の述語は「一語一義」でないと用を足せない
◇官僚文章の癖
□役人の文章
① 漢語を多く使う = 堂々たる処をみせたいから
② かたかな英語を多く使う = わかりやすいと困るから
③ 造語を多く発明する
(例) かつて水田に「圃場」と言う造語
④ 独特の言い回しを多く使う
(例) 句読点の省略
□役人
= 自分たちにはわからないと言うことを隠すために、いっそう難しく表現して国民を
煙に巻き、一方、分かり切ったことをわざわざ難しく表現して、みんなを面倒がらせ、
それによって自分たちを堂々として厳かでいかめしい存在に見せたがる人たち
◇漢字の増殖能力
□読売新聞使用漢字
① 日
② 一
③ 大
④ 年
⑤ 人
⑥ 十
⑦ 会
⑧ 二
⑨ 中
⑩ 市
□昭和41年国立国語研究所
① 日
② 一
③ 十
④ 二
⑤ 大
⑥ 人
⑦ 三
⑧ 会
⑨ 国
⑩ 年
∥
十字中八字まで共通
□漢字の増殖能力 = 漢字の融通無碍
大 鉄 化
◇命名いろいろ
股旅 = 長谷川伸
慕情 = 高見順
ロマンスグレー = 飯沢匡
◇語彙数
NTT「語彙数推定50問」
◇常用漢字
昭和56(1981)年 常用漢字表 1945字
↓
「交ぜ書き」の横行 = 決まった瞬間からたくさんの滑稽を含んでいる
原田種成(漢学者)
「振り仮名は常に傍らにいる教師である」
「振り漢字」 - 江戸時代の表記法
「小浜逸郎さんはこんなことを」18回目、「家族を考える30日」3回目の紹介です。
出版社の案内には
「家族を概念で語るのではなく、あたかも日めくりをめくるように、家族を普通にやって
いればどこかでぶつかる出来事を、1日1項目のスタイルで、さりげなく提出し、繊細
な倍率で照らし出す。家族を考えるヒントに満ちた新機軸のエッセイ集。」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「現代の都市家族は消費共同体」
・「大事なこととは,情報に振り回されず,自分の本来的な欲望や傾向がどこにあるかを
吟味することである」
・「『働く』ことはかっこいいことでも美しいことでもない。つらさや退屈さに耐えて,
日常の時間の中に与えられた仕事の運びをくみこんでしまうこと。」
・「結婚生活の安定は自分たちの不断の努力によって作り出すものと考えるべき」
もう一つ、再掲載となりますが、井上ひさしさんの
「にほん語観察ノート」①を載せます。
役人の言葉に関する記述、なるほどとわたしは感じました。
昨夜は自治会の定例会がありました。
地域の神社にある町の公民館に役員が集まって話し合いがもたれます。
1年目ももうすぐ終わりますが、ようやく動きがわかってきました。
5月の浜松まつりには参加する方向で進んでいますが、
コロナ感染の広がりが悩ましいところです。
<浜松のオリーブ園>
浜松にもオリーブ園ができました。
和Olieve 園のサイト
〈ふじのくに魅力ある個店〉
静岡県には、個性ある魅力ある個店がいくつもあります。
休みの日に、ここにあるお店を訪ねることを楽しみにしています。
機会があれば、ぜひお訪ねください。

<浜松の新名所 浜松ジオラマファクトリー!>
ものづくりのまちとも言われる浜松。
山田卓司さんのすばらしい作品を
ザザシティ西館の浜松ジオラマファクトリーで味わえます。
お近くにお寄りの時は ぜひ お訪ねください。
☆小浜逸郎さんはこんなことを⑱-「家族を考える30日」JICC出版局 1993年 (3)
◇状況に接しながら
□年を世代的に住み分ける
現代の都市家族 = 消費共同体
<食事を共にする>
<子供の養育>
□女よスーパーウーマンを目指すな!
この人たちは立派すぎる
経験を自信を力強い言葉で表現できる人
「完全なる女性」のイメージ
「完全なる女性」というイメージに制約されることの根本的な危うさ
↑
スーパーウーマンのいかがわしさ
表向きほどかっこいいものではありえない
|
パワフルでビューティフルな部分のイメージだけに振り回されるのはばかげている
↑
誰がどこでどういう生き方をしようと自由である
|
人はただ自分に与えられた条件に制約されながら無理をしない選択の道を探るほかない
自由な人たちが存在していい
◎ 大事なこととは,情報に振り回されず,自分の本来的な欲望や傾向がどこにあるか
を吟味することである
□古くて新しい「働く」イメージ
「働く」ことはかっこいいことでも美しいことでもない。つらさや退屈さに耐えて,日
常の時間の中に与えられた仕事の運びをくみこんでしまうこと。
□コードレスの魔力
家族的共同性の意識との折り合いの問題
□みんな幸福と不幸のボーダーライン
滝川一広・竹内洋 バランスを取っていきのびる
□ポスト子育て期を夫婦で乗り切る
晩婚化と平均寿命の延び
① 自分が家族に育てられる時期
② 自ら家族をつくって人を育てる時期
③ それ以後の時期
◎ 第三の時期が人間としての成熟度が測られる試練の時期
↓
結婚生活の安定は自分たちの不断の努力によって作り出すものと考えるべき
□どこで家族を確認できるか
「となりのトトロ」
家族のメンバーの一人がはじめから全く存在しないのではなく,どこかにいながら
その場に不在であること,不在であることによって存在を知らせること,それが家族
の意識空間に大きな意味をと影響力をもたらす
|
「ゆきがかりの体系」なかなかもとにはもどれない
□「となりのトトロ」は家族を救えるか
日常生活一般の時間の流れ方 → 家族 失われた生活
お母さん「存在しているが不在である」
◎必須の条件
= 共感
とぼけた雰囲気 融和的~闘いの観念がない
|
◎ 家族生活を通して求められる。
<神>
<超人>
↑
危機の特質に求められる
☆「にほん語観察ノート」井上ひさし 中央公論社 2002年 ①【再掲載 2012.10】
<出版社の案内>
人生の難局を切り抜け、難問を乗り越える。その力が「ことば」である。新聞投書から首
相の答弁まで、著者が感銘を受けた言葉や迷言を幅広く取り上げる。『読売新聞』日曜版
連載を単行本化。
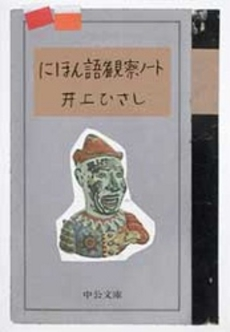
◇敬語壊滅現象
□マニュアル敬語全盛 ~ 「商業敬語」
現代の日本社会は、他人との関係を、お金を介在させた売り手と買い手の関係で、し
かも把握できなくなっている - 親の態度
◇「わからないけど」
□「わからないけど」半敬語法 ~ 言葉のクッション
半疑問形の流行 = 半敬語法の一種か?
|
◎ 日本人はようやく他人に自分の意見を言うようになってきた
しかし、その場合の敬語法がない
◇一語一義
科学の述語は「一語一義」でないと用を足せない
◇官僚文章の癖
□役人の文章
① 漢語を多く使う = 堂々たる処をみせたいから
② かたかな英語を多く使う = わかりやすいと困るから
③ 造語を多く発明する
(例) かつて水田に「圃場」と言う造語
④ 独特の言い回しを多く使う
(例) 句読点の省略
□役人
= 自分たちにはわからないと言うことを隠すために、いっそう難しく表現して国民を
煙に巻き、一方、分かり切ったことをわざわざ難しく表現して、みんなを面倒がらせ、
それによって自分たちを堂々として厳かでいかめしい存在に見せたがる人たち
◇漢字の増殖能力
□読売新聞使用漢字
① 日
② 一
③ 大
④ 年
⑤ 人
⑥ 十
⑦ 会
⑧ 二
⑨ 中
⑩ 市
□昭和41年国立国語研究所
① 日
② 一
③ 十
④ 二
⑤ 大
⑥ 人
⑦ 三
⑧ 会
⑨ 国
⑩ 年
∥
十字中八字まで共通
□漢字の増殖能力 = 漢字の融通無碍
大 鉄 化
◇命名いろいろ
股旅 = 長谷川伸
慕情 = 高見順
ロマンスグレー = 飯沢匡
◇語彙数
NTT「語彙数推定50問」
◇常用漢字
昭和56(1981)年 常用漢字表 1945字
↓
「交ぜ書き」の横行 = 決まった瞬間からたくさんの滑稽を含んでいる
原田種成(漢学者)
「振り仮名は常に傍らにいる教師である」
「振り漢字」 - 江戸時代の表記法



